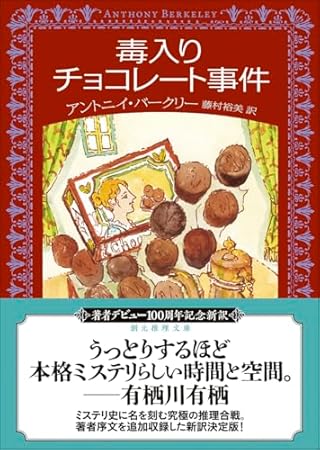■スポンサードリンク
毒入りチョコレート事件
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
毒入りチョコレート事件の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.73pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全29件 1~20 1/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 冒頭で事件の概要が提示されると、「なーんだ、答えは簡単じゃないか」と私は確信しました。その後、とんちんかんな推理は斜め読みして、240ページぐらいで私の「答え」が提示されたのを確認。しかし、まだ100ページ近く残っているのはなぜ?……ここから二度どんでん返しがあるとは。さすが傑作。でも、あいつが犯人であることは、冒頭の事件の情報から推理できるはずがないので、その点はフェアではないように思いました。(だから私は悪くない!) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 無事に届きました、有り難うございます! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 100年近く前に書かれた古典ミステリだが、自分がクリスティやクイーンなど海外ミステリを乱読していた〇十年前に、本作の名が名作として紹介されることは少なかったように思う。最近、多重解決もののミステリが流行っているようだが、その歴史的な先駆けとして再評価されているのだろうか。 現代に生きる自分としては、数多くのミステリに触れる中で様々なトリックや意外な犯人像をすでに知識として持っているので、本作で明かされる真相にそれほどの驚きは感じない。それでも、探偵役のメンバーらによって次々に語られる推理はとても楽しく、古臭さをあまり感じることなく読むことができた。古典であることを前提に評価して4★というところだろうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| >「実際の確率は、おおよそ四十七億九千五十一万六千四百五十八分の一になるはずです。いい換えると、 それはゼロに等しいのです。どなたも異論ありませんか?」 > 第十項、彼女の顔つきから判断したところ、彼女は指先が非常に器用らしいです。 わたしだ。おまえだったのか。危うくだまされるところだったぞ。 上流階級の方々が、ヒマと金にものを言わせて犯人でっち上げ合戦を繰り広げる。 でっち上げ合戦を読みあううちに、探偵小説の語り口の違いに気付ける。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ある男のもとに、製菓会社から新製品のチョコレートが送られてきて、ひょんなことから、そこに居合わせた別の男が、そのチョコレートを譲り受けることになり、譲り受けた男が、チョコレートを持ち帰って、妻と二人で食べたところ、妻は死亡。男も意識不明になる。……チョコレートからは毒薬が検出される。 ……この事件の真相は、警察の捜査では解明されず、ロジャー·シェリンガムが会長を務める“犯罪研究会"の6人のメンバーが、それぞれ自分の推理を発表する。 ……同じアントニイ·バークリーの『ピカデリーの殺人』の探偵役の、チタウィック氏が、ロジャー·シェリンガム氏と"競演“するという、バークリーの小説のファンには、興味深い展開です。 ……ただ、なぜこの“犯罪研究会"でその事件を解明しようということになったのかとか、それぞれの推理が、演繹法に立脚したものか、それとも帰納法かというような、真相究明とはあんまり関係ないところで、議論がされていて、なんか回りくどくてややこしい。……それに、最後はちょっとヒネリすぎだと思う。……一つ手前の推理が真相でよかったんじゃないかと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 面白かった。一回目のどんでん返しの犯人を私は真犯人と途中から考えていたので、やっぱり!と言い気になっていたらもう一回ひっくり返った! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ロジックパズラーの古典である。 ロジックパズラーというのは仮説検証を繰り返す本格推理小説の形式の一つだ。 本格推理小説の最大の問題は、冒頭の事件と最後の謎解きの間に挟まる退屈な無駄話だ。この無駄話はミスディレクションのためにある。それを少しでも短くしようとすると連続殺人になる。 これに対しロジックパズラーの最大の利点は推理で物語を埋め尽くすことができることだ。 ロジックパズラーには、他にコリン・デクスターの『ウッドストック行最終バス』『キドリントンから消えた娘』『ニコラス・クインの静かな世界』があるがコリン・デクスターの作品ではモース主任警部が一人で仮説検証を繰り返す。しかし、本書では6人の人間が推理を披露する。 ロジックパズラーは、"推理→誤りの指摘→次の推理"の繰り返し、という構成になる。このため、推理が次々とバカげたものになっていく。その様は、まるっきりコントだ。おまけに"誤りの指摘"が新事実の提示だったりすると、そのアホらしさに笑いすら出て来なくなる。 仮説あるいは推理とは所詮そういうものなのかもしれないし、"現時点で発表されている作品は"と断るべきかもしれない。しかし、これがロジックパズラーの宿命ではないだろうか。 そう考えればコリン・デクスターが『ウッドストック行最終バス』『キドリントンから消えた娘』『ニコラス・クインの静かな世界』の三冊で、この手法を放棄したのを才能の枯渇と決めつけることは出来ないのではないか。 結局、ロジックパズラーは本格推理のパロディー以上のものには成り得なかった。 読んだことが無いからロジックパズラーがどういうものか知りたいという人もいるかもしれない。 そのためには1冊読めば十分だと思う。 ではどの本が良いかというと個人的には本書を推奨する。何といっても古典だしね(笑)。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 予想より、綺麗だった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 次々と展開される推理が、突飛では無いが展開の早さに引き込まれます。とにかく一度は読んでください。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 若い頃読んだ時は本格推理の傑作と感動したが今回再読してそれほどの評価とはならなかった。本作は探偵小説という枠組みの中で行われる推理そのものを風刺しその基本的な欠陥を明らかにする事がテーマとなっており独創的ではあるが正統から大きくはずれた異端児といった印象が強い。 基本的な筋は記憶していたせいか全体的にまわりくどい理屈の記述が多く前半の3人の探偵までは退屈であった。後半の4番手の探偵シェリンガムからは鮮やかな推理の展開に引き込まれて一気に読めた。盲点を突く鮮やかなトリックには拍手喝采であるが本作を通常の探偵小説として見た場合その解決は強引であり動機などの心理面も表面的な記述に留まっており深みには欠けると思われる。 人物描写も現実感があり各人の個性がわかりやすく描き分けられているが推理の部分が多いため人間ドラマとしては物足りない。ただ脇役で登場する上品でお喋りなベラクル・ラ・マジレ夫人は生き生きとしていて印象に残った。 推理については帰納法と演繹法が示されておりその基本的欠陥が見事に示されている。特に演繹法を使ったブラッドレーの推理は後のエラリー・クイーンを思わせるほどであるだけにその結論は苦笑せざるを得なかった。演繹法が推理小説の王道であると長年信じ込んでいただけにこの部分は痛烈であった。 蛇足であるがチタウィックはブラッドレーの推理(2)を演繹法として分類しているがブラッドレーの推理(1)の誤りではなかろうか。また前半でシェリンガムがモレスビー首席警部にフレミング夫人が「演繹的推論」を引き出したと述べているがこれも演繹法とはいえないのではないか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| “毒入りチョコレートを食べた女性が死亡した!”事件。 だから『毒入りチョコレート事件』。 物語の核心をド真ん中に語りかけるタイトル。 ながら、読んでく裡に…一筋縄どころか幾筋もの推理が絡み合って…。 アガサ・クリスティの原作を映画化したジョン・ギラーミン監督の『ナイル殺人事件』。 事件が起きた客船に居合わせた人々(各々、容疑者でもある)の推理を イチイチ映像で見せる構成&演出が、 こんな感じだったなぁ。 我が国の作品では我孫子 武丸『探偵映画』なんかモロ本作の影響下だなあ。 セサミストリートの人形劇で… パンを持ってる人とピーナッツバター持ってる人が出会って、 更にナイフを持ってる人が切り分けて “ピーナッツバターサンドイッチ”が食べられる。 というのがあった(多分・・・)。 そんな感じのお話。 ネタバレとか気にしてたら、こんな説明しかデキないよ! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容はとても面白い。 もう少し読みやすく翻訳してもらえたら星5かな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 他のレビュアー同様、米澤穂信「氷菓」および「愚者のエンドロール」(角川文庫)を読み、本書を手に取ったくちです。 製造元を装って送られてきたチョコレートによる未解決の毒殺事件を『犯罪研究会』の6人がそれぞれの推論を立てることにより、 また、それぞれの推論の矛盾や穴、着眼点を埋めるべく各々の推論をマッシュアップすることによって真相にたどり着かんと しているが――というストーリーにより、一つの事件に対し探偵が調査を行ない、真相にたどり着くという一般的な推理小説の フォーマットにまったく頼らない、かつアンチテーゼ的な作品なので、ミステリ小説(漫画でも可)をある程度読んだ方向けの作品で あると考えます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒入りチョコレートを食べた婦人が死亡し、犯罪研究会の面々が様々な推理を展開し・・・というお話。 この小説に関しては識者の多くが様々な卓見を披露し、その殆どがその通りの素晴らしい評論になっているので、ここで私が何かを言っても屋上屋を架すだけの様な気がしますが、一応読んだということで、感想ぐらいは書き込もうという事で文字を入力している次第です。 一見、単純そうに見える事件でも深読みすれば様々な解釈が可能という理論を実際の推理小説で提示したのが本書で、これ以前はこういう物はなかったとのことで、推理小説の可能性或いは枠を拡げたという意味で画期的な推理小説であったという事は今、21世紀を過ぎても揺るぎない事実だと思います。小説の扉に題名と一緒に理論的推理小説と掲げた著者の意気込みが本書を凡百の推理小説と位相を異にした怜悧さを備えた作品にしていると思います。解説にもある様にこの後の推理小説に与えた影響力は甚大。私見ではコリン・デクスターなんかにも影響を与えたのでは・・・と邪推したくなります。兎に角、推理や推測の過程だけで小説を構成しても面白いという事実を見事成し遂げた事は重要だと思いました。 画期的な推理小説を物したその慧眼ぶりに脱帽の傑作。是非ご一読を。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品は1929年つまり昭和4年の作品と言うことです。 今読んでも十分に面白いです。ただ翻訳が機械翻訳されたみたいな訳しかたなので読みづらかったですね。日本語になってなってないところとか英語独特のクドい言い回しがそのまま訳されていたりとか。なので読むのは相当つらいと思います。ですがそれだけの価値はあると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| どんでん返しの連続、といった感じのミステリ。これを楽しめるのは、ロジック中毒とでもいうべき本格ミステリの解決編好きマニアといったところか。ちなみに私は大好きな作品だ。 多重解決ものというのは、その中にはどうしようもないダルダルな解決も混ざっているのが普通である。本作でも、展開される全ての解決がすばらしいわけではない。でも、その緩急さもまた、この手の作品の良いところだ。すべて緊張感みなぎるものばかりだったら、半分以上が解決編という本作の最後にたどり着く前に力つきてしまうことだろう。 バークリーという一癖も二癖もある作者の作品である。眉につばをつけて読んでもらいたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 1929年という、ミステリの黄金時代に書かれた作品ですが、 「多重解決ミステリ」の先駆的作品として、 ユニークな内容となっています。 実業家のペンディックス氏は、知り合いのユーステス卿のもとに 送られてきたチョコレートを譲り受け、 帰宅後妻と分け合って食べたところ、 妻が死亡、ペンディックス氏も重体に陥ります。 そして、この事件をロジャー会長率いる 「犯罪研究会」のメンバーが推理していくというのが 本書のあらすじです。 ストーリー展開としては、 6人のメンバーが順番に自らの推理を 披露していくというもので、 一部メンバーが調査に赴くシーンもありますが、 あとはひたすらメンバーの推理結果の発表と それに基づく議論だけで物語は展開していきます。 この作品の面白さは、一見単純に見えた事件が、 どこに重点を置くかによって、 様々な解釈が成り立ち、 6つの解決方法が提示されるという点です。 作品の中でも触れられていますが、 これまでのミステリが、 探偵によって唯一かつ正解である推理が 結末に述べられるというものであったことに対する、 一種のアンチテーゼとして本書は組み立てられているといえます。 ミステリの本題である「推理」という点について、 新しい可能性を開いた作品として、 一読の価値はあると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 殺人事件に対する6つの仮説に対して、論理的に検証していく過程は、現代のロジカルシンキングといった、ビジネススキルにつうじるところがある。確かに短絡的な、仮説もあるのだが、ロジャー・シェリンガムを含む、3名のプレゼンは、どれが真相でもミステリとして、納得できるものとなっている。 一旦つくったものを、何度も再構築し、一冊の本にまとめあげたバークリィの粘り腰に脱帽。まさに横綱相撲。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 探偵役六人による、六人六様の推理が楽しめる《多重解決》ミステリの金字塔。 最初の探偵役の推理が、次の探偵役によって、その矛盾や欠陥が指摘されるという 試行錯誤が繰り返されていくなかで、より説得力のある新たな推理が構築されていく 過程は、知的興奮に溢れ、じつにスリリングです。 また、六人目の探偵役によって「真犯人」が名指しされるのですが、そこまでの段取りと構成も見事。 まず、それ以前の探偵役の推理で、「真犯人」と同じ属性を持つある人物が犯人として 挙げられるのですが、即座に否定されたという事実があるため、そのパターンはもうない、 という予断を読者に持たせるといったミスディレクションの妙。 次に、「真犯人」と目される人物に、六人目の探偵役が最後の推理をする 直前に、犯人という人物像とは真逆の振舞いをさせているという構成の妙。 これは、意外性というより劇的効果という点で抜群です。 このように、本作が傑作であることは、疑い得ないのですが、野心作であるゆえの瑕もあります。 それはデータの後づけ(新しい物証や新事実の追加など)が 多く、読者に対し、必ずしもフェアとはいえない点です。 このことは、作者の恣意で「何でもあり」になる可能性を潜在的に持つ、 ミステリという形式への批評性のあらわれでもあるのですが、同時に、 本作自体の完成度も低くしていることは否めないと思います。 しかしそうだとしても、たった一つの真相を追求するという、従来のミステリに対し、 ミステリが本質的に内包する恣意性を暴露し、批判しながらも、その一方で、論理に 基づき、推理をすること自体の面白さを洗練された手つきで提示した本作は、今なお、 決して色褪せない輝きを放っています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| イギリスのレインボークラブ、そのクラブにユーステス卿あてにチョコレートが届いた。この試供品の感想を求めたいと。 しかし、卿は、こんな下世話なものをこのようなところに送ってくることは勘弁ならない、と怒り狂う。 そこで、同席していたベンディックス氏がこのチョコレートをもらい受け、家で妻と食べると妻は死に、ベンディックス氏も一命は取り留めたものの、倒れ込んでしまった。チョコレートには毒が混入されていたのだった。バークリーの作品を読むのは2度目で、前に読んだのはこの作品の原型ともいえる「偶然の審判」でした。 多くの作品が翻訳、紹介されるなか、この作品を選んだのはそういう理由からでした。 六者六様の推理が展開され、新しい推理が前の推理を凌駕するという構成はとても面白かったです。 クリスチアナ・ブランド、コリン・デクスターの好きな方にも楽しんでもらえるんじゃないでしょうか。 個人的に、クリスチアナ・ブランドが書いたという、もう一つの解決も是非とも読んでみたいです。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!