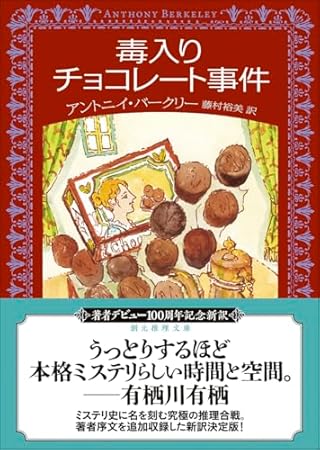■スポンサードリンク
毒入りチョコレート事件
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
毒入りチョコレート事件の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.73pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全7件 1~7 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Kindle版を購入。犯罪研究会の6人が毒入りチョコレート事件の推理を順番に行なっていく話。 翻訳が私には合わなかった。回りくどい言い回しが多く、話に入り込めなかった。 もし今後、違う翻訳が出たらもう一度読みたいと思う作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「アンチミステリ」の古典的作品。ある女性が毒入りのチョコレートを食べて死んだ事件について、ミステリ愛好家の6人がそれぞれ調査し、1日ずつ犯人を当てる推理ショーを繰り広げていく。ちょっとセリフが冗長でまどろっこしく感じる部分が多いが、ミステリーにおいて探偵役のキャラクターがよくやる言動を皮肉りながら、ミステリー小説を小ばかにしていくスタイル。終わり方はちょっともやっとして読後のすっきり感はあまりないが、ミステリファンなら一度は読んでおきたいもの。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 期待しすぎたか、合わないのか、実録の殺人事件と比べてしまい…。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 未解決事件の概要を刑事から聞き出して、それを参加メンバーが調査・考察した上で、その推理結果を披露するという、この多重推理、多重解決のスタイルは、あからさまに言えば、犯人を一人に絞るだけの十分な手掛かりが示されていない段階で、ああだ、こうだと言い合っているだけにすぎない。 刑事の事前説明を読んだ時点で、後で6人の回答者が示した7人の犯人(うち1人はダミーの犯人)の内の3人までは犯人としての想定範囲内だったし、残りの4人についても、各人の調査内容が小出しに示されると早い段階で該当者に気づく程度のものであり、特に切れのある推理が示されるわけでもない。 各人の調査で徐々に明らかになるある人物の女性関係だが、当然警察でも把握してあるはずのことであり、事前の警察からの説明内容が簡略すぎて、これらの説明が省略されており、各人の思い込み、調査内容で推理に差が生じたのだと感じる。また、前の人が調べた証言が実は間違いでしたと次々と覆されるのでは、何でもありの状態で、馬鹿馬鹿しいとしか言いようがない。 最後の人物の回答も抜き差しならない証拠を示してはいないので仮説に過ぎず、さらにその証言も覆るかもしれないので、真相とは言い切れない。 (ネタバレ) ユーステス卿が小包を受け取った時の目撃者として、ベンディックスがレインボー・クラブに呼び出されたとチタウイックは語っているが、ベンディックスがレインボー・クラブに居たとしてもユーステス卿が小包を受け取ったことを目撃するとは限らないと思うのだが。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「毒入りのチョコを食べて、女性が亡くなった」という事件を元に、探偵クラブの6人の会員が、6人6様の解釈と真犯人を示す、というストーリー。一般的な推理小説では、神のごとき探偵が、たった一つの真実を見抜く、というのがお約束のパターンだが、事件はいかようにも解釈できるという、推理小説に対するアンチ・テーゼのような小説。 自分の前に解説した人の説を、次の人がひっくり返していくという面白さはあるが、それぞれの探偵役が、自分が調査して得た証拠を、自分の番にならないと出さないので、読者としては少し釈然としない。 もしすべての手がかかりが、事前に読者に提供された後に、このような多重解決が示されたのであれば、文句なしの傑作と言える小説になったのではないか。 2014年1月17日付の5版の文庫本で呼んだが、日本語訳が、記者会見などでの同時通訳を、そのまま日本語にしたような変な訳で、とても読みずらい。日本語の話し言葉として普段使わないような言葉も多く出てくるし、会話の途中での改行も不自然。 日本語訳がもう少しまともなら、もうちょっと小説の世界に入っていけたのにと、残念。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「古典的名作」と、書名と概要は知っていたが、なんとなく読む機会を逸していた。 この度、機会があって、たまたま読んでみた。 スコットランドヤードからの依頼により、解決を丸投げされた難事件に対し「推理クラブ」のメンバーが順に推理を展開していく。 それぞれの推理については「?」の部分もあったが、このような形式を確立した本書の功績は大きい。 また、結末については少々あっけにとられてしまったし、素人目にも法廷で立証できるとは思えないのだが、このエンディングもありかなと思う。 # ただし、一人の作家が一生に一回しか使えない手ではあるとも思う。 # 評者が「本格推理物」を集中的に読んでいた時期は数十年前であり、そのころに出会っていればまた印象も違ったかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書は犯罪研究会の6名の会員が、未解決の毒殺事件に対しそれぞれの推理方法から7つの解答を示すという作品で、いわゆるアンチ・ミステリーの「はしり」の作品だろう。 同じ証拠・手がかりからそれぞれが別々の推理を組み立てる訳で、解釈の仕方でどのような解決にも導き出せると推理小説を否定されているようで、好きになれない。 ただ、真相を読み解くための手がかりはきちんと与えられており、間に挟まった間違った真相に到達する推理が余分なだけ、と考えればいいのかも知れないが。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!