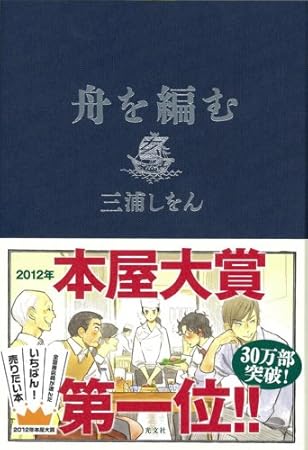■スポンサードリンク
舟を編む
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
舟を編むの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.14pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全559件 481~500 25/28ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大竹まことのゴールデンラジオで紹介されてて興味を持ったので海外から帰国と同時に購入。 期待して読んでみると・・・辞書を作る過程を題材にしたただけの、中学生向けの話でしょこれ? 大人は楽しめないんじゃないかな??なんで、本屋さんはこんなの売りたいの? もう一冊買った翻訳部門の一位『犯罪』にもあんまり期待できなくなっちゃった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本屋大賞の受賞をきっかけに読んでみました。 確かに業界(出版業界)受けする内容なのかなとも思いましたが、 私は、普通に面白く読めました。ベストセラー作家だけあって、 ストーリーもとても面白かったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| もう、すでに多くのレビューが出た後だが、どうしても支持票を1票投じたい。 それほどに読後感がさわやかで、しみじみとした幸福感に包まれる名作だと思う。 三浦さんの著作を読むのは、「風が強く吹いている」に続いて2作目。 その時も感じたが、そこはかとないユーモアと温かな人間味を伝える、著者の言語感覚には、天性のものがある。 それと、駅伝と辞書づくりという、全く異なる分野だが、そこに携わる人の喜びや苦労を追体験するような感性も抜群だ。 登場人物のキャラにも、強い愛着が残る。 今回の作品の最後は、「言葉」の永遠性に対する著者の信念を主人公に吐露させた後、ふっと現実に戻して終わる。 この、著者独特の文の運び方が、えも言えぬ温かさを生んでいるのだろうか。 「本屋大賞」。私は、目利きが選ぶ本には、「さすが」と感じることが多い。 今回の読後感は「天地明察」の時のそれと似たもので、「読んで良かった」と心から思える。 誰が何と言おうが、迷わず☆5つ。断然、オススメ本である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 良点 とても読みやすく 思わず顔がほっこりしてしまうシーンがいくつもあり 日本語を上手に遊び、より魅力的にしている点 やけに、キラキラので汚れた心が洗われる 残念点 メイン登場人物の5人の内、最長老の人物像だけがなぜか? 欠けている点 15年の集大成の中……後半の、忙しない急展開感 映画化、を想定して作ったな疑惑 総合 読みながら、笑顔になれる こんなに穏やかな人間&人間関係&世界に囲まれてみたい | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本屋大賞も第9回を迎え、中立的な立場の業界人が推薦する良書として、出版社が主催する賞以上に、読者が読むべき本を選ぶ場合の大きな拠り所になるものとして、すっかり浸透した感がある。 そんな訳で、私は、本屋大賞受賞が決まるやいなや、早速本書を注文して読んでみたのだが、本書を本屋大賞受賞作と意識して読まなければ、それなりに面白い本だったとは思うのだが、本屋大賞受賞作と意識して読むと、本屋大賞受賞作としては、意外なほど軽い本だったと思わざるを得なかった。 率直にいって、本書の本屋大賞受賞に際しては、出版業界の一翼を担う業界人である本屋の店員さんが、「本に対する強い思い入れ」というすりガラスを通して読んだ結果の過大評価の面がなきにしもあらずで、そうした思い入れのない読者とは、同じ本を読んでも、その感慨が違うのではないだろうかという気がするのだ。 たしかに、本書を読めば、辞書の出版業界における位置付けや、実際には誰が中心になって辞書づくりが行われているのかとか、辞書づくりには、いかに長く困難な道程があるのかといった、辞書づくりの内幕的なことは、よく書けており、よくわかる。しかし、辞書の完成までの期間が15年にも及ぶ長さの物語であるため、紙数の関係で、辞書づくりの道程の途中経過の省略が多く、あるいは、掘り下げが浅いので、いくら辞書づくりには、こんなにも苦労や困難が多いのだと結果だけを書かれても、今一つ、読者には、切迫感・緊迫感が伝わってこないのだ。 したがって、所詮は辞書を利用する立場の一読者に過ぎない者からすると、軽く、スラスラと読める読み易い本ではあったものの、辞書づくりの感動を共有できたという感慨・満足感はほとんど得られず、それまで知らなかった辞書づくりの内幕がよくわかって、それなりに面白かったという以上でも以下でもなかったとしかいいようがないのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 三浦しをんさんの今回の小説は辞書編纂と言うのがテーマだったので 堅苦しそうな印象かなと思い購入に正直二の足を踏みました。 辞書編集部って言うのがどうもイメージが湧かなくてとっつきにくそうだと 思いながら読み始めると、確かに初めのうちは地味な印象が拭えなかったですね でも読み進めるうちには、主人公のキャラクターが微笑ましく意外と感情移入してしまった 主人公のまじめ君こと、馬締光也 第一営業部から引き抜かれて辞書編集部に訳もわからずに 来てしまったと言う下りから、出版界ってこんな事も有るのかな?って思いながら 辞書編集に関わる何となくのイメージが伝わってきて、個性的な登場人物にも違和感が無かった。 四話から時代がいきなり13年行ってしまっていたのには少し、戸惑いましたが・・・ 岸辺と言う女性編集者が来る下りから、話がいよいよ面白く読む速度も上がってきましたね まじめ君、香具矢さんと結婚してんだぁーーって、嬉しく思いました。 最後の最後で松本先生との下りの中で、自分を悔やんでるまじめ君を見るにつけて 最後はホロリときてしまいました。 初めの印象とは違って意外とと言っては失礼ですが、とてもほんわかした心に残る作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書を作る人々とそれに関わる数々の困難が読みどころ。 色恋沙汰よりも仕事ぶりが面白い。 p41 れんあい【恋愛】 特定の異性に特別の愛情をいだき、高揚した気分で、二人だけで一緒にいたい、精神的な一体感を分かち合いたい、出来るなら肉体的な一体感も得たいと願いながら、常にはかなえられないで、やるせない思いに駆られたり、まれにかなえられて歓喜したりする状態に身を置くこと。 辞典の役割はその言葉の持つ意味をハッキリと普遍的な言葉で説明することだ。 千人に説明して千人に「なるほど」と言わしめなければならない。 これほど難しい作業はないだろう。 そしてこれほど達成感のある作業もそうない。 最後に辞典をひいたのはいつだろう。 たまにはWikipediaじゃなくて辞典にも頼ってみようと思える一冊。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 言葉を大事にしている感じが凄く良い! 最後に表紙を見て「そうか!」って思いました。 個人的に西岡が大好きだ! レビューになってないけど読んで欲しいから、こんな書き方にしてみました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 全ては言葉から始まる。言葉がなければ我々は感情すら記憶したり伝えるたりすることができない・・・。 言葉に対する思い、愛情が溢れだす一冊。辞書ってこうやって作るんだという驚き、主人公たちの執念とわだかまりを乗り越えていく強さ。辞書は本の王様であり、「本屋さんが推薦する一番の本」というのもよくわかる。 「活字離れ」などと旧世代メディアから揶揄されても、現代人はネットで、携帯で、職場のPCで、毎日膨大な言葉を消費しながら生きている。辞書がネット化されたことと相俟って言葉のちゃんと意味を調べる機会も増えたけど、そうなると改めて言葉の海を渡る船の大事さを感じることができる。まじめさんのような辞書編集マンに感謝! ただこの本に関していうと、読み終わってもの足りなさが残った。もう終わり?という感じ。最近の本は厚いと売れないのかもしれないけど、もう少し言葉を愛する者達の物語をこってり楽しみたかった。その点で星は4つ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最近の芥川賞はつまらない。今年で審査員を辞める石原慎太郎の評には大いに賛成である。氏いわく、『共喰い』は戦後間もなく場末の盛り場で流行った「お化け屋敷」のショーのように次から次と安手でえげつない出し物が続く作品。『道化師の蝶』なる作品は、最後は半ば強引に当選作とされた観が否めないが、こうした言葉の綾取りみたいな出来の悪いゲームに付き合わされる読者は氣の毒というよりない。こんな一人よがりの作品がどれほどの読者に小説なる読み物としてまかり通るかは、はなはだ疑わしい。故にも老兵は消えていくのみ。さらば芥川賞。 そこへ行くと「本屋大賞」の受賞作は当たり外れが少ない。以前読んだ小川洋子氏の『博士の愛した数式』なども面白く読んだ。数学には余り馴染みの無い人が多いのに、そういったテーマの本で賞を取ると言うのはやはり、読者を惹きつけるものがあるということだろう。三浦しをん氏の『舟を編む』も辞書編纂という一般の人には馴染みの薄いテーマで読者を惹きつける何かを持っているのだろう。日本語に関心がある評者は早速購入して読んだ。 純文学のような重厚さは無いが、こういったテーマで読者をして軽く読ませてしまうのは凄い。主人公の「まじめ君」は対人関係が不器用で服装も氣にしない変わり者と思われているけれども、純粋で内に秘めた情熱がある魅力的なキャラクターだ。ドラマ化すれば向井理に役をやらせたい。そんなまじめ君だからこそ、風采があがらない外見ながら、板前と言う男社会の世界で、自分の職業に必死に打ち込んでいる美人の「かぐやさん」のハートを射止めたのだろう。 辞書が完成するまでのドラマも面白いが、「用例採集カード」とか、辞書に使う紙の「ぬめり感」とか専門的なことも興味深く読んだ。また言葉に対する「まじめ君」の正鵠を射た表現にも感心した。普通の書物とは異なり、辞書での表記は論理性が重視される。「まじめ君」は辞書の編集者にはうってつけの人材だと思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書の編纂という、ちょっと取っつき難いテーマだけど、最後まで一気に読めた。個性的な登場人物が面白いし、でもキャラだけに頼るのでなくて、きっちり辞書の編纂の大変さや難しさ、それでいて言葉を編むことの面白さがしっかり伝わってきた。 ただ、惜しむらくは、後半が駆け足過ぎたかな。あと100ページぐらい分量を増やして、じっくりとした展開に持って行っても良かったように思う。 とはいえ、本屋大賞前に読んで良かった。だって昨年のことがあるので、大賞受賞後だったら、それだけで手に取らなかっただろうから。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本屋大賞につられ、辞書作りという地味な設定も気になったので読みました。 一気読みできる作品です。 香具矢が馬締にラブレターの返事をするシーン、 現実味がないように感じました。 恋愛小説ではないのは承知していますが、 友人もいない馬締が他人と深くかかわる初めての日は、 生涯で忘れない一日になったはずだから。 眠れたのか、眠れなかったのか。 翌日はいつもより髪を整えたりしなかったのかと思ってしまいました。 読者のご想像におまかせします。という感じかもしれませんが、 馬締のような人…周りに居ないので。 馬締の心境も、もっと深く書けていたらと 恐縮ですが、思ってしまいました。 恋愛の部分はさておき、『言葉』を大切に選んで使っていこうと思えましたし、 『愛』など出てくる言葉の意味を、自分ならどうするかと考えさせられます。 作者が執筆にあたり、取材を重ねてこられた事が良く解ります。 紙の製作の部分は特に好きです。 ぬめり感も、辞書の匂いも、めくる音も思い出しました。 類は友を呼ぶように、真面目は真面目を呼ぶのか 『嫌な人』が登場しません。 だから読んでも疲れないのかもしれませんが、 さっぱり読める作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 言葉を使い表現する作家が、言葉に正面から向き合い作品を書き上げるとは、どんなにエネルギーがいるんだろう?作家の言葉に対する深い愛情を感じ、言葉の波にいい気持ちで揺られ、またひとつ、人間の旨味を味わった。 ことばを紡ぐことは、心をかたちにすること。 あたりまえのことを三浦しおんさんは書く。 あたりまえだけど、私はそれに苦手意識があって、今も悶えている。言葉ってやつは。 だから、彼女の言葉で強烈に心が震えた。 言葉をどんなに集積してもそれを引っぱり出してあげないと、埃がかぶっちゃう。 自分だけの辞書を作っても誰にも気付いてもらえないのは寂しいから、いつだってページをめくって言葉を紡いでいこう。そんな風に思える気持ちになった、出会えて良かったと思える2012年、新年度の一冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書制作に携わる者達の人生が描かれている。結びなどから、人の成長もテーマのひとつなのだろう。 正直、この作品は物足りない。涙誘う描写も、笑いも、心温まる場面もあるのだが全体的に平坦に感じる。 個性的なキャラクター達も後半、個性が薄れていく。これは、この小説が持つメッセージや構成上仕方ないのだが―。 作者からのメッセージは素晴らしい。だが、単純に楽しめると思っていたので、当てが外れた感じで残念でした。 ここから先はネタバレです。 主要人物である馬締(まじめ)さんが恋をする。恋愛に疎い馬締は想いを伝えることが出来ず、ラブレターを書いた。これが良かったので冒頭を紹介しておきます。 謹啓 吹く風が冬将軍の訪れ間近なるを感じる今日このごろですが、ますますご清栄のことと存じます〜。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『舟を編む』(三浦しをん著、光文社)は、地味ではあるが、感動的な辞書編纂奮闘物語だ。そして、上質な恋愛物語、友情物語でもある。 玄武書房の第一営業部から辞書編集部に異動となった馬締(まじめ)光也は、27歳の名前どおりの真面目人間。辞書づくりという膨大な時間と金がかかる事業に消極的な経営陣が、辞書編集部の人員削減の方針を打ち出したため、馬締と同期入社の西岡は宣伝広告部に移ることになる。その結果、辞書編集部の期待を担う新しい辞書『大渡海』の編纂に当たる正社員は、浅い経験しかない馬締たった一人となってしまう。彼とともに『大渡海』に取り組むのは、辞書づくり一筋の外部の監修者・松本元教授、長らく松本先生とタッグを組んできた先輩社員で今は嘱託の荒木さん、契約社員のヴェテラン女性・佐々木さんだけだ。 「辞書の原稿は少々特殊だ。雑誌に載る記事や小説などとちがって、執筆者の持ち味や文章の個性といったものは、あまり尊重されない。辞書において大切なのは、いかに簡潔に、的確に、見出し語を言葉で説明できているか、だからだ。辞書編集者は、集めた原稿にどんどん手を入れて文体を統一し、語釈の精度も上げていく。執筆者とできるかぎり協議はするけれど、編集者が文章を修正することもある、とあらかじめ了承はもらっている。そのぶんだけ、辞書編集者の負担と責任は大きい」のである。 一方、「宣伝広告部に異動するまでのあいだに、できるだけのことをしようと西岡は決めていた。対外交渉の苦手な馬締のために」。ここから、一見、軽薄という感じを与える西岡ではあるが、友情に衝き動かされた獅子奮迅の働きが始まる。 「馬締の集中力と持続力も、驚くべきものだった。執筆要領を書いたり、用例採集カードを整理したりするときは、西岡が声をかけてもまったく耳に入らないらしい。昼も食べずに、何時間でも机に向かっている。黒い袖カバーが紙とこすれて発火しそうな勢いだ。『最近、ものがつかみにくくなりました』。馬締は笑って言った。資料をめくりすぎて、指紋がすり減ってしまったのだそうだ」。 「馬締は何度も夢想してきた。俺の気持ちに香具矢(かぐや)さんが応えてくれたら、どんなに幸せだろう。頬笑みかけられでもしたら、うれしくて死んでしまうかもしれない」というほど初心(うぶ)な馬締が苦心惨憺の末に手渡した恋文に対する香具矢の意外な行動には、びっくりさせられる。 「俺たちは舟を編んだ。太古から未来へと綿々とつながるひとの魂を乗せ、豊穣なる言葉の大海をゆく舟を」。漸く13年目に若い女性社員・岸辺が加わった辞書編集部の15年に亘る言葉との格闘が報われるシーンは感動的で、自分もその一員であったかのような気がして、つい目頭が熱くなってしまった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本の匂いや触感のとても好きなものに出会えると、幸せになれるので、作者や登場人物のこだわりは、うれしい。「窓際のトットちゃん」の最初に出た本は、 とてもさわり心地がよく、字体も挿絵も大好きで、好きな匂いでした。そんなことをおもいださせてくれて、ありがたかったです。 ことばに関するこだわりも、辞書を引くのが大好きなわたしには、とてもうれしいものでした。 筋書きとしては、ドラマチックではなく、奇想天外でもありませんが、とてもさわやかで、手元においておきたい本です。 はじめ、図書館で借りて読んだのですが、手元におきたくなり、アマゾンで購入しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書を作る人たちを描いた作品。 非常に読み応えがあった。 主人公と妻とのなれ初めはいまいちだった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本屋大賞受賞し、辞書編纂をテーマにしているということで、 三浦しをんさんの本を初めて読みました。 軽いです。 あっという間に読み終わりました。 テーマから考えてもっと読み応えがあるかと思っていたので、残念でした。 本屋大賞受賞だからという観点で本を購入しないで、 彼女がこれまでどういう本を書いていたか確認してから買うべきでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 15年という歳月を費やして辞書編集に携わった志ある人々の愛と友情と人生の豊かな物語。 出版、辞書、という特殊な職人の世界の雰囲気と使命感の表現、そしてコミカルだが愛情を持って人間を描く描写、三浦しをんの腕前の良さを堪能した。 ついに「大渡海」が完成するが、辞書編纂に協力してくれた監修者の先生はガンにおかされ辞書を手にすることはできなかった。最後の場面、先生の死、出版パーティでの関係者とのやり取り、では涙が出て来た。 「俺たちは舟を編んだ。太古から未来へと綿々とつながるひとの魂を乗せ、豊穣なる言葉の大海をゆく舟を。」 ビジネスマン時代から人間として尊敬する上司の名前は舟崎だった。「ふなは、ちっぽけな舟の方だ」と言っていたのを読了後思い出した。出版社の一角にある小さな工場、そこでとんかちとやすりで手作業で舟をつくる。いや、確かに舟を編む、のか。その舟が大海原を走る。人間世界という大いなる海を棹さしていくのを助ける乗物が辞書である。 三浦しをんは、1976年生まれだから30代の半ば。2006年には直木賞を受賞。この人の小説も読んでみよう。 この小説は、映画になるのではないか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国語辞典というと、どうしても使う立場で辞典を見てしまいます。 しかし、この本を読んで、国語辞典を作る立場の人たちの苦労が ひしひしと伝わってきました。 ふだん、何気なく手にしている辞典ですが、この本を読んで、辞典 に対する私の見方が大きく変わったように思います。 また、主人公の馬締光也さんやそれをとりまく人たちが、実在する 人物のように思えました。 「風が強く吹いている」でも感じましたが、三浦しをんさんは、小説 を書くために、本当によく題材について取材し、研究をしているんだ なあと思いました。 本屋さんが薦める本NO1、納得の1冊だと思います。 ぜひとも多くの人に読んでほしい1冊です。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!