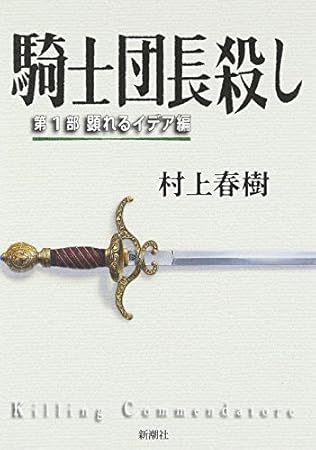■スポンサードリンク
騎士団長殺し
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
騎士団長殺しの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.46pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全721件 521~540 27/37ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| はっきり言ってノーベル賞がほしいだけの売名行為にしか思えない作品。内容がなさ過ぎて2部の途中でギブアップ。星ゼロに近い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ねじ巻き鳥のクロニクルを思い出す所あり、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドを思い出す所あり、1Q84を…と、今までの村上ワールド全開です。 ただ、1Q84もそうでしたが終盤は失速する感は否めません。 村上氏は、テロや地震等を目の当たりにして、普通に生きることの大切さを感じるようになったのかな、とも思いました。 主人公の男性はメタファーの世界に行って産まれ直したのでしょう。 暗くて狭いところを通り抜けて…なんてまさに暗喩ですよね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 村上春樹の作品には、100%の女、とか具体的数字が頻繁に出てくるので、 興味をそそられます。 その数字の「根拠」を調べるのがクセになってしまいました。 それで、今回は、南京事件の犠牲者数について調べました。 本書(第2部の81頁)に、南京虐殺事件の「中国人死者の数を 四十万人というものもいれば、十万人というものもいます」 と書かれていたからです。 調査の結果: 南京事件の犠牲者数 (その根拠) 40万人 (根拠不明) 30万人 (中国の南京大虐殺記念館) 20万人以上 (東京裁判での判決) 10万人以上 (東京裁判での松井大将への判定) 4.2万人 (1938年、中国共産軍の機関紙「抗敵報」) 最大4万人 (秦 郁彦氏) 4万人か (「読売新聞」2017年4月20日号) さて、本書第2部に戻ります。 村上春樹の作品には、『海辺のカフカ』など、カフカが頻繁に出てきます。 「子供がないまま死ぬのは怖ろしい」(ナポレオン) この言葉は、カフカが恋人宛てに書いた手紙(ラブレター)からの引用です。 本書にはありませんが、カフカを調べていて見つけました。 カフカは、ナポレオンの言葉まで持ち出しておきながら、 子供は持たない、と新年に向けて恋人に宣言したんだそうです。 子供を持たないことを怖れながら、子供は持たないと宣言するとは! カフカくんらしい、めんどうくさい性格の29歳の青年です。 めんどうくさい、と言えば、メンシキさんは、自分の「娘」と信じて、 全精力で近付いて確認を続ける、今なら「ストーカー登録」されそうな 非常識な人です。 そして、離婚届を出す前に誰かの子を妊娠してしまった元妻と、もう一度 やり直そうとする「私」も、犬も食わない人です。 もしかして、今の村上さんは、「私」のように気持ちを整理し切り替えて 人生を生きていくのもありかな、と思うようになっているのかも。 メンシキさんのように生きてもいいし、「私」のように生きて行くのもいい、 と柔軟な選択肢を考えて、肯定的に生きることを読者に提案しているのかな。 そんな複数の選択肢もありうるよ、と本書で示してくれているように感じました。 村上さんは「自分の好きなように、勝手に生きろや」の「ほったらかし作家」では ありません。人生の岐路での選択例を、親切に例示してくれたように感じました。 長い人生を生きてきて、ろくでもない、めちゃくちゃな世の中を何度も繰り返し見てくると、 本書のストーリーはなんだか都合よく落ちが付いて、まとまっているかな、と思わないわけ ではありませんが、まあいいか。「ほったらかし」より、いい。ハッピーエンドに近いから。 世の中に絶望しないで、なんとか折り合いをつけて生きていけるような「考え方」の本とか、 嘘でもいいから「気持ち」の整理ができるような、筋の通った小説が読みたいんです。 小説で言えば、どんどん物語に引き込まれるような、渦を巻いた小説を読みたい。 墓石の前の「渦を巻いた線香立て」のように。 現実の中には求めても得られないものを、リアルな夢のように現出させる小説を読みたい。 気付くか気付かないか分からない暗号のように、論理を超えた、意味をなさない信号が 描き込まれた小説を読みたい。 この作品は、そういう読者のわがままを(ほとんど)全て満足させてくれました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 歴史に無知な人は小説を書くべきではないとつくづく思いました。南京戦を取り上げるんなら、最低限、それに参加していた元日本軍兵士たちに取材すべきでしょう。YouTubeにも南京攻略戦に参加した元兵士の証言動画が何本も上がっているので、せめてそれを視てから執筆すべきだったと思います。そうすれば、全然違う内容になったはずなので。中共の独裁政権に媚びてまでノーベル賞が欲しいのか?と勘ぐってしまいます。独裁政権は狂喜したでしょうね。ノーベル賞欲しさのあまり「最後の賭け」みたいな気持ちで書いたのかもしれませんが、「知らないことについては書かない」という選択もあったはず。心根の卑しさを感じますね。ともあれ、歴史オンチが歴史にコミットするとロクなことにはならないと考えます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京大空襲、あの焼野原の犠牲者が約10万人と言われています。 どうやったら”南京大虐殺40万人”など出てくるのでしょう? 中国人による南京虐殺は大正時代から何回かあったと新聞報道があるとの話も聞きますが それを全部日本軍のせいにしているのですか? 村上氏は歴史資料を真面目に調査したとはとても思えません。 デタラメを書いて世界に発信させて 将来を担う日本の子供達にどう責任を取るおつもりでしょうか? こんな本を通した出版社も何を考えているのでしょうか? 新潮社の責任も重いと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| グローバリズムとポピュリズムが渾然一体となって暴走する現代社会への鋭いアンチテーゼにだ。この物語のタイトルである『騎士団長殺し』は、1938年のドイツによるオーストリア併合(アンシュルス)を時代背景とした絵。その前年に起こった南京虐殺事件とともに、雨田具彦という老画家を通して、戦争や暴力、血の記憶が、物語に影を落とす。第1部のサブタイトルにもなっている「イデア」とは、イデオロギーのことであろうか。そして第2部に出てくる「二重メタファー」はジョージ・オーウェル『1984』に出てくる二重思考のオマージュだろう。二重思考とは「戦争は平和である」「無知は力である」といった矛盾した概念を同時に信じることで、1984作中のファシズム国家が、国民の思考能力を奪うために行っていた。『騎士団長殺し』では、イデアである騎士団長が自らを主人公に殺害させ、主人公は二重メタファーに満ちた地下冥界を通り抜けた末に帰還する。共産主義や社会主義などのイデオロギーが死滅した現代にあって、トランプに代表されるポピュリズム政治家は言葉の意味を無意味化し、人びとは「脱真実」を信じようとする。そんな時代にあって、我々はどう生きればいいのか。本書はその道筋を物語によって照らしてくれる気がする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これはぜったいモザールのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」が出てくるぞ、と思って、楽しみにページを繰っていったら、その前に絵描きが主人公だったので、興味津津となりにけり。 身内に売れない絵描きがいたり、「騎士団長殺し」を飛鳥時代風の日本画で描いた老画家、がどことなくうちの近所に住んでいた故小泉画伯に似ているので、ますます個人的に親近感を覚えて、夢中で読み終えてしまったずら。 貧乏画家が生き延びるために絵画教室は常道だが、肖像画で稼ぐという抜け道もあったかあ、と膝を打ちましたね。 今回の村上春樹は、絵画、美術という穴をもうけて、そこからいつものような謎の人物や、女性とのたび重なる都合のよいエロエロや、反ナチ運動や、正体不明の穴ぼこや、クラシックの音楽や、リトリピープルもどきのイデア爺ちゃんを巧みに出入りさせる。 その手際はまことに周到というべきなのだろうが、まことに思わせぶりな大中小の伏線を300ページにわたってばらまき続けて、いったいどうやって後篇で決着をつけるんだろう。他人事ながら、ちょっと心配になるずら。 しかし世の中嫌な事ばかりでお先真っ暗なのに、それらを全部忘れさせてくれるこんな面白い小説、久しぶりに読みました。さすが村上春樹は、谷崎の衣鉢を継ぐ正統的なストーリーテラーだ。早く「メタファー編」に移ろうっと。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「大人のためのお伽噺」と理解すれば、ストーリー上の多少のご都合主義もそれなりに納得できるかもしれない。現代日本を舞台にしながらも、本書の主人公を取り巻く環境は「ファンタジー」です。主人公は肖像画の評判がよい画家であり、海の見える静かで立派な家(その家は日本絵画界でも著名な画家が住んでいた)に一人で暮らすようになる。そこで絵画教室の生徒2人と後腐れのない不倫関係になる。上品な資産家の肖像画を描き、期待以上の出来であると喜ばれ破格の報酬をもらい、豊かな知性と教養が反映された対話をするようになる。美しい未婚の中年女性と、その姪が、肖像画のモデルとなるために主人公の家を訪れ、主人公は大人への階段を上がろうとしている年齢の少女と2人だけでスタジオに篭もる。また、愛していた妻との離婚は最終的に成立せず元の鞘に戻るが、愛人の一人が自ら「もう会わない方がいいと思う」と主人公に告げて去っていくタイミングは、まさにその直前である。どのシチュエーションをとっても、(少なくとも男性であれば)一種の憧れ的な要素が含まれているのではないか。これが作者によるサービスなのかは知らないが、本書を読む間は少なくとも本の中の世界への現実逃避を楽しむことができる。 私は特に村上春樹の読者というわけでもないが、作者の比喩表現それ自体がとてつもない魅力を放っていると感じる。優れた短歌のように、詩情と明確さという相反する要素を手品のように同居させてしまう。恐らく村上春樹の作品の大きな特徴の一つでもあるのだろう。 「瓶からグラスにウィスキーを注ぐときに、とても気持ちの良い音がした。親しい人が心を開くときのような音だ。」(第二部、p171) 「それはヒンドゥー教徒の持ち出す巨大な山車のように、いろんなものを宿命的に踏みつぶしながら、ただ前に進んでいくしかない。」(p.211) 挙げていくときりがないが、これらの比喩表現が読者の過去の知識・経験とそのシーンとを瞬時に結びつけてくれるこの感覚は「匠の技」というよりない。「親しい人が心を開くときのような音」というよく考えてみると逆に意味がぼんやりしてくるような表現も、不思議と感覚としては明確にわかる。表現はストーリーからはある程度独立しているかもしれないが、その巧みさがなかったらストーリーの魅力も目減りするのではないかと感じる。 肝心のストーリーに散りばめられた謎は、自分の中で全く解けていない。イデアとしての「騎士団長」も、メタファーとしての「顔なが」も、彼らは何ものなのか、なぜ彼らはそこに現れたのか、主人公が迷いこんだ色のない世界は何だったのか。しかしこれだけ大量の謎を残しながらも不思議と読後感は心地よく、奥歯に何かがはさまったような不快感は皆無だ。これから、同じようにこの作品を読み終えた人たちと語り合いながら、あるいは一人で、この物語の謎と思い出すたびに向き合っていくことになるだろう。読者はこの作品を通して、頭の中にパズルの詰まったおもちゃ箱を受け取ったようなものだ。そしてことあるごとに、そのおもちゃ箱を開いて、パズルを弄ってみるという豊かな時間を楽しむことができるだろう。いや、「パズルの詰まったおもちゃ箱」という喩えは不適切か。この作品は、著者が我々の「屋根裏」にそっとしまいこんだ『騎士団長殺し』なのかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 良くも悪くも、村上主義者の期待は裏切らない作品だと思う。 ベテランミュージシャンの新しい作品を耳にした時の感覚に近い。 ただ、これで(2部)で完結ではないと思うから、最終結末に期待したい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「ドン・ジョヴァンニ」(モーツァルトのオペラ、台本はロレンツォ・ダ・ポンテ)を裏というか副ストーリーとして考えることは面白い。 主人公ドン・ジョヴァンニの従者、レポレッロが歌う「カタログの歌」では色々な国、様々な年齢、髪の色…の女性達について語られるが、 この本で様々な女性のそれぞれの魅力が描かれていることと無関係ではないのかもしれない。 未聴の方はヘルマン・プライ(Hermann Prey)の歌う「カタログの歌」を聴いてみてください。 好きならツェルリーナのアリアなど、他の曲も。 そしていけそうだったら全部。対訳見たりして。 ストーリーも不思議で、だいたい主人公が最後にあんなことになるオペラって他にあるのか…。 「白いSUVの男」はドン・オッターヴィオなのかな…など、オペラの筋から考えると楽しみも倍に。 Alles Gute! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 結局21冊を買いました。読書が好きな子供にあげました。やりがいがありました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み終わった後、騎士団長に会えたら良いなと思いました。そんな可能性はほとんどあらないのかもしれないけれど。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 第2部では、謎は謎を呼び、主人公とそれを取り巻く内面と外面の両世界が混迷を極めつつめくらめく壮大なファンタジーの全面展開となる。 第1部で盛大にまき散らされた種子を急いで育て、開花させ、その果実を収穫しなければならないのだが、ちょっと急ぎ過ぎたのではないだろうか。物語の本当のエンディングまでには、ちと紙幅が短すぎた、という印象がありますね。 冥界のエウルデーチエを探すオルフェオのように、行方不明の美少女を取り戻そうとする主人公の現実と空想の次元を超越した大冒険は、老画伯と主人公の出会い、主人公による騎士団長殺しをハイライトに延々と続きます。 そもそもが奇想天外な噺、あるいは電脳ゲームなのですが、それをさほど奇想天外と感じさせずに平然と物語る作者のお筆先は、さすがノーベル賞候補作家だと唸らせるほどの凄さだが、それが主人公の地中探検あたりから、だんだん白熱の度合いが醒めてくるように感じられるのはなぜだろう。 穴に始まって穴に終わる。大山鳴動してみみずく1羽。 主人公の遅まきながらの自己投企と漂流の時代は終わり、物語は急速に自己再生のブルダングスロマンの色彩を帯びてくるのですが、わたくし的にはそれが非常につまんない。面白くないのです。 ホラーファンタジーから、因果律と輪廻と恩寵が支配する運命ドラマへの転回など、竜頭蛇尾、興ざめ以外の何物でもないからです。 幸か不幸かまだしぶとく生き延びている2人の悪の分身との熾烈な戦いを描く続編を期待してやみません。 それにしてもこの作家はいつの頃からか、吉本ばななほどではなくとも、精霊のさざめき的な要素を物語の中に大胆に取り込むようになった。スエーデンボルク流の心霊探訪は、ゲーテ以降いくたの文学的遺産をもたらしてきたのであるな。 観念が顕現しようが引喩が流動しようがどうでもいいが村上春樹は直喩の作家 蝶人 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 羊3部作位の頃は最高の作家だと思ってましたが、今や過去作の焼き直しばかり | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「好奇心です」(免色)だけで済ますには、彼の親切と行動の動機に蓋然性が足りないように思えたので。 恋人と別れ、その後亡くしたことで、それまでの自分を見失ったからと考えるより、 その方がしっくりくるような。 主人公と対になっているようにも見えますし、資格ありです。 おそらく第3部は真打ち登場ということで免色を主役にした物語になります(妄想)。 これまでの主役と同じ匂い。心の裏側を覗いてみたい。 そして予想外なイデアにして欲しいです(同)。 なおストーリー自体はおもしろく、楽しめましたし、エンディングにも不満があるわけではありません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 蠍座という星座は「死と再生/性/遺産」を表します。 その蠍座が位置する「第8質」というハウスは「自分では自由にならないもの」を意味し、やはり「先祖・相続・遺産」「生と死」「性に関する事柄」「結婚後の生活」という意味があります。 失われたものを取り戻す旅 と、死と再生、性的なものと暴力、遺産や受け継ぐもの というのは村上作品の根底に流れ続けているテーマで、 彼の作品は非常に「蠍座的」だと思うのですが、一見同じモチーフなのにどんどん進化しているのが毎回驚きです。 「ノルウェーの森」では、電話ボックスで呆然としながら「失うことに甘んじているだけ」だった「僕」が、 「ねじまき鳥クロニクル」でものすごく暴力的な(精神的にギリギリの)体験をしたあと、 「スプートニクの恋人」以降、失われつつある「大切なもの」を、実際に身体をつかって探し始めます(それまでは井戸堀り的な「精神的穴ぐら」の探求はするものの、現実的な行動には積極的ではなく、受身)。 そして「神の子どもたちは皆踊る」で、初めて「子ども」が出てきはじめ、少年カフカでは「子ども」が主人公になったとき、村上春樹のなかでどんな心境の変化があったのだろう?これからどういうふうに変わっていくんだろう?とわくわくしました。 今回は、失われたものを実際に取り戻し、更にメタファー的な意味であっても「子どもを持つ」ところまで成長したのか!と驚きました。 実際に、「友人の子ども」ではなく、「僕」が子どもを持つ という状況は(それが夢を通じてであっても)、村上春樹の作品では初めてなのではないかな? 喪失、井戸堀り、暗闇での冒険、暴力、性的なエネルギーの交換(補給?)というモチーフに拘りながら、「僕」が少しづつ精神的に成長し、タフになり、他者とのコミットメントができるようになる(取り戻したり獲得できるようになる)、ここまでの進化を見せてくれてありがとう!と純粋に感じました。 もう25年ほど読み続けていますが、私自身どんな成長、変化をしてきたのかなあ?と振り返ることのできる良書で、この年齢でここまでの作品を書き上げられる村上春樹はやっぱりすごいです。 順を追って「変容」する課程を楽しめることが、村上春樹をずっと読み続ける理由なんでしょうね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読んでるあいだ、さまざまな記憶・思い出が掘り起こされ(思い出され)、楽しかった。 というのが感想のすべて。(というか、この忙しい時世で、最後まで読めるだけで傑作。不満もあるにはあるが書かない。) 以下は、ツイッターに断続的につぶやいた途中経過。 ・騎士団、南京大虐殺のとりあつかいが適切かどうかはどうでもいい(というか、歴史的事象への適切なとりあつかい法が無いことは尖閣・竹島・エトロフで明らか)が、あれであの作品が中国でバカ売れしたら、たとえばこれまでの2倍くらい売れたら興味深い。そこまで単純なのか、と。 ・騎士団長殺し :第1部 顕れるイデア編 https: 恒例になったが、「最も参考になった」レビューは いちじるしく傷つけてるなあ。自分を。自傷のコンペティション大会になる村上春樹ワールド。なんだろうなあ。その回路は解明してみたい ・騎士団長、ついに読み終えた。何日かかった?1週間か?とくに感動はしなかったが、読んでる最中の記憶ほりおこし、想起もんの量がえげつなく、さすが春樹大明神、と思った。で、まあ、「結婚詐欺みたい」って批判も、「なによ、気障(きざ)なんだから」って非難も分かるが、けっきょく面白い ・騎士団、村上春樹さんとしては初めてのエピローグつき。 ・場所Aで僕が何かを殺す→場所Bで問題霧散。それが村上春樹ワールド←単純化しすぎ ・アカン、騎士団、映画「インターステラー」に影響されすぎ疑惑をぬぐえない。まあ、パクっていても それがどうした問題、「凡庸な芸術家は模倣する、偉大な芸術家は盗む」問題もあるけど ・ええ、ヴォネガットをコピーしただけの粗雑なものだと思ったんです。その表層の奥にある村上春樹さんの深さを見抜けるほど鋭敏な評論家では、わたしはありませんでした。~「大江健三郎、自分自身を語る」 ・あかん、騎士団、みんなの感想がオモロイ。やっぱきのうの新聞 買い占めておけばよかった。。いっちゃんレベル高いはずの毎日は買ったが。。。井波律子さんに担当してほしかった。。 ・騎士団、最後ヨンブンノイチのとこで 不思議の国のアリス になる、意外。さあラストは どない ・騎士団、そういや小学校の絵の時間に、Aという同級生(異性)を描いてるはずが、出来上がりがBにそっくりだった ことがあったなあ。とくにBを意識したことはないはずだったが。。と、まあ、どうでもいいことながら、相変わらず大量に記憶を掘り起こす作品だ。春樹復活か ・騎士団、また新興宗教かあ。美少女と新興宗教。。ちょっと食傷ショクショウするなあ。「意味ありげで意味なし」よりは「意味なさげで意味あり」のほうがうれしい。まあ、闇の領域にまぎらすならナチスと宗教と戦争しかないのか ・騎士団、自殺した叔父さんかあ。そういや僕にも自殺した叔父さんがいたらしい。 ・騎士団、テンパッた人が変な行動をとるところが上手く描かれていて感心。ラストどうなるんだろ ・騎士団、つくづく高級車列伝だなあ。まあ、お金持ちの生き甲斐、なんだろうなあ。で、そうゆうのを喜ぶ外人(と日本人)の読者がやたらいるんだろう。ぼくのように。 ←お前もかーい! ・騎士団 ようやく上巻を読み終えた。最後の数ページにやたら手間取った。さあ下巻だが、あんまワクワクしないなあ。それより寝るか、じぶんの仕事をしたい ・騎士団、絵描きが主人公。スティーブン・キング「悪霊の島」と共通 ・モチーフ2 真っ暗 真の闇の穴蔵アナグラのなかに一定期間とじこもる話。(ねじまき以来)。貞子サダコ的な。まあ、けっきょく井戸か ・騎士団、むずい漢字が激増したのが謎。まあ、ちゃんと振り仮名うってくれてるのが さすがだが ・騎士団、やっと上巻の真ん中。即身仏ソクシンブツの話になってる。ソクシンブツなんて、「火の鳥」以来やなあ ・多崎つくるのときに感じた衰弱の影はなく、マッシブな、ねじまき以来のマッシブさ ・アカン、騎士団、時をわすれるほどオモロすぎるけど明日も早いから寝なあかんわ。わしも大人になったもんや。けど、寝れるんかな、こんな興奮状態で。ギンギンやで。←知らんがなっ ・ 騎士団、同工異曲ドウコウイキョクというか、なじみのモチーフが大量に出てき、それ前にも(別の言い方で)ゆうてはりましたねえ って部分だらけだが、それでも面白く、タンノウできる。あれか、「作曲家は、同じ一つの曲の変奏曲ばかり作るわけさ」(キースリチャーズ)か ・いま数ページだけ騎士団 読んでみたが、すごい。没頭すると その世界に移動するわけだが、ほんまに移動した。数ページで。どうゆうことなんだろうなあ。ま、信者ってだけか ・騎士団 立ち読みしたら わたしはモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」をかけた。 みたいな文章が目に入ったが、こうゆうのが他の作家の作品では ついぞ見れないのはなんやろ。ドンジョヴァンニ聴かないのかな、他の作家は。ハイカルチャー無視ムーブメンツ?もったいない | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ついに古典派オペラの大作をモチーフとすることになった村上文学の最新作です。 村上春樹の小説に音楽は欠かせませんが、これまでにない深みをもった取り上げ方です。 音楽配信サービスのSpotifyではMusic From Novels 3というタイトルのプレイリストで本作の登場曲が楽しめます。 作中のオペラ曲としては表題の「騎士団長殺し」が登場するモーツアルトの「ドン・ジョヴァンニ」の他に、 リヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」が取り上げられています。 本書では触れられてませんがナチスとの親密さが問題視されたリヒャルト・シュトラウスというところに興味がわきます。 職業画家の主人公が絵画に取り組む姿も新鮮です。 CG全盛の時代に伝統絵画の技法をアナログに追求する主人公の生き方はどこか小説家の執筆活動を彷彿とさせるところがあり、 著者の人生観を垣間見る気がしました。 絵画を文章で鑑賞させる新たな試みは成功したと言えるのではないでしょうか。 本作では近代史の暗部であるファシズムが物語の背景として登場します。 作中の人物が語る過去の出来事を発端に、著者の歴史認識について議論が持ち上がっています。 作者としても書けば議論の的となることはわかっていたと思います。 それでもなお世界を相手に文学作品を発表する作家の立ち位置として、 言葉にしないわけにはいかなかった覚悟の物語だったという気がします。 作中の音楽の選曲は登場人物のキャラクターやストーリーの展開とよく合っています。 音楽を聴きながら読み進めると作者の選曲の意図がよくわかります。 物語の構成に与える音楽の役割も今まで以上に緻密に考えられている気がします。 CDを買いそろえなくても作中の音楽を聴ける時代になったのは喜ばしいことです。 聴いてから読むか、読んでから聴くか、聴きながら読むか、 村上文学の楽しみ方が広がりました。 本作は歴史と絵画と音楽が重層的に織りなす村上文学の新境地だと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| なんといっても村上春樹は〈村上春樹〉というジャンルを確立しているところが凄い(だからこそいじられやすいのだろうけど)。そしてこの作家は〝無意識〟の領域をあつかうのがうまいとおもう。抜群にうまい。文体よりも「物語性」のほうに目をむけるとよくわかる。かんじんなのは、なにが語られたか、ではなく、「なにが語られなかったか」なのだ。(……あたりまえではあるが、読者は読書中たえず「読書」という行為をしいられる。視線を上下に移動しつづけ、指はページをめくる。その行為そのものが〈二重メタファー〉を呼び寄せてしまうのだろう、きっと)。 閑話休題。「騎士団長殺し」とは、モーツァルトの歌劇「ドン・ジョバンニ」のなかの一場面――ドン・ジョバンニが騎士団長を殺す場面――を描いた日本画の巨匠雨田具彦の絵の題名である。語り手の「私」が彼(雨田具彦)のスタジオ兼住家の屋根裏部屋でその絵を見つけてから物語はゆるやかに、しかしかくじつにうごきだす。 『ねじまき鳥クロニクル』や『海辺のカフカ』などをもうすでに耽読している読者にはやや不満がのこるかもしれない。最後も急速に予定調和的な方向へかたむく。まるでゆうぐれどきのカラスがうるさく鳴きたてながら森へ帰っていくように。 ただ、「騎士団長」や「顔なが」といった、あいくるしいキャラクターの存在はおおきかった。とくに「顔なが」がいなければこの作品の魅力は半減していたことだろう。 また、「穴」の存在もある。ぼくたちはみな、子どものころは「穴」を知っていたはずだ。ここを抜ければどこにでられるか、あそこにいくにはどこを通ればいいか、と……。意識的にも、無意識的にも、ありとあらゆる場所とつながっていた。そこここをいききできた(ほんとうに)。「この作家は〝無意識〟の領域をあつかうのがうまい」といったのは、つまりそういうことだ。 〈第2部 遷ろうメタファー編〉で「私」は、〈……絵を描くことでひとつの物語を記録しているのかもしれない〉というようなことにおもいいたるところ(p169)があるが、まさに村上春樹は〝記録者にふさわしい人物〟に物語を語らせる。それもまた、個人的に〝なにが語られたか、ではなく、「なにが語られなかったか」〟がかんじんなのだとおもうゆえんである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽配信サービスのSpotifyにMusic from Novels 3というプレイリストがアップされています。 本書に登場する楽曲をストーリーの進行に合わせて編集したプレイリストです。 このプレイリストを聴きながら読書を堪能しました。 古典派オペラをモチーフにして、近代におけるファシズムの台頭がもらした悲劇から、 現代社会の孤独感、喪失感がもたらす葛藤や苦悩、そして歴史を貫く再生までを独自の視点で描いています。 一見すると時代や場所を隔てて無関係に思える出来事を巧みな着想で結び付けるテクニックは見事です。 主人公である職業画家の生き方は小説家の人生観に通じる部分もあり、 現実と空想の狭間で揺れ動く主人公を著者自身を投影したモデルとして描いている印象もあります。 寓話と暗喩を大胆に配置した物語の構成は読み手の想像力を試しているようでもあり、 これまで以上に評価の分かれる作品となるかもしれません。 全世界で読まれる作品であることを考えればその影響力は大きく、 続編への期待を含めて議論を呼びそうです。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!