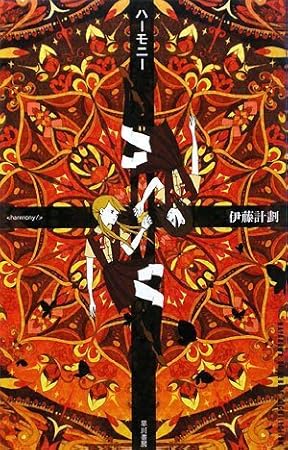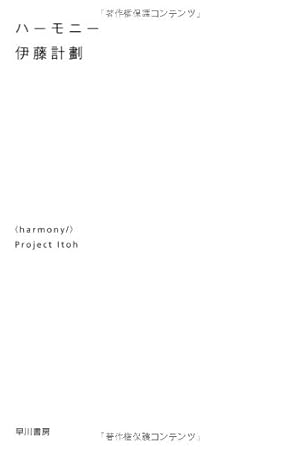■スポンサードリンク
ハーモニー
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ハーモニーの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.15pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全253件 201~220 11/13ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人為的な大災害の末に、高度医療化し「病気で死ぬことのなくなった」社会。面白い設定だなあと思いました。普段SFはあまり読みませんが、解説にあった「ロジックを受け入れやすくするための緩衝材としてキャラクターを利用している」という言葉通り、筋書きはまさにそんな感じの印象を受けました。特に、御冷ミァハなどは本当に人形みたいな少女だなと(最後まで読めばそれもわかりますが)。 全体的に説明が多くて、いまひとつ緊張がないような感じがしたのがちょっと気になりましたが、全体的には面白い設定でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 完全に余談になりますが、 SFとして、また作家の評判から手に取った人には「ラノベ臭せー、セカイ系っつのコレ? エヴァ好き?」と言われ、 かといってそれを真に受けてラノベを求めている人に読ませりゃ「文多いし挿絵ないし無理」と言われよう、 そんな本って多いですよね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 40過ぎたSF好きのおっさんでも十分面白く読めましたよ。まあ年と共に細かな瑕疵や甘さなんかは生温かく見過ごせるようになってきたこともあるが。今高校生位の奴らがその年齢でこの本が読めるのは幸せだろうなと思う。時にこれラノベなの?あんましライトじゃない気もするけど、ラノベ読んだこと無いから分かんねえんだよな。中3の娘に読ましてもいいかな?ちょっと早いか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本人初のフィリップ・K・ディック賞受賞ということで手に取ってみたのですが、いささかラノベ的過ぎると感じました。 論理武装し、リアリティで固められたセカイ系、と一言で表現できる代物です。とにかく、ハヤカワのテコ入れ具合が異常だと感じます。 ゼロ年代、伊藤計劃以後、というある種の区切りがSFファンの中で形容されているようですが、少なくともその言葉がさす意味が分かりません。 世界を憎んだから、世界を攻撃する。すくなくともセカイ系を容認した日本SFは衰退していくと思います。むしろ、小松左京氏亡き今、すでに終わっているのかもしれません。 これを読んでSFを語るぐらいなら、舌を噛み切って死んだほうがましです。それに、このレベルの作品なら、海外でごろごろと転がっています。 日本という国の視野の狭さが滲むようなレビューの数々に、寒気がしました。 内容については語るに及ばず。最後まで読み進められず、投げました。文は読みやすいかもしれません。けれども、生理的に受け付けることができませんでした。 虐殺器官のほうはすんなりと読めましたし、イーガンの訳文をさらにマイルドにした、という感じでした。が、今回のこれは少なくとも、ラノベです。ラノベだから嫌い、というわけではありませんけれど。 星五の評価の乱立は、少しほめすぎやしないかと思います。すごいSFとみんなが言うから読んだ、よくわからなかったけど、みんながすごいというから星五の評価にした、という感じに見えて仕方ありません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 伊藤計劃が優れた作家であるのは認める。だが、エンターテインメントとしてうますぎる事が小説としての出来にマイナスに働くように感じられるので個人的にはあまり好きな作家ではない。しかし、それでも本書はかなりいい線をいっていると思う。 『虐殺器官』は読みやすくて面白い小説ではあったが、内容は納得いかなかった。表現は正しいが内容は間違っていると感じた。本作『ハーモニー』は読みにくいしプロットもそれほど効果的とも思えない。だが、洞察は実にするどい。表現は間違っているが内容は正しいのだ。ミシェル・フーコーの思想をこれだけ的確に物語に組み入れた小説は他にない。私は『虐殺器官』より『ハーモニー』の方を高く評価する。 ただ、本書が小説として面白いかとなると今一歩の感がある。深い小説ではあるが、傑作ではない。各所で高評価されているが、過大評価ではないだろうか。ちなみに、伊藤氏の作品で一番出来がいいのは、中編の『The Indifference Engine』だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 久しぶりにSFにはまりました。究極の医療社会を設定していますが、それはすなわち、人間の意識さえも不必要な社会である。科学を発達させどんどん便利になって行くが、その先に一体なにが待ち受けているのか。筆者が病床で命と真摯に向き合い到達した一つの世界。 この作品のおかげでまたSFにはまりだしました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本はナンセンスである。 ここでナンセンスというのは「つまらない」ということではない。 記述不可能なことを記述しようとしていて、言葉が「意味をなさない」のである。 物語は、世界中から「わたし」が消滅することで終わる。 自我とか、自己意識とか、「わたしはわたしだ」という、そういう「わたし」なるものが、世界中から消える。 そしてそれは世界の調和、つまり「ハーモニー」を意味する。 主人公は世界で最後の「わたし」であり、この小説は、その最後の「わたし」によって語られた「記録」ということになる。 もちろん、「わたし」が消えたからといって人類が滅亡するわけではない。 これまで通り人々は生まれ、育ち、老い、死ぬ。人間の思考力も、これまでと変わらない。 何一つ変わることなく、世界は存続する。ただ、そこに「わたし」だけが存在しないのである。 このように奇妙な世界の到来を、本作は描ききっている。 良質なSFはすべからく哲学的トーンを帯びるものだが、この『ハーモニー』もまた例外ではない。 しかし、である。このような「出来事」は、本当に語られ得るのだろうか? 「わたしから「わたし」が消えた」、このような命題を語っているのは、一体誰なのか? 物語の語り手たる主人公は、最後まで「わたし」として物語を語る。 それは、「わたし」が「わたし」であることが何かを「物語る」ための条件だからである。 物語には、「語るわたし」がいて、「聞くわたし」がいる。たとえそれが形式上の「しきたり」に過ぎなくとも、物語はその枠組なしには語られ得ない。 だから、この物語は、「わたし」の消滅に「臨んでいる」こと、「今まさに「わたし」が消滅しようとしている」ことは語れても、 「わたしが消えてしまった」ことは語れない。「わたし」の非存在に、語りは届かない。 この小説は、「言語の限界」に向かって肉薄している。 そしてそれゆえに、その試みは決定的に失敗している。 この小説は決して(つまらないという意味で)ナンセンスではない。 読んで感銘を受ける私のような読者がいることが、それを証明している。 しかし、ここで語られたことはやはりナンセンスなのだ。意味をなさないのだ。 では、私たちは一体何に感銘を受けたというのか? おそらく、それはこの小説が「語り得なかったこと」について、であろう。 伊藤計画氏は間違いなく一時代を画する希有な書き手である。夭折が惜しまれる。 付記 誤解のないように(あるいは、さらなる誤解を招くように?)云っておきたい。 世界から「わたし」なるものが消え去っても、相変わらず人間達は自分の一人称を「わたし」と呼ぶだろう。 消え去ったのは、「わたし」という語によって語られている対象としての「わたし」ではなく、その「わたし」を「わたし」と自覚する「わたし」の方である。 それは、もし自分とまったく同じクローンを生み出したとしても、コピーすることのできないような唯一無二の「わたし」であり、実は「わたし」という普通名詞では名指すことのできないような、超越論的なわたしである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私は『虐殺器官』が未読で、読んだことがあるSFと言えば 『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』、『たったひとつの冴えたやり方』、『夏への扉』 等古典的作品ばかりでありますが・・・。 大変高評価であり、また現代において日本人により綴られたSF小説として大分期待していました。 しかし、その期待は悪い意味で裏切られたと言っても過言ではありませんでした。 と言いますのも、日本SF大賞、星雲賞、フィリップ・K・ディック記念賞特別賞等、 最大名誉と言っても過言ではない栄誉を何故受賞し得たのか、 読了した今でも自分の中で納得、消化し切れていないためです。 ゼロ年代ベストSFとも言われる本作ですが、果たしてそうなのだろうか、と。 私は同作品群を殆ど読んでいないため知ったかぶりできないのですが、 日本のゼロ年代におけるSF小説作品はそれほど多く発表されていないのでしょうか? これがベストであると賞賛されるのは、少々残念な思いでなりません。 生命主義や螺旋監察官といった設定、オーグ、知性金属から始まるテクノロジー等、 著者の独創的で先見的な設定には初見唖然とし、次に鳥肌が立ったものですが・・・。 やはり文章の見辛さ(勿論、それは意図的なものであることは間違いありませんが)、 主人公たちのメンヘラ臭さ、所謂厨二病的な思想、 ところどころ見受けられる描写不足であろうシーンの数々、 細かい不自然さ(父親の組織の描かれ方、ミァハが独りに待っていた等)、 あっさりとし過ぎた結末など、どうにも釈然としないのです。 世界観と設定の秀逸さでいえば素晴らしいものがあり、 SFに分類され議論される思想や哲学等普遍的テーマを作者なりに解釈し、 表現した完成された一冊ではあります。 そしてもし、原作のイメージを損なうことなく(それが一番難しいわけですが)映像化されたなら、 どれほど驚嘆にせずにはいられない映像作品ができることか、期待せずにはいられません。 しかし現在に至るまで各分野に多大な影響を与えたSF作品が多数世の中に登場している今、 それだけで果たして数々の受賞理由足りえたのか、私には疑問でなりません。 過去の名作と同じくらい凄い作品である、ということなのかもしれませんが。 だとするならば、やはり上記のような細かい点が尚のこと気になってしまうのです。 つまるところ、「遺作は過大評価されがちである」、という印象が拭えない作品だと感じました。 既にSFというジャンル自体が古典的と見なされるかもしれませんが、 氏の栄誉に甘んじることなく、これからも素晴らしい作品が世に出ることを切に祈ってやみません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 下記のように瑕疵はあるのですが、割り引いても星五つ。一気に読まされました。 1.ミァハはチェチェンで酷い目にあってから、日本に来てトァンに出会う。この時間軸に、微妙に無理押しな感がある。ロシア兵士って、この年齢の子に欲情するかな?とか、銃を口に云々が借りて来たエピソードみたい、とか。日本に来て数年だと、もう少し帰国子女っぽさというか何かありそう、とか。 2.トァンは、双方の陣営に泳がされていたということで、双方の筆頭格のイデオローグと対話を交わすことが出来る。 このうち、特にトァンの父が無防備に出てきて 比較的あっさりと殺されてしまう。双方の陣営が、互いの監視下で泳がせていると、お互いに承知の状態で、トァン父のような立場の人が こういう形で出てきて殺されてしまう事に違和感を感じた。 ああ、もう一冊読みたかったなぁ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008年発表。 34歳で惜しくも夭折してしまった伊藤計劃の最終作にして、幼年期の終り (ハヤカワ文庫 SF (341))、ブラッド・ミュージック (ハヤカワ文庫SF)に次ぐ、新たなる人類の到来を描いた傑作。意識ある私たちは偉業に拍手し、そして合掌しよう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ソーシャルメディア上での人と人の関係性に息苦しくなってませんか?監視されているような気分にめまいがしそうになりませんか?そんな方にうってつけ。文字で書かれた近未来の風景がイメージになって物語を盛り立ててくれると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人間のリソースとしての価値が肥大化され、退廃的な嗜好の排除された閉塞的な世界。それを否定したくて友人2人と自殺を試み失敗した女性。彼女の一人称で語ることで、我々のメンタリティがちょっと極端な影響を受けたらこういう社会に簡単に進むのでは、という理解がしやすいものになっています。 そして、この3人の少女という設定も秀逸です。 ふつうに考えるとストーリーの核は語り手のトァンと唯一自殺に成功したはずのミァハですが、もうひとりの少女、キアンの存在が実は大きいと思います。序盤を読んだ限りでは、ステレオタイプなキアンの描かれ方が瑕に思えたのですが、中盤になってその認識をトァン自身が見直すことによって、ミァハとの対峙ががぜんリアリティを増します。 この辺の少ない描写で人物を印象づける鮮やかさは虐殺器官には見られなかったものだと思います。 ただ、作品の中で問題にされる人間の「意識」は、本来人類が種として持つ非常に大きな概念のはずですが、ときおり「近代的自我」と同じレベルに矮小化されてしまっているのでは、というところが見受けられました。 それがなければよりスケールの大きさを感じられたのに、と思うとちょっと残念です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あらすじなどは他のレビュアーさんが書かれている通りですので省略します。 最初に読了した際は言いようの知れない虚無感に襲われて、食事の時も入浴の時もその理由ばかりを考えていました。何度も繰り返し読み、また「意識」や「私」に関する書籍を購入し理解するうちに、この本が、著者が伝えたいことがなんとなくわかるようになりました。 昨今の小説によく出てくる単語として「空気」があげられます。この作品にもその単語が書かれていますが、著者は「空気」そのものではなく、自分の判断を周囲に委ねてしまっている現代日本人の気質に警鐘を鳴らしているのだと(私は推測し)思います。なんでもかんでも他人任せにしてしまうのは危険です。作中にあるように「つけこまれて」しまうからです。また、SFではとくに宗教と結びつけが強いものですが、この作品はキリスト教が前面に出ています。背後にはケルト神話があります。 それに関連して、人間は「意識」を得る前、つまりキリスト教的に言えば「エデンの園の住人であった頃」は極めて動物的な思考の持ち主でした。「私」はありませんでした。エデンの園は楽園です。つまり作中の〈異端派〉の陰謀の根幹は「意識を失くすことでエデンの園(楽園)に帰り、我々は幸福になる」ということです。作品のラストは意見のわかれるところではありますが、かいつまんで解説するとこのようなことが言えるのではないかと思います。 作品全体に関わる「生命主義社会のわたし」としての個人的な解釈を述べると、 「〈わたし〉は過去の記憶を未来に生かし、より生存と種の保存に適した〈知恵〉を生み出すための受動器官としてある。老い以外で死ななくなったら生存と種の保存という生物の究極的な本質は達成され、極めて恣意的な認識と解釈を行う〈わたし〉は、他者との思想的な摩擦を生み出すだけの存在になる。人間同士の対立は結果的に生存と種の保存という生物的な本質に反すると歴史が証明しているから、〈わたし〉はもはや必要ない」 ということです。 これらを理解したうえでもう一度作品を通して読むと、私はラストに関して「それなら悪くはないのかもしれない」と思うようになりました。トァンがミァハの意見に「異議はない」としたのもわかる気がしますし、また、ミァハが「わたしが無価値であることを証明させて」と叫んだのも、わかります(ここらへんのミァハの主張はさまざまな「意識」に関する書籍を読んでようやくわかりました)。「〈わたし〉の本来的な主体性は脳そのものにある」ということを踏まえてもう一度読むと、また違った面白さが発見できるのかもしれません。 著者の主張は文章だけではとても伝わりにくいと思いました。とはいえ、それも末期癌に冒されながら書いたのだと思うと、このくらいでも十分だと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文庫版をジャケ買いしましたが、その後、こちらもジャケ買い。一人称で語られる物語が好きな方、特におすすめです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本は前作「虐殺器官」と併せて、今の若い世代の人間に是非お勧めしたい物語ですね。 言うなればSF版「ファイト・クラブ」とでも言うべき作品です。 ここに描かれるのは誰もが誰もを想いやり、助け合いして行くのが義務となってしまったディストピアです。 現代にも蔓延しているその偽善的精神の究極的な行く末がこのディストピアだとしたら、その崩壊を描くのが「娯楽」としての正しい在り方だったのかもしれません。 けど、この作品はそうではない。その根っこである「心」や「意識」の存在に疑問を呈する、というとんでもない事をやってのけるのです。 「心」という言葉が、その捉えようの無さと利便性によって現代ではとても良く使われます。 そんな物は存在しない、と鮮やかに言ってのけるこの作品は、かえって今一度私たちに、「心」や「意識」が何であるか、そもそもそんな物は存在するのか、ということを真剣に考えさせる機会をくれます。 「感情」を売り物にしつつ、さも「感情」を崇高な物のように扱ってみせる、そんな恥知らずな世界を蹴り飛ばし、私たちが生きている世界を再認識させてくれる素晴らしい作品です。 SFでは無い、という理由や娯楽では無いという理由でこの作品を毛嫌いする方もありますが、はっきり言ってお門違いです。 お決まりの体裁である物語が読みたければ他のジャンルの作品をどうぞ。 この、伊藤計劃という作家の作品群はどれも、そういった決まりきった体裁が蔓延する世界に疑問を持つ人々へ脱出口を提示する、数少ない作品の一つなのですから。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とにかくテンポが悪くていらいらする。 そして登場人物たちの名前にも何か釈然としないものを感じる。未来ではこんな名前が普通なのか? そりゃさすがにないだろう。 評価が高かったので読んでみたが、期待はずれだった。 ……と思ったんだが、ラストでやられた。 鳥肌がたった。 まさかこんな落としかたをするとは思わなかった。 一生忘れられない小説になりそうです。 途中つまらなくても投げ出さずに、最後まで読んでみることをオススメします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019年の大災禍(前作虐殺器官の出来事で第3次世界大戦相等)後の資本主義社会が医療福祉社会に変わった究極の管理社会いおいてそれぞれの立場(思想・意思)において戦う大人になった少女達の物語。 著者自身影響を受けたであろうアニメ(ナウシカ・甲殻機動隊・エヴァンゲリオン)、文学(志賀直哉・坂口安吾・村上春樹(ねじまき鳥クロニクル))・哲学(ミッシェル・フーコー)等々の作品・作者へのオマージュを文中に散りばめながら大災禍(現代人におけるハルマゲドンや第3次世界大戦相等)後の人類の進化の一つの形を生命第一主義(健康・長寿)や社会に対する個人の意思(意識・魂)を切り口として深く鋭く描いています。 小説として推敲されるべき所も気になりましたが、東日本大震災や核(原子力)の恐ろしさを体験し、今後、更なる試練を経験するかもしれない日本人が如何にハルマゲドン(第3次大戦・大震災)やアセンション(=次元上昇・ニュータイプや人類補完計画的な人類の進化)について自ら深く考え、取り組むべきかのヒントを与えてくれるミステリーのスパイスが効いた優れた小説です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 伊藤計劃「ハーモニー」を読了。作者の「虐殺器官」を非常に興味深く、そして楽しく読ませて頂いたので、購入。本作もジャンル的にはSFなのであろうが、そのリアリティー溢れる描写にノックアウトされました。現実感溢れる、非現実なのです。ここに描かれている世界観は将来きっと訪れるであろうことを予感させます。テクノロジーの発達と人体や生命の関係性は現実味を帯びています。 そしてテクノロジーはその人間の肉体以上のものをコントロールしようとします。そこに世界の調和(ハーモニー)が生まれるのでしょうか。それは調和が訪れた世界なのでしょうか。 エンターテイメントの要素もふんだんにあり、わくわくしながら読み進めることができます。前作に引き続き、傑作SFであることは間違いありません。がしかし、それにしても考えさせられる書でありました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 虐殺器官が殊の外おもしろかったので期待して読んだのですが、はっきりいってがっかりの一言……。 「トァンとキアン、そしてミァハという名の女子高校生3人が、優しすぎる世界に反撃するために自殺を試みるというところから物語は始まる」 この一文を読んで拒否反応を起こす人にはお勧めしませんが、エヴァンゲリオンが好きな人は楽しめるかもしれません。 (ここからは個人的な感想です) 作中にムージルやらボルヘス、フーコーらの名前が出てきますが、彼らの作品を読んでいるという博学多識なミァハという人物が、ただの中二病の少女にしか見えない……。 カリスマ性も特に感じられませんし……。 虐殺器官と違って、残念ながらこの作品には魅力的な登場人物が全くいないなと思いました。 (以下若干ネタバレ) その他、ミァハが率いる異端派のワーキンググループのメンバーが1人(ヴァシロフ)しか登場しないのは如何なものかと……。 少なくとも、あと2、3人は出して欲しかったです。 ミァハに心酔している(ヒトラーを心酔していた将官のような)人物などなど。 ワーキンググループのメンバー以外にも、意識が消滅している状態の人物も登場して欲しかったですね……。 トァンとミァハの会話の場面も、何か動きが欲しくてミァハにステップを踏ませたり、突然両手を叩き合わせて音を鳴らしたりさせたんでしょうけど、もっと上手い表現があったのではないかと……。 ミァハを、会話の最中にステップを踏んだりする人物にしたかったんでしょうか? どうしてもそうは思わないので、この場面はあまりにも酷かったと思います……。 ★2つでもいいんですが、過剰に評価されていると思うので★1つにしておきます。 この作品を楽しめなかった人も多数いると思うので、そういう人はレビューを書いて欲しいです。 故人に対して遠慮してる部分もあるとは思いますが、それと作品の評価は違うんじゃないかと……。 このレビューが、購入を迷っている人の参考になれば嬉しいです。 最後に本音を言うと、これが21世紀の日本のSFを代表する小説ならば、もう日本のSF小説に未来はないなぁ、と思いました。 それくらい、おもしろくなかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| すでに国内では、第40回星雲賞日本長編部門と第30回日本SF大賞を受賞している本作『ハーモニー』。 今年の2011年4月23日には、アメリカのフィリップ・K・ディック賞の審査員特別賞も受賞しました。 日本のSF小説がアメリカの大きな賞を受賞するのは今回が初めてらしいです。すごいですねー。 ちなみにフィリップ・K・ディックとは、映画『ブレードランナー』の下敷きとなった名作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』 の著者として有名なアメリカのSF作家です。 第一級のエンターテインメントでありながら、ごく自然に哲学的要素を織り交ぜた『ハーモニー』は、その神秘性、普遍性において 『アンドロイド〜』と相通じるものがあり、今回の受賞も納得でした。 少々クセのある文体で、しかも近未来めいた謎の記号がたびたび出てくるので、はじめはとっつきにくいかもしれませんが 主人公が幼馴染と再会するあたりから急速に物語が展開し始めます。 すべての終わりを目にしたとき、あなたは「謎の記号」の真の意味を知るでしょう。 とにかくオススメ。SF小説の枠にとどまらない傑作です。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!