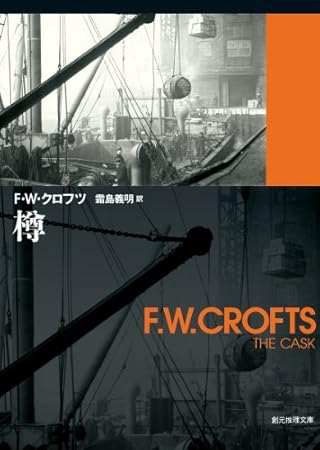■スポンサードリンク
樽
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
樽の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.26pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全47件 21~40 2/3ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 事件が発生して、警察が地道な捜査を行っていきます。 具体的には、関係者の話を聞いて裏を取るなどです。 こう書くとつまらなそうに思えるかもしれませんが、警察が論理的で地に足をつけた捜査を展開するので、読んでいて爽快感すら感じさせます。 捜査の結果、予想外の事実が明らかになるという展開の連続なので、私は一区切りつく度に小休止して、頭の中を整理しながら読んでいました。 地名や人名を理解していないと、途中でついていけなくなるかもしれません。 細かくメモをとると、本書の魅力を十分に堪能できると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 始めから最後までドキドキすることがなく…地味かな?非常に論理的ではあると思います。 矛盾もなきにしもあらずだけど。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 前評判?通り、面白かったです。 天才的な閃きのある刑事や探偵は出てはきませんが、地道に足を使って調べを重ねていく昔気質の警察官と探偵が、とても好感の持てる作品になっていました。 この作品の前に読んでいたのがエラリークイン物だったので、余計に新鮮な気がしました。 ちょっと1度読んだだけでは「樽」の動きが複雑すぎて理解出来かねたので何度か繰り返して読み返すのも楽しいかなと思っています。 とにかくプロットが素晴らしいと思いました。 これから年代順を追ってクロフツ作品を読んでいくのが楽しみです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 翻訳者が友人で気に入って購入した。旧訳がどういうものか比較できませんが、読みやすかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 樽といえばドンキーコング。1989年生まれの私は連想する。樽の中には仲間が入っていたり、樽の中に入って飛んでいったりしながらステージをクリアするゲームに小学生の頃にハマっていた。 シリーズは好評で2作から3作ぐらいを続けてやったような気がする。そんなドンキーコングも驚きの事件がこちら。 樽の中には女性の死体。身元も分からなければ、どこから来たのかもはっきりしない。届け先へは謎の手紙だけが前もって届いていた。 まず、警察が樽を手元に置くまでにもひと悶着あり、やっと死体を見つけると、そこから調査へ。この樽はどこから来たのか。で、中に入っている死体の女性は誰なのか。そこから調査を進めていく。 物語の中で「あといくつ樽を探すことになるのだろうかと訝った」の台詞が出てくるように、読者が飽きてしまいそうになるほど、樽がつきまとってくる。実際、トリックも樽が鍵になっているので、仕方ないのだが、樽、たる、タル。樽を追い求める物語の果てに、古典的な謎解きが待っています。 足の探偵・フレンチ警部を生んだクロフツの処女作らしいのですが、「フレンチ警部」の物語を読んだことがないので、「クロフツさんがいい」とか語るのは出来ません。ただ、人気の古典ミステリーらしく、派手ではない手堅い王道ミステリーといえるでしょう。 トリックのミスもあるようなのですが、それを読みながら考えるのも面白いです。 とりあえず、「フレンチ警部」のミステリーを一作は読もうと思うとともに、もし、ドンキーコングが事件の樽に入ろうとしたらどんな反応をするのかを考えだすとニヤニヤが止まりません。 【手に入れたきっかけ】 Webサービス「本が好き!」の献本サービスで入手! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 正直、何度読んでも(訳が変わっても)、私にはなぜこの作品が推理小説の傑作とされているのか全くもってさっぱりわかりません...。好みの違いなのでしょうか?それだけでは片付けられないような...。いわゆる古典本格推理物(パズラー)が好きになってこれからあれこれ手を伸ばそうとしていらっしゃる方には、私は絶対にお勧めしません。傑作と聞いて期待しても、だらだら長い文章を読まされたあげくガッカリする可能性が高いと思います。あくまで個人の意見ですし、案外こういうのが好きな自分を発見される方もいらっしゃるのかも知れませんが。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 樽を運搬中、荷崩れした樽の中から女性の死体が発見され・・・というお話。 この作品についてはもう多くの人が多くのことを書いて名作、傑作のお墨付きを与えているのでこれから何を行っても屋上屋を架すことになると思うので、あまりいう事はありませんが、今回久々に再読してみてやはり時代や地域を超えて面白い名作であるということを確認しました。 兎に角、徹底したリアリズムにこだわる姿勢に感銘を受けます。最初の方の樽の移動をめぐる足跡の痕跡の綿密な調査、海峡を越えて移動する樽に如何にして死体を入れたかの調査、最後の方で疑われた人物に関する途中から主役になる探偵の徹底的なアリバイ工作の調査等これ以上ないくらい理詰めで読者を圧倒してくれます。クロフツが処女作の時点でその世界を完成させていたのが驚異的に思えました。 それと忘れてはならないのが瀬戸川猛資氏が指摘していたように後のハードボイルド/クライム・ノヴェルにも影響を与えたと思われるアクション・シーンや冷酷な犯人像でハメットやブラック・マスク系の作家も絶対読んで影響を受けていると思います。私見ですが、これがなければ「87分署シリーズ」や「マルティン・ベック・シリーズ」や更には「フレンチ・コネクション」や「太陽にほえろ」もなかったか遅れていたとさえ思います。 今回の新訳版で解説が二つついていて有栖川有栖氏の解説の方で、若干瑕疵があるのを初めて知りました。これは不覚でしたが、本書の価値を下げるものではないと思います。ミステリの名作には若干の欠点があるのは色々ありますので仕方ないと思います(「ホッグ連続殺人」や「Xの悲劇」とか)。 今、2010年代に読んでも面白い作品。ミステリ好きでまだ読んでいない方はこの新訳を機会に是非。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 原題 The Cask 原著1920年刊 旧訳版(大久保康雄訳)以来30年以上ぶりに再読したが、予想を上回る面白さに興奮冷めやらぬままレビューを書いている次第。 ロンドンの波止場で荷下ろしされた樽の中から金貨とともに発見される女の死体…ショッキングな発端、フランスさらにベルギーへとドーヴァー海峡を越えて拡がる捜査網。深まる樽の移動の謎と明快でスリリングな謎解きの妙。そして余りに劇的で波乱に富んだ結末。 とても100年近く前の作品とは思えないアクティブな展開を見せる傑作が新訳によって更に現代的に甦る。 付言すれば本書は日本ミステリにとってとりわけ重要な作品だ。 横溝正史の『蝶々殺人事件』(1947年刊)や鮎川哲也の『黒いトランク』(1956年刊)といった本作にインスパイアされた傑作を生み出し、現在に至るまでアリバイ崩しテーマの日本における隆盛をもたらした影響力、それは言い尽くせない程大きい。 そしてクロフツに刺激され、偉大な作品群を生み出した鮎川哲也の情熱、それと同じミステリへの無私の愛情を巻末の有栖川有栖氏による力の入った熱烈な解説にも感じるのだ。 因みに解説で触れられている鮎川哲也が本作の記述上のミスを指摘した「ヒッチコック・マガジン」での座談会は(横溝正史、鮎川哲也、中島河太郎、田中潤司・・・何という豪華メンバー!)当時の編集長であり司会を務めた小林信彦の著書『東京のドン・キホーテ』(晶文社1976年刊)にも収録されている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| うろ覚えなのだが、ジャズ評論家の寺島靖国氏は「名盤には2種類ある」といい、一つは内容が音楽的にすぐれているもの、もう一つは歴史的な意義のあるもの、といった意味のことをどこかで述べていた。それになぞらえて言うなら本作『樽』は後者で、これが現れた1920年という時期を考えればきわめて斬新、独創的な作品であっただろう思う。だが細部の詰め、完成度という点では後のクロフツ作品からみると「甘い」ところが多く、これをクロフツの最上作というわけにはいかない。クロフツは、『樽』で生み出したこの作風を、その後も(多少の変化はあっても、基本的には)頑ななまでに守り通す。本作が古典的名作と言われるのは、ひとえにクロフツの最初の作品だったから、ということにあるのではないかと思う。 どういうところの詰めが甘いかはネタバレになるから書かないが、興味のある方はぜひクロフツの他の作品と読み比べていただきたい。彼の書く作品はどれも面白い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ミステリーのパイオニアといって良い優れた作品ー樽。これ程、地に足の着いた理に適った推理はお目に描かれません。おそらく,ほとんどの方が手本にしたと思う、アリバイ捜査のバイブルといっても過言ではないでしよう。面白いこと請け合いの大傑作ここにあり。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「探偵小説」というジャンルを切り開いた歴史的作品であるために、内容にケチをつけにくいのだが、これだけのボリュームの本をミスリードするのは忍びがたく、ネタバレにならない程度に正直に感想を書く。 紙数を費やした、もったいぶった筋の展開の割りに、容疑者は中盤で意外とあっさりわかってしまう。それで最後にどんでん返しがあるかと思いきやないので、後半はひたすら「アリバイ崩し」に終始する話になってしまった。地味でたゆまぬ「足の探偵」という評価を否定するつもりはないが、金にものを言わせた捜査も目立つ。証言を得るためにやたら金をばらまき、数千の雇用主全員に回覧状を送るまでやれば、さすがに何か出てくるだろう。最後の犯人の仕掛けが鮮やかだっただけに、もっと往生際が悪くてもよかったと思うが。 古典としての評価は揺るぎないものなので、敢えて辛いコメントをつけたが、発表された1920年という時代を考慮すれば、ドーバー海峡を挟んで二国にまたがる鉄道と船を利用した犯行と「アリバイ崩し」という筋書きは新鮮であったと思われる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品がなければ、日本に溢れるアリバイ崩しものやらトラベルミステリーやらも存在したかどうか、それぐらいこの作品とクロフツの登場は、画期的な出来事だったと思います。 私がこの作品を読んだのは、高校生の時だったのですが、前半の樽から死体が発見されるまでのくだりが長くて、途中で挫折しそうになったのを記憶しています。しかしいよいよ事件が発覚してからの展開は面白く、別の樽の存在が明らかになってくるあたりで読むのがやめられなくなりました。 本作は、オリジナルが持つ特有の魅力を今尚保ち続けている古典ミステリーの一つであり、この作品を題材とした鮎川哲也の「黒いトランク」の本当の面白さを理解するには、本作を読む必要があると思います。 読んだ当時の紫を使った樽のイラストの表紙が好きでした。それが変更になってしまったのが残念です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 現代にはこの作品より複雑なトリックを用いた作品はたくさんある。ただ、あの時代にこの作品が描かれたという点は高く評価すべきだ。クロフツの作品全般に言える事だが、ストーリーの進行が遅く、なかなか進展しないため読んでいて疲れを感じたり、イライラしてしまうかもしれない。そのため、じっくりと腰をすえて読める人でなければ読破出来ないかもしれないが、これがクロフツなんだから、それくらいは覚悟して読むべし | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読了して思ったのは「面白いじゃん、これ!」ってこと。 なんで今まで読めなかったのか。翻訳ってつくづく大事だなあと思いましたね。 加賀山 卓朗さん、ありがとう。 とにかく、地味、テンポが遅い、つまらない、とさんざんなクロフツですが、 この作品に関しては、地道な捜査や人間味のある登場人物が好感でした。 まあ、現代の作品にくらべれば、派手さはありませんが、アリバイ崩しの部分は なかなか読ませました。 大陸と英国を結ぶ船、パリからブリュッセルに至る鉄道の旅。 1920年発行という時代の雰囲気もまた読みどころです。 捜査に関わる警部、弁護士、探偵。 それぞれが、手間を惜しまず、優雅にかつ勤勉に働く様が、とても興味深く描か れてました。 夜中まで会議したり、捜査したりしながら、優雅にカフェやレストランで食事を 楽しんだり。移動方法もまた、荷馬車で荷物を運び、人間はタクシーを利用する、 など時代の変革が感じられて面白かった。 もちろんミステリとしての先駆的役割は知られている通りです。 この「樽」から、事実を一つ一つ検証し、推理を積み上げていく緻密なミステリ が始まったのです。 長年の課題、古典ミステリの傑作が、こんなにも面白く読めて本日は大満足です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| フリーマン・ウィルズ・クロフツの代表作にして、 推理小説の新しい地平を開いたといわれる本書「樽」は、 これまで触手が伸びなかったのですが、 最近ミステリの古典に興味を持つようになったことから、 手が伸び、このたび読み終えました。 これまで読まなかった理由は、 「アリバイ崩し=地味=退屈」 というイメージがあったためですが、 この先入観をものの見事に覆すほどの傑作でした。 「アリバイ崩し」は、確かに出てきますが、 それはこの小説の一要素に過ぎません。 犯人像が絞り込まれていくうちに生じた壁の中に 「アリバイ」があるのであって、 小説の主眼は、 緻密な捜査を行い推理を積み重ねていくことで、 事件の真相が次第に明らかになっていく過程を 描くことにあります。 「地味」という点では、 確かに題名の「樽」からして地味。 しかし、20世紀初頭の当時としては、 一般的な運搬道具であった「樽」という日常性から、 女性の変死体という非日常性が出現する冒頭は、 衝撃的であるし、 「樽」がドーヴァー海峡を行き来していた 不可解さを解いていく過程は、 十分に興味深いものです。 そして「退屈」。 それはこの小説には全く当てはまりません。 樽を追いかけていくうちに、 生じた疑問を複数の探偵が一つ、また一つと解消し、 犯人に迫っていく過程は、 リアルかつスリリング。 次の展開が気になり、 頁を繰る手がもどかしくなること請け合いです。 1920年刊行という年月の隔たりを、 全く感じさせない傑作に巡り合えたことについて、 この上ない喜びを感じます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| かの江戸川乱歩を筆頭に、絶賛以外の評価を目にしたことがない作品だった。推理小説に新機軸をもたらした古典と聞いていた。当然、期待満々で購入し、徹底的に堪能するつもりで、長期出張に1冊だけ携えて出たのだが…。 確かに前半は面白かった。衝撃的な幕開け、現実感のない「神の如き名探偵」ではなく英仏の刑事が互いに連絡を取りながら積み重ねていく地道な捜査、情景描写の妙、読者を翻弄する謎また謎の展開。しかし、後半に入って謎解きが進むに従い、一気に疑問が膨らんでくる。 推理小説の種明かしはルール違反なので詳述は控えるが、重要な手がかりや伏線になるかと思われた内容が、実は単純な偽装だったり、満足な説明がないまま消えてしまったりする。一つだけ言わせてもらうと、筆跡とはそんなに簡単に真似られるものなのだろうか? 謎を解く探偵役の登場も何か唐突で必然性がない気がしたし、激情に駆られて人を殺したはずの犯人が直後に一転して冷徹な策略を巡らせるというのも不自然ではないだろうか。クライマックスも、それまで描かれてきた人物像とはあまりにかけ離れた展開で幕が引かれてしまい、結局最後まで納得がいかないままだった。 一応それなりには楽しめるものの、全体的に見て、特に傑作とも、古典の名に値する作品とも思えない、しかし衆目は「名作」「古典」ということで一致している、自分の感覚はおかしいのか…。読み終えたあと、しばらく悩んでしまった。皆さん、どうなのでしょう? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| クロフツと言えば、鉄道時刻表トリックのアリバイ崩しが有名(らしい)だが、本作は魅惑的な謎と意匠に満ちたミステリの醍醐味が味わえる名作。 冒頭に読者を惹きつける謎を提示し、証言者の話が次々と食い違っていく筋立ても魅力的で、 どのように展開していくかがまったく予測不可能で最後まではらはらしながら読むことができる。 薀蓄が語られたり、描写力が格別すごいわけでもなく、 ひたすら謎の解明に主人公達が挑んでいくストーリーなので飽きがきてしまうかもしれないけど、 推理の手際のよさが無駄なく明晰なので野暮ったくない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ノンフィクションしか最近読んでいなかったのだが、急に推理小説が読みたくなって手に取った本。 読んでびっくりで、こんなに精緻に人を陥れる計略がめぐらされた推理小説は見たことがない。これを一人の頭の中で考え出せるということ自体がすばらしいこと。古典的名著といわれるのは納得。クロフツすごいぞと伝えたくなる一冊。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者の代表作であると共に、ミステリ黄金時代のアリバイ崩し物の代表作。当時、最も構成美を誇っていたヴァン・ダインの「グリーン家」を上回る構成と賞賛を浴びた。作中、センセーショナルなのは冒頭の船着場の死体出現場面だけで、後はひたすらアリバイ崩しである。作者の前歴は鉄道技師で、そのため鉄道を使ったアリバイ・トリックが多いのだが、イギリスという地理的条件から、英仏海峡を跨いだ作品も多い(「英仏海峡の謎」という作品もある)。クロフツの影響を受けた日本の代表的作家は鮎川哲也氏だろう。 クロフツはクィーン等と異なり華麗なトリックこそないが、とにかく手堅い。本作は、クロフツが練りに練ったアリバイ・トリックを披露したもので、私も樽が一つのうちは謎解きについて行こうと思ったのだが、樽が二つ存在することが分かった時点で追うのを諦めた。まさしく精緻な構想である。 ミステリの黄金期を飾るアリバイ・トリック物で、後世に大きな影響を与えた名作。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 奇抜なトリックやよけいな情景描写は無用、ただただ自分も一緒に推理することに喜びを感じる、という人ならば間違いなく十指に入る傑作と思うはず。「推理小説は二度読んで本当の良さがわかる」と言われるが、本当に二度読もうと言う気になる作品はなかなかないのが本当のところ。「樽」なら確かに二度目も十分に面白い。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!