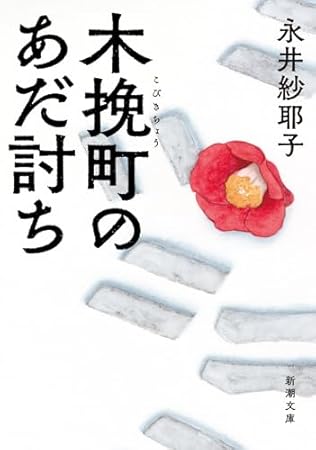■スポンサードリンク
木挽町のあだ討ち
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
木挽町のあだ討ちの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.26pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全124件 1~20 1/7ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 後半に思いがけない展開が新鮮!それぞれの登場人物が魅力的。山本周五郎賞、確かに。人情の機微、心に残る。なかなか楽しませてもらい、味わい深かった。 映画は俳優が魅力的だが自分の想像力を越えた映画は過去一件だけだったので観るのを迷っている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「芝居茶屋の場」の途中で挫けた。ダラダラと身の上話。話が盛り上がらない。映画を観て面白ければ、もう一度読み直しします。小説で初めての途中放棄。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読みやすい。 どんどん引き込まれて、あっという間にラストだった。 読了後のスッキリ感がなんともいえない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| こんな切り口もあるんだなぁと感心しました!良い読後感に感謝。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作り物の首を作る職人の登場の時点でオチが想像できてしまう。物語自体にも深みはない。私にはどうしても良い作品には思えない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 二年ほど前図書館で借りて読み、歌舞伎座で新作歌舞伎として上映した時も観劇して、また読みたくなり、文庫化されたので購入し、一気に読みました。面白く、江戸時代の歌舞伎の様子も知れ、また歌舞伎界で働く人々の人情に打たれました。映画化の噂も聞きますが、歌舞伎座で再演を望みます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年上期直木賞受賞作である。著者は、観劇好きとのことで、本作も章ではなく、6幕で構成され、6人が一人称で話を展開する。落語か一人芝居を読んでいるようだ。6人が夫々の生い立ちなどを語り、人の業を語り尽くす。本作は、山本周五郎賞も受賞しているが、山本周五郎のような社会問題に対する目線よりも、藤沢周平のような時代劇を通した武士、人の業の深みを感じさせる作品かと思う。 2026年2月末映画化とのことである。こちらも楽しみですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今回はaoudibleで聴きました。 正直いって、本を読むのが苦手で、2,3ページくらいで寝落ちしてしまうので。 この作品は出版当時、神田松之丞(現・神田伯山)がラジオで紹介していて、興味を持っていまして、aoudibleになるのを待っていました。 子どものころは、時代劇のテレビを観ていました(大江戸捜査網、用なし犬、子連れ狼あたり)が、 時代小説は35年前の大菩薩峠、花神くらいしか読んだことがありません。 最近の作品は叙述トリックという読者をだますような作風が多いと聞いています。これもそのひとつでしょうか。面白いですね。 やりたくない仇討ちだが、話の流れからして敵役が自ら斬られにいくだろうというところは誰しも予想できるでしょうけど。 最後に、すべての伏線回収とさらなる展開がありました。 かなり時代小説を読む人の中には、昔の作品の焼き直しだと評される方もいますが。 たまには時代小説でも読んでみようかな、という人にお勧めだと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 筋書きが凝りすぎ 結末が雑い | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 面白い登場人物の構成と喋り言葉での文章で、仇討を果たす人物が主人公で物語が展開するのかと思ったらーーー | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作家さんは知りませんでしたが 好きな作家さんが監督と脚本をするので映画の方が楽しみです。 その前に原作のこの小説も読んでみます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中編の物語ですが、時代劇の形をしていますが完全な時代劇ではなく、人情物語だね、映画を見る前に読んでおけば映画を楽しむことが出来ますね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| つまらなかった。 とても楽しみにしていて、本屋で文庫化されたのをみて購入して…つまらないな、いつおもしろくなるんだろう… と我慢しながら、なんとか読了。 ご都合主義で、どこかで見たような聞いたような話。本当におもしろい小説、感動する小説に最近なかなかであえない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人間同士の思いやりがみんなの幸せを作ると思います | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み終えてしみじみとわかる、タイトルの秀逸さ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| That`s entertainment!面白かった‼ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎にもなった原作 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読んで見たいと注文しましたが残念ですが 興味か惹かれずなかなか進みません 私だけかもしれませんが… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 仇討ち1件でここまでストーリー展開が広がることにアッパレ! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 浅田次郎のようなモノローグだが,読み続けるうちに疲れた。期待をしていただけにちょっと残念。物語の構成は良かったが、ちょっとダラダラした感じを受けた。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!