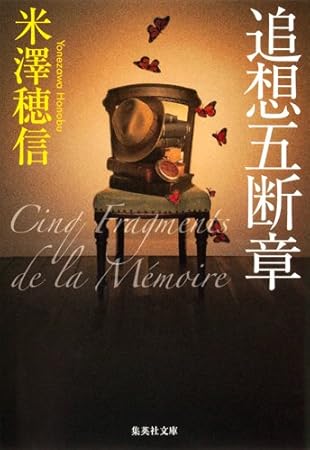■スポンサードリンク
追想五断章
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
追想五断章の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.75pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全96件 81~96 5/5ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公は、バブル崩壊の煽りで大学を去った青年。故郷に戻る気が起こらず、東京にしがみつくために伯父の経営する古書店に居候しています。主人公は、ある日古書店を訪れた女性から、無名の著者の手による5つの小説を探してほしいとの依頼を受けます。5つの小説はいずれも結末の曖昧なリドルストーリーで、女性は、5つの結末部分だけを持っていて...... 主人公は女性の依頼を受け、かすかな手がかりを頼りに関係者を訪ね歩き、誰にも紐解かれることなかった書物を探り当てていきます。そのパズル自体の「仕掛け」はたやすく見抜けますが、着想はなかなか類をみないものです。そして中盤以降は、リドルストーリーの謎を牽引車として、ある人物が書き残した文章を頼りに、その人物を「追想」するという行為そのものが主題となっていきます。そこに漂う切なさ、息苦しさは、前半がパズル的な展開を予期させるだけに不意打ちのように心を揺さぶります。「探偵」役である主人公や、その周囲の人々も、しっかりと意味を持ってこの物語を構成する大切な要素となっています。 そして、パズルを組み立てる旅は、なぜ5つの掌編が書かれなければならなかったのか、という謎解きへと着地します。この物語には、自らの足で人を訪ね、話し、探し当てた古ぼけた書物の頁を捲るという行為がふさわしいです。携帯電話とインターネットが普及した現在を舞台にしたなら、まったく別の顔つきの物語になったでしょう。1990年代前半は、日本でそうした物語が自然に成立する最後の刹那だったのかもしれません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公は、バブル崩壊の煽りで大学を去った青年。故郷に戻る気が起こらず、東京にしがみつくために伯父の経営する古書店に居候しています。主人公は、ある日古書店を訪れた女性から、無名の著者の手による5つの小説を探してほしいとの依頼を受けます。5つの小説はいずれも結末の曖昧なリドルストーリーで、女性は、5つの結末部分だけを持っていて...... 主人公は女性の依頼を受け、かすかな手がかりを頼りに関係者を訪ね歩き、誰にも紐解かれることなかった書物を探り当てていきます。そのパズル自体の「仕掛け」はたやすく見抜けますが、着想はなかなか類をみないものです。そして中盤以降は、リドルストーリーの謎を牽引車として、ある人物が書き残した文章を頼りに、その人物を「追想」するという行為そのものが主題となっていきます。そこに漂う切なさ、息苦しさは、前半がパズル的な展開を予期させるだけに不意打ちのように心を揺さぶります。「探偵」役である主人公や、その周囲の人々も、しっかりと意味を持ってこの物語を構成する大切な要素となっています。 そして、パズルを組み立てる旅は、なぜ5つの掌編が書かれなければならなかったのか、という謎解きへと着地します。この物語には、自らの足で人を訪ね、話し、探し当てた古ぼけた書物の頁を捲るという行為がふさわしいです。携帯電話とインターネットが普及した現在を舞台にしたなら、まったく別の顔つきの物語になったでしょう。1990年代前半は、日本でそうした物語が自然に成立する最後の刹那だったのかもしれません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| このミス4位という事で初めて米澤穂信を読みましたが、想像以上に良かったです。 主人公は決して魅力的とは言えませんが、人物の魅力よりも、1話1話のリドルストーリーの出来が秀逸で、それだけでも この作品を読む価値はあるのではないでしょうか? ミステリーというカテゴリよりも、一つの短編小説集として完成した作品だと思います。 結末も悲しくはありますが、決して期待を裏切らない暖かい気分にさせてくれるメッセージが詰まっていて余韻を楽しめます。 血眼になって犯人捜しをするミステリーばかりがミステリーではないと納得させてくれる作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| このミス4位という事で初めて米澤穂信を読みましたが、想像以上に良かったです。 主人公は決して魅力的とは言えませんが、人物の魅力よりも、1話1話のリドルストーリーの出来が秀逸で、それだけでも この作品を読む価値はあるのではないでしょうか? ミステリーというカテゴリよりも、一つの短編小説集として完成した作品だと思います。 結末も悲しくはありますが、決して期待を裏切らない暖かい気分にさせてくれるメッセージが詰まっていて余韻を楽しめます。 血眼になって犯人捜しをするミステリーばかりがミステリーではないと納得させてくれる作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本の雑誌『ダ・ヴィンチ』の’09年11月号で「絶対はずさない!プラチナ本」として紹介された“青春小説の旗手”米澤穂信が“青春後”を描いたミステリー。初出の『小説すばる』’08年6月号から12月号まで連載されたものに加筆修正が施されている。 事情があって大学を休学中で、伯父の古書店で居候のアルバイトをしている芳光は、ある女性から頼まれ、彼女の亡くなった父親が書いた短編5編を探すことに。探して欲しい短編はみな、結末が伏せられたリドル・ストーリーとなっているという。調べて次々と発見するうち芳光は、22年前の「アントワープの銃声」という、かの地で日本人女性が死んだ事件のことを知るのだが・・・。 彼が出会うリドル・ストーリーの登場人物やその背景に見え隠れするドラマ。そして最後に突き当たる真相・・・。その作中作を織り交ぜた、謎解きの興味に満ちた構成の妙にただただ圧倒される。最後まで読んで、あらためて序章を読み返すと理解が一層深まる仕組みになっている。 それにしても本書は、平成4年というバブル崩壊後のやるせない時代に生きる芳光といい、やむにやまれず5編の短編を書いた父親の意図とその煩悶といい、22年前の事件にかかわった父親と娘の悲劇といい、読後にいつまでも哀しみの余韻が残る本格ミステリーである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本の雑誌『ダ・ヴィンチ』の’09年11月号で「絶対はずさない!プラチナ本」として紹介された“青春小説の旗手”米澤穂信が“青春後”を描いたミステリー。初出の『小説すばる』’08年6月号から12月号まで連載されたものに加筆修正が施されている。 事情があって大学を休学中で、伯父の古書店で居候のアルバイトをしている芳光は、ある女性から頼まれ、彼女の亡くなった父親が書いた短編5編を探すことに。探して欲しい短編はみな、結末が伏せられたリドル・ストーリーとなっているという。調べて次々と発見するうち芳光は、22年前の「アントワープの銃声」という、かの地で日本人女性が死んだ事件のことを知るのだが・・・。 彼が出会うリドル・ストーリーの登場人物やその背景に見え隠れするドラマ。そして最後に突き当たる真相・・・。その作中作を織り交ぜた、謎解きの興味に満ちた構成の妙にただただ圧倒される。最後まで読んで、あらためて序章を読み返すと理解が一層深まる仕組みになっている。 それにしても本書は、平成4年というバブル崩壊後のやるせない時代に生きる芳光といい、やむにやまれず5編の短編を書いた父親の意図とその煩悶といい、22年前の事件にかかわった父親と娘の悲劇といい、読後にいつまでも哀しみの余韻が残る本格ミステリーである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公にまったく魅力がありません。 帯には「青春去りし後の人間を描く」とありますが、青春去りし、どころか、生活に疲れてうらぶれた中年男のように、ひどくくすんだキャラクタです。 せちがらい現実の風にふかれて、閉塞状況をどうすることもできず、おそらくはこのまま負け犬で一生を終わるであろう主人公に、どう共感すればよいのでしょうか? もちろん、このような作風が好きな人もいるのでしょう。 これこそが、まさしくリアリティというものである、とありがたがる人もいるのでしょう。 残念ながら私はそうではありません。 「インシテミル」あたりから、作者は大きく変化しているように思えます。 もともとそんなに単純な登場人物を描かない人でしたが、おそらく、今まで描いた人物ですら、単純すぎて飽き足らなくなった、ということでしょう。 どんどん、歪んだ人間、現実に存在する複雑な人間、色合いの濁った人間、といったものを描こうとしているように見えます。 むろん、読者には、作者の変貌を止める権利などありません。 変わっていく作者の後姿を、淋しく見守るばかりです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公にまったく魅力がありません。 帯には「青春去りし後の人間を描く」とありますが、青春去りし、どころか、生活に疲れてうらぶれた中年男のように、ひどくくすんだキャラクタです。 せちがらい現実の風にふかれて、閉塞状況をどうすることもできず、おそらくはこのまま負け犬で一生を終わるであろう主人公に、どう共感すればよいのでしょうか? もちろん、このような作風が好きな人もいるのでしょう。 これこそが、まさしくリアリティというものである、とありがたがる人もいるのでしょう。 残念ながら私はそうではありません。 「インシテミル」あたりから、作者は大きく変化しているように思えます。 もともとそんなに単純な登場人物を描かない人でしたが、おそらく、今まで描いた人物ですら、単純すぎて飽き足らなくなった、ということでしょう。 どんどん、歪んだ人間、現実に存在する複雑な人間、色合いの濁った人間、といったものを描こうとしているように見えます。 むろん、読者には、作者の変貌を止める権利などありません。 変わっていく作者の後姿を、淋しく見守るばかりです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 伯父の古書店で居候兼店番をしている主人公は、父親の書いた小説を探しているという女性からの依頼を受けて、結末がわからない五つの物語を探し始めます。探していくうちに明らかになる謎とその真実。短編とその結末に22年前の事件がからみ、複雑ですが面白い。 米澤さんはロストジェネレーション(氷河期世代)なんですね。夢もなければ希望もない。救いもない。こうして謎を解いても残るのは苦い思いだけ。 それなのにどこか一筋の希望が見える気がして、読後感はかなりよかったです。 米澤ファンとしては満足のいく一冊でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 伯父の古書店で居候兼店番をしている主人公は、父親の書いた小説を探しているという女性からの依頼を受けて、結末がわからない五つの物語を探し始めます。探していくうちに明らかになる謎とその真実。短編とその結末に22年前の事件がからみ、複雑ですが面白い。 米澤さんはロストジェネレーション(氷河期世代)なんですね。夢もなければ希望もない。救いもない。こうして謎を解いても残るのは苦い思いだけ。 それなのにどこか一筋の希望が見える気がして、読後感はかなりよかったです。 米澤ファンとしては満足のいく一冊でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いやあ、良かった。 期待通りだった。 米澤穂信はおもいっきりミステリーマニアと思ってます。 なのでミステリーファンの期待を裏切りません。 依頼人の亡くなった父の書いた5つの小説を探して物語が進むのですが、 22年前の事件が絡んできて、 見つかった小説を読むと色々と想像できて、 なんともワクワクです。 しかも、見つかる小説が全てリドルストーリーなんですよ。 リドルストーリーとは最後の結末が書かれていないのです。 最後の結末を書くと蛇足になったりして面白くない場合などに しばしば使われます。 今回は、別に父が5つの結末を残していて、 小説が見つかるたびに、それを付け足して読んでみて、 なぜ、リドルストーリーにする必要があったのか なぜ、この結末なのか などを考えながら、謎解きをやるんですよ。 そこが良かった。 色々想像できた。 最後はなんというか、 悲しい気持ちになったけど、 それをリドルストーリー5つで描いた父の気持ちは ものすごく大切な宝物でした。 去年の「」の最後の一行の魔術といい。 今回のリドルストーリーといい、 期待を裏切らない手法に満足です | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いやあ、良かった。 期待通りだった。 米澤穂信はおもいっきりミステリーマニアと思ってます。 なのでミステリーファンの期待を裏切りません。 依頼人の亡くなった父の書いた5つの小説を探して物語が進むのですが、 22年前の事件が絡んできて、 見つかった小説を読むと色々と想像できて、 なんともワクワクです。 しかも、見つかる小説が全てリドルストーリーなんですよ。 リドルストーリーとは最後の結末が書かれていないのです。 最後の結末を書くと蛇足になったりして面白くない場合などに しばしば使われます。 今回は、別に父が5つの結末を残していて、 小説が見つかるたびに、それを付け足して読んでみて、 なぜ、リドルストーリーにする必要があったのか なぜ、この結末なのか などを考えながら、謎解きをやるんですよ。 そこが良かった。 色々想像できた。 最後はなんというか、 悲しい気持ちになったけど、 それをリドルストーリー5つで描いた父の気持ちは ものすごく大切な宝物でした。 去年の「儚い羊たちの祝宴」の最後の一行の魔術といい。 今回のリドルストーリーといい、 期待を裏切らない手法に満足です | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 伯父が経営する古書店でバイトしている主人公はある日、女性に叶黒白という筆名の人物が書いた小説が載っている雑誌を売ってほしいと頼まれる。その雑誌を見つけたのがきっかけで、追加の依頼が。 叶黒白の作品は全部で5篇、その残り4篇を探してほしい。報酬は1篇10万。 女性が探しているのは亡き父親が書いた小説だった。 5篇の小説は全て結末を書かないリドル・ストーリー。そして女性は、その結末を全て持っているという。 なぜ女性は父親の小説を探すのか、父親はなぜ作家でもないのにある時期リドル・ストーリーを5篇書き、そして知人達に送ったのか。 残りの小説を探す主人公はやがて22年前の「アントワープの銃声」という事件を知る―― 主人公が今までの作品の雰囲気、特に「古典部」や「小市民」と違うので面食らいました。青春ミステリの、あの掛け合いはありません。どちらかというと重苦しい。個性的なキャラなどが活躍するタイプの話が好きな方には合わないと思います。あの諦念や絶望感は『ボトルネック』などとも少し違いますし。『さよなら妖精』とかが好きな人なら合うのではないでしょうか? ともあれ、ぐいぐいと引き込む雰囲気や構成は流石としかいえません。 個人的には、作中作である叶黒白の作品の文章は辞書をひかないと意味が分からない言葉があった為、そこでペースダウンしてしまいました。 気になったのは時代設定。主人公のいる現在はどうも平成四年。人物の背景にはその時代ならではのことが起っていますし、インターネットや携帯電話を使うシーンはありません。何か意図があってのことなのでしょうか。それともただの設定なのでしょうか。 面白かったのですが、やや消化不良。この作品自体もリドル・ストーリーなどではないのかと疑ってしまったのですが…… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 伯父が経営する古書店でバイトしている主人公はある日、女性に叶黒白という筆名の人物が書いた小説が載っている雑誌を売ってほしいと頼まれる。その雑誌を見つけたのがきっかけで、追加の依頼が。 叶黒白の作品は全部で5篇、その残り4篇を探してほしい。報酬は1篇10万。 女性が探しているのは亡き父親が書いた小説だった。 5篇の小説は全て結末を書かないリドル・ストーリー。そして女性は、その結末を全て持っているという。 なぜ女性は父親の小説を探すのか、父親はなぜ作家でもないのにある時期リドル・ストーリーを5篇書き、そして知人達に送ったのか。 残りの小説を探す主人公はやがて22年前の「アントワープの銃声」という事件を知る―― 主人公が今までの作品の雰囲気、特に「古典部」や「小市民」と違うので面食らいました。青春ミステリの、あの掛け合いはありません。どちらかというと重苦しい。個性的なキャラなどが活躍するタイプの話が好きな方には合わないと思います。あの諦念や絶望感は『ボトルネック』などとも少し違いますし。『さよなら妖精』とかが好きな人なら合うのではないでしょうか? ともあれ、ぐいぐいと引き込む雰囲気や構成は流石としかいえません。 個人的には、作中作である叶黒白の作品の文章は辞書をひかないと意味が分からない言葉があった為、そこでペースダウンしてしまいました。 気になったのは時代設定。主人公のいる現在はどうも平成四年。人物の背景にはその時代ならではのことが起っていますし、インターネットや携帯電話を使うシーンはありません。何か意図があってのことなのでしょうか。それともただの設定なのでしょうか。 面白かったのですが、やや消化不良。この作品自体もリドル・ストーリーなどではないのかと疑ってしまったのですが…… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 家庭の事情で大学を休学し、伯父の古書店に住みこみで働いている芳光は、 松本から来た可南子という女性の依頼で、彼女の父が生前に書いた五篇の リドルストーリーを探すことになる。 やがて芳光は、二十二年前の、ある未解決事件の存在を知り……。 五篇のリドルストーリー(結末を書かない物語) が作中作として収められた入れ子構造の本作。 可南子のもとには、それぞれの小説の結末に当たる「最後の一行」が遺されて おり、小説が発見されるごとに、対応する結末が付されていくことになります。 それにしても、可南子の父は、リドルストーリーという形式で小説 を書いたにもかかわらず、なぜ結末を別に遺していたのでしょうか? その謎を解く過程で、芳光は、それぞれ独立している五篇の小説から共通項を抽出し、 それらと二十二年前の未解決事件との間に、どのような照応関係があるかを、手紙や 雑誌記事といった「残されたテキスト」を参照することによって、読み解いていきます。 そういった意味で本作は、過去に埋もれたを追及する暗号ミステリなのですが、 扱われているのは、米澤さんが言うところの 〈虚空に放つような暗号〉です。つまり「読まれてはならない」 「でも、読んでほしい」という作成者の撞着が、暗号に反映されているわけです。 謎の中心となる過去の事件が単純で、その演出にも外連味がないのが、よくも悪くも 米澤流なのですが、二者択一を迫る五篇のリドルストーリーとその結末を再構成する ことによって、語られなかった真実をおぼろに浮かび上がらせる本作の清新な手法は、 高く評価されるべきだと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 家庭の事情で大学を休学し、伯父の古書店に住みこみで働いている芳光は、 松本から来た可南子という女性の依頼で、彼女の父が生前に書いた五篇の リドルストーリーを探すことになる。 やがて芳光は、二十二年前の、ある未解決事件の存在を知り……。 五篇のリドルストーリー(結末を書かない物語) が作中作として収められた入れ子構造の本作。 可南子のもとには、それぞれの小説の結末に当たる「最後の一行」が遺されて おり、小説が発見されるごとに、対応する結末が付されていくことになります。 それにしても、可南子の父は、リドルストーリーという形式で小説 を書いたにもかかわらず、なぜ結末を別に遺していたのでしょうか? その謎を解く過程で、芳光は、それぞれ独立している五篇の小説から共通項を抽出し、 それらと二十二年前の未解決事件との間に、どのような照応関係があるかを、手紙や 雑誌記事といった「残されたテキスト」を参照することによって、読み解いていきます。 そういった意味で本作は、過去に埋もれた《スリーピング・マーダー》を追及する暗号ミステリなのですが、 扱われているのは、米澤さんが言うところの 〈虚空に放つような暗号〉です。つまり「読まれてはならない」 「でも、読んでほしい」という作成者の撞着が、暗号に反映されているわけです。 謎の中心となる過去の事件が単純で、その演出にも外連味がないのが、良くも悪くも 米澤流なのですが、二者択一を迫る五篇のリドルストーリーとその結末を再構成する ことによって、語られなかった真実をおぼろに浮かび上がらせる本作の清新な手法は、 高く評価されるべきだと思います。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!