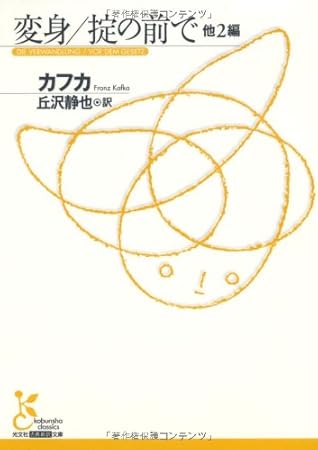■スポンサードリンク
変身
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
変身の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.08pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全390件 21~40 2/20ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| シンプルで読みやすい。でもカフカがギュッと詰まってる。はじめの一冊がこれならカフカを好きになるんじゃない? 学生におすすめ。星新一が好きな人にも。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 訳者「川島 隆」さんによる本書文庫版『変身』の人気はすごい。 令和4年の初版なのに、なんと一年後の令和5年には第6版。 この人気の理由は、何でしょう? 『変身』のドイツ語原作は、1912年。 今年は2023年ですから、111年も前の古い小説です。 読み古された物語なのに、今なお生きています。 本書103頁から始まる「訳者解説」に注目して、人気と長生きの秘密を探りました。 「『この小説に解説は必要ない』と言って解説を終わらせるのが、本当は一番妥当なこと」(105頁) と言いながら、71頁にも及ぶ、長文の詳しい「訳者解説」を本書に綴る訳者の川島さん。 いくつかの先行翻訳はもちろん、ナボコフの意見や多数の英訳まで参照した解説です。 最後の圧巻は、川島さん自身が翻訳のときに参照した既訳との比較検討結果です。 訳語の選択や文意の取り方が難しかった点などについて、解説しています。 文学研究者ならでは、の詳細解説になっています。 解説の見出しのみ列記してみましょう。 ① 虫けら ② 出張の多いセールスマン ③ 絵と写真 ④ 神と悪魔 ⑤ 体験話法 ⑥ 業務代理人 ⑦ メイド、料理女、派遣家政婦 ⑧ ザムザ家の間取り ⑨ 人間と動物の境界線 ⑩ 家族の物語の「ハッピーエンド」 この訳者解説を読んでみると、完璧な書評にもなっています。 本書が歓迎される理由の一つがここにあるのでしょう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 100分de名著で絶賛されていた為、試しに購入。主人公や家族や間借り人、家政婦など問題に対する視点がグルグルと移動させられる感覚が面白かった。 しかしテレビでは全てオチまで放送していたので、単にあらすじの確認作業となってしまった(笑)古典なのでオチまで言ってもいっかとの判断になったのだろう。本が売れない時代なので、オチまで言う紹介のしかたでも俺は許す! その点で、数ある「変身」の中で本書を選んで良かったと思ったのは、本編と同じくらいの分量で解説が書かれていたところだ。いまだかつて解説にこれほどバカ長いページ数を割く小説は出会ったことが無い! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| "掟の前に門番が立っていた。この門番のところに男がやってきて掟のなかに入れてくれと頼んだ。だが門番は言った。まだ入れてやるわけにはいかんな。"2007年発刊の本書はくり返しを意識的に残して翻訳したカフカ傑作4編。 個人にカフカ好き。と言うこともあって久しぶりに手にとりました。 さて、そんな本書はドイツ文学者が"少ないボキャブラリーで書き、散文を強く歌わせるために、くり返しを多用した"カフカを意識して翻訳したもので、あまりに有名なある日、突然虫になった男の視点から"家族"を描き『百年の孤独』のガルシア・マルケスにも影響を与えた『変身』カフカ作品としては最も言及、引用されるわずか1ページ半の短い作品『掟の前で』"ぼく"がサルだったときのことを報告する『アカデミーで報告する』そしてひと晩で書きあげられた息子と父親の対話『判決』の4編が収録されているわけですが。 いやあ。若い時に手にした時は不条理な展開に挫折したものですが。年を重ねてから読み直すと、ビジネスパーソンとして『終生サラリーマン作家』とだったカフカへの親近感も生じているからか、それぞれの作品を【どのような心境で書いたのか】思いを馳せつつ、流れるような新訳を楽しませていただきました。 また、4編の中では特に『掟の前で』を別の著者が引用しているのを見て久しぶりに読んだのですが。この短い作品。何度読み返しても【暗喩的なじわじわ感があって】やっぱり好きだな。とあらためて。 読みやすいカフカの入り口的一冊として全ての人にオススメ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカの作品たち(変身だけでなく、審判、城、流刑地にて・・・、判決、などなど)が凄いのは、読むことで世界の見え方を一変させる効果を持っているところにある。世界の見え方が変わったところで別に日常生活にアドバンテージができるというわけではない。ただ毎日を過ごす中で、いたるところに「カフカっぽさ」を発見するようになるのである。日常のシチュエーションだけでなく、自分の感情や読む本や観る映画にも「カフカっぽさ」はたびたび出てくる。つまりカフカは、これらの作品群で、この現実世界に確かに存在するある種の(不可解な)現象を、「カフカ的」と呼ばれるほど初めて上手に切り取ったのである。こんな芸当ができる人間は滅多にいないだろう。その点でカフカは唯一無二なのである。 彼の作品群が不完全に見えるのは仕方ないことだと思う。カフカ的というのはごく簡単にいうと「到達できない」とかそんな風にも言えそうだからである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本編ももちろんですが、あとがきが面白かったです。カフカの人生を知ることで、本編の捉え方や矛盾点の背景がわかるようになりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 面白い | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「ある朝起きると自分が毒虫になっている。」というショッキングな始まりは、余りにも有名。 外面が変わっても、家族愛や将来を心配する内面は全く変わっていない。 変わったのは自分か?周囲の人間か? 人が信じる「常識」というものの不安定さを鋭く描く。 最後に死を選択した主人公が、多数派が正しいと安易に決めつける現代における犠牲者を象徴しているように思える。 そして、何時、自分が「毒虫」側になるか分からない危険も。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ドグラ・マグラとは、違いますが考えようとすれば理解しようとすればするほどいろいろな考え方や解釈ができるそんな本でした。 内容も、長い本ではないので読みやすいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 汚れが多く、読んでいて少し気になります。 商品説明に記入してほしかった | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公グレーゴルが、ある朝起きたら「虫」の姿になってしまい、家族との関係や、家族のグレーゴルに対する感情が激変してしまう、という物語。 初読の際の感想は、グレーゴルが「虫」になったことで、家族(父、母、妹)のグレーゴルに対する感情が激変してしまう様子の冷たさ・残酷さに慄いたというものだった。 しかし再読してみると、もう少し俯瞰で見える構成のようなものがあるように思えた。 グレーゴルは元々(人間の姿の時)、家族の借金の返済のため、上司との人間関係が息苦しいような勤めたくない職場で勤務していた。 つまり人間の姿の頃のグレーゴルは、家族のために我慢し、職場の上司を相手に我慢しと、自分を押し殺して生きていたことが伺える。 そんなグレーゴルは、「虫」になると「虫」の本能に侵食されてか、我慢というものができなくなっていく。 まだ思考力は残っており頭では家族に気を遣い遠慮する必要があると考えながらも、自分の振る舞いたいように振る舞うことを抑えられなくなるのだ。 つまり、グレーゴル自身の周囲に対する感情が変わっていくのだ。 グレーゴルが変わったのは姿だけではなく、それを契機に心が「変身」し、周囲に無関心になっていく。 対して家族の「心の変身」は、グレーゴルと真逆に対置される。 父も母も妹もかつては比較的気ままに過ごしていたことが伺えるのだが、グレーゴルが「虫」になったことで、「耐える」ことを強いられるようになる。 それはあたかも、人間の姿であった頃のグレーゴルの心情そのものだ。 家族は最後、「虫」のグレーゴルから解放されるが、その際に互いに示し合う安堵の様子は「耐え」の苦しさが如何程のものであったかを彷彿させる。 そしてその彷彿はそのまま、人間の姿だった頃のグレーゴルの心情の苦しさを推量させるものとなっている。 このように本作は、「虫」になることで他人に無関心で欲に抗わない性格に「変身」するグレーゴルと、「虫」の登場から「耐え」に転落する家族という、ある意味心情面の立場が入れ替わるという対比構造から成り立っているように感じられた。 人間の感情の多くは他者との関係、つまり人間関係に由来しており、人間関係の悩みが人間にとっての大きな苦しみの1つであるという主題が浮かび上がってくるようだ。 これは、カフカ自身の苦しみの本質だったのかもしれない。 本作をグレーゴルの「心情の変身(自分本位になる)」と読み、グレーゴルの成れの果てを見るならば、昨今自己啓発界を席巻する「他人のことなんて気にしないで自分のことだけ大切にすれば楽で幸せ」的な教条は、「虫」になることを唆す蠱惑なのかもしれない・・。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ある朝、起きてみると巨大な虫に変身してしまっていたグレーゴル・ザムザのお話。非常に有名な作品を読み返してみて、2つのことが気になった。 1つ目は、変身直前にグレーゴルが「不安な夢」を見ていたということ。本作でいう「変身」とは別人へと「変化」するような生易しい事態ではなく、表面上、全く別の存在へと置き換わってしまった、そしてそれは取り返しがつかない事態だった、ということである。読者諸君だって、これから夜眠って、不安な夢を見た次の日に人間じゃなくなっている可能性がゼロだと言い切れるだろうか?それをどうやって証明すればいいんだろう・・・?そんな風に考えていると妙に不安な気持ちになってくるものだが、この種の不安がグレーゴルが見た夢の不安と重なっているような気がした。 2つ目は、変身直後のグレーゴルはまだ中身が人間そのものだったのに、彼の変身ぶりにうまく適応できない家族とともに生活しているうちに、徐々に中身が虫そのものになっていったということ。別の存在に置き換わってしまったといっても、あくまでもそれは表面上だけのお話だった。のではなく、やっぱり中身だってゆっくりと変わっていったのだ。「見た目は虫でも、中身は人間」だったのが、正真正銘の虫に変身してしまう。こういう事態を目の当たりにすると、生命の中身(本質)なんて、最初から存在しないような気がしてくる。そして、そう考えるとまたしても妙な不安に包まれるのである。自分が自分の本質だと考えている「自分自身」なんて、最初から存在なんてしていなくて、ただの幻想ではないか・・・?そんな不安がまた、グレーゴルの夢の不安に重なっていく。 さて、グレーゴルは変身前に一体どんな夢を見たのだろう? 本書は、『変身』だけでなく『判決』、『アカデミーで報告する』、『掟の前で』の3作が収録されている。ただ、『変身』以外の3作(+訳者による解説、あとがきも)は私にはあまりピンと来ず、楽しめなかった。解説によれば、カフカの解釈で明らかになるのはカフカの本質ではなく解釈者の性格である、という説があるらしいが、仮にその説が真だとしても、私はカフカ作品から自分の性格を明らかにしたいとは思わないし、そういうところがカフカ作品にはあまり馴染まないのかもしれないなと感じた。そういう意味で、個人的評価としては★3つである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本の裏の内容紹介には「レポートのような文体」と書いてあったけれど僕は無味乾燥だと思えた。人物描写などでこの描写はうまい、と感じた記述は特にない。カフカはそう意識して書いたなら最後はもうちょっと露骨に明るい文章にしても良かっただろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 希望に満ち溢れキラキラ光ったものだけでなく、人生で誰しも一度は経験する不条理がこの本にはあります。一気に引き込まれる世界観。意外と薄い本なので読了まで時間はかかりません。読んだ後色々な登場人物の視点で考察を巡らせるのもまた面白い一冊。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカの小説(97頁の分量)を読んだ後に、その舞台裏を描くといった感じで付された「訳者解説」(72頁の分量)が、実に秀逸。それほど面白い物語と思えなかったカフカの謎めいた小説が、その背景に、こうした諸々(もろもろ)のことがあると提示してくれたおかげで、作品がくっきりと、引き立って見えてきましたから。 なかでも、『変身』が生まれる最初の萌芽について記した次のくだりは、とても興味深かったです。 《(前略)カフカは有頂天になり、また長い手紙を書くが、その末尾に次のように付け加える。 〈ベッドでふて腐れているうちに思いついた小さな物語を書きとめないといけない。妙に気になっているんだ。〉 この気になる「小さな物語」こそ『変身』の最初の萌芽(ほうが)だった。つまり、恋人からの返事が来ない絶望感に浸りながら、ベッドから起き上がるまいと自分に縛りをかけている状態で思いついたのが、虫けらに変身したがゆえにベッドから起き上がれなくなった男の物語だったわけだ。》 p. 137 もうひとつ。『変身』の結末について述べた解説文も示唆に富むものであり、なるほどと思わされました。 《きわめて主観的な主人公の視点で覆い隠されていた家族の側の視点に思いを馳せながら読んでいくと、この小説が実はグレゴール・ザムザの物語であると同時に、変身した彼の介護に悩む家族の物語でもあった事実が浮かび上がる。》 p. 172 ~ 173 おしまいに、川島 隆(かわしま たかし)訳による『変身』の最初の一文は、こんなふう。 《ある朝、グレゴール・ザムザが落ち着かない夢にうなされて目覚めると、自分がベッドの中で化け物じみた図体の虫けらに姿を変えていることに気がついた。》 p. 5 文庫表紙カバーの絵は、ヴィルヘルム・ハマスホイの「白い扉、あるいは開いた扉」。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ほぼ新品でした。とてもよかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 学生時代、意味も解ってなかったのに、”シュール”というイメージで決めつけ、無意味に咀嚼していた内容が、自分の日常の中に溶け込んできます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 海外文学の名著という事で、どんなものなのだろうかと思い読んでみた。 ※新潮文庫の100冊とかいうのにも選定されている。 「主人公が朝目覚めるとなぜか虫に変身していた」というシュールな設定や引き込まれるストーリー展開は流石に名著だと思った。 また、文庫本にして100ページ強というコンパクトさは非常に魅力的だ。 コンパクトさに加え翻訳も安定しており、難解な文章ではないので、読むのが早い人ならサクッと読み終えてしまうだろう。 休みの日に何か1冊という時の選択肢としては非常に魅力的だと思う。 ぜひ、読んでみてはいかがだろう? ここからは少し掘り下げて書かせてもらう。 というのは、この作品に於いて必ず挙がってくるという、主人公が変身してしまった「虫」とは何なのか? という問いについて。 それは単なる文学的な設定なのか?あるいはメタファーなのか? あとがきにはカフカの内面の反映であるとか、当時迫害を受けていたユダヤ人であるとか様々な憶測が記されていた。 僕は、恐れ多いのだが、この「虫」に対して現代的な解釈を施してみた。 「虫」=「社会的な営みをすることが出来なくなってしまった家族」なのだとすると、 ・ブラック企業に勤めたため、うつ病になってしまい働けなくなってしまった者 ・そもそも働き口がない者 ・老齢で心身不全のため介護が必要な者 etc これらの人々が昨今の日本社会における「虫」なのではないかと思うのだ。 実際、この作品の主人公にこれらの人々をあてはめてみたらどうだろう? 現実社会におけるこれらの人々に対する家族たちの反応と、この作品における虫に変身してしまった主人公に対する家族たちの反応は、当たらずと雖も遠からずといった事がニュースを見れば割と頻繁に起こっているような気がするのは僕だけだろうか? いつまでも働かない息子に対して疎ましく思う親たち。とか、家族だからと一生懸命介護してはいたが、とうとう我慢の限界にきて殺してしまった。とか。 割とよくある話ではなかろうか。 社会から脱落した人々に対して冷たいのは古今東西同じなのだろう。 他者に対して何らかのメリットを与える行動が出来ないものは生きる価値がない。それは最も親しいであろう者=家族でさえ、そう思っている。 結局、「無償の愛」などないのだ。 この作品は人間のそういった性に対するカフカの嘆きなのだろうか。 ここまで書いて、ふと太宰治の人間失格が頭をよぎる。「無抵抗は罪なのか?」と言う名言と共に。 人間を失格した人間=虫。 大庭葉蔵は虫だったのではないか。 くどくど書いたがそろそろ〆よう。 最後に、僕は主よ、あなたに問いたい。「無償の愛とはなんですか?」と。 P.S. 主人公のグレーゴル・ザムザって名前、なんかかっこいいよね! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| フランツ・カフカ(1883~1924年)は、オーストリア=ハンガリー帝国領(当時)プラハのユダヤ人の家庭に生まれ、プラハ大学で法律年を学んだ後、保険局に勤めながら作品を執筆し、肺結核で41歳の若さで死去した。生前には、1915年に発表した本作を始め多数の短編を残したが、注目されることはなく、死後に友人により『審判』、『城』等の未完の作品が発表されて評価が高まり、20世紀を代表する作家の一人と見なされるようになった。 その作品は人間存在の不条理を主題としており、アルベール・カミュ(1913~1960年)とともに、代表的な不条理文学と言われている。 ストーリーは、真面目な布地の販売員グレーゴル(グレゴリー)・ザムザが、ある朝目を覚ますと、巨大な虫に変身しており、家族からも忌み嫌われながら(妹だけは最初は食事を運んだりしてくれるが)、自室に閉じこもって虫として生活を続けていたが、父親にリンゴを投げつけられて死んでしまい、その後、家族は生活への希望を見出す、というもの。 巨大な虫になっている自分に気付く始まりは衝撃的で、その後もどのようなことが起こるのか、もしかすると何かの拍子に人間に戻るのではないか等と思わせる展開は、退屈させることはなく、一気に読み通させるのだが、結局、原因も分からずに虫になったグレーゴルが救われることはなく、不条理の極致である。 カフカが、グレーゴルにより具体的に何を暗示していたのかについては、執筆当時の自分、或いは、当時差別を受けていたユダヤ人等、諸説あるようだが、明確なものではない。 ただ、現代の我々にとっても、本質的に類似した境遇(突然、周囲が自分に否定的になり、自分の主張も通じず、救われることがない環境が続くような)に陥る可能性を否定することはできず、強烈な印象を残す作品といえる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これを読んだら名前の似ているカミュは明らかに二流で、一括りにされて不条理だなどと言っていた時代が馬鹿らしくなる。『異邦人』は大して面白くなく、『変身』は今読んでもというより、今読んだほうが絶対に刺さるようになっている。 これだけレヴューがあるのも私には不思議である。古典作品なんて出版されてもほとんど無視される。実際、大してつまらないからである。私が最近読んだフォークナーの『土にまみれた旗』なんて誰が読むのだろう?元々から長編好みではないというのに加えて、退屈なところが海外作品には多い。 カフカの作品はトーマス・マンのように頭でっかちのものではなく、思いつくがままに描かれているという気がする。それも、何か考えのようなものではなく、イメージを描いているという気がする。そういうものに付随する文章は軽快で、決してしかつめらしいものになることはないだろう。 翻訳は古典新訳文庫の丘沢静也訳と見比べると、やはりこちら川島隆訳のほうが説得力があるし、あちらはあっさりし過ぎている。新しいものを目指しながら結果としては中途半端になっている。虫けらはただの虫。業務代理人はマネージャー。“音楽に感動するのに、動物なのか?”は「音楽に感動するから、動物なのだろう」とあっさりしている。この感じだと丘沢氏のニーチェも軽そう。全部持っているけど(笑)(実はヴィトゲンシュタインも持っている。) それからナボコフが虫けらをGにしたくない理由とか、面白かった。ちなみに私は水生ではあるけれど、ダイオウグソクムシあたりでイメージしている。肢がたっぷりあって、グロテスクでもあるし、加えてかわいげもある。しかし、正解は甲虫類らしい。これでもサイズは小さいからな……。目に見えたかどうか。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!