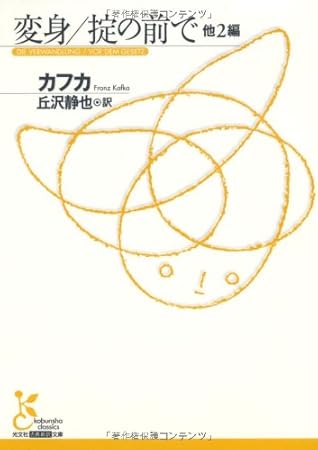■スポンサードリンク
変身
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
変身の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.08pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全293件 1~20 1/15ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカの変身。初めて読んだのは二年前のことでした。その時私は大病を患い、全身が痛くて働けなくなりました。その時までは順風満帆な人生を送ってきたのです、それこそエリート外交販売員だったグレーゴル・ザムザのように。私は、真面目にやっていればそれなりに給金の入る職の国家資格をとり、いざ働こうという時に身体が動かなくなりました。全身の痛みで家事以外はできない人間になり、一文も稼げない無職になりました。実家の家族はそんな私を受け入れて、養ってくれるようになりました。ある日、家事も一段落して暇になり、私はたまたま家にあったこの本を見つけました。カフカは読んだことがないので教養として読んでおくべきだろう、と気軽な気持ちで手を伸ばし、そして後悔することになりました。どうにも身につまされるのです。グレーゴル・ザムザと私が同じように思えて仕方ありません。グレーゴルは虫に変身するまでは身を粉にして家族のために尽くし、家族にも愛されてきました。私も、こうなるまでは家族の期待と愛にまっすぐに応え、うまいことレールの上を走ってきました。虫になったと早々にばれてからも、迫害を受けながら、グレーゴルは実家で飼ってもらうようになりました。しかし、その間にも虫から人間に戻る様子は一向にありません。私も、居心地の悪さを感じつつも、養ってもらっています。ところが一向に痛みが引く様子がありません。やがてグレーゴルの立場はどんどんと下がっていき、ついには家族にも見捨てられ、殺されてしまいます。さて、次は私の番です。私はいつまで養ってもらえるのでしょう。痛みに喘ぎ、薬も不応で、呼吸すら痛くてきつい時があるのに、生きていく術を見つけるまで面倒を見てもらえるのでしょうか。 読んで、しっかり後悔しました。他人事ではありません。家族とはいえ、共同体のなかでお荷物を常に抱えていられるほどの余裕は年々減少しているのです。社会全体も不況の煽りを受け、生産性の多寡で他人の存在意義に審判を下す、嫌な風潮になってきている気がします。 次は、私の番でしょうか。生きていきたいです。 絶望。 本としてはかなりおすすめです。文体も軽妙で、高橋義孝さん翻訳はかなり邦訳特有の読みにくさがなくすらすら読めます。中身に関しては、こんな感じで、考えさせられますよ。 一度手に取ってみてはいかがでしょうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 有名なこの小説の題名、虫に変身する主人公、家族の名(ザムザ家)などはいろんなところに引用されているから知っている人も多いと思われる。古来多数の翻訳本が刊行されていて、中でも著名なドイツ文学者の故高橋義孝氏の翻訳があるが1952年の刊行で如何にも古いので2年前に川島隆氏が訳し下ろした新しい角川文庫を選んだ。本文は100頁足らずの中編だが、72頁に及ぶ訳者川島氏の解説は著者カフカ(1883-1924)の出自(ボヘミアのユダヤ人)からその前半生、定説となっている暴君的な父親と弱い母親像の誤りの指摘、変身の成立・出版史から翻訳上留意した点の説明に加え、舞台となっているザムザ家の間取り図まで添えられている。物語は或る朝、主人公グレゴール・ザムザが目覚めると虫(具体的にどんな虫かは読者の想像に任されており最後まで分からない)に変身していて、本人の独白とそれを知った家族(両親 妹 女中)、訪ねて来た会社代理人、医者、通い家政婦などの対応とその変化が克明に描かれる。当初は驚き心配して世話をする妹が次第に疲れ、早く兄を始末したいと思うようになる。父親が投げつけたリンゴが体にめり込んで、それが元で次第に食欲の失せた主人公は遂に干乾びて死ぬが、何故虫に変身したのか理由の説明はなく謎のままに残される。彼の死後、家計の目途も立った家族が晴れ晴れとして郊外にピクニックに出かけるところで終わっている。古来、小説の背景となっている当時のドイツ思想界との関連、主人公がどんな虫に変身したのか、何故変身したのかについての考察などがゴマンとあるようだが、訳者が示唆されている如く平凡な一家が抱え切れない程の災難を蒙った際の家族の対応に焦点を当てて読むと面白かった。難しい小説は解説を読んでから本文を読むのも1つの方法だが、この小説は自分の感性を信じて先ず本文を読んでみるのがよさそうに思える。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 元々フランツ・カフカ先生が好きだったのでよく図書館で借りてたのですが、買いました✌️話の内容が好きなので面白いです | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本としては古典に近い本なので本屋で探してもなかなか見つかりません。そんな時速やかに手元に届くのはありがたいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校生の時に読んだ覚えがあり、この間、ニーチェやカミュを読んだので再読してみた。虫になることは覚えていたが、結末まで覚えていなかった。 川島隆の解説はカフカについて具体的に書かれており、非常に参考になった。カフカは、「もしぼくらの脳天を直撃して目を覚まさせてくれる本でないなら、何のために読むのか。ほんとうのものは、ぼくらの中にある凍りついた海を叩き割る斧でなければならない」と言った。確かに、この物語は脳天を直撃する。 この虫は何か?について、カフカは出版社の担当者に次のような手紙を書いた。 「シュタルケは即物的な画風の人ですし、虫そのものを描きたがるのではないかという気がします。それは、ダメです。それだけは!画家の領分を侵害するつもりはありませんが、この物語については私の方が当然よくわかっているはずではないですか。虫そのものは描かせないでください。遠目に見た姿でもダメです。」この指摘は実に興味深い。虫はあくまでも読み手が想像するものとなる。 それにしても、この虫は何かを知りたい。 川島隆は、読者の脳裏に浮かぶイメージがゴキブリのようなものからムカデやイモムシのようなものまで多様であると言及している。昆虫学者のロシア人作家ナボコフ(『ロリータ』で有名)は、ゴキブリ説を否定し、丸みのあるコガネムシのような六本足の甲虫の絵を描いた。「凡人どもに囲まれた天才」の悲劇として読んでいる。 グレゴールは、第三章で「クソ虫」と呼ばれるため、フンコロガシのような甲虫の一種と見なす説もある。ムカデ説やイモムシ説も否定できない。 カフカの朗読を聴いた人は、ナンキンムシの物語だと感じた。高橋義孝は「毒虫」と訳していた。この訳は既存の価値観に闘いを挑む実存主義に基づいている。しかし、その後、この小説には毒と思わせる描写はないため、1970年代の訳では、虫になっていく。 多和田葉子は、2015年の訳で「ウンゲツィーファー(生贄にできないほど汚れた動物あるいは虫)」と訳した。川島隆は、虫あるいはケラと訳している。カフカは読み手の想像に任せるため、虫にしても良いであろう。この変身のテーマは、滑稽さと哀れさを表現し、疎外感やアイデンティティの喪失である。 それにしても、グレゴールが大切に思っていた妹が「そのうち二人(父と母のこと)とも、あれに殺されてしまうわよ」と言うところが印象的である。これまでは「グレゴール兄さん」と呼んでいたのに、「あれ」に変わる。「耐えられないわ。私だってもう耐えられない。」「とにかく、あれがグレゴリー兄さんだという考えを捨てればいいのよ。あれがグレゴリー兄さんなわけがない」と言い切る。 ここからグレゴリーの存在が大きく変化する。劇的な場面の描き方が素晴らしい。 家族から避けられることは、やはり辛い作品である。読んだ後には、さすがに疲れがどっと出た。そこには明るい未来や希望がなかった。ニーチェやカミュとは異なる作品である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 学生時代にはじめてよんでよくわからないまま頭から離れない本のひとつですプラハをたずねたときカフカの家にもいきましたがこの作品につながるものは私は見つけることはできませんでしたでもいつまでも人々の研究心を掻き立てる作品なのだと思います | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 朝、外交販売員であるグレーゴルが目を覚ますと、自分自身が一匹の巨大な虫になっていた。 巨大な虫と化したグレーゴルと、変わらず人間である一家での生活。やがて生活に慣れが生じるも苦痛は拭えない。 人間の定義や家族とは?を考えさせられる作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 千原ジュニアさんと伊集院光さんの対談をYouTubeで見て、大学教授の翻訳魂?に火をつけた??エピソードみたいなので気になって購入しました。そもそも読書割と好きなのに、有名な物を意外と読んだことないお恥ずかしい限りな人間なので、良い機会と思い購入して読んでいます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初読は原田義人訳。母に「中学生でわかるわけがない」と揶揄された。まったくわからなかった。 『判決』…自身の作風を確立した短編で一晩で書き上げた。[F]lice [B]auer(1887-1960)への献辞。ロシアのペテルブルグに行った友達に手紙を書くうちに、友達が婚約の話に興味を持ち出す。婚約者は[F]rieda [B]randenfeld。友達は二通の手紙を持っているというオチがサスペンスっぽい。 『変身』…虫をどのように想像するか。長椅子の下に隠れるぐらいだから大きい。腐りかけのの食物を好むところでシデムシを想像した。「父親が立ち止まれば、グレーゴルも止まる」というのだからGかハンミョウみたいにも思えてくる。作者は原稿をマックス・ブロートの前で朗読する際、笑っていたという。実存主義の傾向があるとされる。 反精神医学を貫いたR.D.レインの『引き裂かれた自己』(みすず書房)は「石化」「離人化」を以下の様に説明している。彼を一個の物に変えようとする他者の行為は彼にとっては現実に、石化されることなのである。基本的に彼は、自分がひとりの人間であることを、いつも他者から不断に確認してもらう必要があるのである。石化(一個の物)→馬鹿でかい虫。他者とはいうまでもなく両親と妹、家政婦、間借り人。グレーゴルは何度か両親や妹に対して、人間として見てもらいたいと声を上げている。 『アカデミーで報告する』…以前、猿だった僕が人間になったわけ。人間になるために先生から調教を受ける過程で、猿の本性が、からだをまるめ、すごい速さで僕の中から抜け出した。そのため先生が猿の様になった。これは落語の枕で聞いたパブロフの犬を思い出す。実験過程で犬にベルを鳴らしていると、最終的に人間が犬を見ただけでベルを鳴らしてしまうというオチ。 『掟の前で』…まるでイエスが律法学者やファリサイ派の人々に話す譬えの様。門を潜るのは「今は駄目」。いつなら許されるのか。門番の監視を続けるうちに、門から消えることのない光が洩れてくる。それは男の希望の光だったのだろうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 三界に家なしの主人公が理不尽という魔物に殺される話。 読み進めれば進める程、心が壊死します。 考えることを放棄したくなる究極の鬱本です。 引き籠もりの情緒が沢山詰まっています。こういう作品は、人生に諦観を持たないと生きていけないような挫折を味わってないと書けないと思うのですが、100年も前の文豪が現代の引きこもりと同じような感情を持っていたことに驚きます。もし、引きこもりやイジメを経験せずにこの作品を生み出したとしたらカフカは天才ですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 1915年に出版された本とは思えないほど、現代にも通じる問題が多くて驚かされた。序盤は数時間の遅刻程度で、支配人が家まで訪ねてきたりコメディ要素が多少あり。 "ただ妹だけは兄に特別の情愛を示しつづけていた。" 食事を持って来たり、部屋を這い回れるよう家具を移動させようと頑張る妹。その妹が部屋に入る時、麻布で身体を隠す事で感謝を伝えようとするグレーゴルと妹の美しい兄妹愛。しかし一番頑張った故に限界に達し、兄を「放り出そう」「兄なら自分から出ていくはず」と批難する描写は読んでいて辛かった。 最後は人間に戻ってハッピーエンドかも、と淡い期待を抱いた。 しかし第一次大戦直後の欧州で生きる病弱なチェコ系ユダヤ人の作者にとって、人生はそれほど甘いものではなかった。 来年には国民の4人に1人が75歳以上になる日本。胃ろう拒否 延命拒否等、終末医療をどこまでやるのか。介護する側が潰れないよう、家族で話し合っておく必要性を強く感じた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 美品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 物語の解釈については、すでに様々出されているので省きます。 高橋義孝訳のおもしろさについて。 明治から昭和初期の、いわゆる文豪とよばれる作家の作品を読み慣れた人には、大変おもしろく、言葉使いも違和感なくすらすらと読めます。淡々とした語り口には、悲劇的な表現でさえ、ユーモアが漂います。翻訳にありがちな、くどさやつっかえ感がありません(もちろん原作が簡明、達意なのでしょう)漢文のようなリズムのよさを味わえる訳になっています。 ということは、逆に、現代作家の作品、SNSのような普段使いの言葉や文章に慣れてしまった人には、とても読み辛く、意味も分かりにくく、違和感が大きく、古くさいと感じると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 不条理小説の古典ともいえる本書ですが、今や不条理は、誰にでも前触れなしに起こりうる世となりました。若き日とは違った感慨で、面白く読むことができました。読後感爽快とはいきません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あまり細かく書いてしまうとネタバレになるのであれですが、主人公は家族に搾取されています。 ・主人公は父がこさえた借金の返済のために、ストレスフルな高給取りの仕事について家族のために頑張るものの、それが当たり前になってしまった家族はそこまで感謝していない ・本当は働けるのに主人公に寄りかかってみんな働かない ・主人公に内緒で父は主人公の稼ぎを溜め込んでいる(それで借金返済してしまえばよかったのに) 変身の結果この家族は崩壊してしまうのですが、実は変身する前からこの家族は機能していなかった。主人公の犠牲のもとなんとか成り立っていた (あるいは、それこそが家族の本質?) 稼げなくなった途端、彼は厄介払いされます。 虫への変身は、彼が無意識に家族の重圧、搾取から逃れようとしていた結果では?と思うのですが、その先には死が待っていた(金を持ってこないやつに用はない)、と。 カフカの、家族(特に父親)に対する怨念が現れている気がします | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| シンプルで読みやすい。でもカフカがギュッと詰まってる。はじめの一冊がこれならカフカを好きになるんじゃない? 学生におすすめ。星新一が好きな人にも。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 訳者「川島 隆」さんによる本書文庫版『変身』の人気はすごい。 令和4年の初版なのに、なんと一年後の令和5年には第6版。 この人気の理由は、何でしょう? 『変身』のドイツ語原作は、1912年。 今年は2023年ですから、111年も前の古い小説です。 読み古された物語なのに、今なお生きています。 本書103頁から始まる「訳者解説」に注目して、人気と長生きの秘密を探りました。 「『この小説に解説は必要ない』と言って解説を終わらせるのが、本当は一番妥当なこと」(105頁) と言いながら、71頁にも及ぶ、長文の詳しい「訳者解説」を本書に綴る訳者の川島さん。 いくつかの先行翻訳はもちろん、ナボコフの意見や多数の英訳まで参照した解説です。 最後の圧巻は、川島さん自身が翻訳のときに参照した既訳との比較検討結果です。 訳語の選択や文意の取り方が難しかった点などについて、解説しています。 文学研究者ならでは、の詳細解説になっています。 解説の見出しのみ列記してみましょう。 ① 虫けら ② 出張の多いセールスマン ③ 絵と写真 ④ 神と悪魔 ⑤ 体験話法 ⑥ 業務代理人 ⑦ メイド、料理女、派遣家政婦 ⑧ ザムザ家の間取り ⑨ 人間と動物の境界線 ⑩ 家族の物語の「ハッピーエンド」 この訳者解説を読んでみると、完璧な書評にもなっています。 本書が歓迎される理由の一つがここにあるのでしょう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 100分de名著で絶賛されていた為、試しに購入。主人公や家族や間借り人、家政婦など問題に対する視点がグルグルと移動させられる感覚が面白かった。 しかしテレビでは全てオチまで放送していたので、単にあらすじの確認作業となってしまった(笑)古典なのでオチまで言ってもいっかとの判断になったのだろう。本が売れない時代なので、オチまで言う紹介のしかたでも俺は許す! その点で、数ある「変身」の中で本書を選んで良かったと思ったのは、本編と同じくらいの分量で解説が書かれていたところだ。いまだかつて解説にこれほどバカ長いページ数を割く小説は出会ったことが無い! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| "掟の前に門番が立っていた。この門番のところに男がやってきて掟のなかに入れてくれと頼んだ。だが門番は言った。まだ入れてやるわけにはいかんな。"2007年発刊の本書はくり返しを意識的に残して翻訳したカフカ傑作4編。 個人にカフカ好き。と言うこともあって久しぶりに手にとりました。 さて、そんな本書はドイツ文学者が"少ないボキャブラリーで書き、散文を強く歌わせるために、くり返しを多用した"カフカを意識して翻訳したもので、あまりに有名なある日、突然虫になった男の視点から"家族"を描き『百年の孤独』のガルシア・マルケスにも影響を与えた『変身』カフカ作品としては最も言及、引用されるわずか1ページ半の短い作品『掟の前で』"ぼく"がサルだったときのことを報告する『アカデミーで報告する』そしてひと晩で書きあげられた息子と父親の対話『判決』の4編が収録されているわけですが。 いやあ。若い時に手にした時は不条理な展開に挫折したものですが。年を重ねてから読み直すと、ビジネスパーソンとして『終生サラリーマン作家』とだったカフカへの親近感も生じているからか、それぞれの作品を【どのような心境で書いたのか】思いを馳せつつ、流れるような新訳を楽しませていただきました。 また、4編の中では特に『掟の前で』を別の著者が引用しているのを見て久しぶりに読んだのですが。この短い作品。何度読み返しても【暗喩的なじわじわ感があって】やっぱり好きだな。とあらためて。 読みやすいカフカの入り口的一冊として全ての人にオススメ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカの作品たち(変身だけでなく、審判、城、流刑地にて・・・、判決、などなど)が凄いのは、読むことで世界の見え方を一変させる効果を持っているところにある。世界の見え方が変わったところで別に日常生活にアドバンテージができるというわけではない。ただ毎日を過ごす中で、いたるところに「カフカっぽさ」を発見するようになるのである。日常のシチュエーションだけでなく、自分の感情や読む本や観る映画にも「カフカっぽさ」はたびたび出てくる。つまりカフカは、これらの作品群で、この現実世界に確かに存在するある種の(不可解な)現象を、「カフカ的」と呼ばれるほど初めて上手に切り取ったのである。こんな芸当ができる人間は滅多にいないだろう。その点でカフカは唯一無二なのである。 彼の作品群が不完全に見えるのは仕方ないことだと思う。カフカ的というのはごく簡単にいうと「到達できない」とかそんな風にも言えそうだからである。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!