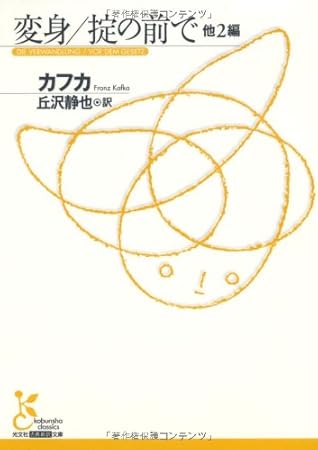変身
※タグの編集はログイン後行えます
【この小説が収録されている参考書籍】 |
■報告関係 ※気になる点がありましたらお知らせください。 |
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点7.50pt | ||||||||
変身の総合評価:
■スポンサードリンク
サイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
全2件 1~2 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
佐藤究「トライロバレット」に触発されて本作を読む。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
前に読んだ虐殺器官でやたらカフカが出てくるので | ||||
| ||||
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカの変身。初めて読んだのは二年前のことでした。その時私は大病を患い、全身が痛くて働けなくなりました。その時までは順風満帆な人生を送ってきたのです、それこそエリート外交販売員だったグレーゴル・ザムザのように。私は、真面目にやっていればそれなりに給金の入る職の国家資格をとり、いざ働こうという時に身体が動かなくなりました。全身の痛みで家事以外はできない人間になり、一文も稼げない無職になりました。実家の家族はそんな私を受け入れて、養ってくれるようになりました。ある日、家事も一段落して暇になり、私はたまたま家にあったこの本を見つけました。カフカは読んだことがないので教養として読んでおくべきだろう、と気軽な気持ちで手を伸ばし、そして後悔することになりました。どうにも身につまされるのです。グレーゴル・ザムザと私が同じように思えて仕方ありません。グレーゴルは虫に変身するまでは身を粉にして家族のために尽くし、家族にも愛されてきました。私も、こうなるまでは家族の期待と愛にまっすぐに応え、うまいことレールの上を走ってきました。虫になったと早々にばれてからも、迫害を受けながら、グレーゴルは実家で飼ってもらうようになりました。しかし、その間にも虫から人間に戻る様子は一向にありません。私も、居心地の悪さを感じつつも、養ってもらっています。ところが一向に痛みが引く様子がありません。やがてグレーゴルの立場はどんどんと下がっていき、ついには家族にも見捨てられ、殺されてしまいます。さて、次は私の番です。私はいつまで養ってもらえるのでしょう。痛みに喘ぎ、薬も不応で、呼吸すら痛くてきつい時があるのに、生きていく術を見つけるまで面倒を見てもらえるのでしょうか。 読んで、しっかり後悔しました。他人事ではありません。家族とはいえ、共同体のなかでお荷物を常に抱えていられるほどの余裕は年々減少しているのです。社会全体も不況の煽りを受け、生産性の多寡で他人の存在意義に審判を下す、嫌な風潮になってきている気がします。 次は、私の番でしょうか。生きていきたいです。 絶望。 本としてはかなりおすすめです。文体も軽妙で、高橋義孝さん翻訳はかなり邦訳特有の読みにくさがなくすらすら読めます。中身に関しては、こんな感じで、考えさせられますよ。 一度手に取ってみてはいかがでしょうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 有名なこの小説の題名、虫に変身する主人公、家族の名(ザムザ家)などはいろんなところに引用されているから知っている人も多いと思われる。古来多数の翻訳本が刊行されていて、中でも著名なドイツ文学者の故高橋義孝氏の翻訳があるが1952年の刊行で如何にも古いので2年前に川島隆氏が訳し下ろした新しい角川文庫を選んだ。本文は100頁足らずの中編だが、72頁に及ぶ訳者川島氏の解説は著者カフカ(1883-1924)の出自(ボヘミアのユダヤ人)からその前半生、定説となっている暴君的な父親と弱い母親像の誤りの指摘、変身の成立・出版史から翻訳上留意した点の説明に加え、舞台となっているザムザ家の間取り図まで添えられている。物語は或る朝、主人公グレゴール・ザムザが目覚めると虫(具体的にどんな虫かは読者の想像に任されており最後まで分からない)に変身していて、本人の独白とそれを知った家族(両親 妹 女中)、訪ねて来た会社代理人、医者、通い家政婦などの対応とその変化が克明に描かれる。当初は驚き心配して世話をする妹が次第に疲れ、早く兄を始末したいと思うようになる。父親が投げつけたリンゴが体にめり込んで、それが元で次第に食欲の失せた主人公は遂に干乾びて死ぬが、何故虫に変身したのか理由の説明はなく謎のままに残される。彼の死後、家計の目途も立った家族が晴れ晴れとして郊外にピクニックに出かけるところで終わっている。古来、小説の背景となっている当時のドイツ思想界との関連、主人公がどんな虫に変身したのか、何故変身したのかについての考察などがゴマンとあるようだが、訳者が示唆されている如く平凡な一家が抱え切れない程の災難を蒙った際の家族の対応に焦点を当てて読むと面白かった。難しい小説は解説を読んでから本文を読むのも1つの方法だが、この小説は自分の感性を信じて先ず本文を読んでみるのがよさそうに思える。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 元々フランツ・カフカ先生が好きだったのでよく図書館で借りてたのですが、買いました✌️話の内容が好きなので面白いです | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本としては古典に近い本なので本屋で探してもなかなか見つかりません。そんな時速やかに手元に届くのはありがたいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校生の時に読んだ覚えがあり、この間、ニーチェやカミュを読んだので再読してみた。虫になることは覚えていたが、結末まで覚えていなかった。 川島隆の解説はカフカについて具体的に書かれており、非常に参考になった。カフカは、「もしぼくらの脳天を直撃して目を覚まさせてくれる本でないなら、何のために読むのか。ほんとうのものは、ぼくらの中にある凍りついた海を叩き割る斧でなければならない」と言った。確かに、この物語は脳天を直撃する。 この虫は何か?について、カフカは出版社の担当者に次のような手紙を書いた。 「シュタルケは即物的な画風の人ですし、虫そのものを描きたがるのではないかという気がします。それは、ダメです。それだけは!画家の領分を侵害するつもりはありませんが、この物語については私の方が当然よくわかっているはずではないですか。虫そのものは描かせないでください。遠目に見た姿でもダメです。」この指摘は実に興味深い。虫はあくまでも読み手が想像するものとなる。 それにしても、この虫は何かを知りたい。 川島隆は、読者の脳裏に浮かぶイメージがゴキブリのようなものからムカデやイモムシのようなものまで多様であると言及している。昆虫学者のロシア人作家ナボコフ(『ロリータ』で有名)は、ゴキブリ説を否定し、丸みのあるコガネムシのような六本足の甲虫の絵を描いた。「凡人どもに囲まれた天才」の悲劇として読んでいる。 グレゴールは、第三章で「クソ虫」と呼ばれるため、フンコロガシのような甲虫の一種と見なす説もある。ムカデ説やイモムシ説も否定できない。 カフカの朗読を聴いた人は、ナンキンムシの物語だと感じた。高橋義孝は「毒虫」と訳していた。この訳は既存の価値観に闘いを挑む実存主義に基づいている。しかし、その後、この小説には毒と思わせる描写はないため、1970年代の訳では、虫になっていく。 多和田葉子は、2015年の訳で「ウンゲツィーファー(生贄にできないほど汚れた動物あるいは虫)」と訳した。川島隆は、虫あるいはケラと訳している。カフカは読み手の想像に任せるため、虫にしても良いであろう。この変身のテーマは、滑稽さと哀れさを表現し、疎外感やアイデンティティの喪失である。 それにしても、グレゴールが大切に思っていた妹が「そのうち二人(父と母のこと)とも、あれに殺されてしまうわよ」と言うところが印象的である。これまでは「グレゴール兄さん」と呼んでいたのに、「あれ」に変わる。「耐えられないわ。私だってもう耐えられない。」「とにかく、あれがグレゴリー兄さんだという考えを捨てればいいのよ。あれがグレゴリー兄さんなわけがない」と言い切る。 ここからグレゴリーの存在が大きく変化する。劇的な場面の描き方が素晴らしい。 家族から避けられることは、やはり辛い作品である。読んだ後には、さすがに疲れがどっと出た。そこには明るい未来や希望がなかった。ニーチェやカミュとは異なる作品である。 | ||||
| ||||
|
その他、Amazon書評・レビューが 390件あります。
Amazon書評・レビューを見る
■スポンサードリンク
|
|
|