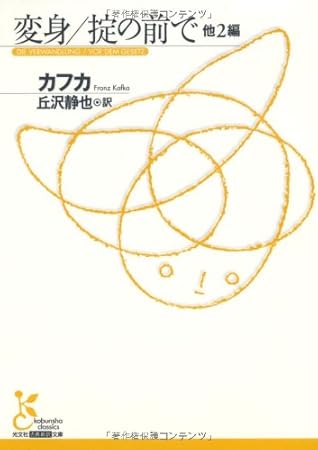■スポンサードリンク
変身
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
変身の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.08pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全390件 301~320 16/20ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 有名というだけで何気なく読み始めた本書。内容的には暗いグロテスクなものですが、何もかもがさらりと書かれているせいか非常に読みやすかったです。 私は根っからの理系人間なので、何をどう解釈してよいやら…という感じで、この本が有名な訳もよくわかりませんが、自分の身の回りにあてはめてみたときに色々と考えさせられました。 特に感じたのは「思いやり」の大切さ。登場人物皆の身勝手さに目が行ったのは、最近立て続けに育児関連の本を読んでいたせいかも知れませんが…。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品を私は、学校内で強制的に書かされる読書感想文のため、推薦図書として頻繁に目にした。 今となっては無数に存在する解釈も納得できるし、自分なりに理解もできる。 ただ、はっきり言ってまだ「殺那的」に生きている学生の時期に、この作品を理解できる者がどの程度いるのだとも思う。 作品をそのまま解釈するだけではSF的駄小説。深い理解を得ようとして、はじめて一級品の作品となる。 素晴らしい作品だと思うけれど、これが何らかの形で理解できてしまう学生は若さがなくて嫌だなぁ、なんて思ったりもする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 以下書くことは、人から聞いた話である。 グレゴール・ザムザはなぜ、毒虫にならなければならなかったのか。 彼は一家を養っていた。グレゴールからしたら、養っている家族のほうが、お邪魔虫であり、寄生虫のようなものであったはずだ。彼には罪はなかった。罪があるとすれば、家族を邪魔者と、――たとえそれが潜在意識の中でしかなかったとしても、――考えてしまっていたこと、かもしれない。グレゴールは、自分の意志とは無関係に、結果的に、家族を救った、と言える。ひたすら養われていた一方だった彼らは、いわば、生ける屍のようなものだった。グレゴールの死により、彼らは、息を吹き返した。本当に、生きはじめることが出来た。聖書の言葉を借りれば、一粒の麦が地に落ちて、多くの実を結んだのである。そう、グレゴールは、メタモルフォーゼされた、イエス・キリストなのだ。 以下は、私が考えたことである。 誰かに養われる、というのは、後ろめたい気持ちが伴う。グレゴールには、家族が抱いていた、そんな後ろめたさを察する優しさが必要だったのではないか。彼にその優しさがあったならば、彼は毒虫にもならず、死なずにすんだかも知れない。家族全員、助け合って生きていく道も開けたかもしれない。当たり前のことだけれど、私たちは、一人では生きていけない。迷惑を掛け合いながら、お互い助け合っていかなければ、生きる道は開けない。カフカ自身は、こんな、お説教くさいことを言いたかったわけではあるまい。ただ、生まれてこの方、迷惑をかけっぱなしの私は、そんな風に考えさせられたまでの話である。 以下は、私の戯言である。 九頭見和夫氏は、本作「変身」と太宰治の短篇小説「花火」とを比較し、太宰が「変身」を翻案し、「花火」を創作した可能性がある、と指摘している。「変身」を「花火」に〈変身〉させてしまった太宰。〈変身〉。太宰は、〈変身〉願望を根強く持っていた、と私は思う。町田康さんは、人の肉体を〈宿〉にたとえ、不滅の〈魂〉が、〈宿〉から〈宿〉へ泊り歩く寓話を、「宿屋めぐり」に書いた。太宰の人生そのものが、〈宿屋めぐり〉だったのではないか、と私は考えている。 太宰の創作した作品が〈宿〉であり、太宰の〈魂〉は作品という名の〈宿〉から〈宿〉へと旅を続けていったのではないか。芭蕉が、〈旅人〉と呼ばれんとして、つまりは、名もない〈旅人〉と呼ばれんとして、漂泊の旅を続けたように。それは、〈自分〉を〈他人〉へと、一歩、また一歩、と近づける努力である。それは、彼が究極のモットーとした、〈己を愛するがごとく、汝の隣人を愛せ〉に通ずる努力だった、と私は思いたい。私の文章は、まったく、論理的でないかもしれない。しかし、人は、論理だけで生きているわけではない。盗人にも三分の理、という。私にあるのは、どうやら、これだけらしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 朝起きるとザムザ君が虫になってるという、言わずと知れたカフカの代表作。さまざまな解釈があると思いますが、僕は他の作品同様テーマは『孤独』や『疎外』だと思います。ある心境に達するともはや人間は虫になってしまうといったかんじでしょうか。短いですがとても深い内容で、何度読んでも飽きません。しかし、いくらなんでもザムザは可哀想です。虫になったことではありません。一家を支えていたザムザが邪魔者となり慕っていた妹にも見捨てられ、孤独の内に死に、一家は再出発の希望を抱く。ある種の効力を発揮していた者も、不要になると捨てられてしまう、なんだかホッカイロみたいな扱いです。しかも僕の大好きなカフカ特有の無駄な長台詞や比喩、シュールな展開(出だしは死ぬほどシュールですが)がほとんど無いので、☆4つにしました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公はある日、職を失い、家族の信頼を失う。 働くべく前の職場に行っても追い返され、努力しても新しい職にもつけない。 やがて家族の中で「こいつはうちに居ない」ことにされる。 部屋から出ることも、家族の輪に入ることもできない。 うっかり人前にでてしまうと、とんでもないことをしたかのように言われる。 あげく、こんななら出て行くのが当然のように扱われ見殺しにされる。 死ぬ前に出て行けばよかったのか、出て行けば何とかなったのか。 これはそう言う話。 「毒虫になった」てのはきっかけでそれは「失業した」「病気になった」「ぼけた」など言い換えることができる。何かがきっかけで家族が家族でなくなるとどういうことになるか。 毒虫から立ち直るのにこの家族は何もしない。毒虫として扱うだけ。 結果、主人公は死に家族はすっきりとふたたび「きれいな家族」として暮らして行く。 いや、恐ろしい話だけど「毒虫になる」を文字通りとらなければ現実にありそうなホラー。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| こんな小説があったなんて、衝撃でした。 「ある朝、グレゴール・ザムザがなにか気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な毒虫に変っているのを発見した。」 という出だし。 出だしだけで衝撃的。 でもおもしろい。 絶対に読むべき傑作です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| シューレアリズムの傑作だが、不条理な世界観は読み手を選んでしまうかもしれない。 しかし、これは紛れもない傑作だ。 読者に対する突き放した設定はそれ自体が強烈なメッセージなのだ。 狂気なる現実とそれに対して普通に暮らし主人公を疎ましく思う家族達。 そこから見いだすモノ… どう考えてもリアルな人間の闇の部分にスポットを当てている。 やはり読み手を選ぶ書なのかなぁ(笑) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 変身がよいものであるなら、不条理ではない。 自分が評価できないものに変身してしまったら、どのように対処すればよいだろうか。 自分には答えがなく、その場でどう判断するかは分からない。 しかし、この本が呼んであれば、苦境に陥っても、どのような対処方法が可能かを考えるきっかけにできるかもしれない。 そうでなくても、何か得ることが出来る本だと感じている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| シューレアリズムの傑作だが、理解するにはそれ相応の人生経験が必要となる。 故に中高生10代、20代でもついて行ける代物ではない。 残酷なまでの現実感と設定は読む者をひたすら打ちのめす。 これが駄作だというのなら門前払いだ。 あと10〜15年は人生を積んで再びトライすべきだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 名作だと聞いてさっそく読んでみた... 苦痛でした... 虫になったことにもっと驚けよ!!つっこめよ!! 当時の情勢、文化や習慣を知らないせいか、物語が進むほど 読んでる私自身が置いてけぼりにされ、全然感情移入できなかった。 ファンの皆さん、ごめんなさい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカの「変身」の噂はよく話に聞いていたので、一度読んでみたいと思っていました。 小説として完成度が高いです。ページ数は90ページぐらい、 両親、妹と暮らすあるセールスマンが、朝起きたら体が毒虫に変身していたという 一風変わった内容です。 ある日突如として起きた異変を素直に受け入れるところがシュールと言えばシュールで この小説の魅力になっています。 かつ、異変が直接的にではなく寓意的に表現されているため、家族の持つ内面の感情という 重いテーマが読みやすくなっているんだと思います。 「毒虫に変身した」という異変を、「重いケガ・病気にかかった」と置き換えると、 現代にも通じる介護の問題とも読み取れます。 本書に含まれるもうひと作品、「ある戦いの描写」は詩的過ぎて、正直肌に合わない というか読むのが難しかったです。意味がわかりませんでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| う〜ん、スゴイ話しですね。みんなが冒頭だけ知ってる、朝起きたら虫になっていた男の話し。でもほとんどの人が最後まで読んでないのでは?私もこの年まで読んだ事なかったです、恥ずかしい話しですが。 ストーリーはみなさん知っている通り、ある男(独身で老いた両親と妹と生活)が朝早くからの仕事(行商のセールスマン)の為に目覚ましをかけたはずなのに、気が付くと時間を大幅に過ぎている!!しかも自分の身体に大きな異変が!!虫になってる!!!硬い殻をまとい、足は細かく細くてたくさん生えてる!!寝返り打つのも一苦労で、ベッドから降りるのに頭を打つしまつ!!! というパニックから、仕事先の上司や家族を巻き込んだ恐ろしいくも(私には)笑いを感じさせる冷静さで、ストーリーは進みます。著者フランツ・カフカの時代と現代では捕らえ方に違いはあるかもしれませんが、私には不条理な部分を恐くもさせていますが、笑いにも通じるものとして、感じました。最後の最後なんか、ある意味吉田戦車の不条理ギャグです。恐ろしくも可笑しいそんな話しですが、これそんなに名作なのでしょうか?ちょっと疑問は残ります。 乾いた笑いを求めている方に、あるいは古典を再認識して見たい方にオススメ致します。短いし、すぐ読めます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| クラシック音楽におけるピリオド楽器によるオケの演奏は、ほとんどの場合好まない。特にベートヴェンやバッハの多くについては。 訳者は翻訳(これはある意味演奏と同様の行為だ)における「ピリオド奏法」を謳い、実践している。高橋義孝訳、池内紀訳を併読したが、この丘沢訳が一番しっくり来た。といってもドイツ語を解するわけではなし、先行訳にも美点は大いにある。 『変身』は、怖ろしい物語だ。筋だけを辿っていても、この力強さは旧約聖書に匹敵する。こういう真の世界文学の新訳は大歓迎だ。『星の王子様』程度のお子様物語の新訳に躍起になるのはどうかと思うが、『カラマーゾフ』といい、本書といい、意義がある。 そういえば『カラマーゾフ』の訳者・亀山郁夫は『罪と罰』にも取り掛かっているらしい。 光文社古典新訳文庫には大いに期待したい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 簡単な言葉で訳すことで、カフカの天才が出てきた。 養老猛司の言うように、自分は自分のままと思い続けた主人公ザムザは不気味だ。 だが、それ以上に頭に引っかかったことがある。家族はなぜ馬鹿でかい虫をザムザだと思ったのだろう。 馬鹿でかい虫に目がいって、家族の視点で読んでしまいそうになるにこらえて、 ザムザの視点で読み進めていきました。人生は切ない喜劇でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み終えて、胸の中がすこし重くなったような気がしました。 解釈としては色々あるのでしょうが(どういった解釈があるのか調べてないので知りませんが)、私は、後半場面での妹の発言がこの作品の中で一番印象に残りました。 やるだけのことはやったのだから、もういいでしょう。というような言葉です。 なぜかこの言葉を聞いて、各地の貧困であえいでいる人たちの姿が思い浮かびました。 妹は、虫になにをしたのか。 虫だけでなく、妹の行動、発言に注目してみるのも面白いと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 判決、変身、アカデミーで報告する、掟の前で、の4編を収録。 カフカの作品といえば、面白くないという印象がある。 作品の内容は、わけの分からない状況に置かれた主人公が右往左往するのを淡々と描くだけなので、読んでいるこちらも訳が分からす、それが延々と続くので、ただ退屈なだけ。 評論家はとそれを不条理とかなんとか難しいことを言って高く評価しているけれど、やっぱりだた退屈なだけ。 あまり読みたくない作家だ。 しかし、そういうカフカ像を産むに至ったのは、どうやら原典の編集段階に問題があったらしく、また、日本訳にもいろいろ問題があったらしい。 史的批判版」に基づく本書は、カフカのそんなイメージを覆す。 なによりも読んでいて面白い。退屈で無味乾燥なカフカではなく、筒井康隆のある種の作品に近い感じ。いやもっと近いのは、やはり吾妻ひでおのマンガだな。 考えてみれば、不条理というのは、主人公がヘンな目に遭わされて困っているということだから、「笑い」とかなり近いところにいるはずだ。不条理作品を読んで笑いが出てくるのは、だから、そんなにおかしなことではない。というよりもむしろその方が自然なのではないか。 最後の「掟の前で」は、いかにもいろいろな解釈をしたくなるような結末だが、「なんだこれ?」、という感想だけでも十分ではないか。 カフカを楽しめる一冊である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 規則正しい労働に嫌気が差したザムザはむしになった 巨大な醜い虫になった 家族はその汚らわしい虫に元のザムザの人間性を見出さずに部屋に閉じ込めた しかしザムザは部屋の中のちょっとしたことや妹のヴァイオリンにまで感動するのである。 労働にとらわれた家族 感動するザムザ。 真の人間らしさとは何なのだろう、カフカは家族とザムザのどちらに人間らしさを見出したのだろうか・・・ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ある日目が覚めたら虫になっていた 巨大な汚い虫・・・・・ 会社のマネージャー、家族の反応と対応で1冊終わっていまう 「なんじゃこりゃ」 解説によると不完全な作品とか、マルクス主義や聖書に置き換えて読めとか何とか・・・有名だけど不完全・・・不思議だ とりあえず「海辺のカフカ」でも読みますか 違うかな? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 突然巨大な虫になってしまう主人公。家族は驚き、彼を部屋に封印して苦悩する。 主人公は分かってほしいものだと思いながらも自分がどうしようもない迷惑をかけていることを考え、どうすることもできず不条理と排除を受容してしまう。あるいはそれが主人公の最後の優しさだったのか。この不思議な優しさと、主人公の死によって苦悩から厳かに開放される家族の対比がなんともいえない読後感を醸し出している。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いやな夢の後、体が虫じゃん! その点で人間かなりっつうかありえないんで、現実逃避したりなんだりで、もう死にたくなりますわな。 でもなんか主人公、出勤しようとするし(現実逃避後、つうかこれ自体現実逃避か?逆に現実的すぎ?)、 家族と上司に自分の体みてもらおーとするし、鍵あけてね。部屋の。(出勤の過程かな?) まあ話は暗い方向に向かうかんじなんですがね。(つうか結局死ぬんだけどね) わたしにはこのはなし、コントにしか思えなくって。もう。 なんていうかとかげのおっさんみたいな(?) とにかく面白くって、読んだ後、また読んでしまい、それからまた読んでしまいました。 人それぞれ感想ありますけど、私の感想はシリアスなコントを延々観てるってかんじでした。 棺桶に入る前にぜひ読んでください! 興ざめするので、興味のある方は以下を読んでください。 ・もし無脊椎動物、甲殻類、陸上で生きる「虫」そのものを数倍(ドラえもんの道具みたいなので)にしたら、 虫は生きていけません。大気圧+自重(殻の重さ)に、内圧(肉)が耐えられず、存在してまもなく死にますねぇ。 ぐしゃり!べこっ! | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!