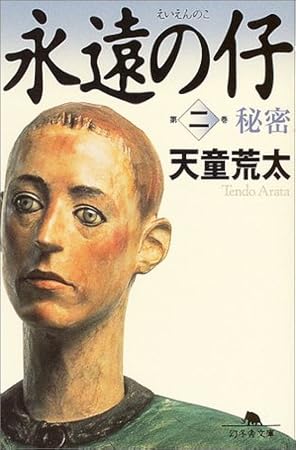■スポンサードリンク
永遠の仔
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
永遠の仔の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.56pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全165件 101~120 6/9ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 優希は下山途中、2人の少年と父親を殺した。17年後に、2人の少年と偶然の再会をし、当時の記憶が強く思いだされる。第1巻では再開までのストーリーが描かれる。作品に強く引き込まれる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 少し重い内容です。 分厚い上下巻の本ですが、 分量の割には比較的読みやすいと思いました。 構成も良く、 少しずつ明らかになっていく事実が、 心にのしかかってきます。 終盤は少しあっさりとしている気がしましたが、 全体的にみて大変良くできていたと思います。 虐待、介護など、 読んでいて考えさせられ、 決して明るい内容ではないです。 好き嫌いが別れる内容だと思いますが、 個人的には読んで良かったです。 評価は星5つで。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 5巻という気の遠くなる小説かと思いきや、皆さんのレビューにあるようにあっという間に読みきった。 早く読みたいなと気が気でなく。 優希の父親・母親を、幼少の優希の立場から描写される前半では、どんなにひどい人たちなのかと思っていた。 途中、父親の苦しみや、優希への愛情、家族への愛情がありあまるほど。それにも勝てない父親の心の弱さの露呈。 最後で判明する母親なりの苦しみ。今までの言葉の意味。 優希・ジラフ・モウル、この心に闇を持つ3人に共通するのは、幼少期に関連した親の心の弱さ、未熟さ、にある。 それでも、子供は親を求める。 子を持つ親となる時、子供らの幼少期のこの繊細な感情を思い出し、子供の心に闇をつくらないように努めたい。 優希・ジラフ・モウル、最後は幸せに終わってほしかった。 あんなに苦しんだのに。 負の連鎖を断ち切るにはどうすればいいのだろうか。 現実に起こっているであろう社会問題に心が痛んだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| よくこの作品は感動巨編と書かれたりしているが感動はしない(僕はしなかった、衝撃は受けたけど)。緻密に練られた伏線がだんだん一本の太い線になっていく展開力はすごいし、読んだらほとんどの人がハマって、寝る間も惜しんで読んでしまう作品だと思う。 ただ、ラストが結局誰一人過去のトラウマを本当の意味では乗り越えられなかった事が非常に残念だ。同じような体験をした全ての被害者の為にも誰か一人でも完全にトラウマに打ち勝ち今を生きる姿を見せて欲しかった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 天童荒太の他の作品が読みたくて、 古本屋にあったこの作品にしました。 話題になった小説だったのに、 まったく内容を知りませんでした。 またしても負の文学。 あまりにもすっきりとした文体。 さわやかささえも感じられるその文体。 にもかかわらず、書かれている内容の醜悪さ。 リアルな分だけ、背筋が凍る。 謎の一つは、 ほぼこの1巻でわかってしまったが、 過去と現在の行き来が見事で、 ガンガン引き込まれました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 思うとおりになんかいかない。 そんなに高い望みだとは思わない。 けれども、それもかなわない。 これだけの内容を無責任に書けるわけもなく、 おそらく徹底した取材で、 かなり研究しているのだろうと思う。 その分のリアルさが、 鳥肌が立つほどの深い感を誘う。 幼児虐待、DV、殺人・・・、 もちろん言い訳もできない犯罪である。 あらゆる犯罪において、 もっとも被害を受けるのは、 いつでも社会的弱者である子どもたちである。 保護されるべき、 保護されたい子どもたち。 その子たちが、 保護者によって歪められた。 どんなに彼らを取り巻く状況や、 保護する側が言い訳しようと、 子どもたちのとってはつらく冷たい記憶にしかならない。 そして、 その記憶は、 彼らの生きる支えにはならない。 すべての人がそんな苦い記憶を持っているわけではない。 しかし、 何らかの、共感・共苦があると思えてしまう。 そしてきっと、 人はだれも、 誰かに抱擁されたい、 そう思っているに違いない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文庫版で全5巻。最初は気が遠くなるほどの長さ、と思っていたんですが、読み始めたらそのテンポのいい展開にすぐに読めてしまった。 ストーリーは一人の少女と二人の少年を主人公に、過去と現在が交互に進められていくというもの。幼児期に受けた虐待からある事件を起こした彼らが、一度は別々の道を歩んだにもかかわらず、運命の糸に手繰り寄せられるかのごとく再び出会い、止まったままだった時間が動き出す。 二転三転する展開と心の葛藤を描く描写力、飽きさせないスピード感はなかなかのもの。リアルさに欠ける部分は多々あれど、この作品はあくまでミステリー小説、散りばめられた伏線は後半収束し、そして見事に着地する。長さを感じさせない傑作だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 似たようなタイトルで「大地の子」という山崎豊子の大河小説がある。こちらは「子」だが、本作品は「仔」の字をあてている。 山崎作品では、二つの国・二組の両親に挟まれた主人公が、成長と共に自己の存在を位置づけていく自立した人格として「子」の字が使われたのだと思う。一方、天童の作品では、親の庇護の元で存在する場所を与えられている子、さらにいつまでも自立できない精神的な子どもである大人を象徴して「子」の傍らに親が寄り添う「仔」の字なのではなかろうか? または「子」を独立した人格として認めて、お互い理解し合う存在としての友人を象徴する他者として、「人」が寄り添っているのかもしれない。 主人公たちを取り巻く環境は辛く悲惨である。そん中で、親子関係では構築できない信頼感や、救済されない気持ちが、閉ざされた空間で出会った異性の友人との間で成立するというのは一種のおとぎ話にも思える。また誰もが自分や家族に対して真剣に考えていて、それを相手にたいして真摯に語り、自分の考えや気持ちを伝え理解を得ようとする場面がある。これも現実ではなかなかあり得ないだろう。おとぎ話の形でしか救済の物語が描けないほど絶望的な状況に我々はいるのだろうか。思わず、身近な誰かに問いかけたくなる。 「生きていてもいいんだよ」というメッセージに辿り着いたとき、本書を読めて良かったなと思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これ以上の作品はないと思いました。ミステリーの中では私の読んだ中で一番です。 心を病んだ者の心情を丁寧に描いています。嵐を避けて、大きな木の下の穴で「生きてていいんだ、生きていいんだ」を3人で繰り替えすシーンは、最も好きな箇所です。 ミステリーとしての物語も完璧で、最後は「あっ」と叫ぶほど、驚きでした。絶対のお勧めです。長編ですので、まとまった長い休みにじっくりと読むことをお勧めします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「永遠の仔」という題名自身がそもそも日本語として違和感があるのだが、作品における人生観が偏り過ぎている。世の中の人々全てが幼年児期のトラウマに支配されて生きている訳ではないだろう。登場人物が全て精神的に幼過ぎるのである。その意味での作品名かもしれないが。 それに誰よりも幼い命の大切さを実感している筈の主人公が、堕胎を勧めるという矛盾。話が長いだけで、構想が破綻している。幼年児期のトラウマについて作者は勘違いをしているのではないか。人は日常の苦しさの中で、些細な喜びを見い出し、一日一日を送っているのである。それを幼年児期のトラウマを過大視して、「生きていてもいいんだよ」は無いだろう。 作者の死生観、人道感に大きな疑問を抱かせる作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ストーリーよりも、作者の人生観・人間観に違和感がありました。 主要キャラクターに、尊敬できる大人少なくとも年齢にふさわしい 精神的成長を遂げていると思える大人が皆無なんですよね。 例外は梁平の養父母くらいですか。 大人はみんな、精神的に脆い傷ついた大きな子供。 人生における苦しみは、すべて子供時代の親あるいは大人との関わりによるもの。 それがテーマだからといって、登場人物のほとんど、 主要でない端役にいたるまでが 「子供時代おとなから受けたトラウマ」に苦しむ世界には辟易です。 主役の三人だけで充分なのではないでしょうか? 自分の作品世界に登場する人間にはみんな、弱いまま、 傷ついたままでいて欲しいのでしょうか。 罪を犯したら犯したで、ちゃんと償いをする大人も皆無ですし…… 自殺するより相手の目を見て謝るべきだと思うのですが。 さらにいえば、性的虐待を受けた女性が看護婦、 身体暴力を受けて育った男性が警官や弁護士なんて仕事に ついたりしないと思います。 たとえなっても、トラウマを刺激されるばかりの仕事内容に 耐えられないのではないかと思うですが。 「生きていてもいいんだよ」というセリフも不可解です。 生物に対しそのようなことを言えるのは神さまだけです。 そして作者は神さまではありません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2000年度版このミス10 1位。 1999年文春ミステリーベスト10 2位。 2000年 第53回日本推理作家協会賞長篇部門 第121回直木賞候補作品 作者の代表作品。 直木賞の選考では、選考委員の大先生方に「作品が長すぎる」「子供同志の会話が子供らしくない」等々の評価を受けたようであり、実際読んでみると、なるほどその通りである。しかし、その不器用さゆえ、読者に強いメッセージが伝わっているように思う。作品自体は過去と現在に起きた殺人事件を軸に展開するミステリーとなっているが、まず作者が作品を通して伝えたいメッセージがあり、その表現方法としてミステリーを選択したように感じた。とにかく「力」がみなぎった作品である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2000年度版このミス10 1位。 1999年文春ミステリーベスト10 2位。 2000年 第53回日本推理作家協会賞長篇部門 第121回直木賞候補作品 作者の代表作品。 直木賞の選考では、選考委員の大先生方に「作品が長すぎる」「子供同志の会話が子供らしくない」等々の評価を受けたようであり、実際読んでみると、なるほどその通りである。しかし、その不器用さゆえ、読者に強いメッセージが伝わっているように思う。作品自体は過去と現在に起きた殺人事件を軸に展開するミステリーとなっているが、まず作者が作品を通して伝えたいメッセージがあり、その表現方法としてミステリーを選択したように感じた。とにかく「力」がみなぎった作品である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 第53回日本推理作家協会賞受賞作品 「週間文春 二十世紀傑作ミステリーベスト10」 国内部門 第10位 「週間文春 傑作ミステリーベスト10」 1999年 第2位 「宝島社 このミステリーがおもしろい」 2000年度 第1位 「ダヴィンチ 今年の1冊」 1999年 総合ランキング 第1位 「ダヴィンチ 今年の1冊」 1999年 ミステリー・ホラー・SF部門 第1位 「人生」… 人間が過去を振り返ると、それぞれドラマがあります。 それらには、一つとして同じものはありません。 その「人生」という人間ドラマの重さを本作品は再認識させてくれました。 人間誰でも自分の「人生」が一番だと思う節がなくはないと思いますが… 私は「人生」という人間ドラマの重さを再認識することで、生命の大切さも再認識しました。 親は親なりに、子は子なりに本作品を読むと考えるところがあると思います。 将来私が人の親になることができたら、再度本書を読んでみたいと思います。 その時、私が感じることは今感じたことと違うでしょう。 『永遠の仔』全5巻にレビューを載せようと思っているので、参考にしていただけると幸いです。 ソレデハ… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本を読んで気づく事。 主人公らがモウル(もぐら)、ジラフ(きりん)等と英語のあだ名で互いを呼び合っていること、設定となっている70年代は私はまだ生まれたばっかりだけれどもちょっと、やはり違和感を覚えましたね。 全体的にいえることはこの作品、ハリウッドっぽいです。・・っていう よりアメリカンの感覚丸出しです。絶対ありえない展開とかにもいえるんだけれども一番の類似点は単純な感情表現において顕著に認められます。つまり主人公らは終始表に出すか否かは問わず常に『Papa,Mama,Do you love me?』とだけ繰り返し問いかけて訴えかけています。それ以上の複雑さは彼らの意識の上には上らない。上らせる余裕がない。彼らは終始被害者で物の見方や対人意識が特殊なので本来であればついていけない筈ですが著者は主人公ら、とりわけヒロイン優希をやさしい眼差しで暖かく包み込みます。 ストーリーについて言えば、 この世界では人々は皆申し合わせたように ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『人間が人として受け入れられることの大切さを主人公らに訴えかけ、そして我が子を愛せない人は親に愛されなかった人間であるという事実』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ が嫌という程の例示によって読者に開示されます。この世界観、人間観。当作品においてこの法則に例外はありません。これを単純化にすぎと見るか悲しき真実として彼らに共感するかどうかがこの本への評価の一つの分水嶺となるかと思います。 しかしながら著者はかなり凄腕のストーリーテラーですので一旦読み始めるや否やぐいぐいと中に引き込まれてしまうこと請け合いです。筆力もそうですが登場キャラへの思い入れにも並々ないものが感じられてなりません。そのせいか私もヒロイン優希は読んでいくうちに個人的に好きになっていきました。 しかし少し冷静な眼で見ると、優希がいるのは現実世界というよりは著者の心の中にいることに気づきます。フィクションなので当たり前すぎる話ですがずばりこの作品には優希しかいません。優希中心にありえない事件が多発しますがそこに統一感を見いだすか逆に矛盾を見てしまうか、つまるところ優希への共感度、一体感のレベルによって作品への評価が決まってしまう一品かと思いますが・・あなたはどう評価しますか?とりあえず一巻は読んでおいて損はないでしょう。 個人的には接触できて良かった本だと思ってますので皆様にも是非ともご一読をお進めしたいと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 数年前にドラマを見ていたから 登場人物をそのときの俳優さんに当てはめて読み進めていったから 読みやすかった。先を知りたくてぐいぐい読めた。 早く下巻が読みたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品をミステリーという範疇に含ませていいのかどうか 壮大なドラマです。 全5巻のボリュームはどこもカットできない圧倒的なものとして 自らの魂をゆさぶられます。 主人公3人のあまりにもせつなすぎる家庭環境。 しかし現在の世の中ではとても小説の中の出来事とすませられない 悲しい現状があります。 この本はまさしく「魂」に語りかけてきます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 皆さん絶賛されていますが、正直僕はピンときませんでした。 ジラフ、モウルってあだ名で呼び合う設定から違和感を覚え、 この二人の少年のキャラクタの違いが最後までわかりにくかった。 ミステリとして読んではいけないのかも知れませんが、 伏線がないため、後で明かされる行動とのつながりがぴたっと こない印象も。 虐待する親を殺せばそれで子供は救われるのか。 虐待される側の視点はいやというほど描かれているが、 なぜ虐待するのか、という点が掘り下げられておらず単に 悪い親とけなげに耐える子供、という構図でしかないのが残念。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読みごたえのある作品でした。 単行本で二段組、上下2巻。 しかし、その厚さを感じさせないような作品でした。 ただ気になったのは、 彼らの疎外感や被害意識を際立たせるために 意図的に描いているのだとは思うのですが (あるいは彼らの目を通して描いているためか)、 医療関係者や学校関係者の3人への対応、言葉などが あまりにも無神経で、あまりにも何の知識もないように 描かれていることです。 90年代という時代のせいなのかとも思いましたが、 この点に違和感を感じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作品中に家事、子育て、介護をしなくていいのは子どもだけではないか、という内容を読んだ時にはっとした。 この三つは人間の義務であるが、それを果たしている大人は少なく、だからその足りない部分を人間は協力しあっていくことが必要だという内容だったと思う。 決して恵まれた環境で育たなかった優希たちのような人は、自分の育てられた子育てしか知らず、そうしてしまうとわかりながら、同じような子育てを繰り返してしまうことがある。だから梁平のように親となることを恐れる人もいる。 ここで「協力」なのだと思う。優希たちはすべてのことを「自分がもっとしっかりしていれば」と背負い込んでしまう。自分で自分を責め閉鎖的になるのではなく、周りに相談し協力してもらえばいいのだ。これは優希たちのようにあまりにも辛い過去を背負っている人には難しいのかもしれない。しかしすべての人に言えることだと思う。 この作品に対する感想としてはあまりにも幼いものだと自分でも思うが、自分が幸せに育ててもらったことに感謝しつつ、親、子どもを大切にすること、そしてうまくいかないことは協力しあっていくこと。大切で当たり前のことを学びなおした気がする。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!