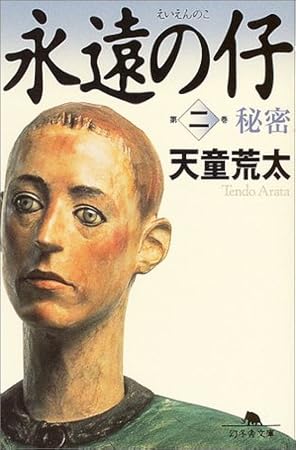■スポンサードリンク
永遠の仔
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
永遠の仔の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.56pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全165件 81~100 5/9ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 以前、ハードカバーを買って、読んでいたことがあり、たまたま、読書好きの知人に勧めました。感激していました。もう一度、同じ感激を味おうと思って、再び、購入してしまいました。やはり、生涯で読んだ中で最高の本だと思います。よく東野圭吾の白夜行と似ていると言われますが、全然、内容の深さが違います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 親に存在を否定され続け、自分の存在意義を見出せないまま大人になってしまった。 そんな人に読んでみて欲しい。 もしかしたら救いになるかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 坂本龍一 Lost Child が気に入って10年ぶりに読み返した.今の時代だからこそ,もう一度読み通したい.子育てを経験して初めて理解できることも多い.この本のメッセージを十分に理解するには,もっと自分の時間が必要かもしれない.大人のもろさ,子どもの強さを思い出せる小説. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 被虐待児を美化し、虐待親への復讐の殺人を神聖なものとして書いてある。よく虐待は連鎖するものと言われる。親から子、大人になった子から孫へと。親を恨まず、子に同じことを繰り返す。しかしそういうことは特に描かれていない。書かれてあったのは許せない親への復讐計画。一昔前までは最も罪の重い尊属殺人だ。本の中で、虐待が重く書かれているのに対し、親への殺人は重くないし、是認しているようにも読み取れる。虐待されて傷ついたからって親をやってはいけない。やってしまうとそれは犯罪になる。だからみんな苦しんでいるのだ。虐待は悪いが、殺人も悪い。著者の方は実際にあった栃木実父殺害事件を参考にされていて色々踏まえて書いておられるのだろうが、私は単純に感動はできなかった。心の中で恨むのは分かるが、行動に移すのはどうかと。恐ろしく、悲しすぎる。文脈から、ラストはある程度推測できる。文字の量はかなり多く、読みごたえはある。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 一気に読ませていただきました。面白いという表現より物語に引き込まれる作品でした。推理物としてではなく、人生について非常に考えさせられる本だと思います。 娘がまだ小さいので、良い時期に読ませていただきました。構成についてはもどかしく感じましたが、物語に深みをあたえていて、引き込まれる要因になったのでは と読後には感じました。この作者の他の小説も読んでみようとおもいました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初版時に読了。 でも、ずっとレビューを書けませんでした。 簡単には言葉にできない深い読後感。 虐待を受けた子が心に刻みつけていく傷口を 丁寧に描写しています。 長編です。 未読の方は、すべてが解き明かされるラスト5巻まで どうぞあきらめずに読み進めてみて下さい。 きっと心に「何か」を残すはずです。 これから親になる人、今子育て中の人に特にお薦めします。 子育てをする時に最も注意しなければいけないのは、 その子の心に、親の手で「傷」をつけないこと。 どんな育児書よりも雄弁にそれを語っています。 日本推理作家協会賞受賞作。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 上巻で大体筋書きが予想出来たので、下巻にはくだくだしい説明やあり得ないほどに大人じみた子供どうしの会話が濫用されているように感じた。一巻におさめればよかった。あり得ない子供どうしの会話もさることながら、非常識な状況で幼少期を送った思春期の子供が、厳格な教育を受けて育成された大人の知性にのみ可能な「常識」とその言葉を備えていることに驚かされる。リアリズムではない。少年少女の登場人物は、おそらく作者の理想の大人の像である。無垢で無防備な者が不条理の暴力の犠牲にさらされるという状況は、古来人々の理性を揺るがす深い哀惜と激しい悔悟の源で、歴史的にはその哀惜と悔悟が「魂」の語を生んだとも言えるのである。しかし劇作家がよく理解しているように、こうした状況を感動を生む形で表現することは至難の業である。悲劇は他人事としてみる限り無関心の対象、あるいは喜劇にしか見えないという事実は、それ自体が悲劇的だ。たびたび報道される児童虐待において、いかなる状況で虐待の事実が傍観者の心を動かしたのかを考えればよく分かる。マスコミや法廷という劇場で事件が演出され、子供が被害者の姿で認識されてはじめて、一般大衆は涙した。安易な自己投影によって、それまで隣家に起こっていても介入しなかった事件は、人類史上の悲劇と認定された。演出は次第に紋切り型になり、人々はいずれ飽きてしまうだろう。想像を介した他者への共感は、思う以上に社会的な価値基準のバイアスを受けている。一定の状況で社会的価値基準とされるものは、常に言葉の一側面にすぎない。普遍的とされる憐憫の情は通念に還元されること多々である。広義の写実主義と小説ジャンルが切り離せないものであるならば、小説家はそうした社会通念こそを相手にすべきと思う。他方、肉体を蝕まれ、恐怖の中で起居する子供の精神状態を「そのまま」映し出したところで、感動を呼ぶことが出来ただろうか。おそらく、嫌悪感が先立ち、小説ならば不成功に終わったことだろう。スキャンダルとなったかもしれない。さらには、人間の意図外にある「悪」をそこに描き出す集団被害妄想を生むところまでいったかもしれない。リアリズムが美学として成り立つためには一切の感傷主義を排さなければならないが、大衆は感傷を、感傷だけを求める。感傷と写実は大衆心理において齟齬しない。この小説においてもしかりである。最近のテレビドラマがそうであるように、実際のところこれは大人による大人の目から見た子供のための復讐劇である。ユートピア思想の表現であり、ウェスタン的な勧善懲悪の欲求の昇華手段だろう。それならば完全に幻想小説にしてしまうことも可能だったと思う。反対に作者は、子供たちに言語操作の能力と、自らの状況を客観的に見据える「常識」の目(そんなものを持っていたら天才だ)を与えることで、外部からは決して見て取ることの出来ない無言のドラマに感傷的悲劇性と写実の印象を同時に与えようとしている。無茶な試みである。写実主義小説が人の心に耐えることの出来ない現実の諧謔であるという意識を失っては、おそらく持続的な感動を呼ぶことは出来ない。この小説が「リアルで怖い」と思う読者がいたなら、その人の心は、汚れてはいないとしても、あまりに弱いのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 上巻で大体筋書きが予想出来たので、下巻にはくだくだしい説明やあり得ないほどに大人じみた子供どうしの会話が濫用されているように感じた。 一巻におさめればよかった。 あり得ない子供どうしの会話もさることながら、非常識な状況で幼少期を送った思春期の子供が、厳格な教育を受けて育成された大人の知性にのみ可能な「常識」とその言葉を備えていることに驚かされる。リアリズムではない。少年少女の登場人物は、おそらく作者の理想の大人の像である。無垢で無防備な者が不条理の暴力の犠牲にさらされるという状況は、古来人々の理性を揺るがす深い哀惜と激しい悔悟の源で、歴史的にはその哀惜と悔悟が「魂」の語を生んだとも言えるのである。しかし劇作家がよく理解しているように、こうした状況を感動を生む形で表現することは至難の業である。悲劇は他人事としてみる限り無関心の対象、あるいは喜劇にしか見えないという事実は、それ自体が悲劇的だ。 たびたび報道される児童虐待において、いかなる状況で虐待の事実が傍観者の心を動かしたのかを考えればよく分かる。マスコミや法廷という劇場で事件が演出され、子供が被害者の姿で認識されてはじめて、一般大衆は涙した。安易な自己投影によって、それまで隣家に起こっていても介入しなかった事件は、人類史上の悲劇と認定された。演出は次第に紋切り型になり、人々はいずれ飽きてしまうだろう。想像を介した他者への共感は、思う以上に社会的な価値基準のバイアスを受けている。一定の状況で社会的価値基準とされるものは、常に言葉の一側面にすぎない。普遍的とされる憐憫の情は通念に還元されること多々である。広義の写実主義と小説ジャンルが切り離せないものであるならば、小説家はそうした社会通念こそを相手にすべきと思う。 他方、肉体を蝕まれ、恐怖の中で起居する子供の精神状態を「そのまま」映し出したところで、感動を呼ぶことが出来ただろうか。おそらく、嫌悪感が先立ち、小説ならば不成功に終わったことだろう。スキャンダルとなったかもしれない。さらには、人間の意図外にある「悪」をそこに描き出す集団被害妄想を生むところまでいったかもしれない。リアリズムが美学として成り立つためには一切の感傷主義を排さなければならないが、大衆は感傷を、感傷だけを求める。感傷と写実は大衆心理において齟齬しない。この小説においてもしかりである。 最近のテレビドラマがそうであるように、実際のところこれは大人による大人の目から見た子供のための復讐劇である。ユートピア思想の表現であり、ウェスタン的な勧善懲悪の欲求の昇華手段だろう。それならば完全に幻想小説にしてしまうことも可能だったと思う。反対に作者は、子供たちに言語操作の能力と、自らの状況を客観的に見据える「常識」の目(そんなものを持っていたら天才だ)を与えることで、外部からは決して見て取ることの出来ない無言のドラマに感傷的悲劇性と写実の印象を同時に与えようとしている。無茶な試みである。写実主義小説が人の心に耐えることの出来ない現実の諧謔であるという意識を失っては、おそらく持続的な感動を呼ぶことは出来ない。 この小説が「リアルで怖い」と思う読者がいたなら、その人の心は、汚れてはいないとしても、あまりに弱いのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今、下巻の300頁。 このまま朝まで読破するか、明日にとっておくべきか。 先に進みたいけど、終わってほしくない。すごい。面白い。 運動会の昼食のシーンは、思わず涙がこぼれました。 虐待は許せないが、娘に火傷を負わせるに至る母親の気持ちはよくわかった。 同意できたのではなく、理解できた。 父親の無責任さが我が身を振り返らせて、眠れない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 家族というものは小説の題材にはうってつけではあるが、実にナイーブなものであるために、同時に書き手の力量がことさらに重要視されるものでもある。天童は、その家族を取り扱った群像劇に拘りを持った作家であるが、そんな彼の作品群の中にあっても、これはとりわけ刮目すべき書だという事実に異存はない。 酷薄な運命に嘲弄されることになる三人がかつて霊山の頂で得た「神」は、本物の神だったのか、或いは、邪なものだったのか。その霊妙な序章から、人知を超越した魂のドラマの幕開けには充分で、作者の豊かな想像と創造の一閃が感じられる。 医療、法曹、公僕。進路は違えど、いくら努力しても決して満たされない主人公達は、自らが犯した罪がもたらす鎖に捕え続けられている。禁忌を共有することで絆を結ぶ三人の悲しき仔が、成長し、偶然の再開を果たしたことから、誘発されてしまう新たな悲劇。想念が交錯し、倒錯すると共に、彼らの歯車は狂っていく。 三人による神の山での事件を端緒とした運命の歪みと、それゆえの彼らの社会へのデタッチメント。罪が罰を呼ぶのか、それとも、全ては最初の殺人から彼らの神の意思だったのだろうか。家族の脆さや人間の弱さといった、社会を取り巻く救いようのない現実を表象する作品の底流のソリチュードに、頁を繰る者は否応なしに突き上げられることになる。 未だ上巻の段階故に、その伏線は朧であり、結末が待ち遠しくなるが、一方で、下巻へ手を伸ばすのは躊躇われもする。それはひとえに、物語を包み込んだ妖麗ともいえる光明のせいかもしれない。終幕に待ち受けるのは奇蹟か破滅か。神秘のドラマはまだまだ続く。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大人になるとはどういうことなのか考えさせられる作品です。 読み終えた後はきっと優しくなれると思います。 過去の話が多少長い印象もありましたが、その描写力には感嘆します。 心身ともに愛を求めた続けた3人の悲しい話で、無性に悲しくなりますが、 彼らを救うためにも是非最後まで読んでみて下さい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 数多いるミステリ作家の中でもこの作家は頭一つ抜けていると思います。 ストーリーの重厚なこと重厚なこと! 人間関係ひとつとっても泥臭さ、生臭さがリアルきわまりない。 文句なしに今年読んだ本の中では一番の出来でした。 一つ難癖をつけるとしたら、伏線の張り方があけすけであること。 弟が脳障害で息を引き取る際、直前に面会した姉が彼の異変に気付かなかった理由付けのためでしょうが、少年時代の彼をくどいほど洟垂れにするのは如何なものかと・・ それだけが惜しい。あとは文句のつけようがない出来栄えだった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 児童虐待がテーマで 涙なしでは読めない作品。 ハッキリ言ってすごく重い作品。 その他にも、アルツハイマー、介護問題、等 決して他人事ではない問題も描かれていて。 こういう話、今の時代 きっと現実でも起こっているんだろうなぁ…と思うと 哀しくて辛くて切なくてたまらない気持ちになってしまう。 かなりの長編だけれど 感情移入してしまうので、全然長さは感じず 一気に読み進むことができた。 読み進むうちに 10年ぐらい前に見たドラマのシーンが 頭の中に浮かんできて ドラマの内容なんて忘れていたはずなのに それぐらい印象に残ってた作品だったのか、と驚かされた。 後書きに書かれていた 「子」ではなく「仔」にした理由。 それを読むと、また涙があふれてきた。 「優希」も「笙一郎」も「梁平」も 本当に存在していたような錯覚に襲われる。 本編の最後の2行 声を大にして3人に伝えてあげたかった。 もう一度見てみたくて ドラマのDVD借りました。 またじっくり観直そう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ボリュームのある上下巻。 読み終えるまで、私はたっぷり2週間かかりました。 約10年前にテレビドラマを見てしまったので、 原作には手を付けませんでした。 そろそろその記憶も消えた今、新たな気持ちで読んでみましたが、 そのなんと重いこと。 特に上巻は子ども時代の描写がつらく、 読んでいない時も気持ちがふさがれるほどでした。 子どもは親を選べません。 人間としてどんなにダメな親であっても、子どもは自然に求めてしまいます。 主人公三人は、幼少体験が悲惨であったが故に、 いつまでも理想の親を捜し求め、大人になることがかなわなかった、 そんな気がします。 ”私がこの子達だったら”、”私が親だったら”と、 自問自答せずには読むことの出来ない作品でした。 色々な世代の方におすすめしたいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作品はすばらしいですが、タイトル通りです。誰が悪いと言うのは簡単ですが、人間の作り出す社会は、こんなにも残酷なのだなあと思ってしまいます。救いがなく、読み終わって、じゃ、親として、子として、どうすりゃいいんだと深み落ち込んでしまいます。まあ、それがテーマの小説なのかもしれませんが。 一つだけ、気になる点とすれば、第8病棟の英語のニックネーム。ちょっと凝りすぎ。誰かそういう凝った名前をつけたがる登場人物が出てくるならいいんだけど、あんなニックネームは自然とつくとは思えないです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 子供をめぐる痛ましい事件のニュースを目にする度に、この本を思い出します。 親の人生の歯車がどこからずれ始めたかは、それぞれですが子供たちに大きな傷を負わせ、”負の連鎖”という言葉が頭の中をよぎります。 悲しく重い内容ですが、最後に僅ながら光が差し込みます。 人間が背負う業を取り上げながら、何処かに救いがある遠藤周作の小説を思い起こします。 作者の後書に編集者への謝意が述べられていました。 天童 荒太氏がこの小説を書き上げる為、心身共にどれだけの労力を費やしたか想像も付きませんが、編集者の強い想いもあって始めて成立した力作でしょうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今年の直木賞を受賞した、天童荒太の作品。 前から気になっていた作家でした。 行きつけの古本屋で上下¥200で発見。即買い。 しかし、¥200で購入したことを申し訳なく思わされるような、素晴らしい作品でした。 この「永遠の仔」。 単行本は二段組みで、上下2巻。 結構な厚さですが、2日間くらいで読み終えました。 読んでないときは、 何をしてても話の続きが気になり、手に付かない。 読んでいるときは、 病院で順番待ちをしているときも、自分の名前を呼ばれても気付かない。 周りの音が一切、入らなくなるような不思議な感覚。 それほど、この本の中に入ってしまうのです。 そして息を詰めるように読みすすみ、優希、モウル、ジラフの生き方を見つめる。。。 この作品は、ミステリーなのでしょうか? 私にはもっと違うように思えます。 長い長い物語を読み終えたのは渋谷の喫茶店。 こみ上げてくるものもありましたが、一番は 切ない。 切ないよ。 生きるって、こんなに切なかったっけ? 本当に読みごたえのある作品でした。 おすすめです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「悼む人」を読んで著者を知り、本書を読んだ。 内容、完成度ともこちらのほうが遥かに高いと思う。 読後は爽快感よりもモヤモヤとした霧の中にいるような、 感想を言葉で表現することが難しい、いろいろと考えさせられる本である。 いわゆるインスピレーションを与えられる、優れた良書だと思う。 子どもの心がいかに繊細で傷つきやすく、また大人になってからも 子どもの頃に感じた様々が、いかに影響を及ぼすもので あるかということを思い知った。 哀しくて痛い内容だったが希望もあった。 そしてそれはどんな状況におかれても消えることのない 人生の、生きるうえでの灯だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本に出遭えたことを感謝したいです。 これまで、自分はあまり小説など好んで読む人間ではなかったのですが、 あるラジオがきっかけで興味を持ち、読ませていただきました。 読み進める上で、人間の奥に潜む欲望・葛藤、そして醜さや脆さといった部分をすべて見せつけられているような、しかしその一方で、「生きること」の意味を深く考えさせてくれるような感じを受けることができました。ここまで心を揺さぶられた本は初めてです。 ぜひ一読してほしい作品ですが、特に、20前後の(自分のような)多感な時期である方にはぜひ読んでほしいと感じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 虐待の恐ろしさを書いているだけだったらここまで引き込まれないと思う。 私が一番好きなのは森の中のシーンです。 まるで自分が一緒にいるかのような、子供としての気持ちに返り、 息が詰まるような切なさ、苦しさ、本を読んでる事を超える臨場感。 読んだ後、しばらく衝撃で動けなかったです。。。 ぜひ虐待を受けた方は、最新のカウンセリングを受けて、克服して頂きたい。 じゃなきゃ悲しすぎる。 相手を超えて、ゆるしていかないと(ゆるすのは相手のためではなくて自分のために) 幸せにならなければ一生虐待側の思うつぼではないでしょうか。 虐待の連鎖を断ち切る、苦しみを断ち切ることがこの本の意味ではないかと。 自分の子供は大事に育てたいと思いました。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!