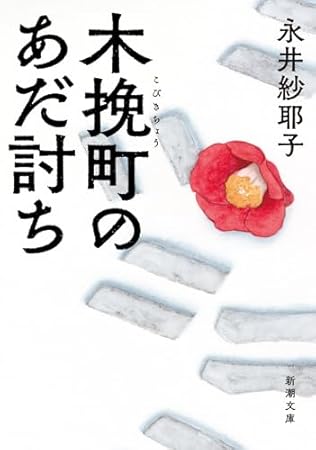■スポンサードリンク
木挽町のあだ討ち
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
木挽町のあだ討ちの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.26pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全101件 21~40 2/6ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 江戸の人情と謎解きの面白さがバランスよく書かれていて、楽しめました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 芝居小屋を主たる舞台にしていることにかけて、5つの幕と最終幕で構成した物語。 それぞれの幕は、その幕の主人公の一人語りの形で描かれて、特に時代がかったセリフ回しでもあり、中盤くらいまではテンポが悪く感じられた。 のではあるが、中盤くらいからはそのセリフ回しがそれぞれの登場人物の個性を描き出し、内容に厚みを与え始めてきた。 「藪の中」のような、「オリエント急行殺人事件」のような読後感。 幕の引き方がなかなか乙であった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 面白いって! なんだか泣けてしまう場面もあり、本当に面白かった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み進めるにしたがって、木挽町の各人の言葉から徐々に真実にせ まり、最後はすばらしい仇討ちの詳細が明かされる。直木賞にふさわしい小説でした。淡々とした流れが、ゆっくりと深く人生を描いていく。主人公と木挽町の皆様の生きざまの真実に迫る物語。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 漢字が難しくてめげそうになるけど、 時代背景や仇討ちの仕組みに面食らうけど、 「悪を懲らしめる」と言う単純な話ではなく、 色々な人と触れ合い見聞を広め、 それこそ清濁合わせ呑んで、生きていく。 ただ単に歳をとったから元服するのではなく、 深く考え、生きていく。 これが大人になるってことだよね。 話を読み続けると、 久蔵あたりで、オチはなんとなく分かるけど、 それぞれの登場人物がどう思っているかを知りたくなって、熱中しながら読めました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| インタビュー形式で複数の目撃者からの証言を積み重ね「あだ討ち」の真相を少しづつ明らかにする展開。普通ならば証言者の生い立ちなど物語の裏として現わさないのをじれったいほど描写してしまう。それが最終展開に重要な意味を持ってくる。完全に著者の思惑にはめられました。 映像化すると楽しめそう。仇討ちというと血なまぐさいドロドロした感情と正義への葛藤が全編にただようと想像していましたが、逆にそれを踏まえながら明るいあと味を感じさせる結末は良い読後感を与えてくれました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初はあだ討ちをそれぞれの立場から見た語り、またその個人の生い立ちなどが語られ、興味もスローでした。が、第五幕から徐々に引き込まれていき、そこからは一挙に読みほしました。最近読んだ本の中では一番面白かったかもです。 作者の表現力が凄く、私にとっては勉強にもなりました。永井さんの本を読みたくなりましたが、この「木挽町のあだ討ち」以外でお奨めがありましたら、お教え願います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最後のドンデン返し。仇討ち制度があったとは知らなかったけど、この制度が伏線。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者さんと編集さんがあまり江戸期の芝居や歌舞伎には詳しくないんだな(ところどころ語彙がおかしい)というところが気になりましたが、総じていい作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本周五郎賞の受賞作を好んで読書しています。本作は直木賞受賞もしていますが、読み終えて、これはまさに山本周五郎の正当なる系譜の作品だと感じました。 登場人物たちの実に生き生きとしたこと。 どの人物の語りもその語感が素晴らしく、それぞれの人物の人生観、価値観に裏打ちされたリズムでもって語りかけてきます。 この登場人物毎の語るリズムが読んでいて実に心地いいのです。 多くの方が「一気に読んでしまった」というレビューを書いていらっしゃいますが、本作のこのリズムの良さは間違いなくそれに加担していることだと思います。 ひとたび朗々と語りだした人物の言葉を途中で区切るなんて、そうそうできることじゃありません。一気に読んでしまいたくなります。 途中泣いたり笑ったりしながら一気に読み終え、爽やかな読後感を味わうことができました。 とても良い作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 芝居小屋の前で起きたあだ討ち。この事件や自分の来し方を、縁のあった木戸芸者(いわば呼び込み・広報)、立師(殺陣の師範)、衣装係兼女形、小道具係、戯作者(筋書き作者)が語る。 語りでは、武家の四角四面の世界と異なる、町人、特に「河原乞食」とまで賤視されていた芝居の世界の住人の豊かな世界が浮き彫りとなる。そして最後の章でこの事件の意外な真実が…。 直木賞受賞の時代物エンタメ。人情モノであり、かつ読者をアッと思わせる仕掛けがある。すごい。 筋書き作者の「芝居を馬鹿にするんじゃねえよ」というセリフが本作を象徴しているように思えた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| すごい衝撃的な読了感!! 数十年ぶりに自分の中のランキングナンバーワンが更新されました! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とても良くできた 人情味あふれるお話で あっという間に読み終わってしまいました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 一つ一つの出会いが極めて重要 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本好きの間で大層評判になっているので読んでみた。ジャンル分けすると、時代劇で人情ものでちょこっとミステリーという感じ。期待通り面白かった。芝居小屋の呼び出しや小道具係など、裏方さんの人生が語られるのだが、よくもまあこんなプロットを思いつくなと感心しきり。 だから、266頁という、今売れ筋の小説としては比較的短い部類に入る本作には、多くの魅力的な人生が詰まっている。読後に知ったのだが、直木賞と山本周五郎賞をダブル受賞している。道理で面白いはずだ。きっと映像化されるはず。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎好きにはたまらない小説です。さりげなくNew Waveの時代小説になっています。 一粒で4度美味しい小説です。江戸期の芝居小屋を支える人々を描くことで、この小説は読者に歌舞伎の原初的姿を知る楽しみを提供してくれます。と同時にこの小説は極上のミステリーでもあります。と同時に、建前やシステムや掟や慣習を超えて、どんな時代にせよ、人間が自分の心の声に従って生きることへの賛歌でもあります。同時に、この小説は、人間がリアルと感じることは、その人間が消費してきたフィクションをなぞっているだけであり、現実とは別物であるということも教えてくれます。 江戸時代の芝居小屋の近く、ある雪の晩に、あだ討ち事件が起きました。凛々しい少年武士によって起こされたものでした。 その少年武士は、故郷からひとり江戸に出てきて、父の仇を求めつつ、芝居小屋の黒子として働きます。その少年のことを気にかけ情をかけるのは、芝居小屋の前で劇の筋と立役者の台詞を口真似で紹介して客を呼び込む男に、役者に殺陣(たて)を教える元武士に、衣装部屋で舞台衣装を仕立てたり繕ったりと働く元蔭間の脇役女形に、小道具職人夫妻に、当時は筋書と呼ばれた芝居台本作家。 彼らは、少年のために、一世一代の芝居を打つ。それはどんな芝居だったのか? 非常に読後感が爽やかです。登場人物たちの市井の人々の気風の良さに人品の高さ。 寝床でちょっと読み始めたら、止まらなくなってしまい夜が明けてしまいました。どーしてくれるの!! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 食いつめた人間、訳ありの人間、 〜等々 様々な人間が吹き溜まる場所、悪所。 しかし、そこにいる人々の何とあたたかいことか。 そこにたどり着いたのがあだ討ちを使命とする菊之助。 悪所にいる海千山千の訳ありの人間たちが菊之助に惚れ込む。 芝居小屋に関わる登場人物一人一人の人生模様も様々で、だからこそ菊之助を放っておけなくなるのである。 そして、そのことが結果としてあだ討ちを「成功」させることになる。そして、その絵になるあだ討ちのシーンの何と劇的なことか。後日談も含め余韻の残る物語であった。 鬼平の、四季折々の風景に重なるジプシーキングのタイトルシーンを想起した。 本作を丁寧に作り込まれたドラマを見てみたい。 登場人物を動かし、ストーリーを回した本作の作者こそが一番の「戯作者」ではないだろうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 語り口がテンポよく、良い気分で読み進めました。ありがとうございます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 江戸時代は芝居小屋が様々な階級の人達がそれぞれの分担と自分の器量をうまくあわせ芝居がなりたっている さまはまさに当時の人間模様を写した社会でそれぞれの創意で建前社会の武士階級に投げかけられた 人の生き方が実にこの小説をひじょうに楽しく読ませていただきました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「木挽町のあだ」が最高の舞台でした。ありがとうございました。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!