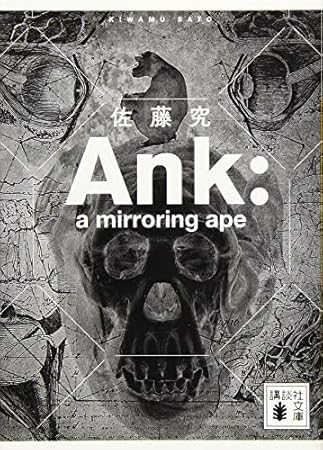■スポンサードリンク
Ank: a mirroring ape
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
Ank: a mirroring apeの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.59pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全27件 1~20 1/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 鏡の中の自分自身に殺される同胞を見てしまった。私の目の前にも「鏡の中の自分自身」がいる。さて、どうしようか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 佐藤究『ank』読了。 まず冒頭に、本書内で事実と異なる可能性のある記述について、指摘しておきたい。 • ゾウの祖先がデイノテリウムであるという記述が見られるが、正確にはデイノテリウムはゾウの祖先ではない。 ゾウに似た姿を持つ近縁グループであり、これは収斂進化の一例にすぎない。 • また、「太陽の光が地球に届くまで8分20秒」とあるが、(※ある人物が8分19秒に修正したことが、ある意味で象徴的な場面となるが、ここではネタバレを避けておく)この数値も厳密には一定ではない。 地球は楕円軌道を公転しており、太陽との距離は日々変動している。 最も近い近日点:約1億4700万km → 約8分10秒前の光 最も遠い遠日点:約1億5200万km → 約8分30秒前の光 → 年間で約10秒の誤差が生じている。 …と、こうした蛇足めいた科学的注釈はさておき、本書の主題はそこではない。 本作の核心は、“鏡”という象徴を軸に展開される深遠な物語である。 思い返せば『テスカトリポカ』でも、“水”や“鏡”は象徴的に扱われていた。 おそらく、これらは佐藤究の中核的なテーマであり、「自己とは何か」を問うための装置=メタファーとして位置づけられているのだろう。 本作で描かれる「自己鏡像認識能力」とは、社会的・心理的には共感・同調・集団行動・高次のメタ認知へとつながる進化のステップである。 そしてそれは、人類が“他者の心”を映すために獲得してきた認知機構=ミラリングに通じていく。 作中では、特定の類人猿がこの能力を獲得するに至るまでの経緯が、本能・遺伝子・歴史・科学・進化論の視点から重層的に描かれる。 それはまるで、暗闇の中で一筋の光が真実を照らしていくかのようだ。 だが、読み進めた先にあるものは、決して純粋な希望ではない。 光に照らされるのは、人工的な不安の影であり、読後には静かに揺れる疑念が残る。 それでも、読み応えは確かにある。歯ごたえがある。 鏡が自己を映すように、人類もまた歴史の鏡に自己を映し続けている。 だが、その鏡は真実を映すだろうか? 歴史は繰り返すが、決してそのままの姿ではない。 ミラリングとは、他者を見ることで自分を知ろうとする過程だ。 けれど、最後に立ち戻るべきはやはり、自分の内側だ。 「過去に縛られるな。しかし未来を恐れすぎるな。歴史の鏡を見続けろ」——そう書き残しておきたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 暴動シーンで「眼球」って単語が出てくるたびにひえーって感じだったし(まつ毛が一本入っただけでめっちゃ痛いのに)、結局なんだかよくわかんなかったとこも多々あったけれど、個人的に好きなポイントがいくつかあって、 ①パルクール使いの少年←めっちゃカッコいい ②神話(ナルキッソスとエコー)の中に残されている失われた人類の記憶ってとこ ③小道具(ガルウィングのスーパーカーとロレックスの腕時計)の使い方 そこの部分だけで、なんかもう全てが許せる気分になる不思議な小説でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 面白いです。 人類の進化に興味がある人は思いと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ●すごい小説に出会ってしまった・・・ 前半は知的探究の静的な高揚、中盤以降は凄絶なバイオレンスの連続です。メリハリの利いたダイナ ミックな展開です。ジェットコースターに身を任せた私は、上下左右に揺さぶられっぱなし。絶叫し たり嘆息したり・・・。ラストは痒いところに手の届くような伏線の回収と興奮を静めるためのエピ ローグにただただ感心するばかりでした。 SFの科学的発想をベースにミステリーの謎解きにも似た論理展開。大型類人猿や自己鏡像認識、St Sat反復・・・等々まるで脳科学の論文を想起させる迫力です。 本書は大藪春彦賞と吉川英治文学新人賞を受賞していますが、なぜかSF関連あるいはミステリー関 連の賞は受賞していません。斯界の文壇はこれ程の秀作に全く目を向けていなかったのでしょうか。 それとも排他的な感情を抱いていたのでしょうか?残念です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 丁寧に調べ尽くされた霊長類の進化に関する圧倒的な情報。そして時期と場所それぞれ違えた地点からの描写は読者を決して飽きさせることなく、この「異常」な事態に没入させる。あまりに痛ましい事態にも関わらず読後感に何か温かいものを感じるのは何故なのだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 著者の本は4冊目だが、一番すごかった。感動はしなかったが、よくもまあこんなことを思いつくなあと感心した。殺戮の原因としてあの着想を得てから、物語の構成を練って、矛盾なくわかりやすく長編小説に仕上げるのは、さぞかし大変だっただろう。これを読んで連想した他の作家は篠田節子でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『わぉ!』 これは力作ですよね。 佐藤究さんの作品を読むのは初めてなのだよ。 SF小説として大切な(理論や技術に裏打ちされた)説得力が揺るぎなく物語の屋台骨を支えているので、読者は最後まで安心して身を委ねていられるのである。 『わぉ!』 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 鏡映反転認識とても興味深いでした。人間とチンパンジーの遺伝子の違い1.8%の差の人類進化の謎、これは小説なのか?時系列が逆転しながら進めていく編集がまた斬新な新感覚な作品でした。引き込まれていきますよ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 先月、佐藤究の最新作である『テスカトリポカ』を読んで、構想は壮大だが粗が目に付くとレビューしたところ、友人から「『Ank:』は読み始めたら止まらなかった」というようなコメント貰い、それならと読んでみた。 感想は、まったくその通りで、ジャンルとしてはパニックSFとでも言うのだろうか、マイケル・クライトンの『アンドロメダ病原体』やその続編『アンドロメダ病原体 変異』とも共通したものを感じるが、本作はこれらの世界的大ヒット作にも負けてはいない。 類人猿が900万年ほど前に獲得した鏡像認識を物語の核にしながら、京都に新設された私設の霊長類研究所での秘密の研究、そして突然勃発する京都暴動という流れで、ストーリーは息をつかせぬテンポで疾走していく。 主人公たちの人物造形も厚みがあって、説得力がある。 どんな小説にも無理筋というのはつきもので、それが目についてくるのは展開力や表現力が追い付いていない場合である。 本作でも、当然にも無理筋はあるのだが、それを覆い隠すだけの展開と表現に黙らされるしかない。 しかも、本作のタイムスパンは900万年だ。 大した作品である。 こんなすごい小説を読んだ後は続けて小説ではなく、少なくとも1冊はノンフィクション系を読まないと、心のバランスが取れない。 次はジェームズ・C・スコット『反穀物の人類史』を読む。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| テスカトリポカより「明るく」、サージウスの死神より「楽しい」作品。天文学的な巨額になると思われる故、映像化は未来永劫ないだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品は丁寧に包装され、発送時期も速やかに行われた。商品は古書でありながら、十分満足のいくものでありました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| SF映画『planet of the ape』は日本で公開された際『猿の惑星』と訳されたことから、日本人の多くはあの映画は「猿」が地球を支配したと思ってしまいがちですが、「ape」は「類人猿」ですので、あの映画で地球を支配したのは「monkey:猿」ではなく「チンパンジー」なのです。 チンパンジーと猿との間には、知能の高さに格段の差があり、人類にとてもよく似通った遺伝情報をもつチンパンジーを研究することは、人類進化の謎を解く格好の研究対象だといいます。 霊長類研究者である鈴木望の研究は、まさに人類進化の謎を解く一歩手前まできている。 そのキーワードは鏡。 そして本書のタイトルは『ANK:a mirroring ape』 古代エジプトでは、鏡は単なる日常生活品ではなく宗教的意味合いを持っていた。鏡は古代エジプト語でアンクと呼ばれ、生命との意味でもあるという。 この「人類の進化」に触れるSF作品というだけで、もう無上に期待が高まります。 京都市で発生する謎の暴動と、ヒトの遺伝子レベルの話を絡めてくるあたり、思わずお見事と言いたくなる盛り上げ方です。 突然、攻撃性をむき出しにした人が、目に付く他人を素手で攻撃するとの設定だけ聞くと、ダニーボイル監督のイギリス映画『28日後』を彷彿させますが、あちらはウイルス感染により攻撃性を増した人々がゾンビのように他者を襲うというものでしたが、本作で凶暴性をあらわにする人々からは何ら感染を疑うウイルスなどは検知されない。 しかも攻撃性が現れるのは、約8分20秒の間だけ。 その間は、完全に理性を失った人々が暴徒間で殺戮を繰り返す。自身の手の骨が折れようと関係なく、その白骨が露出した手で他者を殴りつけるという凄まじさ。 いったい何がヒトをそうさせるのか。 『a mirroring ape』とは何を意味するのか。 一気読み必至の面白さです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| グロテスクだけど、とても面白かったです。普段レビューしない自分がレビューしたくなるくらいこの作品は好みでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 衝撃を受ける作品であることは間違いない。 想像もしないテーマ、結末であった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| サイエンス分野の小説が増えるのは嬉しい。専門用語でごまかす感じがなく、丁寧な文章でこれからの作品が楽しみ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文芸作品沢山読むほうではないですが、久々にひとりで本屋を見て回れる時間ができ、あらすじに惹かれて購入。 あまりにも面白く、読む手が止まらず睡眠時間を削って一気読み!読後の高揚を忘れたくなくて、思わずレビューします。 散りばめられた科学的・神話的トピックとその連関はどれも純粋に興味深く、驚かされる。 物語の根幹部分についても、ある種の「エビデンス」から離れたものであったとして、その飛躍を醍醐味と思わせてくれる物語の力を感じた。 ちょうど2歳になり言葉を覚えはじめた息子を、有史以前の果てしない時間を感じながら見つめてみたいと思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| 【ネタバレあり!?】 (1件の連絡あり)[?] ネタバレを表示する | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本のタイトルにある通り、鏡がキーポイントである。 人類、類人猿の進化の謎に触れている部分が面白く、全体を通して スケールが壮大で、もし今後映画化されることがあれば観たいと思った。 終盤に出てくる有史以前の話が神秘的で物語をうまくつないでいる。 表現やシーンのつなぎ方に磨きがかかれば星5つだと感じた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| 【ネタバレあり!?】 (1件の連絡あり)[?] ネタバレを表示する | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!