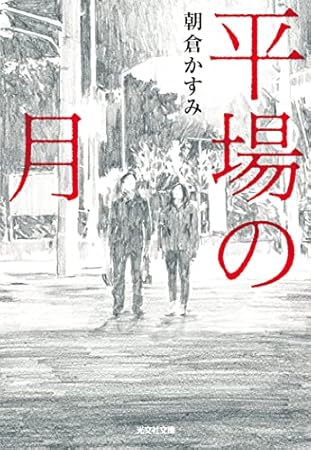■スポンサードリンク
平場の月
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
平場の月の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.04pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全145件 61~80 4/8ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 青春時代に戻れたら、あの日もしきちんと勇気を出して彼女に告白していたら、その後の自分の人生はどうなっていただろうか? どんな人生を送っていても自分は自分らしく生きられただろうか? 私より10歳以上は若いこの男女の生き方、言葉を自分は使えるだろうか? 病に侵されそれでもなお自分らしく振舞おうとする中年になった女と、それを気遣う同級生の男。人間の強さとは何か、日々平穏に生きられる幸せを改めて考えさせられた本だった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『平場の月』(朝倉かすみ著、光文社)は、中学の同級生、青砥健将と須藤葉子が、地元の中央病院の売店で35年ぶりに再会し、心も体も微妙に揺れ動く過程を綴った、「中年の、中年による、中年のための恋愛小説」です。 青砥には、中学3年の時、「太い」と感じた須藤に、「友だちからでいいので付き合ってください」と告白して振られた経験があります。この「太い」は肉体的なものではなく、精神的にしっかりしている、肝が据わっているといった意味合いで使われています。 「須藤が中央病院の売店で働き始めたのは二年前だったようだ」。「青砥が、六年前に寡婦となった母の近くで暮らそうと地元に中古マンションを買い、ほどなくして妻子に出て行かれ、三年前、母が卒中で倒れたのをきっかけにして都内の製本会社を辞め、地元の印刷会社に転職した」のです。 須藤の何を知っても、青砥の須藤に対する思いは揺らぎません。「青砥の内側で、須藤は損なわれなかった。それが愉快だった、どんな話を聞いても、そこにどんな須藤があらわれても、損なわれないと思った。酒乱と知って一緒になって、途中でやっぱりうまくいかず、そのまま(同級生から奪い取った夫と)永遠の別れとなってしまっても、歳下のクズ(の男)に浮かされて(経済的に)丸裸になっても、安アパートに住み、(売店の)シフト入れまくってやっとこ生活していても、青砥のなかで須藤の値段は下がらない」。 進行性の大腸がんと宣告された須藤は、ストーマ(人工肛門)を造設することを決意します。「須藤を大事に思うきもちが揺さぶられた。しょせん、親友でも恋人でもない。・・・ストーマがどんなものかはまだ知らないが、青砥にとって須藤は須藤だ。損なわれるはずがない。確信はあるのだが、口にしなかったのは、たぶん、歳を重ねることでいつのまにか培われた慎重さゆえだった」。 「『やめてよ、青砥』とあばれる須藤の手首を握り、胸の下で交差させて抱きしめ、頬に頬をつけた。おとなしくなった須藤の顎を上げさせ、口づけを落とした。唇を離したら、『どうするんだよ』と須藤が泣くのを我慢しているような声で言い、『どうもしないよ』とまた唇を合わせた。今度は長くなった。吐息が漏れた。・・・須藤のジーンズのボタンを外した。指で探ったら、ちゃんと湿った音が立った。指を使うと音に厚みがくわわった。須藤のそこは若い女のようであり、若い女にはない折り重なった熱気が青砥の指を濡らした。『痛恨だなぁ』と須藤が喉の奥で笑った。そして八月二十三日火曜日。須藤は腫瘍をふくむ直腸を切断し、肛門を閉じ、ストーマを造設した」。 その後、リンパ節への転移が分かり、抗がん剤治療が始まります。「『おまえの面倒はおれがみるから』という科白が喉まで出た。口から出なかったのは、それが須藤の嫌いな言い方のような気がしたのと、青砥がまだ腹を決めていないせいだった。青砥はまだ『おれがいる』でさえ口にできなかった。須藤は大事だ。これはほんとだ。だから、『おれにできること』を考えると、なにもさせてもらえないくせに、とさみしく足がすくむのだった」。 「『青砥には充分助けてもらってるよ。青砥は甘やかしてくれる。この歳で甘やかしてくれるひとに会えるなんて、もはやすでに僥倖だ』。『おれはもっとおまえのためになりたいんだがな』。青砥が少ししつこくなったのは、嬉しさのせいだった。須郷が青砥へのきもちを初めて明かした」からです。 「『大丈夫か』と振り向いた青砥に須藤が言った。少し笑っていた。のろのろとからだを起こすところだった。『日本一気の毒なヤツを見るような目で見るなよ』。『んなことないよ』」。 「付き合っているというよりも、も少し深く根を張った間柄となった須藤との恋人同士としての時間が、得難いものに思えてきた。それはそれで、たぶん、濃密な時間だ」。 青砥は思い切って、「須藤、一緒にならないか」と口に出します。「須藤の気配は拒絶だった。取りつく島もないタイプの、真っ暗な、拒否だった。須藤が言った。『もう会わない』。さらに言った。『青砥とは、もう一生、会わない』」。そう言い張る須藤を何とかなだめて、1年間は会わないということで折り合いをつけたものの、それからは、何度、LINEを送っても既読がつかず、LINE電話をかけても呼び出し音が続くだけでした。いったい、須藤はどうしてしまったのでしょうか・・・。 一気に読み終わった時、青砥と完全に一体化してしまっている自分に気づき、女房に気づかれなかったか心配になりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いい小説でした。中学の同級生で若い頃はそれなりにもてた2人。男も女もバツイチ独身で、地元に戻り、収入は少なく生活は質素だが、不幸せでもない。そんな2人が女の職場で再会する。 2人の会話が軽妙で、前半中盤にかけては、楽しくテンポよく読めるが、女に病気が見つかってからは、どこか重い展開となり、、、最後は涙する。 地味なストーリーですが、是非ドラマ化してもらいたい。誰かのレビューでは女性役は吉田羊がいいと言ってた。確かに適任だが、ドキドキしなさそうなので、私は原田知世を推す。男性役は、かつてイケメンで今はすっかり中年になってしまった人がいい。引退したけど山口達也とか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| どこかの書評でこの本を知って図書館に予約を入れました。 予約したら50人待ち。 数か月後、予約を入れたことさえ忘れた頃にようやく図書館から 連絡が。 わたしは切ない小説を読むと、胸が締め付けられて苦しくなるのですが、 この本は読んでいる時や、読み終わった直後はそれ程でもありませんでした。 読み終わった直後はそれ程でもなかったのですが、 振り返って後からジワジワと切なさのこみ上げてくる小説です。 須藤のあの時の気持ちと、全てを知った後の青砥の喪失感。世界が色あせ、 ぼやけた感覚。 この本を読んで、評価の高い人が多いのに頷けます。 ただ、この本を読んで極端に低い評価の人たちがいるものわかる気がします。 章も変えずに時間が前後して、いつの話しているのか分かりづらいのと、 どうでもいい日常のどうでもいい言動の描写が多いのがちょっと気になりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 自分と同年代の恋愛事情……ラストが切なすぎた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公と同年代男子。 これまで歩んできた人生。ありきたりの現在。先が見えてきたこの頃。 そんな「50歳」にも光が射し込む瞬間は訪れる。 いろんなものを背負っているからにわかに燃え上がることも全てを投げうつこともできない。 そんなもどかしさと切なさが、全編にわたって沁み込んでいます。 映画化?いや僕は小説がいいと思う。行間からこそ、切なさを存分に感じることができる小説だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 50歳くらいの男女のラブストーリー。若い人の恋愛話ではない、熟した恋愛が展開される。青砥は離婚歴がある男、須藤も離婚歴がある女性である。病院で検査を受けた青砥が同級生だった須藤と出会う。須藤は癌に犯される。青砥と須藤はすでに深い仲になっており、これから二人で病気と戦うのだなと読者は予想する。この筋書きは間違いではないが、読むべきは中年カップルが悲劇に襲われて絆が強まる恋愛のあるある話ではない。この二人の50歳ならではの優しさや意固地さが、この人生100年時代の現代において、普通の恋愛小説として成立していることである。私も似たような年齢であり、この二人に共感できる。青砥が優しすぎるのが非現実なところだろうか。でも、その青砥の性格が物語に深みを与えている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ヒロインはなぜここまで頑な?て思い、感情移入できませんでした。人生、色々あって再会した同級生の男の子。お互い気が合っていて楽しいし、男性からここまで尽くされていて、この結末はなに?こういう女性にはなりたくない。 「平場」とあえて言っているので、夢がなく現実感満載の小説。病気についてまじめに現実と向かい合っている点は評価できる。もし自分もこういう状況になったらどうするかなって考えて、恋愛小説というより闘病小説なのかな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中学時代の初恋女子との思い出。それを実らせられずに、一時の気の迷いと勢いとで別の女性と結婚した若気の至り、そして離婚。結果として、単調な一人暮らしの日々の気楽さに安住するも、50歳を超えて時折蘇る、初恋の懐かしい思い出と辛い後悔。こんな「自分を軽蔑するひと」のひとりとして、この小説に言葉を失うほど感動、感涙してしまいました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 複数場面が矢継ぎ早にたたみかけられる冒頭に混乱した。中心視点人物の混乱を表現したのだろうとは思うが、そうとしても読者に不親切すぎる。あるいは場面を描き分ける筆力不足か。 その後、中盤までストーリーが平板でツラかった。山本周五郎賞受賞作品でこんなことある?とくじけそうになった。 終盤のアンチクライマックスは良かった。冒頭場面と響き合う 重要人物の不在感、死のあっけなさが胸を締め付ける。 前半部は、映画「ディアハンター」のダラダラ長いパーティー・シーンと同じ効果を狙ったのかな。途中で読むのにくじけそうになってる人、我慢、我慢だよ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 気に入らないことはない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| お堅い本ばかりでなく、久しぶりに小説でも読もうかと思い、購入して読み始めたが、最初の数ページで呆れかえった。文章構成力が全くない。何を言おうとしているのか、作者以外で分かる人がいるのだろうか。最終ページまで読む自信がない。金返せ!! 久しぶりに最低の本に出合った。再度登場人物を理解するために最初から読み返してみるが、腹立たしくて、、。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初の章がややこしくて「?」と思いましたが、その「?」をずっと抱えながら読んでいくと少しずつ理解できてきて、その過程がなんともいえない良い味わいでした。そして最後まで読んだあとに読み返すとその上手さにさらに驚きます。 当方40代前半女性ですが、とても好きな本のうちの一つになりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公と同年代だ。大切な人が死んで「泣ける~」なんて幸せなアホだと思っていた。10年前にはそう思っていた。お涙頂戴ものなんてしゃらくせぇ、チー坊だぁ?ファンシーなものも大嫌い。なのに最近なぜか、確かに、まんまるで微かに甘いものが「ちょうどよくしあわせなんだ」 死にオチなのに読後感は軽妙洒脱、ユーモラスですらある。「どちらさま」「息子の健将」「死にました」 思わず噴飯してしまう会話が随所にある。そしてリアリティ。いつの間にか2人がしんしんと降る雪のように心の中に棲んでいた。 本を読むとき、溜飲を下げるアフォリズムに付箋をつけ文章を味わったり、主人公の「スタイル」に憧れてお気に入りのくだりを何度も読み返したりしてなかなか先に進まない。ところがこの本にはそういうフックは何もなくするりと読み終えた。10年前までは知識や教養を身に着けるために本を読んでいたのだろう。何のために?色々な経験をへた今は尖鋭なカリカチュアより平凡でとりえのない日常に埋もれる微かな甘さがちょうどよくしあわせなんだ。それはまさに平場のまんまるいお月様。 失って、失って、最後に残ったもの。ある日ノーサイドゲームからの~「馬と鹿」の歌詞を見たら青砥が重なって泣けた。私もとうとう幸せなアホになったな…いや、そういえば元々すぐに泣いちゃうような女の子だった。私もようやく無駄な鎧を脱いで馬鹿(平場の月)になれたのかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 身につまされますなー! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中古で1,000円まで下がっていたので購入しました。バリューブックさんいつもありがとう。予定より早くつきました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まず、読み始めから感じたのは、何もかも語ってしまう作家さんだな…、状況説明し過ぎているな…と思いました。 読者に想像の余地を与えてくれない本は、個人的には面白味に欠けるんですよね。 不満が募るだけでした。 初めて読んだ作家さんでしたが、この本、私には合いませんでした。 物語は、こと恋愛における男性の鈍さ、無神経さ、意気地無さ、独りよがり…を丸ごと一冊にした内容で、アラフィフの私は、そうそう男性ってこうなんだよね…。 彼女の上っ面の言葉を何故そのまま受け取るの? 何故、心の奥底を感じ取ろうとしない? て言うか、基本的には無理なんだよね。 男性脳では女性の感情を理解出来ない。 全く…、どうしようもないな…。 そんな男性に対する不満の共感だけで、物語からは感動とか切なさ、哀愁といったものは感じられませんでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 50を超えた青砥健将は、中学時代の同級生・須藤葉子が死んだと聞かされる。その1年以上前、青砥は胃の検診で病院を訪れたとき、そこの売店で働いている須藤に偶然再会していた。互いに独身に戻っていた青砥と須藤は、静かにゆっくり愛情を育てていたのだが……。 ------------------ 1980年にジューシィ・フルーツ『ジェニーはご機嫌ななめ』が流行った時、主人公の二人は中三だったという記述が出てきますから、男と女は1965年生まれくらいでしょう。この小説を手にした私とほぼ同世代です。 そして物語は、2016年ころに設定されているので、50歳をちょうど超えたあたりの男女の物語となります。 王道をいく中年男女の恋物語、といってまず間違いないでしょう。出会いは病院、とくれば、暗喩としての病というまでもなく、不治の疾患によって二人に別れが訪れるまでの道のりが描かれるのも予想できることでしょう。 実際のところ、須藤の死は物語が始まってわずか4頁目で明らかにされ、そこから二人の出会いへと時空が遡ります。その仕立ても決して新味のあるものとはいえません。 さらにいえば、作者の文章は潔いまでに短く、時に主語の省略が過ぎるあまり場面の行方を見誤りそうになるほどです。さかのぼって読み直すことも一度や二度ではありませんでした。 であれば、この小説は良いところなしかと思わなくもありませんが、唯一目を引いたのが、ガン治療の描写です。不治の病にまとわりつくどことなくロマンチックな要素はありません。医学が進んだからこそ、生活の質を多少は落とした形での延命をときに強いられる現代にあって、須藤は「ストーマ」とともに生き、働く道を選ぶことになります。この点はなかなかに現代的であり、生きることの生々しさを強く感じさせます。巻末に参考資料として十を超える文献の名が列挙されていて、作者が真摯に現代のガン医療について調べたうえで小説を構築したことがわかります。 それだけに、須藤が最後の1年に青砥に求めた事柄は彼にとって少々苛烈な仕打ちに思われてなりません。生きるとは人と関わることだという真理を須藤が放擲しているように私には思えたのです。 --------------------------- 年月を経てのち、再会した男女の物語として私がお奨めする小説を以下に掲げておきます。 ◆宮本 輝『錦繍』(新潮文庫) :この小説に登場する主人公二人は、時を経たお互いを今一度見つめなおして、そしてまた新たに分かれ道を歩んでいきます。その分かれ道をゆくそれぞれにとって、かつて共にした時間は、もう振り返ってばかりの過去ではありません。それはいまや、生きる支えとすべき記憶に姿を変えていることをあらわす小説です。 ◆乙川 優三郎『太陽は気を失う』(文春文庫) :14の短編を集めた一冊です。そのほとんどが50代を超えた男や女の人生から切り出したある時節を描いています。 「海にたどりつけない川」という一編は、余命いくばくもないと宣告された男が若いころにやむなく別れた女と一目会いたいと思い、彼女が暮らす町へと旅する物語です。 . | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 高評価の作品ということで読んではみたものの、期待外れでした。まず同年代の人間としてはあの二人のまるで中学生同士のような会話は有り得ないと思ってしまう。それも学生時代親友同士であったのならいざしらず一応意識しあった二人ですがただのクラスメート。50歳にもなって普通の社会経験を積んだ人間なら再会してすぐにあんな乱暴な物言いは考えられません。物語の中で彼女をいくら美化しても蓮っ葉なイメージの女性しか浮かんできません。あの会話に説得力を持たせようと思うのなら二人が20代じゃないと無理があり過ぎ。 文章も奇をてらった表現が多く集中して読めませんでした。 中高年の恋愛のピュアさを伝えたかったんだと思いますが・・残念ながら共感は出来ませんでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 週刊新潮の書評を見て購入した63歳の男です。 情景描写と心理描写に脱帽です。 読了後、切ない気持ちのまま「満潮」の文庫本を購入しました。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!