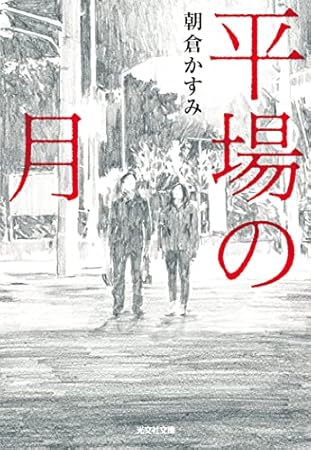■スポンサードリンク
平場の月
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
平場の月の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.04pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全10件 1~10 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 描いている時代が2015年頃に50歳くらいの男女。内容は病気でなくなる級友女子と恋慕する男の懊悩。ややもたもたした進み。ストーリー半ばで大腸がんとわかったところで読み進められなくなった。似た経験を持つため。先にそれを明かしてくれた上で淡々と語り綴る方が私は良かったなあ。筆致はやや古い気もする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 映画化ということで読んでみた。50代の主人公が中学時代の同級生と再会するラブストーリー。 序盤に恋人が亡くなったことを知るところから始まる回想的な展開。 派手さはないが生活感がリアルに伝わってくる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初めての作家の初めての作品を読了。おとなの恋愛小説。癌との闘病中の自分をかっこよく見せたい姿は大人の女性か。切ない物語でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 猫は死ぬ前に飼い主の前から姿を消す、というのは嘘か真かわかりませんが、 この本を読んでまっさきに思ったのはそれ。 須藤の見た目に対するイメージもやっぱり「猫」。 青砥が惚れ込むのもわかる気がします…。 話の流れがわかりにくいとか場面がごちゃごちゃするとか人物の喋り方が気になるとか、 いろいろ感想はあると思いますが、私は、読後感がよければ(または、たとえばイヤミスみたいに 読後感が著者の意図したとおりもしくは読者の希望したとおりになれば)、その小説は成功だと思います。 いい本でした…。一度枯らしちゃったけど、ローズマリー育てたくなりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 感動はあまりしなかったー。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まず、読み始めから感じたのは、何もかも語ってしまう作家さんだな…、状況説明し過ぎているな…と思いました。 読者に想像の余地を与えてくれない本は、個人的には面白味に欠けるんですよね。 不満が募るだけでした。 初めて読んだ作家さんでしたが、この本、私には合いませんでした。 物語は、こと恋愛における男性の鈍さ、無神経さ、意気地無さ、独りよがり…を丸ごと一冊にした内容で、アラフィフの私は、そうそう男性ってこうなんだよね…。 彼女の上っ面の言葉を何故そのまま受け取るの? 何故、心の奥底を感じ取ろうとしない? て言うか、基本的には無理なんだよね。 男性脳では女性の感情を理解出来ない。 全く…、どうしようもないな…。 そんな男性に対する不満の共感だけで、物語からは感動とか切なさ、哀愁といったものは感じられませんでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 50を超えた青砥健将は、中学時代の同級生・須藤葉子が死んだと聞かされる。その1年以上前、青砥は胃の検診で病院を訪れたとき、そこの売店で働いている須藤に偶然再会していた。互いに独身に戻っていた青砥と須藤は、静かにゆっくり愛情を育てていたのだが……。 ------------------ 1980年にジューシィ・フルーツ『ジェニーはご機嫌ななめ』が流行った時、主人公の二人は中三だったという記述が出てきますから、男と女は1965年生まれくらいでしょう。この小説を手にした私とほぼ同世代です。 そして物語は、2016年ころに設定されているので、50歳をちょうど超えたあたりの男女の物語となります。 王道をいく中年男女の恋物語、といってまず間違いないでしょう。出会いは病院、とくれば、暗喩としての病というまでもなく、不治の疾患によって二人に別れが訪れるまでの道のりが描かれるのも予想できることでしょう。 実際のところ、須藤の死は物語が始まってわずか4頁目で明らかにされ、そこから二人の出会いへと時空が遡ります。その仕立ても決して新味のあるものとはいえません。 さらにいえば、作者の文章は潔いまでに短く、時に主語の省略が過ぎるあまり場面の行方を見誤りそうになるほどです。さかのぼって読み直すことも一度や二度ではありませんでした。 であれば、この小説は良いところなしかと思わなくもありませんが、唯一目を引いたのが、ガン治療の描写です。不治の病にまとわりつくどことなくロマンチックな要素はありません。医学が進んだからこそ、生活の質を多少は落とした形での延命をときに強いられる現代にあって、須藤は「ストーマ」とともに生き、働く道を選ぶことになります。この点はなかなかに現代的であり、生きることの生々しさを強く感じさせます。巻末に参考資料として十を超える文献の名が列挙されていて、作者が真摯に現代のガン医療について調べたうえで小説を構築したことがわかります。 それだけに、須藤が最後の1年に青砥に求めた事柄は彼にとって少々苛烈な仕打ちに思われてなりません。生きるとは人と関わることだという真理を須藤が放擲しているように私には思えたのです。 --------------------------- 年月を経てのち、再会した男女の物語として私がお奨めする小説を以下に掲げておきます。 ◆宮本 輝『錦繍』(新潮文庫) :この小説に登場する主人公二人は、時を経たお互いを今一度見つめなおして、そしてまた新たに分かれ道を歩んでいきます。その分かれ道をゆくそれぞれにとって、かつて共にした時間は、もう振り返ってばかりの過去ではありません。それはいまや、生きる支えとすべき記憶に姿を変えていることをあらわす小説です。 ◆乙川 優三郎『太陽は気を失う』(文春文庫) :14の短編を集めた一冊です。そのほとんどが50代を超えた男や女の人生から切り出したある時節を描いています。 「海にたどりつけない川」という一編は、余命いくばくもないと宣告された男が若いころにやむなく別れた女と一目会いたいと思い、彼女が暮らす町へと旅する物語です。 . | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本周五郎賞受賞時、直木賞候補時の評価が高かったため期待を込めて手に取った。リーダビリティーが高く1時間ほどで一気読みした。「泣かない主人公の代わりに読者が泣く」の評判どおり、私は泣いたが、この涙はフランダースの涙を見れば自動的に流れる涙と同質で「そりゃ泣くわ」な当たり前の生理現象である。どちらかといえば感情を揺り動かされた部分より、何も起こらない日常の描写こそが見どころであり、この作者の特質なのではないだろうか。是非、この作者の他の作品を読んでみたいと言う気にさせられた。しかし、それは同時にこの作品一作ではなんとなく消化不良だった、と言うことに他ならない。 全体を通して、文章の端々から才気が匂い立つように感じられた。が、その才気について、この一作では全貌を計りかねたのだ。もともと捉えどころのない作風なのか、はたまた「難病もの」というパッケージが作者の作風にマッチしていないのか。 一作しか読んでいないため見立てちがいなら申し訳ないが、抑えた玄人好みの作風を持つ作者が「私、こんなものもやっちゃえますよ」「朝倉風世界の中心で愛を叫ぶはこうですよ」と嘯いているような印象が拭えないのだ。中二病を卒業し、大二病罹患中の精神構造を見せつけられたというような。あるいはもう少し戦略的に、通好みの達人が、売れそうな題材で「セルアウトした」ということなのだろうか。しかしそれにしては思い切りが足りず、初読者にもわかる作者のこだわりが見え隠れし、せっかくのわかりやすい感動を阻害する。 例えば、6月の別れのあと、青砥は須藤にいくらでも会いに行けた。家がわかっているのだから家の前で待ち伏せすることだってできたはずだ。もちろんその「行動しないこと」の違和感自体は、この小説の瑕瑾とはいえない。もっとも問題なのはその違和感が、小説内での諦念や悔恨として実感できないことである。「青砥が会いに行かなかった」のではなく、「作者が青砥に会いに行かせなかった」、「青砥は泣かない」のではなく、「作者が青砥を泣かせなかった」と感じさせてしまうのだ。難病もののパッケージを採用しながら、達者な作者の自意識が透けて見えてしまう。その中途半端さが消化不良の正体だ。 「難病」「低所得者の日常」「毒親」「不幸な生い立ち」「上品な抑えた筆致」エトセトラ。全てがハーモニーを奏でることなくそのままの形でそこにあり、「結局何が一番見せたいの?」と混乱したままラストを迎えてしまう。だから作品の印象もページをめくる都度変わる。是枝監督作品や初期新海監督作品のような静謐な諦念を感じたかと思えば次のページでは日曜の「ザ・ノンフィクション」みたいなどうしようも無い底辺の遣る瀬無さ、を感じさせられる。それがいちいち上質なのが始末に悪い。現実をそのまま写し取りましたと言われればそこまでだが、エンターテイメント好きとしてはある程度の「見せたいもの」の取捨選択をしてほしいと感じてしまった。 とにかく「なんだかわからないけど才能ありそう」な片鱗だけお披露目してくれたと言う意味で「セルアウト」は成功と言えるのかもしれない。おそらく私はこの作者を追いかけるし、初読者の入り口としてはなかなか美味しい作品であった。しかしおそらくこれは「難病もの」の最高傑作でもないし「朝倉作品」の最高傑作でもない。と、思うし思いたい。 ちなみに山本周五郎賞で選考委員の石田衣良氏が激賞した「文体の発明」は、残念ながら冒頭だけ。冒頭1ページを読んだ時、まるで「悪童日記」を初読した時くらいの胸に迫るような感動と期待を抱いたのだが、その文体はわずか1ページで終わりを告げる。なんらかの感動を呼び起こす装置としていつ再登場するのだろうかと期待して読んだが、最後まで姿を現さなかった。あれは一体なんだったんだ。どう言う狙いであれを発明し、お披露目したのかわからない。そう言う点を含めて、なんとなく焦点のぼやけた、手練れの試作品、みたいな印象で終始した。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この著者の作品はこの本しか読んでいないので、作風については詳しくないことを前置きとしておく。 例えば(文才はこちらのほうが明らかに上だとは思う)少し前の別の作家のヒット作『キミの膵臓をたべたい』同様、ターゲット層が明確で、その層に共感されるように書いている感が強すぎて、登場人物の台詞も、説明文も読んでいてくどさを感じる。 売ってなんぼの商業小説なので多くを求めるのは間違っているのは分かっているが、「書ける」という凡人には持ち得ない稀有な才能を持っているからこそ、こういうものはあまり書いてほしくない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「ちょうどよくしあわせ」が「ものすごくしあわせ」になったら… 「死ぬまで生きる」だったのが「どうしても生きたい」になるのが自明 ↑になるのが怖い お前らは、何で 「だらだら」「何となく」「なりゆきで」 でいられんかったんだ もどかしさと甘い苦さがあとを引く 大変に楽しみました | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!