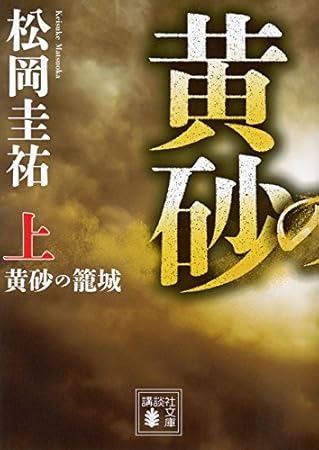■スポンサードリンク
黄砂の籠城
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
黄砂の籠城の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.49pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全116件 1~20 1/6ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| プロローグ箇所を読み進めているのだが、浅田次郎作品と言われても異議はない。珍妃の井戸を好ましいと思っているかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「見つめる」「しめす」という動詞が頻出するのが素人くさくて気になりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 他のレビューアーも言及してる通り、日本スゴイ系の臭いが強く、ちょっと受けつけない部分が多いです。 自国民をかっこよく描き他国民を悪者にするのはどこの国の作品も同じですが、この作品はそういうのではなくこの時代に大流行した「日本スゴイ系TV番組」と同じで、ことあるごとに外国人の口から日本人の美点を褒め称えた歯の浮くようなお世辞が続きます。 まあ、歴史小説でまで日本スゴイと言い続けてもらわないと安心できないくらい、今の日本は自信を喪っているんでしょうね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私はどちらかといえば右寄りの考えの持ち主ですし、これまでいくつかの書評で「ストーリーに関係なくぶちこまれる稚拙な左寄りの主張」に苦言を書いたりもしてますが、この本はこの本であまりに日本人賛美しすぎてて、ちょっとその辺で気恥ずかしい思いをしました。それも「ふっ、まったく日本人にはかなわないぜ」みたいなことを外国人に言わせる場面が何回かあり、何だかなぁ。 肝心のストーリーは荒唐無稽であまりに主人公強すぎではありますが、まぁエンタメなので楽しめました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 3年半前本書の発行直後に、上下2巻を買って読んだ。 冒頭に「この小説は史実に基づく」とあり、それなりに期待した。 だが途中で、余りの荒唐無稽ぶりに読むのを止めようとしたが、とにかく読み通した。 「小説」と銘打ってはいるが、これは単なるドタバタ劇にすぎない。 帯には石破茂氏の推薦文があるが、石破氏は本当にそう思っていたのだろうか。 アマゾン購入から3年半たっているが、本書を廃棄する前に一言、書き残したくなった。 とかく批判のある米映画「北京の55日」だが、こちらの方がよほど有益だ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 史実に基づいた話ですが、ついつい先が気になって読みたくなってしまいます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 下巻の方にコメントを、先に書いてしまいました。m(_ _)m 良かったら、読んでください。 とても日本人として、誇りを持てる本です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本当に明治時代の日本人は、立派でした。 尊敬に値する人達が沢山いました。 彼らだったら、今の日本より、素晴らしい日本を創ってくれたでしょう。 本当に、残念。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 特にお花畑野党の議員には最良のテキストになるだろう。(笑) また、高校の必読書にしてもよいくらいだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 良い | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これがフィクションの要素が混じってると口角泡を飛ばして必死で指摘しなくても、だれの目にも小説だと分かります。「蒼穹の昴」と同じです。ノンフィクションが読みたければ、柴五郎の語りをまとめた本がちゃんとあるのだし、そっちを読めばいいでしょう。重要なことは、こういう日本が世界にデビューした時の偉業が、幕末物語のように虚実入り混じったストーリーとして語り継がれることさえなく、ただ教科書の一行で消化されてしまっているという事実です。冒険譚なんだから美化しすぎ、ヒロイックすぎという指摘は、清国側から描いた「黄砂の進撃」や、両面を描いた「義和団の乱」という著書があることを知らないだけの話です。大筋で重要な事が語られていて、歴史を知るきっかけになるという意味で、この作品は万人が読むに値すると思います。なお某国会議員が賛辞を寄せたからうんぬんという指摘はまったく的外れです。議員は与党にあっても現政権とは対立関係にあるじゃないですか。誰が褒めたとか関係なしに、まずは楽しんで読んでいただきたい作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ノンフィクションの柴五郎関連書物を紐解くと、当時の現地には地下坑道なるものが確かに図面にあります。しかしそれはあくまで建物の地下に存在するトンネルであって、あのような大砲の攻略戦は史実になかったと思われます。けれどもそういう所は作劇上の工夫であって、冒険小説として大いに盛り上がる所ですから、純粋に楽しむべきだと思います。それぞれが命の限りを尽くし戦った事実はあるのですから、様々なエピソードでそれをわかりやすく描いたと考えるべきでしょう。「黄砂の進撃」と両方読むべきですし、1冊で読みたいという人は両方がミックスされた「義和団の乱」を読めばいいと思います。戦争は常に味方側しか見えないものであり、両側が見える神の視点は本来存在しないものです。その意味でもこのリリースの仕方は正しいと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 一気に読み切りました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「久々に凄い戦記小説を読んだ。政治的背景も文化も異なる11か国の兵士と民間人が、外国人を問答無用で惨殺する復讐心に燃えた数十万の暴徒に包囲され、僅か半径1キロに満たない居留区に籠城する。苛烈な戦闘で日々1m、又1mと失われていく陣地、次々と倒れる味方、待てど暮らせど来ぬ援軍、しかも川伝いを特攻し、更には地下トンネルまで掘り、あらゆる手立てで侵入を試みる敵暴徒たち。その上味方の陣中を自在に闊歩し、次々と暗殺を仕掛ける謎のスパイの恐怖が追い打ちをかける。果ては超巨大大砲までもが設置され、砲弾により居留区を吹き飛ばされる絶体絶命の危機に。 だがこんな絶望的事態を物ともせず、武士道精神を発揮して勇猛果敢に活躍し、大胆にも民間人救出の為に城外にまで出撃していく我らが日本兵の活躍は実に痛快だ。最後の不倶戴天の仇敵だったロシア兵との友情シーンは胸を打つ。 正に最後の最後まで目が離せない、超一級のエンターテイメント小説である。」 ・・・と評すべきところだろう。この小説が「史実を基にしたフィクション」ときちんと明記されていたなら。 冒頭の商社マンの台詞を借りて作者が弁明しているのに係わらず、この小説がどのような意図を持って、どのような客層受けを狙って出版されてのかは、帯の石破茂氏のコメントや商品説明欄の版元の謳い文句を見れば一目瞭然である。 だが肝心の内容はストーリーが進むにつれ荒唐無稽化していき、アクション映画さながらの様相を成す。主人公は一介の伍長でありながらジェームズ・ボンド並みに数か国語を自在に操り、ランボー並みに立ちはだかる敵を次々と倒す無敵のヒーロー。他国の公使、将兵はみな自国の利害のみ追及する纏まりのない烏合の衆で、日本人だけが沈着冷静、かつ公平に残る10か国の人々をまとめ上げる。他国の将兵は偵察・作戦に悉く失敗し、次々と倒れていくのに、日本兵だけが見事な成果を挙げ、殆んど誰も死なない。 最後の大砲破壊作戦の件ではもう鼻白んでしまった。ここまで着色が激しいとどこまでが史実なのか、どこからがフィクションなのか皆目わからない。歴史小説に演出は付き物だが本書は内容全てが虚構と疑われても仕方ないレベル。城外の漢人キリスト教徒救出作戦すら作り話に見えてしまった。これで「日本人の叡智と勇気を知ろう」と言うのは、ドラマの「暴れん坊将軍」を見て徳川吉宗の功績を、「西部警察」を見て日本警察の能力を知れ、と言ってるような物だ。 突拍子もないアクション、演出で史実を着色して広めることは、かの地を現在支配している政権の常套手段であり、我々はそれを「プロパガンダ」或いは「歴史の捏造」と呼んで軽蔑していたのではなかったか? 筆者は本書の評価に気を良くしたのか、義和団側の立場から描いた小説「黄砂の進撃」との合作本まで出してしまったが、そんな暇が有るのなら史実に基づいた「実際の」日本人の活躍ぶりを解説すべきだ。 ただ、この籠城戦の実際の経緯、柴五郎中佐の功績を知りたくなり、「真面目に」本事件を描いた書物を読みたくはなったので、それだけでもアナウンス効果は有ったのであろう。その功績に星一つプラス。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 義和団の乱については歴史の教科書で触れられていたが詳しいことは知らなかった。 今から50年以上も前に私がマニラに駐在しているときにアメリカ映画「北京の55日」が公開された。 1900年、欧米列強の蹂躙に任されていた中国(当時の清国)に農民を中心とする武装勢力「義和団」が発生、北京に公使館を置く列強11か国の居留民、在外公館に対し攻撃をしかけてきた。この映画を見た時、マニラの中国系フィリピン人たちは義和団が格闘技を駆使して欧米人をやっつける場面には拍手喝采していた。 当時の清国の実力者、西太后(せいたいこう)は義和団を鎮圧するどころか義和団と一緒になって列強を攻撃、ついに一敗地に塗れることになる。 この映画に出てくる列強11か国の一国であった日本は芝五郎中佐の指揮のもと整然と行動し欧米各国からの賛辞をほしいままにした。この映画でが若かりし伊丹十三が芝五郎を演じており、アメリカ軍と呼応して結構活躍していたの見て私も誇らしく思ったものだ。 振り返って本書は、桜井伍長なるスーパーマンが主役である。伍長という一般兵卒の位ながら、英語、フランス語、中国語に堪能で、芝五郎中佐に目をかけられ、戦闘のさなか各国との連絡に奔走する。そればかりではない、この桜井伍長は不死身であって、度重なる義和団(本書中では紅巾と呼ばれている)との遭遇戦にも、さながら講談のように相手を銃撃、刺殺、斬殺などの方法でことごとくやっつけ、最後まで生き延びる。この桜井伍長に輪をかけたスーパーマンが芝五郎砲兵中佐である。桜井同様、語学に優れ、沈着冷静、慌てふためく列強の公使たちをまとめ、ついに彼らを心服させるに至る。 列強公使館が次々と紅巾に攻撃され、清国側の秘密兵器クルップ砲によって公使館建物が次々と破壊されていく中、辛うじて残った日本公使館を根拠地として桜井伍長を中心とする4人組がクルップ砲を破壊するのが本書のクライマックスである。このときタイミング良く列強の援軍が到着、清国群を蹴散らして列強の大勝利となる。 本書の帯には石破茂氏推薦の文字が見られるが、書いてあることが事実とすれば日本人の優秀性、規律の良さなどに胸のすく思いがすることは確かである。 桜井伍長は実在してないと思うが、芝五郎中佐はれっきとした実在の人物で、本書に出てくる英国の雑誌「タイムズ」の特派員モリソンによって、その活躍は欧米で広く報道されイギリス、フランス、ロシア、イタリアなどの欧米各国か ら多くの勲章を貰ったこともまた歴史的事実である。 本書のストーリーには読みだした最初からグングン引き込まれる面白さがあるが、文庫分上下2冊600ページを超えるといささか繰り返し、冗長の感は免れない。 このレビューは上下巻両方に亘るものです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本人の謙虚さ、真面目さ、勤勉で勤労で勇敢で親切、 そんな「日本人って奥ゆかしくて優秀!」な感じがやたら書かれている。 それに、そういう文章にやたらハイライト(マーカー)が付いている。 最近のテレビでも外国人が称える日本人や日本の商品をフューチャーして 「すごい」って言わせてるインタビューや番組が多いので、少し食傷気味。 謙虚さ、どこ行った? 考え方は欧米化して、言いたいこと言ってやりたいことやって 超個人主義が格好良い的な現代に嫌気が差していたので、読んで爽快感はあった。 理想的な日本人が理想的な行動で周囲から称賛を浴びるけど常に控えめ、みたいな。 史実を交えて極めて理想的な日本人が描かれている。 でも、この本を読んで思うのは「昔は良かった」みたいなことじゃない。 昔も今も、嫌な奴はいるし、ダメな奴もいる。 だから、史実を交えた小説、っていう理解で読んで、とても面白かったです。 結局、日本人は日本人という人種を誇りたいんだと思う。私もそうだけど。 だから、自分だけでも正しく行動しようと思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 百田尚樹著「日本国紀」にも出てくる柴五郎中佐(当時)が指揮を執った、義和団と清正規軍との北京の東港民巷をめぐる481対20万の奇跡の籠城戦。 柴中佐の優れた人格は勿論のこと、登場してくる若き日本人の下士や義勇兵の勇気に落涙する。 すぐにでも映画化出来そうな臨場感と、内通者が誰なのかというミステリー要素も夢中にさせる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「友のために自分の命をなげうつ者、これに勝る愛はありません。」(ヨハネ15:13) この言葉を聖書も読まない明治の日本人たちがが当たり前に体現できている。日本人としてもっと胸を張っていいはずだ。 「力の無い愛は無力であり、愛無き力は暴力である」という言葉の真実味を改めて実感させた作品。 そして明らかになる内通者の背景にも驚愕する。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あまりに面白く、上下巻を一気読みしました。 ラストがキレイにまとまりすぎているのが、 ヒネクレ者の私にはひっかかったところではありますが。 いやぁ、おもしろかった。 続編の「黄砂の進撃」も面白かった。 これを読むと「義和団の命の無駄遣い」の理由も納得できます。 義和団側から視点も書くというのが、この作家の誠実さかと。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| どんどん引き込まれていった。清国での籠城の中で活躍した日本人の活躍、フィクションでないことに驚いた。同国の者として、誇りだし胸を張れることなのは間違いない。 ただ、この勤勉さを今の日本人が持っているだろうか?その時代の教育があったからこそできたことだと思う。 今の時代に同じことは出来ない。思想も信念も異なる。ただし、日本人は規律を重んじ、謙虚であることは受け継がれている。欧米化する中でどんどんその価値が失われつつある気がするが、それを活かすかどうかは当人次第。本書の真似は出来ないが、学び特性を活かす方法を考えたい。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!