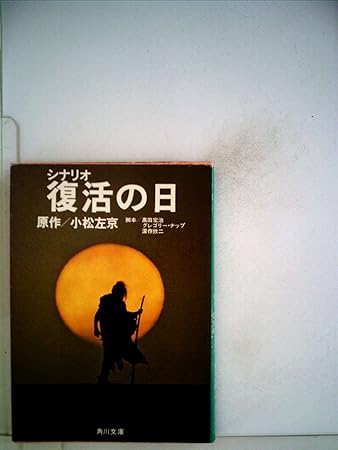■スポンサードリンク
復活の日
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
復活の日の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.38pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全195件 161~180 9/10ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| オリジナル版とジュニア版との差異、それに対するコメント ストーリーの順に書いていくと、オリジナル版では主人公の吉住には付き合っていた恋人がいたのが、ジュニア版では妹に変更され、その妹がオリジナル版の恋人同様に独り死んでいくのだが、その描写がオリジナル版の恋人が死にゆく描写と違っている。 オリジナル版の恋人は足腰が立たなくなり、閉め切った部屋で独り死んでいき、その描写も敢えて残酷で冷たい視線で書かれていた。 ジュニア版の妹の死にゆく描写が悪いとか言っているのではない。今時の若い女性らしい行動描写だったし、正直ジュニア版となっているだけにオリジナル版のあの描写は残酷だと思う。 それにこの主人公の最も身近な異性が死ぬ描写こそ、オリジナル版とジュニア版との45年という年数と時代の違いが出てしまっている場面であり、恋人から肉親である妹へ変更し、その死にゆく描写も変更したことは本気でジュニア版を出すに当たっては正解だったと思う。 逆にこの場面の描写を変更しなかったとしたら、口先だけの変更、修正作業、ジュニア版出版になっていたと思うし大きい違和感が残ったハズである。 そもそもオリジナル版が書かれた時代は終戦からまだ20年近くしか経過してなく、経済の方も本格的な戦後の高度経済成長夜明け前であったが、その前触れはもう表れていて、人から物まで全てが前向きで光り輝き、心の繋がりを重視する大家族主義から個人の意志と核家族化と、心と家族の在り方が激変していった時で、それを警告する意味で敢えて状況説明だけの冷たい描写方法で恋人の死を扱ったのだと思う。 45年後の09年に出版されたジュニア版は、社会の状況から全ての面においてオリジナル版が出版された時代とは殆ど真逆の状況にある今の時代と、何事も“自分がこの数時間内に確実に死ぬ事”すらにも嘆き悲しむこともなく、他人事の様に淡々と受け止めてしまう、今の日本人の心のあり方が描写されていて良かったと思った。 その妹が取材先の土屋医師との会話で、子供の頃にこの本(復活の日)を映画化した破滅の日を観たと話す場面。 ジュニア版の著者の半体験談なのだろうが、初見した時は自分もテレビでだが観た事があるので微笑ましい場面に受取れたが、読み進めていくうちに変に現実味があり、デジャヴの様な不気味で嫌な予感を感じてしまった。(それだけ現実感ある描写であったと云う事。) モンゴルの名もない家族の場面の省略。 これは下手に話の世界観を広げる事も無いので良かったと思う。 A・リンスキイ博士が名前だけでの登場に変更。 これは残念だった。そもそもオリジナル版でもほんの数行しか書かれていなかったし、かと言ってジュニア版の方でも自己犠牲の結果得られた成果を、南極にいる後世に託す重要な人物だっただけに残念だった。 北町病院の土屋医師が2度登場する点。 オリジナル版では取材先の医師、ジュニア版で初登場した時の土屋医師の役に相当する医師、そして2度目に修羅場と化した北町病院で登場する土屋医師の役に相当する医師と、3役それぞれ別々の人物だった。 この省略対応も、無暗に登場人物を増やしてしまうよりは、統合した方が良かったので正解ではと思う。 ジュニア版で2度目に登場した土屋医師と休憩室で会話をした同僚医師が、オリジナル版では死体が折り重なる病院内で自分もその中に倒れ込み、今まさに死にゆく運命にある女性患者に慰め励まされながらも、医学の無力さに悔しがり泣きながら死んでゆく場面の割愛。 これも残念でしょうがない、出来れば割愛、省略はして欲しくなかったが、しょうがない。 全体的に理解、想像しやすくする為に、細かく日付を点ける事への変更。 オリジナル版では、ある月の上旬中旬下旬とか、ある月の第何週位までしか分からなかった。大きな点以上だと思う。 感想。 オリジナル版ジュニア版どちらも甲乙つけがたい。ジュニア版と言ってお子様向けと馬鹿にするなかれ。数年前にスマップの草'g剛主演で日本沈没が再映画化されたが、復活の日が再映画化されるとしたら、ジュニア版の方をベースにするのではと思える程、しっかりとしたリメイク内容になっている。 戦後約20年1964年頃書かれたオリジナル版は、人間の愚かさと傲り昂り、馬鹿さ加減をそれこそ学者がモルモットを見る様な、感情のない冷たい目で上から見下す様な立ち位置で書かれていたが、ジュニア版は時代背景を平成20年代、西暦も2010年辺りに変更したこともあり、冷たく見下すと言うよりは、事実だけを淡々とレポートにまとめ報告するように書かれていたし、その時代背景を変更した事に関係する変更作業も、オリジナル版で書かれていたスポーツチーム名や選手名を今現在存在するチーム名に変更したり、オリジナル版が書かれた当時には存在すらしなかったプロサッカー、パソコン、インターネット、携帯電話、東京ディズニーランド、地上のチームが全滅した為に補給の道を断たれ、見捨てられた揚句に確実に死んでいく運命にある国際宇宙ステーションの宇宙飛行士達など、必要最小限に止めながらも“今現在”を感じさせる事には成功しており、その昔オリジナル版を読み映画も観た大人の自分から見てもたいへん読みやすく、また本の内容を古びさせないで、(オリジナル版が余りにも先見の明あったと言うことなのだが)まだまだ有り得る話と警告するには良かったと思うし、年齢に関係なく手に取り易い好印象を持った。 ※おじさんから対象年齢の子供達へ、出来るならオリジナル版にも手を伸ばしてほしいが、このジュニア版だけでも構わないから、ぜひ買ってじっくり読んで頂きたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 気力、体力が漲り、何の根拠もないが先の時代を見極める自信がある。 総じてこう云う時にある人間を、波に乗っている人間と言うのだが、その波に乗っている人間の研ぎ澄まされたパワーは凄い。 多分、この作品も著者の小松左京氏がそんなときにあった時に書かれたものだと思う。 作品の内容は商品の説明で知って貰うとして、これから購入される若い方には時代の差を感じてしまう描写や表現もあるが、そんな事で内容が分からなくなったり、白けて読む気が無くなることは無いので心配なく。 それにサイエンスフィクションはちょっと苦手と言う人もご安心を、出版されてから50年近く経っている事がSFぽさの部分を目立たないものにしていますし、そもそもこの世に100%純粋なSF小説はありません。SFだけではなく様々なジャンルで様々な方の作品がありますが、どのジャンルのどの方の作品もそのジャンルの最低限の設定や枠組みだけを借りて、実際書いているのは(描写や表現方法にはどうしても書いた時代が最低限は出てしまうものの)経年劣化する事のない人間や社会、国家間が抱える大小様々な、それも損得勘定を捨て助け合う心があれば簡単に解決する問題ばかりだからです。 只、この作品が違う所は “根本的で簡単過ぎる理由であるが故に、中々、どうしてもそこから抜け出す、一つ上の段階に登る事が出来ない”と言う基本的な性が、順位づけが大好きな人間が自分の持っている腕力を誇示して自分の思い通りにしたがるもう1つ別の基本的な性と絡み合い、結果としては全滅は阻止できるものの、自ら自分達を断崖絶壁に追い込んでしまう、この手のパンデミック物の原点であり頂点であり世界規模の壮大さを持った作品であるという所と、その絡み合った2つの基本的な性は、無意識な本能で尚且つ人間の弱点でもあるので、この本の様にそれこそ死に物狂いの努力をしても無駄な努力に終わる方の可能性も大いにある事を感じ取る様に書かれている所だと思う。 それにしても何回読んでも50年も前に書かれていた事と、年数が経てば経つほど現実味を増してくる内容に驚くばかりだ。 これから初めて読む方々に感想を訊きたくなる本でもある。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まず第1に、この小説が1964年に出版されたものだということに驚く。もうすぐ50年経とうとしているわけだが、その当時にウイルスの突然変異によるパンデミックで人類が死滅してしまう話が書かれていたということがすごい。きっと、当時には本当に荒唐無稽のこととして(当時の科学技術の発達ぶりを踏まえてはいるのだろうが)書かれていたのが、21世紀となった現代では今にも起こりうる話どころではなく、この数年世の中を騒がしている実際の話として存在しているのだからすごい。50年が経過して、ウイルスについての知識も増えたり、東西冷戦が終わってしまったりという細かい違いや古めかしさはあるものの、そんなことをいちいち感じさせないで終わりまで読ませてしまうところもすごい。 全編を通じで、すごいとしか言いようがないのだが、それはあくまでも表向きというか、この話をSF小説として成立させるために小松左京が用意した設定にしかすぎないのかもしれない。 小松左京がここで伝えたかったことは、実はこの物語の半ば過ぎ、人類が滅亡に瀕している時に最後のラジオ講座を行っていたヘルシンキ大学のスミルノフ教授の長い講義にあるのかもしれない。約13ページにわたり、その前後の表現とは異なり、教授の講義という形を借りた独白が続くのだ。 そこでは、科学の発達がもたらすもの、科学が発達した時代の哲学について、そこから導き出される人類の未来についての講義がなされるのだが、教授の独白とも言える講義はあたかも小松左京の考えそのものでもあるように読めてしまう。ここで語られていることを文学の中で表現しようとすると、SFという形を取らざるを得ないのだろうし、小松左京がSFと出会った時にそのような啓示とでも言えるような考えが宿ってしまったのではないか。 個人的には、1980年に公開された角川映画の原作として知り、その当時にも読んだはずなのだが、その時には単なるSFとしてしか読まなかったという記憶がある。しかし、この小説は単なるSF(もちろん、SFとしても完成度は高いのだが)ではなく、もっと大きな命題を提示している文学なのだということに改めて気付いた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 1980年公開、角川映画『復活の日virus』のシナリオです。たぶん撮影前の完成稿なのでしょう。完成した映画そのままではないのではないかと思いますが、記憶は定かではありません。 小松左京の原作小説ともかなり雰囲気が違っています。両方を改めて読みなおして、そんなことに気づきました。まあ、原作と映画は別物だとは思いますし、映画が公開された当時はそれはそれで楽しんだ覚えもあります。 原作を離れれば、大作映画とはいえコンパクトにまとまって、だれることなく、シナリオだけでも楽しめる作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 地球全体を巻き込む、人類の絶滅を扱った小説、映画はウンザリするほどありますよね。 大体、主人公は格好よく死に、ヒロインは助かり、世界も救われるストーリーで、あんまり 面白くない。この、復活の日では、登場してくる細菌学者や軍人、そして、政治家 さらにはごく普通の一般人も、どんどん倒れて死んでいきます。誰にも平等に非情です。 アルプス山中に落下した、戦略用に開発研究されていた小さなアンプル内のウイルスのために、 当時人口35億の人々が続々と死んでゆくのですが、その事件に至るまでの出来事と、その後の 関係者たちの心の中の葛藤が緻密に描かれています。 細菌兵器を悩み続けながら開発する研究者。当時の米、旧ソ連の冷戦時に、本当は戦争をしたくないと 思いながらも軍事施設に勤務する軍関係者達。彼らもすべて、死んでしまいます。 インフルエンザに似た症状で、蔓延拡大していくこの未知のウイルスと戦う、医者たちの姿も リアルに描かれていて、徐々に人口が減っていく現実と絡み合い、何回読み返しても恐ろしいです。 また、後半に出てくる、南極に向かう途中で発症者が出た潜水艦が自枕する、エピソード的な話なども なにか瞼が熱くなるような感覚を受けました。 高校生の時に初めて読みましたが、大人になって、また読んでみると、気が付かなかった事がたくさん ありました。むずかしくて読み飛ばす箇所もありますが、小松左京作品の最高傑作だと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人類は地球を誰にゆずるのか──。 BC(生物化学)兵器として開発された新種の細菌、それは、ちょっとした偶発事故からでも、人類を死に淵に陥れる。 ──吹雪の大アルプスで小型機が墜落し、黒こげの乗員と胴体の破片が発見された。 春になり雪どけがはじまると、世界各地で奇妙な死亡事故が報告されはじめた。ヨーロッパ各地で走行中の運転者が心臓麻痺を起こし、交通事故が激発! 日本では、新種の流感に罹った患者3千万、死亡率は急上昇し病院は大混乱をきたしていた。南米アンデスの奥地でも、まうでペストの大流行のごとく、インディオ部落全員が死亡していた。だが、これらの現象が何に起因するものか、優秀な科学者たちもまったく知らなかった。 <神>の怒りがとける日はいつのことか。 人類の"明日"ためされるとき。著者最高のSF傑作長編小説。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界を牛耳っている軍事国家と一部の資本家が、このまま金のためだけに軍事開発を続けたらどうなるのか? 結局、この小説のような最期になるのではと危惧する昨今。 世界中の政治家さん、是非この作品を読んで下さい。 人の手に負えないものを、人類は持ってはいけない。 数ある小松作品の中で、いえいえ、私が過去に読んだ小説の中でも一押しの作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 未だに、 「僕はSFは読まないが・・・」 などと言って、日本文壇を語る 評論家がいます。 ブルシット!! アホかあ!? 日本の60・70年代の文学支えたん、 小松さんや星さんや、筒井さんじゃあ!! 馬鹿はほっときましょうね。 ぼくらオールドファンには映画としても有名な名作。 最後のほうで、大学の教授が世界に向かって 語るシーンに、小松さんの言いたいことが つまってると思います。 これ新品で買えるようにしてくれてる春樹さんに敬礼!! 小松さんは凄いんだよ。 その死は大江健三郎を3人失ったくらいの喪失・・・。 いい加減目を覚ませ日本クソ文壇!! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初めて読んだ小松左京氏の作品です.読了後直ぐに映画版も拝見しました. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本SF界の偉大なる巨匠であるSF作家・小松左京氏(2011年7月26日逝去、享年80歳)が1964年に発表した初期の長編SF小説である。1980年には角川映画の超大作として劇場公開(1980・6・28)され、映画史上初の南極ロケ敢行や主役の草刈正雄氏を始めとする日本を代表する俳優陣やヒロインのオリビア・ハッセーを始めとするハリウッドで活躍する外国の俳優陣による日米オールキャストの映画(近年の邦画でもこれほどの大規模な作品はない)としても話題を呼んだ作品である。 2009年、突如、ヨーロッパ全土を襲った脅威の感染力を持つ“悪魔風邪”は、瞬く間に世界中に広がり、やがて、人類は死滅してしまった。極寒の地、南極にいた約一万人を残して―。 本書は元の原作を新井リュウジ氏がジュニア(10代)向けに改変され、そのため幾分ソフトな内容となっており、また2009年現在を舞台にしているので元の原作では35億の世界人口(映画では45億)が、本作ではその倍の70億近い世界人口である事や元の小説や映画にもなかったインターネットや携帯電話、電子メールを作中に取り入れているのも本作の特徴である。 南極観測隊の一員で地震を研究している若き地質学者・吉住利夫、吉住の実妹でこの世でただ一人の肉親である雑誌記者・吉住則子、吉住と同じ南極観測隊の一員・辰野、悪魔風邪により孤立した南極地域をまとめるアメリカ隊隊長・コンウェイ提督、悪魔風邪によりさすらいの航海を続けるアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦『ネーレイド号』艦長・マクラウド、その病原菌を研究する南極基地に属するラ・トゥール博士、悪魔風邪に翻弄されるアメリカ合衆国大統領・リチャードソン、大統領の先輩で常によき友人であり助言者である合衆国国務長官・ジョーンズ、常に好戦的な視野を持つ合衆国戦略ミサイル軍総司令官・ガーランド将軍などなど。 私自身、原作と映画の両方を拝見しているものの、何分原作を読了したのが16年前なので物語の内容の記憶が曖昧であり、今回、本作を読むにあたって映画を基に意識しながら読み進める中で、その比較対象でいえば、作中における登場人物の設定(吉住の妹)や悪魔風邪に感染した乗組員のいる潜水艦の描写、南極基地における女性隊員の挿話、ARS(ミサイル発射)を阻止するために決死隊を募る描写やその後の展開などジュニア向けらしくソフトな内容に改変されているものの『復活の日』の入門編としては物語自体の面白さは損なわれる事なく、読みやすさもあって十分堪能した。 本書で初めて『復活の日』を手にした方は是非とも原作と映画をおススメする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大震災、原発事故のあと、あの人はどう思って、何を考えているのか?と、その発言を待ち望んでいた知識人が何人かいました。 その一人が小松左京先生でした。 間違いなく、語りたいことが多かったと思います。 しかし、神は先生と僕等にその時間を与えませんでした。 そのかわり、僕等には『復活の日』を読んで、そして自分で考える猶予をくれました。 あなたがくれたSF魂、私は守り抜いてこれから生きていきます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 全くの偶然ですが東北関東大震災の日(2011年3月11日)の朝に読み始め帰宅難民で身を寄せさせて頂いた帝国ホテル内で読了しました.「復活の日」は生物兵器の漏洩により南極以外の人類が絶滅してしまいますが,南極に生き残った人々は、互いに励まし合い支え合いながら前向きに暮らし,最後には南極を脱出し人類の復活に向けゼロから一歩を踏み出すことで終わっています. 今回の震災も復活の日同様,理不尽な現象により多くの方の人命があっという間に奪われてしまいました.今回の震災空の復興は並大抵のことではないと思いますが,我々日本人も互いに協力し合い前向きに復興してゆかなければならないと思います. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品を読んでいる間中、私はこの中の登場人物のような気分でした。息を詰めて、この先どうなるのかとじっと見守り続け、気がついたら最後まで読破している…何度読み返しても、その気持ちは変わりません。人物も世界もどこまでもリアルに描かれていて、この本に途中でしおりを挟めるひとはいないんじゃないでしょうか。子供向けにわかりやすく書いてある作品ですが、大人こそ、今、改めて読むべきテーマだと思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本SF界の巨匠《小松左京》氏による、世界破滅テーマSFの傑作です。宇宙空間から採取された未知のウィルス《MM―88》が、軍事兵器として開発されることによって世界が破滅の危機に見舞われる、という内容の物語です。特に圧巻なのが、第1部「災厄の年」です。最初は軽いインフルエンザの流行から始まった《MM―88》ウィルスの繁殖が、やがて人類全体を破滅の危機にまで追い込んで行く過程が、社会科学的な視点から、実に緻密に、実にリアルに描かれています。また、第2部「復活の日」では、絶滅の危機にまで追い込まれた人類が、ある《事件》を切っ掛けにして、《復活の日》に至るまでの糸口をつかむ場面が描かれ、これもまた、大変感動的です。歴史的に見ても、アーノルド・トインビー博士の《挑戦と応答の相互作用の法則》にある通り、破滅的な危機を乗り越えた国家は、その危機に匹敵する繁栄を手に入れるものです。小松左京氏の、この傑作SFにも《ピンチこそがチャンスである》という作者からのメッセージが織り込まれているように思います。単なる娯楽作品としても、最高に面白いですが、それ以上の《何か》を訴えてかけてくる、大変、素晴らしい作品です。ここにもまた、20世紀・日本SFの凄さが隠されています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 生物化学兵器による破滅テーマ作品。 ネヴィル・シュートの「渚にて」に影響を受けていると思われますが、決して二番煎じなどではありません。 唯一難を逃れた南極の基地に駐留する各国の隊員たちはどうやって生き延びるのか。 そしてミサイル発射を阻止すべく、潜水艦でワシントンに向かった主人公たちの運命は。 「渚にて」に比べれば、将来への見通しがあるという点でだいぶ元気の出る作品ではあります。 南北アメリカ大陸を延々と一人で縦断するのは多少無理がありますが。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| SF作品のイメージは『内容が難しくて、楽しめなさそう…』でした。 しかしこの作品は、そう思っていた私のイメージを覆しました! ジュニア版なので噛み砕いて書かれていますが、物語の内容はとても濃く、ぐいぐいストーリーに引き込まれてしまいます。 “悪魔風邪”によって人類が死滅してゆく過程は迫力があり、自分に置き換えたら…と、思わず想像してしまいました。 そして、“悪魔風邪”に立ち向かう人類の勇気や、残された人々の愛と絆も描いていて、人間にとって一番なにが大事なのかを深く考えさせられました。 この作品は大人も子供も楽しめる良質な物語だと思います。 いろんな方に読んでもらいたいと思いました! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| SF小説と聞いて皆さんはどういった印象を受けますか? 「なんだか難しそう」「専門用語だらけでめんどい」etc……。かくいう僕も、最初はそう思ってましたが、この本は一味違います。ジュニア版と銘を打たれているだけあって、子供でも分かりやすく書かれており、なおかつ必要以上に噛み砕いて書いているわけではないので大人でもスムーズに読めます。さらに凄いのはこの原作が1964年に発表されたものであり、今尚風化しない魅力を放っているところでしょう。これはひとえに原作者の小松左京先生、そして現代風にアレンジされた訳者の新井リュウジ先生の凄さでしょう。SF小説入門編としてオススメです! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 細菌兵器,核ミサイル,最新技術を駆使した殺人装置(自動報復システム), 空虚なスパイ合戦,金と裏切り等々, 人間の愚かさと悲惨が満載であるのに,作者の目は温かい. ラストは印象的. 人類は滅亡の淵に立ち,最後,南極に残ったわずかな人類が,偶然により, 復活のチャンスを得る.その時点で,物語の幕が下りる. 神の視点から見れば,人間の愚かさは児戯であろう. ただ「生きて命をつなぐ」こと,人類という「種」を残すことのみが人類に課せられた 業であり,ささやかな幸せなのだろう. そうしたことを感じさせてくれる作品.ハッピーエンドではないが,深い感動が得られる. (パニック小説とは一線を画する.この作品の読後は,巷にあふれる活劇や冒険物語では 満足できなくなるかも知れない) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「H1N1」の広がり方は まるで「MM-88」のようだ! というわけで この大型連休は 小松左京さんの不朽の名作 『復活の日』を読み返そう。 あえて今 この不朽の名作を読み返すことに意味がある。 不謹慎だが、なによりもスリル満点。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| WHOが、史上初のフェーズ5を宣言しました。 ついに、現実が小説に追いついてしまったのかもしれません。 今でも充分通用する部分が、少なからずあると思うので、一読をおすすめします。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!