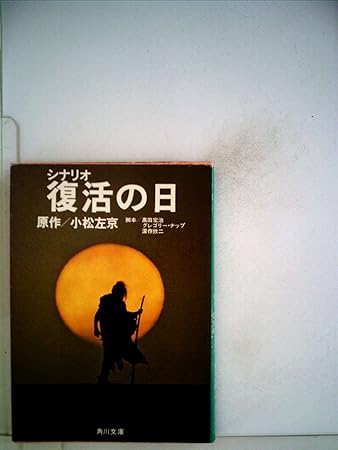■スポンサードリンク
復活の日
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
復活の日の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.38pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全195件 141~160 8/10ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Reader Store版で読了。 寒河江智果さんの新作「湖畔の女」をきっかけに、小松左京作品をぽつぽつ読み返しています。 この作品では世界破滅ネタに、当時問題になっていた○○○○○を絡めておもしろく処理しています(ちょっと「機械仕掛けの神様」的ではありますけれど)。 フランケを代表とする当時の思弁系SFは自分の視座を据え直すのに大いに役立ちました。小松左京作品の中では、大きな問題を扱った本作だけでなくより身近な問題を扱った「女」シリーズや「くだんのはは」を始めとする恐怖短編にも文明と社会に対する告発があり、SFの潮流を多いに反映しているように思います。これもまたセンス・オブ・ワンダーの一つですね。 それも今日の自称「リアリスト」たちに言わせれば「お花畑」なのでしょう。寂しいことです(実際そんなレビューがありますし)。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 小説が先か映画が先か不明だが、TVで草刈正雄主演の映画を見た記憶は有る。 今では草刈正雄は真田昌幸のイメージしかないけれどもね。 1964年初版だから半世紀前に書かれた物語だけれどもパンデミックの描写は古くない。 以前鳥インフルで鶏卵不足で卵の値段が上がりワクチン不足とかのニュースが有ったしね。 ワクチンは生ものだから、今も昔も変わらずと言う事なのかな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 圧巻のストーリー構成。最後まで息をつかせぬ展開が続きます。死者や都市の荒廃の様子の描写は、第二次世界大戦後の空気が濃厚な時代を生きて来た著者ならではのリアリティでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 50年以上前に書かれたものとは思えないですね。名作です。 30年振りに読み返して思ったのですが、主人公にもっとドラマ性があればいいのですが。 映画では日本に残した恋人がいたり、南極から出発前にヒロインとの出会いが あって。 それでクライマックスが盛り上がるんですが。。。。。そこが残念。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 80年代の角川大作路線の最後の映画化でお馴染みだが、作品自体は60年代初頭に書かれている。 細菌による人類の滅亡を描いた壮大なスケールながら、後半の活劇的な要素や最近滅亡の要因の皮肉な落ちなど娯楽性も高く、今読んでも古さは感じない。 改めて小松氏の先見の明の凄さが実感できる作品である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 迅速かつ丁寧な対応 ありがとうございました。 綺麗な商品状態に 大変満足しております。 また機会がありましたら、宜しくお願いします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品を初めて読んだのは、ちょうど急激に寒くなって体調を崩した時期でした。ゲホゲホしながら読んだ本書はとても臨場感があって恐ろしかったです。もし風邪じゃなかったらどうしようと。小説を真に受けてはいけないと思いつつも、弱った脳みそにはダイレクトに響きました。そして毎年寒くなってくると思い出す作品にもなりました。 とても古い小説ですから、いろんな側面で時代を感じます。なにせ書かれたのは1964年! 半世紀以上前の作品です。時代も何もかもが違いますね。Amazonもなかった時代の本です。 しかしながら古さはそこまで感じません。SFの形態を借りていても、この小説の神髄がガジェットや技術を書くことではないからでしょう。極限に直面した時、人はどう行動するのか。年齢も人種も職業も多様な人々の終末に至る生き様が、非常に生々しく書かれています。ハリウッド映画でしたら人類存亡の危機だ!アメリカは一致団結!大統領を筆頭に異星人やっつける!で、ハッピーエンドなんでしょうが、この小説ではそうはいきません。助かる道はあったはずなのに、自分の進退や出世、影響を考えて握りつぶす輩。何かがおかしい、これは普通ではない、根本的な手を打たなければならない、とわかっていながらも目の前に押し寄せる患者を見捨てられず、疲れ果てた体をむち打って現場に立ち続ける医療従事者。死を覚悟してなお、せめて生き延びた人に真相を伝えなければと望みを託す人。状況を理解できず、ただ助けを求めるしかない幼児。救いを求める幼い声を聞いても、助けに行くことはすなわち共倒れにしかならないため、歯を食いしばって見捨てる生存者。 また、事態の始まりそのものが研究成果の盗みあいであり、人類の未来を憂いた学者の覚悟と甘さ、職務に忠実であっても視野は狭いバイヤーの計算違い、といくつものボタンの掛け違いから恐ろしい事態まで発展します。そして絶望しかない状況で必死にあがく人間をよそに、あっけなく事態は悪化していきます。ひたすら希望は叩きおられ、それでも諦めない人間の姿が書かれています。 とにかく多様な人が死に面し、それを理解する人、理解できない人、目を背ける人、多くの生き方が登場します。 SFではなく人間小説としてお勧めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本のSF小説聡明期にあたる1964年、早川書房の福島 正実プロデュースで日本人作家による「日本長編SFシリーズ」第1巻として書き下ろされた小松左京による本格SF小説の名作。 1975年 、角川書店に移籍して角川文庫として刊行される。 そして1980年、 学生時代から本作のファンであった角川春樹社長(当時)は悲願でもあった映像化を実現し、角川映画として公開。 その映画公開記念として文庫版と並行してハードカバー単行本版も刊行されたのが本書。 巻末のあとがきは映画化に伴う本作の随筆経緯の回想録は単行本版のみ収録。 カバー装丁、口絵、本文イラストは生頼範義画伯という豪華な一冊。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| トムクライトンのアンドロメダ病原体に似ているけれども、 あれと地球最後の日というSF映画を掛け合わせたような内容になっている。特に無地のホワイトハウスに、核発射ボタンを止めに行く場面は、ある港町に謎の発信音を探しに行く場面にいている。宇宙から来た謎の病原体によって人類がほぼ死滅し、南極に残された人々にも、核爆弾による報復のミサイルが降り注ぐという話だけれども、かなり病原体についての専門的な説明があり、そいうのが苦手な人には辛いだろうなと思える。 第一部の病原体によって、世界中の人々が死滅する描写が割と詳しく書かれているが、第二部の南極に残された人々が、米ソの核発射に対抗する描写は、割とあっさり書かれているのが、残念。そちらの方も、詳しくかいてほしかった。 それでもSF界の巨匠らしく、読み応え満点。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| きっと原作は面白いんだろうなあ・・・と思い読んでみました。 人類が滅亡していく下りは非常に怖くて緊迫感もあり 良かったです。 その分、後半の復活編がややとって付けた感が否めず・・・という感じです。 書かれた時代(東西冷戦時代)を考えれば切迫感のあるストーリーなんでしょう。 まあ、考えてみれば今の方が科学技術は進んでいるし世界は混迷の度合いを深めていますからこんなバイオ兵器が有ったらマジで怖いですけと゜・・・・・・ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 電子書籍になって、いつでも持ち歩けるようになりました。 インフルエンザ流行の話しを聞くたびに読みたくなります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 映画は観ました。 当時、角川映画全盛で、大々的にキャンペーンしており、 太陽をバックにズタボロの男の映像が目に焼き付いています。 それで、本も読んだつもりでいました。(恥) エボラ出血熱の「ホットゾーン」を購入するつもりで検索中、 「復活の日」にたどりつき、レビューを読んで、 映画で満足している場合じゃない! 読むべき本だ! しかも、今! 今、読むべき本でした。 映画よりも濃く、恐ろしく、リアルで、何十年も前に書かれたとは思えない、 遺伝子操作が簡単に可能な現在、いつ起きてもおかしくない内容でした。 映画で、オリビア・ハッセー演じる女性が、原作では大きく違います。 でも、原作の方がずっと素敵。 最後の夜には思わず泣いてしまいました。 あのシーンだけでも、読んでよかった、と思います。 映画だけ観て原作を読んでいない人にこそ、読んでほしい本です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 特に違和感無く、現代風に変化してます。 初めて読む方も、映画を観た方も、旧作を読まれた方にも楽しめる作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 現在、エボラ出血熱の脅威について、ニュースなどで多く語られている 真っ先に、この作品を思い出した (最もエボラウィルス自体は、作中のウイルスのような空気感染能力は持たないが) ワクチンを作り出す為の生殖卵が死滅していき、その研究を行なうべき医学者も次々と死んでいく じわじわと、しかし確実に訪れる絶望と破滅、滅び行く人類社会の阿鼻叫喚 ウイルスの侵入を防ぐ防壁は「極低温」のみ 図らずも「人類存続」の責務を負わされた、世界各国の南極越冬隊員達 そして顕在化する、生物としての「繁殖」の問題・女性の絶対数の少なさ 主人公吉住が、文字通り「決死」の覚悟で米国国防省に向かう前夜、南極臨時政府の計らいでせめてもの慰み(肉体的なを与える為に来訪した中年女性、イルマ・オーリックに対して「人間にはセックスよりも重要なことがある」と性行為を固辞し、「自分の母も家族もウイルスで死んだ せめてあなたを母だと思って肩を揉ませてほしい」と肩揉みをするシーンは、涙無くしては見られない そしてラストの「人間を救う為の筈のものが人類を滅ぼし、人間を殺す為だけに作られた筈のものが人類を救う」という、大いなる皮肉 最後に僅かながら人類に残された「希望」 過去に角川で映画化もされたが、当時の角川映画お得意の「角川解釈」があちらこちらに見える 例えば中年女性イルマの役どころが「あまりに華がない」という事で、オリヴィア・ハッセー演じるマリトという女性と吉住(草刈正雄)のラブストーリー的なものに変更されており、上記のしみじみとした感動エピソードも映画版では無くなっている また、小説原作では生存総人口が数千人であったのに対して、映画版では数十人しか描かれていない(この人数では種としての存続すら危うい)など、かなり解釈が異なる もし「映画版しか観ていない」という人がいれば、是非とも小説原作を読んでほしいと共に、出来うるなら原作により忠実な形で、最新の医学テクノロジーを取り入れた映画版のリメイクを望みたいところだ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「バイオハザード」という言葉が知られる30年以上も前に書かれた、日本史上最高のSFの一つ。 些細な事から、取り返しのつかない事態に陥るまでの、息を呑むような真実味に溢れた展開。 偶然、世界から隔離されていたため、否応なく人類の未来を背負わされる主人公と南極の人々。 私も含め、今のかなりの世代では、「何時、ソ連の核ミサイルが落ちて来て人類は滅亡するのか」という 現実味を味わっていないため、ガラスの向こうの空想世界として楽しめる物語であるが、実際に60-70年代を 分別盛りで過ごした人たちには、単なる「作り事」ではすまない恐怖をバックグラウンドにした話なんだろうな、 と今更ながら感じている。 でも、そんな事を差し置いても、この物語は楽しめる。13才の春にこの話を読んで以来30年以上忘れることが できないくらいのインパクトが、この作品にはある。 クライマックスで、ある男女が泣きながら抱きあうシーンは、未だに強烈な印象を残している。 どうせ読むならこんな作品を読みたい。という訳で、一刻も早くKindleに入る日を待っている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説が書かれて今年でちょうど半世紀。しかし内容は少しも古さを感じさせない。当時としては最先端の知見、しかも将来性のある、方向性の正しい知識に基づいた話であったためである。この点にいちばん唸らされた。膨大な学識と非凡な着想で編み出されたストーリーに脱帽である。南極に向けられた核ミサイルで絶体絶命と思われた人類が、信頼、良心といった、予想外の人類の資質によって救われたところがクライマックスだろう。 ただ、大量の知見を解説するための講義的な会話や、作者自身の思想を登場人物に長々と開陳させる場面など、衒学的な面が多々あるのでマイナス1点。 マイクル・クライトンの「アンドロメダ病原体」を読んだときは、デジャビュを感じた。つまり、「復活の日」をパクッたとしか思えない。あれはあれで面白いのだが。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本作は1964年,アメリカとソ連(ロシア)の両国が,あまりにも強力すぎて自国さえ滅ぼしかねない核兵器を持つことで,逆に戦争ができないという状態が続いていた冷戦時代に出版されました。 しかし,本書で人類を絶滅に追いやるのは,核兵器ではなく細菌兵器として生み出されたウィルスなのです。 人類を殺害するために作り出された核兵器の存在が結果として戦争を抑止し,人命を救うはずの医学が,人類を破滅させる原因を作り出してしまうというこの矛盾。 人間社会は矛盾に満ちあふれている。 「個々の人間はそれぞれ理由を持って行動し,決してバカではない。しかし,人類総体の見地からみた時,そのやっていることはきちがいざたみたいなことが多い。医学は人命を救おうとする一方,呪わしい細菌兵器の研究にも利用されている。一方で人類を助けようと努力し,他方で人類を絞め殺そうと努力している」 小松左京は「日本沈没」でも絶望的な状況にある日本人の描写をしていましたが,本書でも同様の描写があります。 「突然パニックがまきおこり,人々は先を争って病院の入り口に殺到するかと思わせる危険な感じだったにもかかわらず,実際は普段のときよりも,人々はかえって秩序正しく,その秩序は群衆全体の内面からわき上がってきているようだった。小さい子どもをつれた母親が最後尾につけば,それはたちまち,次から次へと最前列に送られた。」 本作では,世界的規模でのパンデミックのため,国外では略奪や暴動が発生する中,国内では上記のとおりで,これはまさに日本人として世界に誇れる国民性と言えるでしょう。そしてその国民性の描写は,あの東北大地震で証明され,世界の賞賛を受けました。 さて,原因不明の病原菌がもとでパンデミックが発生するという設定の物語は少なくなく,その中でも本書は,その先見性やリアリティある設定などから断トツの出来ですが,最近の作品だと,小川一水の「天冥の標2 救世群」もお勧めです。こちらは,壮大な物語の一部として発表されたものですが,この'2単独でもパンデミックものとして十分楽しめます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 凍てつくような真冬のある日、とある山頂に細菌兵器を搭載した軍用ジェット機が墜落した。 細菌兵器は寒さに弱く、冬のうちは鳴りを潜めていたが、 春がきて、雪解けが始まったある日、羊飼いの少年は恐るべき光景を目にする。 墜落事故のあった山の麓で、多数の羊が命を失って横たわっていたのだ…。 小松左京氏の作品中、最も繰り返し読んだ作品がこれです。 謎の「風邪」が蔓延してゆく描写が具体的で素晴らしく、 国会が定員割れで閣議に入れないとか、大相撲が休場力士多数のため、千秋楽を待たずに興行中止とか、 ドキドキしながら読みました。 本作品で印象的な場面は日本のある医師が、「風邪」をひいた患者の応対に明け暮れ、 「どんなことでも、「終わり」はある、ただどんな「終わり方」をするかが問題だ」 と呟いて息を引き取るところですね。 前述した通り、細菌は寒さに弱いため、南極の越冬隊に被害が及ばず、 ゆっくりと終わってゆく世界を傍観するしかない、無常さの描写も素晴らしい。 北米の男の子が「風邪」で家族がみんなやられ、アマチュア無線で、 「誰か返事してよ…でないと僕…死んじゃうよ?」 という通信を越冬隊が無線機で傍受し、子供を元気づけてあげたい隊員と、 第3者が無線を傍受して、南極が無事と分かれば、 感染者が大挙して押し寄せてくることを案じる隊員とが、 無言で泣きながら殴り合う場面も忘れがたいです。 大傑作小説です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 期待通りの保存状態でした。古いものですが、やっと手に入れました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初めて読んだ気がしないと思ったらたぶんTV(映画)で見た覚えがある。 アイデアも素晴らしいが、その科学的な洞察力・推理力はすごい。 これは現実になると思った。 国益になるなら他の国がどうなってもよいという政治家。 金さえ稼げれば他人はどうなってもよいという人間。 その手足となって働く科学者。 このリアル感が日本沈没に続いている。 もっと早く読んどけば良かったと思う一冊。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!