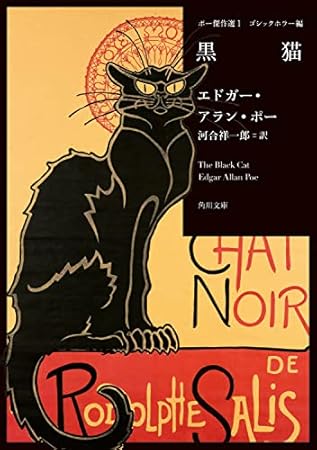■スポンサードリンク
(短編小説)
黒猫
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
黒猫の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.41pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全66件 41~60 3/4ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 還暦近くなって江戸川乱歩にはまり、一気に全作品を読破した後で、 やはり彼が大きく影響を受けた黒岩涙香とエドガー・アラン・ポーは読まない訳にはいかないと思いました。 先ず推理小説のモルグ街の殺人(もちろん粗筋は知っていましたが)等を読んで、 次に怪奇小説の本短編集を読んでみました。 成程ポーならではの世界と言うかこのジャンルの祖というかここから始まったんだという感じがあります。 どれも面白いですが、個人的には赤い死の仮面が好きです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 小学生の時に始めて読み、不気味でリアルな絵に心底怯えました。 表紙の黒猫のリアルさからもお察しできると思います。 『早すぎた埋葬』は怖すぎて夢にまでみました。 しかし、年を重ねてから読むと、ただ怖いだけではなくて、人間の精神が崩壊していく様を、当事者になって味わう恐怖(『黒猫』)や、無常を感じさせるアッシャー家の最期など(『アッシャー家の崩壊』)、非常に味わい深い作品たちであることがわかりました。 この本は、児童書なので、小学校高学年くらいから読めるよう、易しい言葉で訳されています。 それでいて、ポー作品の味わいを損なうことなく読むことができます。 挿し絵も大好きなので、ずっと変わらず残ってほしい本です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ポーの奇怪で暗鬱で破滅的な雰囲気が面白いです。 ポーの悲劇的な人生にも興味を引かれます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| エドガー・アラン・ポーの小説を読むのはこれが初めてでしたが、 楽しく読めました。 最近は猫を小説に登場させる作家が多いですが、 ポーの黒猫ほど上手く描けている作品は少ないのではないでしょうか。 おもしろい短編集だと思います。おすすめです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『アッシャー家の崩壊』を収録。 「無機物や、植物や死体にも霊魂は宿る」はずはないのに、 「無機物や、植物や死体にも霊魂は宿る」のではないか、 「無機物や、植物や死体にも霊魂は宿る」のは、当たり前のことである。 と読み進めるうちに思えてしまうのがこの小説の怖さである。 それは生きた人間の技である。と思えるところはもっと怖い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今や古典的名作となった「黒猫」など5作品を載せている。「アッシャー家の崩壊」は高校時代、英語のダイジェスト版を副読本で読んだ記憶があるが、邦訳を呼んでも不気味さは独特のテイストがある。ただ、書かれたのが日本の江戸時代にあたり、訳されたのも昭和20年代で文章が古いので今の感覚では読みづらいと思うが、そこは時間の余裕があるときにゆっくり繰り返し読むと作品の持つ味わいが伝わってくると思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今や古典的名作となった「黒猫」など5作品を載せている。「アッシャー家の崩壊」は高校時代、英語のダイジェスト版を副読本で読んだ記憶があるが、邦訳を呼んでも不気味さは独特のテイストがある。ただ、書かれたのが日本の江戸時代にあたり、訳されたのも昭和20年代で文章が古いので今の感覚では読みづらいと思うが、そこは時間の余裕があるときにゆっくり繰り返し読むと作品の持つ味わいが伝わってくると思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ポーの短編集を1冊選ぶとしたら本書をお勧めする。作者作品の真価を味わうのに必要にして最小限の作品が掲載されている。それにポーの肖像画とか資料写真や年譜も掲載されており、他の文庫本の短編集よりも資料価値が高い。 掲載作品は次のとおりである。 ・リージア ・アッシャー館の崩壊 ・ウイリアム・ウィルソン ・群集の人 ・メエルシュトレエムの底へ ・赤死病の仮面 ・黒猫 ・盗まれた手紙 掲載作品の中では『盗まれた手紙』が異質ではあるが、推理ファンとしては外せない作品である。どうせなら『モルグ街の殺人』も入れてくれていたら言うことなしである。 なお、『アッシャー館の崩壊』は『アッシャー家の崩壊』の訳題が一般的だが、「家」ではなく本書の「館」の方が適切である。「アッシャー家」では家庭内の崩壊みたいだが、実際には建物が崩壊する作品なのだから。 (実際、私は作品を読むまで、アッシャー家の家庭が崩壊するまでの登場人物たちの心理を描いた作品かと真剣に思っていた。) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初めてポーの作品をしっかり読んだのは、大学の授業。 それも『アッシャー家の崩壊』。最近のホラー映画で観られる気持ち悪さや ハッというおどろかされる怖さではなく、少しずつ知らない間に恐怖心を あおり体の芯までゾクゾクとするような感じ。授業中に先生の解釈付で読み 進めた時のなんとも言えない不気味な感覚を、今でも忘れられない。 この本には、題名にもある通りポーの作品でも有名な『黒猫』も収められ、 彼独特なゴシックホラーの世界が楽しめる。是非、お試しを。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ポー生誕200周年ということで、巽孝之氏による新訳の短編集。 黒猫ぐらいは読んだことあったけど、ちゃんとポーの作品を読んだことがなかったので、面白かった。 しかし、100年以上前に書かれたとは思えないぐらい、ポーの作品って怖いなぁ。真のゴシックホラー。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ポーの生誕200年記念に出版された短編集、第一弾。 「ゴシック編」と銘打たれたこの本には、以下の6作が収録されています。 温厚だった男性がアルコールで身を崩し、やがて罪を犯し自滅する様を 彼が可愛がっていた黒猫を印象的にからめて描いた「黒猫」、 疫病から逃れるため城に閉じこもり、遊興にくれている王侯貴族に やがて影が忍び寄る「赤き死の仮面」 最愛の妻を亡くした男の、妻への想いとその後の生活の独白「ライジーア」、 スペインの異端審問にかけられた男の「落とし穴と振り子」、 自分にそっくりな男がつきまとう「ウィリアム・ウィルソン」、 級友に招待されて行った屋敷でおこる不気味な事件「アッシャー家の崩壊」。 多くが、作中人物の独白形式で書かれています。 物語は美しい、絢爛な文章でつづられながら 緊迫感と不気味な雰囲気も併せ持っていて、まさに名作。 巻末には年譜も収録されています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書に収録されている「赤き死の仮面」(The Masque of the Red Death)は、トム・クランシーの「合衆国崩壊」第4巻P.117と、「教皇暗殺」の第1巻p.67に、「赤死病の仮面」として登場する。 どんな本か興味があって、調べてみたところ、ポーの新刊(後述のように単なる復刻ではない)として発売された本書に含まれていることが分かったので買ってみた。 読んでみたが、確かに、トム・クランシーの作品に出てくるお歴々の記憶に残るのもなるほどと思える、強烈な隠喩を含んだ作品である。 なお、ポー作品は、高校生時代に読んだが、「黒猫」と「アッシャー家の崩壊」は印象が強かったのか、よく覚えていた。 ただ、幾つかの作品が載っていないようなので検索したら、どうやら、昔、私が買った文庫本には、「黒猫」、「アッシャー家の崩壊」以外に、「黄金虫」、「ウィリアム・ウィルソン」、「メールストロムの旋渦」が掲載されていたようだ。 本書は、短編集1とあるので、いずれ紹介されることになるのであろうが、「黄金虫」と「メールストロムの旋渦」(要は浦島太郎的な話)にも何とも言い表しがたい強烈な印象を受け、「ポーは天才」との思いを当時強く持ったことを付言しておきたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作家としての後世の評価に対して、ポーは不遇で貧しい人生を送った人だった。年表つきで丹念にそのへんを解説してくれるこの新潮文庫版は、彼の小説のもつ暗鬱なテイストと、若くして死んだ彼の精神状態の呼応を読み取れるようで、作品を更に味わい深くしてくれる。 子供の頃に「推理小説」として読んだ人も、そういった作者の人生を感じながら読み返せば、また新鮮な読み応えがあるだろう。何度でも新鮮に読めるのが、古典の味わいである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ポーという作家は多彩な方だ。詩人であり 探偵小説家であり 暗号小説家であり ホラー作家である。こういう方は 他に類を見ない。あえて言うなら ポーの名前をそのまま借用した江戸川乱歩が 忠実な弟子なのかもしれない。 本書における「黒猫」は 犯罪小説なのだろう。猫を壁に塗りこめてしまい その鳴き声で犯罪が発覚するという話だ。間抜けな犯罪の話かもしれないが 壁の中から猫の鳴き声が聞こえるという場面を想像するだけで 皮膚にひりひりするような恐怖感が生れる。その「皮膚感」こそが ポーの作品を凡百の作品とは違うものにしている。 「黄金虫」も 宝島まがいの暗号小説なのだろうが その雰囲気たるや ぞくぞくしてくるものがある。これも やはり 彼の詩人としての資質から来るとしか思えない。 ポーの影響は大きい。ある意味で通俗的な小説を書いた作者が齎したオーラは 今なお 僕らを惹きつけてやまない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本には、エドガー・アラン・ポーが書いた代表作のうち 4つ("The Black Cat", "The Oval Portrait", "Berenice", "The Mask of the Red Death")がリトールドされて収録されている。 日本でも怪奇小説で有名なポーの作品を、1200語程度に制限された語彙の中で 気軽に読める、お勧めの本です。しかも、4つの話にわかれているため、 短い話をたくさん読みたい読者にも向いています。 夏の夜などに、よみたくなるちょっと怖い内容ですよ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ポォの作品のなかでも異彩を放つのは黄金虫だと思います。 基本的には推理小説ですが、本作は宝探しでもあるからです。 下僕の間抜けでおっちょこちょい振りが結構好きです。 黄金虫を鍵として、海賊の宝を掘り当てるまでの過程はかなり面白いです。 筆者独特の?底の浅さは現代人には馴染めませんが、 推理小説の古典として楽しめると思います。 ちなみに黒猫とかが有名ですが、私はあまり好きじゃないです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 久しぶりに読み返しました。 本書では特に、『黒猫』と『赤死病の仮面』と『アッシャー館の崩壊』なんかが好きです。 ポーの作品は、奇妙で面妖な雰囲気で物語が進み、最終的にはオチをつけるものが多いことが印象的です。 『黒猫』での、主人公のラストでのあの行動は、ポー自身の性格をそのまま現しているように思います。 なんでもポーは、例え何かの物事が上手くいっているとしても、何故だか逆にどうしてもそれを破壊したい衝動に駆られ、そして実際にそうしてしまうという悪癖を抱えていたそうです。 いずれにしても、ポーは、良い意味でのおどろどろしさを表現でき、その奥には自流の思想も兼ね備えているセンスある作家の一人だと思います。 何処となく、中学生の頃に読んだ漫画『金田一少年の事件簿』を想い出したりしました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 表題作「黒猫」「黄金虫」の他に「アッシャー家の崩壊」「ウィリアム・ウィルソン」「メールストロムの旋渦」の五編を収録した短編集。 「アッシャー家の崩壊」「ウィリアム・ウィルソン」などは展開自体が既に恐怖小説のテンプレートと化している感があり、筋そのものを追うのは退屈かもしれないが、やはりその美文は圧倒的。 特にメルヴィル「白鯨」を髣髴とさせる「メールストロムの旋渦」における神々しい自然描写は、SFやファンタジーの域に達しているのではないか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 怪奇小説といえばやはりポー。色々読んでも最後はここに帰ってきてしまう。子供のころ『黒猫』読んだときのゾッとするような恐ろしさは忘れられない。一度は目を通してほしい永遠の名作。特に怪奇小説ファンでなくても充分に楽しめるはず。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私はこの本をアメリカの英語の授業でやったので、深いところまでは理解できませんでしたが、古英語で書かれていて、重々しさや、異常な雰囲気が下手なホラー小説なんかよりも恐怖感が伝わってきます。ほかのレビューにイギリス出身とありましたが、たしかアメリカ出身のはずです。イギリス出身だったらここまで有名にならなかったんじゃないかな。アメリカだと異端児だったんではないでしょうか、ポーは。ポーはかなりムーディ(暗い)な雰囲気の人だったようです。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!