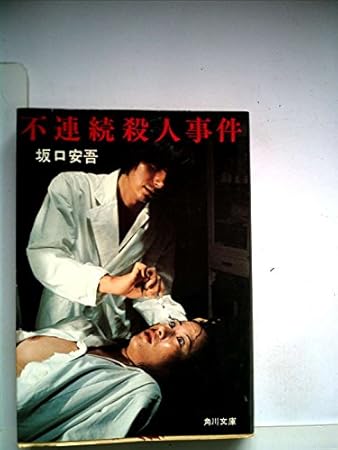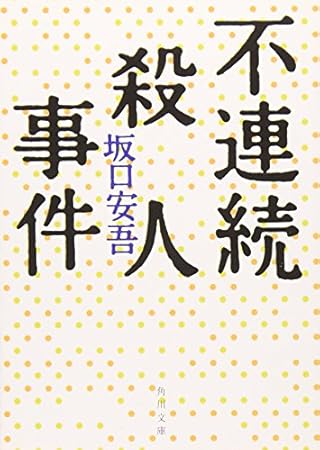■スポンサードリンク
不連続殺人事件
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
不連続殺人事件の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.84pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全17件 1~17 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 死んでいく感じ。 なんでその場にみんな残ってるのか?結局これが納得いかないので自分には合わなかった。 特に医者が不快だった。時代背景はともかく、そもそも4km離れた所に毎日来るのかな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 普段は推理小説とか探偵小説とか全く読まないのですが、 坂口安吾なら面白いかも知れないと思って読んでみました。 登場人物が多い上に、その関係性も複雑怪奇なので、 登場人物一覧をコピーして栞がわりに読み進めて行ったのですが・・ 50ページぐらい読んでも一向に興が乗らず、 取りあえず最後まで読むことを目的に読み進めました。 なにしろ推理、探偵の類を全く読まないので、 この小説が推理小説として如何ほど優れているのかは分かりませんが、 多分・・私が愚考するには、 作者は小説を創作する事よりも犯人探しゲームの方が楽しくなっちゃったのではないかと・・ そんな気がします。 なので、小説としてよりも犯人探しゲームとして読めば面白いのかもしれません。 世上評価が高いというのは、つまりそういう事ではないでしょうか。 私は『堕落論』とか『白痴』の方が好きです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 学生時代に角川文庫版で読みましたが、登場人物が多く、それぞれのキャラクターを把みきれなかったこともあり、読後感はいまいちでした。 年齢を重ね、老眼も進行してきましたので、活字が多少大きくなった?新潮文庫版を新規に購入し、当時の時代背景を堪能してみたいと思います。 新たな発見・感動がありましたら、星の数を増やしますから(笑) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 全く面白くなかった。 坂口安吾は好きであり、ファンも自称していて「安吾捕物帖」も好きなのだが、これは面白くない。 何故だ!?と思ったが、ミステリーファンには評判が良いようで、どうも自分はミステリーが嫌いらしい。逆に本書が面白いという人は、生来のミステリーファンなのだろう。 そういう試金石的作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 登場人物が全員色情狂で、変人ばかり。 妙にエキセントリックな人もいるが、殺人事件が起こっている事と無関係にそういうキャラ。 事件の行く末も何が何やらで分からず、これと言って印象に残らなかった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人的には坂口安吾というと純文学のイメージが強かったため、本作のようなミステリーも書いていたこと、さらにそれが各方面から高い評価を受けていることを知って少し意外だった。 戦後間もない昭和二十二年、某県の山奥にある資産家・歌川家の屋敷に、自身も作家であるこの家の跡継ぎ・歌川一馬からの招待を受けて、戦時中歌川家に疎開していた知人やその関係者たちが集まってくる。小説家、詩人、画家、学者、女優…。しかし彼らが受け取った招待状には何者かによって手が加えられており、招待客には複数の招かれざる客たちが含まれていた。屋敷に集まった人間たちの間に渦巻く愛憎と複雑な人間関係。謎の人物からの脅迫状。その中で次々に殺人事件が発生するが、被害者の間に共通する要素はなく、犯人の意図もつかめない。何かの隠された動機が背後にあるのか? それともこれは、複数の犯人による不連続な殺人事件なのか…? 登場人物がやたら多く、誰が何者かを覚えるのに少々苦労したものの、複雑な人間関係や登場人物たちの奇矯な言動そのものがトリックの一部となっているなど、かなり練り込まれた本格派のミステリーである(海外で言うとクリスティあたりの作風に近いような気がする)。ただ、要となる1カ所のトリックに気付けば、あとは芋づる式に犯人から動機までたどり着けるかもしれない。 あるいは坂口安吾は、本作で探偵役を務める巨勢博士を主人公にしたシリーズを考えていたのかもしれない。だとすると、それが実現しなかったのは少し残念だが、本作だけでも読む価値は十分にあるので、ミステリーファンであれば押さえておいて損はないと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文豪の書いた推理小説として、更に横溝氏の獄門島や高木氏の刺青殺人事件を押しのけて探偵作家クラブ賞受賞と評価が高い作品だが、実際読むと、まあ非ミステリー作家が書いたミステリーとしてはよく出来ているが、文豪が書いたからと言って文学的趣向がある訳でもなく、やや癖のある読みにくい文体が特徴的だが、ミステリーにはこの文体では状況把握がやや難しく、読みづらいくなっている。 トリックとそれに至る論理的根拠は明確であり、その点はミステリーとしてきっちりまとまっているが、正直今から読むとその連続殺人の真相も心理的欠陥のトリックも驚きはない。よくあるパターンである。 何かと日本推理小説史上屈指の傑作と言われている本作だが、そこまでのものか・・という感じが正直した。これなら賞を逃した獄門島や刺青殺人事件の方が数段ミステリーとしては出来は上だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 桜の花の満開の下、を読んで坂口安吾作品がすごく気になっており、本作も買ってみた。 文体はやっぱり綺麗で洒落ていると思う。 登場人物はなんだかみんな変で、普通の人がいない。 ミステリー作品自体が自分にはあまり合わないのか、何が言いたいのかな?と思いながら読んでいたら終わってしまった。 よくわからない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 戦争直後の物がない時代に、一冊の本を何度も読み直して楽しむには、このくらい多くの人物を登場させても読者は苦痛ではなかったのかもしれないが、今の感覚ではやはり多すぎて、人間関係を別に整理して書いておかないと、途中で間を置いてしまうと、次に読むときにまた最初から読まないとわからなくなるだろう。 これだけ多くの登場人物なのだから犯人探しは難解かと思ったが、あまりに多くの人々が死んでいき、犯行の動機として資産家の遺産相続目当てであることは本の中でも疑われているのだから、最後に残った数少ない人物の中で遺産の相続権がある人物を疑っていけばいいわけで、謎解きは思ったほど難しくは感じなかった。 確かに著者は楽しんで書いており、屋敷とその周囲の詳しい見取り図やバスの時刻表を載せたり、内容的にも当時の上流階級の退廃を男女の性の乱れや狂ったような男の登場などで風刺しており、当時の読者を飽きさせなかっただろうが、今読むと話がもったいぶってくどい印象のほうが強いのでは。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 評価が頗る高かったので読んで見ました。 トリック自体は面白かったです。ただ現代だと、それほどインパクトを与えるものではないと思います。登場人物の把握が難しかったので、この評価にしました。もう一回読めば、安吾の凄さに驚けるかも知れませんが、初読ではこの程度です。文学的な人物描写や心理描写は私には良く分かりませんでした。初心者にはオススメしない作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本探偵小説ベストテンの常連でもあるし、かなり期待して読んだのだが、ハッキリ言って期待ほどでは無かった。果たして「戦後文学の騎手」坂口安吾の作で無かったならば、かくも高い評価を得たであろうか疑問である。 確かに、真犯人を当てるのは困難だが、それはこれほど登場人物を多くすれば、確率的にも真犯人は当て難い。しかし、その真犯人も別に「意外な犯人」と言うことも無く、真相が解明されたときも「ふーん」ってくらいのものであった。巻末の高木彬光の解説で激賞されているもんだから、もっと大きなトリックが使われていて、最後にどんでん返しでもあるのかと思っていたが、それも期待はずれに終わった。 第二回探偵作家クラブ賞で対抗馬として候補になりながらも、本作に敗れたらしい『刺青殺人事件』の方が私にはずっと名作だと思われた。横溝正史の作としてなら「中の下」位のものではなかろうか? 文章は適度に砕けていて読みやすいが、なんとも臭みのある下品な(?)文体であるので、好みは分かれよう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本探偵小説ベストテンの常連でもあるし、かなり期待して読んだのだが、ハッキリ言って期待ほどでは無かった。果たして「戦後文学の旗手」坂口安吾の作で無かったならば、かくも高い評価を得たであろうか疑問である。 確かに、真犯人を当てるのは困難だが、それはこれほど登場人物を多くすれば、確率的にも真犯人は当て難い。しかし、その真犯人も別に「意外な犯人」と言うことも無く、真相が解明されたときも「ふーん」ってくらいのものであった。巻末の高木彬光の解説で激賞されているもんだから、もっと大きなトリックが使われていて、最後にどんでん返しでもあるのかと思っていたが、それも期待はずれに終わった。 第二回探偵作家クラブ賞で対抗馬として候補になりながらも、本作に敗れたらしい『刺青殺人事件』の方が私にはずっと名作だと思われた。横溝正史の作としてなら「中の下」位のものではなかろうか? 文章は適度に砕けていて読みやすいが、なんとも臭みのある下品な(?)文体であるので、好みは分かれよう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者は戦後新文学の旗手にして太宰治と並ぶ無頼派を代表する作家のため、本書も文学的な作品のように思われがちであるが、さにあらずで「推理小説というものは推理をたのしむ小説で、芸術などと無縁である方がむしろ上質品だ。」との作者自身の理念に基づき、「謎解きゲーム」に徹したのが本書である。 本書の骨格は『ABC殺人事件』を基に(横溝正史は本書を「ABCの複数化」と評している)、さらにメイン・トリックもクリスティーの別の著名作品からアレンジしたものであるが、全体としては作者の理念に基づいた論理パズル・推理ゲーム的な作品で、クリスティーよりもむしろクイーン作品に近い。 確かに本書は論理こそ隅々まで通ってはいるが、例えば冒頭で一馬は加代子とのあれほどの熱愛ぶりを告白していたにも関わらず、その加代子が殺されたときやそれ以後も一度も嘆き悲しむわけでも犯人に対して怒りに打ち震える姿を見せるわけでもないなど、登場人物たちをゲームの駒として扱い人間を描いていない点、本書はロジック重視のファンだけが喜ぶ作品であって「小説」とは言えず(それもまた作者の理念に合致しているのだが)、読み物としての味わいや面白さを期待してはいけない。 本書は犯人当て懸賞小説として雑誌『日本小説』に連載されたもので、最終的に4名が犯人だけでなく犯行方法までほとんど完全に推理しているが、そのことをもって逆に作者は本書がそれだけ論理的・合理的であることを証明するものであると自負している。 だが、屋敷内やその周辺で連続殺人が起きながら、誰1人として次は自分が狙われるかも知れないなどと懸念する様子もなく、それぞれが1人で無警戒に出かけたりするのが果たして各人の行動として「合理的」と言えるのか。また、それに対して各人に護衛なり尾行なりをつけない警察の無警戒ぶりも不自然そのものである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者は戦後新文学の旗手にして太宰治と並ぶ無頼派を代表する作家のため、本書も文学的な作品のように思われがちであるが、さにあらずで「推理小説というものは推理をたのしむ小説で、芸術などと無縁である方がむしろ上質品だ。」との作者自身の理念に基づき、「謎解きゲーム」に徹したのが本書である。 本書の骨格は『ABC殺人事件』を基に(横溝正史は本書を「ABCの複数化」と評している)、さらにメイン・トリックもクリスティーの別の著名作品からアレンジしたものであるが、全体としては作者の理念に基づいた論理パズル・推理ゲーム的な作品で、クリスティーよりもむしろクイーン作品に近い。 確かに本書は論理こそ隅々まで通ってはいるが、例えば冒頭で一馬は加代子とのあれほどの熱愛ぶりを告白していたにも関わらず、その加代子が殺されたときやそれ以後も一度も嘆き悲しむわけでも犯人に対して怒りに打ち震える姿を見せるわけでもないなど、登場人物たちをゲームの駒として扱い人間を描いていない点、本書はロジック重視のファンだけが喜ぶ作品であって「小説」とは言えず(それもまた作者の理念に合致しているのだが)、読み物としての味わいや面白さを期待してはいけない。 本書は犯人当て懸賞小説として雑誌『日本小説』に連載されたもので、最終的に4名が犯人だけでなく犯行方法までほとんど完全に推理しているが、そのことをもって逆に作者は本書がそれだけ論理的・合理的であることを証明するものであると自負している。 だが、屋敷内やその周辺で連続殺人が起きながら、誰1人として次は自分が狙われるかも知れないなどと懸念する様子もなく、それぞれが1人で無警戒に出かけたりするのが果たして各人の行動として「合理的」と言えるのか。また、それに対して各人に護衛なり尾行なりをつけない警察の無警戒ぶりも不自然そのものである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 安吾ファンだけどこの作品はムリ。 作者が完結させた数少ない長編小説、という価値しか見出せない。 根本的にダメなのは、殺人事件が立て続けに起こる歌川家に客人らが留まり続ける理由が示されていない点である。 おめーら殺人事件に遭遇したら逃げろよ。 外部との交通手段を断たれた訳でもないのにさ。孤島でも吹雪の山荘でもないのにさ。 てか、日中外出して夜になると殺人犯のいる館に戻ってくるってのが意味不明なんだよ。 逃げろよ。留まる理由ねえだろ。明らかに留まる義理のない客も留まってるし。 作者は上記の点を考慮すべきであった。 そこは割かし安直な舞台設定でナントカなった気がするのだが……。 ちなみに私は角川文庫版で購入したのだが、本文庫では連載時に付いていた「読者への挑戦」が省略されているらしい。 この手紙は作者が読者を挑発して推理を煽るものだったらしい。至極残念。よく調べてから買うべきだった。 こちらには付いてくるらしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 登場人物が異様に多く、皆、奇人変人揃いで、殆ど全ての男女間に異性関係がある(あるいは、あった)ように設定されており、かなり不自然。しかし、その設定がなければ犯人のトリックが成立しない。あまりに個性的な人格をたくさん集めたため、逆に各キャラに個性がなく、誰が誰だか、フォローするのが大変。推理小説としては、あまり良い出来だとは思えないが、古典的な作品としての、骨董品的価値があるかも。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 登場人物が異様に多く、皆、奇人変人揃いで、殆ど全ての男女間に異性関係がある(あるいは、あった)ように設定されており、かなり不自然。しかし、その設定がなければ犯人のトリックが成立しない。あまりに個性的な人格をたくさん集めたため、逆に各キャラに個性がなく、誰が誰だか、フォローするのが大変。推理小説としては、あまり良い出来だとは思えないが、古典的な作品としての、骨董品的価値があるかも。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!