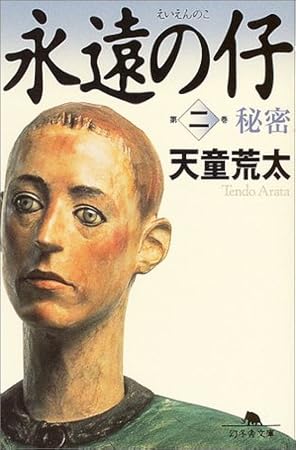■スポンサードリンク
永遠の仔
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
永遠の仔の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.56pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全146件 21~40 2/8ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あっという間に読み切ってしまった作品です。 それぞれが傷を抱え、大人になって再会した3人。 とても悲しいのですが、その悲しさのなかに希望も感じることができました。 生きていくことの意味を感じさせられる・・・そんな1冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (5)まで吸い込まれるように読み進めました。 私は仔の思いになり、どうして天童氏がこんなにも仔の思いの 洞察ができるのかが不思議なほど暖かく厳しい仔へのかかわりが感じられて 私にとって重くて強い印象をもった書籍になりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (5)は、いよいよという思いでページを開くのが楽しみでした。 最後の展開はさすがに自分には想像できていませんでした。 女である自分が女性の強さ、怖さに感動すらして印象深かった。 最近の一連の世の中の事件でも・・女性が強くしたたかであることは ある意味世の中のバランスとして必要なことなのではないかと 思えることもあります。 読み終わった後にも頭から離れないような内容も大作だったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 雪国の冬・・吸い込まれるように読みふけりました。 もっともっとと思い読みふけったのは久しぶりでした。 私はこの中の(仔)と同じような生い立ちをもっています。 天童さんがその子どもや親の人間がとてもことばでは 表せないような細部の心や行動がどうしてこんなにも 理解して表現してくれているのか・・ということに感動して読み終えました。 最終章の展開もとてもショッキングでした。 とにかく自分がこの本の中で子どもに戻って行動している そんな錯覚がありました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| うーん。いい文章だ。読みやすい!それが感想の一つだった。読みやすさ。さらりとして一気に読める。そしてヒロインの「過去」を最後にもっていくところなど。最後まで読者をひきつける。一晩で読んでしまおうという気になり、実際 一晩で読んでしまえた。ただ、現代の3つの殺人について(ネタバレだが)、その動機が弱い。殺しまで行くだろうか? 後にのこった2人は手を染めていないので、今からでも生きていけるが・・・ 殺しまで行くだけの幼児期の傷があったといえばあるだろうが。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本当に力作だ。しかもすらりと読める筆力には驚いた。しかし「すらりと読めすぎる」のだ。残るものがいまひとつない。最後の終わり方だろうか?現代の「殺人」の描き方だからだろうか? 読みやすい文章だ。かなり書きなれていると思う。だから一晩で読みきってしまえた。だが・・ この時代のこと「子供の虐待」が話題になるころの時代背景を思えば、ベストセラーにもなるだろうが 推理小説、ミステリーとなると、さて?こういう終わり方でいいのだろうか? やはりどこか「軽さ」を感じる。 ちなみにこの年の直木賞候補になったが「王妃の離婚」と「柔らかな頬」が受賞した。賞のことを言うのは辛いが この2作と比較したら「やはりまだ甘い」気がするのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| もう、かなり前ですが、なぜか、この本の単行本の表紙に惹かれて本屋で手に取り、そのまま購入し、一気に読みました。もの凄い衝撃を受けました。この本とは、運命的な出会い、と言っていい。この本を読んだことで、自分自身の姿、存在を、明確に理解することが出来ました。別に親に虐待されたわけじゃないけれど(むしろ逆)、自分と親の関係をいろいろ考え、理解することが出来ました。私は、4歳のころに母親の体調がすぐれなかったため祖母と祖父の家で育った経験があります。そのために少しわがままになってしまい、親元で暮らすようになっても、親との関係が今一つよくないと幼いながらに意識していました。反発するのでなく、逆に、親に気に入られるために、善行を積む、努力を積むという生き方を、潜在意識の元で選択せざるを得なかった。また相当歳を重ねるまで、無償の愛を疑うという、いやな性格を自覚せざるを得なかった。そういう自分自身の姿、その理由が、この本を読むことで、客観的に、ようやく理解できました。 この本を読んだ同じ時期、シロクマの赤ちゃんを飼育係の方が自宅で育てたドキュメンタリーのテレビを見ました。シロクマはある程度大きくなると、飼育係の家から出て檻の中で一人で暮さねばなりません。シロクマは、それがとてもつらく悲しい。早朝に動物園で、飼育係とシロクマが束の間の散歩を一緒にする。そのときにシロクマは、とてもうれしそうに(自分の親と慕っている)飼育係の後をついて歩き回る。その姿を見て、これは、僕の姿だと思い、涙が出て止まらなかった。この時、私は、ある意味、解脱、できたのでしょう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 親の虐待を受けながらも健気に生き抜いてきた子供たちにこんな悲しい結末が待っていたとは神も仏もないものか。。。。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 興味深い小説で、大作の深みを感じながら今最後の部分に到達しました。 自身が幼い時、虐待児であったこともあり、心や体にも直接響いて苦しいとも思いました。 作者が同様な経験がないにも関わらず書き上げられた作品だと添付の告知に 書かれていましたが・・どのようにこの気持ちと共感されたのか知りたいと感じました。 私には信じられない程に自分の心情と三人の思いが重なります。 小さな苦しさや悲しみが手に取るように解るのです。子どもの虐待という言葉が無かった時代に子どもとして当たり前の 生活をおくることができなかった悔しさ、私の気持ちを解ってもらうことは絶対に無理だったと思える両親(母は健在) 自分を大事にすることができない苦しみ。振り払っても消えてくれない親への思慕と憎しみの繰り返し。 私はもう初老になろうとしているのに・・それでも突然出てくる苦しさはきっと死ぬまで消えることはないと 諦め始める。うつ病に変化した体を薬で騙しながら「あんたの自由にしなさい」と音信が途絶えた母の言葉が頭を支配していきます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 児童虐待から生き抜く子供たちの物語。 実際にこんなつらい思いをしながら生きている人が いっぱいいるんだろうなと思いながら読みました。 自分を律することの出来ない親に限って 子供を律しようとするのだなと感じました。 子供は親が支配できる所有物ではないと思えた一冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容自体はとても重く、読んでいても感情が揺さぶられることが多かった。 なんとも、胸を締め付けられるものだったが、不思議と読後感としては、底から力が湧いてきた。 感情が揺さぶられた分、自分も人生と向き合わないとな、と思えたし、今の自分の辛い状況にも重なり、何とかしていかなければと勇気をもらった。心が締め付けられた分、大きな力が湧いてきた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文庫5冊の長い物語が終わった。 結末については、単純に考えるなら、この最終巻の展開だけでもいろんな選択肢があっただろうと思う。 最後まで、ある種の意外性も残されているが、 しかし実際に書かれたものを読むと、最終的な処理には、何か重い必然のようなものが感じられる。 それは最初から決まっていたもので、この作家のこの作品にはこれしかなかったのだろうと思われるものだ。 それをどう受け止めるかは、ひとりひとり読者の問題なのだろう。 巻末の「報告」や、長いあとがきを見ても、天童荒太がいかに倫理的な作家かというのはわかる。 参考資料の多さは、真面目な作家であるというだけでなく、 こうした重い問題と、人生の長い時間をかけて付き合って生きていける資質を示すものだろう。 そのスタンスは、なかなか一般の読者には辛いものでもある。 それでも、 自分には重すぎるそれをこの作家がやってくれるからこそ、 彼の作品を読むということもあるのだと思う。 辛く、重苦しいと同時に、頭と心の両方でスリリングで、味わい深い読書体験でもあった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この巻では、並行して描かれる現在と過去とでそれぞれ大きな進展がある。 この、何か起こりそうでいて実際にははっきり示されない、 示されないような流れでいて、事件が描かれる、 という出し入れのさじ加減がなかなか巧みだ。 展開は私が予想したよりも重いものだった。 たまたま前の巻から間を開けて読んで、 この作家の文章のしっかりしていることや、行間から窺える倫理観のようなものが好ましく感じられて、 妙に安心してしまっていたせいもあるだろう。 相当な破局のような悲劇のようなものがあるのは、暗示にせよかなりはっきりしているから、 いよいよその段階に入りつつあるのだな、と、あらためて読む側として、 ある種の覚悟のようなものを覚えた巻だった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 副題は希望を抱かせるもののようにも見えるが、実はアイロニカルなものである。 しかし、そうは言っても、救いの芽のような暗示は、ここに来て表に出てもいる思う。 この巻、いよいよ激しい展開が見られる中で、悲劇は起こる。 破局に向けた流れと感じられるのは間違いないと思う。 一方ではしかし、救いを思わせる描写、場面が、これまでになく出ているのも確かだ。 主人公三人は、深い傷を負ってはいる。しかし、いや、それゆえにこそ、 彼らは一方では、三人ともまっとうで倫理的でもあるように見える。 ふつうにいい人になりたくてもがいているように見えるのだ。 だからこそ彼らに救いが訪れて欲しいと願う読者は少なくないはずだが、 それは期待しがたいものなのだろうか。 たとえば、叔父夫婦を呼んで歓待しようとする梁平が珍しくもらす真実の言葉は感動的だ。 だが、その後には希望を一気に奪うような展開が待ち受ける。 こうして次の最終巻に向けて、物語は希望と絶望とのはちきれそうな暗示の嵐をはらんで、 予断を許さぬままに突き進む。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 長い小説だからこの文庫版では5冊になったが、シリーズものというわけではない。 だからレビューも一通り読み終えてからと思っていたが、ムズムズして書きたくなった。 そういうものがたぶん物語自体にあるのだ。 並ではない小説だというのを理解するまでさほど時間はかからない。 話は、重く、濃く、激しい。 だから好みは相当分かれるだろうという気がする。 夢中になって読み続ける読者もあれば、激しく拒絶反応を示す読者もありそうだ。 私自身まだ読んでいる途中だから、最終的な印象は結末までたどり着かないとわからないが、 まず間違いなく言えることが一つある。 この天童荒太という作家は、本物の作家だということだ。 たとえ結末の処理に納得できないとしても、それはおそらくスタンスの問題であって、 作家の能力に失望するとかそういうことはないと確信できる。 題が示すように「仔」、子供が大きなテーマである。 直接には、簡単に言ってしまえば、主に「虐待」の問題がある。 だがそこに重層的に、もっと広く家庭の問題、家族の軋轢や家庭の崩壊の問題が絡む。 重いわけだ。 この作家はどうやら一貫してこういうものを書いているらしい。 いわばミステリー版の『罪と罰』を問い続けている。 話はしかし、重くてもドロドロしてはいない。 重さを単純にドロドロという言い方をしてしまうことはあるだろうが、 厳密に言えばちょっと違うだろう、という気がする。 そこには何かしら、ドロドロになるまいとする作者の清潔さ、倫理性のようなものを感じる。 たぶんそれは、この作家に本質的なものだ。 一般に、現代の日本のミステリーに、 心の問題とか社会的な問題を真摯に扱おうとする流れがあると常々感じていて、 この作品、作家もその一端を成すのだろうが、 ちょっと半端なものではないと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まず設定がいい。 かつてそれぞれに心の問題を抱え、同じ病院で絆を結んだ少年二人と少女一人が 20年近くを経て再会する。 過去に何かしら決定的なことがあったらしいとわかる。 現代においても、再会の後に大きな展開がある。 それを20年の時間を往復しながら交互に描く。 物語のアクションが徐々に大きくなる展開で 1巻目はこちらにもどの程度の物語なのかと警戒心があったし、話自体が緩やかだったのが ここへ来て俄然動きが激しくなり、一気に読める。 それでいてしかし、ある意味では何も起こっていないのだ。 何かが起こっているらしいことは分かっているが、それが表面化していない、という意味である。 これがまたすごい。 水面下のものがいずれ一気に吹き出して爆発するのは間違いない。 じれったいというのではないが、すごく気になるし、今後が楽しみだ。 ストーリーを考えるのに、作家のアイデアはもちろん自由なはずで、 ロールプレイングゲームの選択肢のようにいろんな展開がありえるはずなのだが、 実際の読むことになるのは、これしかありえない、というものだ。 抗いがたい必然としての物語展開の迫力。 この一つの宿命が不可避であることを痛切に感じさせるリアルさ。 ストーリー展開もそうだが、何よりも描かれる人間がいかにも生きていて 鷲掴みにされたまま目を背けることができない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 値段も商品も良かったし 読んで深い感銘を受けました。 また良い本があれば利用したいと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 値段も商品も丁寧なサ-ビスにも十分、満足出来ました。 また、利用したいですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 単なるエンターテイメントや推理小説としてだけではなく、現実社会の問題へ目を向けるきっかけとして、詠まれてほしいと思います。 ここからたとえば、虐待・非行・発達障害 困難を抱える子どもへの理解と対応―土井ファミリーホームの実践の記録などの本があります。 ほかにも類書がたくさんあると思いますので、探してみてください。 また、愛着障害と修復的愛着療法―児童虐待への対応などもあります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 単なるエンターテイメントや推理小説としてだけではなく、現実社会の問題へ目を向けるきっかけとして、詠まれてほしいと思います。 ここからたとえば、虐待・非行・発達障害 困難を抱える子どもへの理解と対応―土井ファミリーホームの実践の記録などの本があります。 ほかにも類書がたくさんあると思いますので、探してみてください。 また、愛着障害と修復的愛着療法―児童虐待への対応などもあります。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!