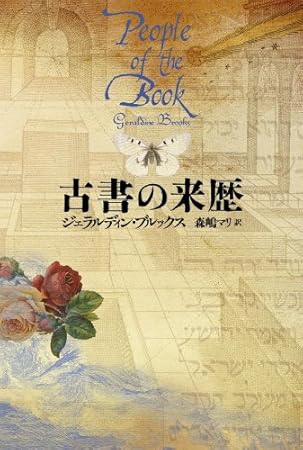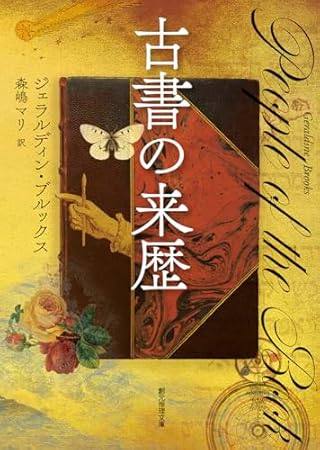■スポンサードリンク
古書の来歴
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
古書の来歴の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.44pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全21件 1~20 1/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 時々再読している木田元著『哲学散歩』のなかに「悠久の旅」という章がある。 本書『古書の来歴』に興味を持ったのは、先の『哲学散歩』のなかで「古代ギリシャで書かれたものが、時間的だけでなく、空間的にだって、ギリシャ、アラビア、中央アジア、北アフリカ北岸をぐるっとまわり、ジブラルタル海峡を渡ってスペインへ、そしてピレネー山脈を越えたり、シチリア島を経由したりして西欧世界へ運ばれてきたのである。」(同書P81)と、書いていたことに拠る。 イベリア半島は、八世紀初頭以来イスラム教徒の支配下にあったが、イスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒が穏やかに共生することができる寛容の文化圏が形成されていた。 十世紀ごろからキリスト教徒の騎士たちによりレコンキスタが遂行されたが、十二世紀になるとイスラム教徒もキリスト教徒もユダヤ教徒もお互い寛容であり古書の研究や翻訳、写本などで協力しあっていていたのである。 本書のテーマである「サラエボ・ハガダー」とは、出エジプト記を記念する過越の日のための物語と祈りの言葉が記されている中世の細密画が描かれたヘブライ語の本である。 この本が出来たのは、最後のレコンキスタ(1492年)頃のイベリア半島のグラナダ辺りと本書では設定されている。 その後この本が500年ほど辿り、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中行方不明としてあったこの本を、博物館から学芸員が危険を顧みず持ち出して銀行の金庫に隠した。 研究者仲間のイスラエル人から電話で連絡があり、主人公ハンナがこの「サラエボ・ハガダー」の鑑定と修復を政治的人選で依頼され、戦火収束間もないサラエボへ行き銀行金庫の部屋で一週間で修復することになる。 本のページの中で見つけた「蝶の羽」「ワインの染み」「海水」「白い毛」の微細な欠片をグラシン紙の小袋に収めて後に知人の専門家に調べてもらう。 「蝶の羽」「ワインの染み」「海水」「白い毛」が何故この「サラエボ・ハガダー」に付着していたのかなどを次の章で時を遡って物語を紡いでいく。 ユダヤ教で禁じられている豪華な細密画を描くなどを想像豊に物語を紡いでゆく。 ハンナの時と「サラエボ・ハガダー」の時を、何世紀も行ったり来たりしながら、だれがこの細密画を描いたのか、だれが文字を書いたのか、ハンナと母親との確執などを、読者の予想もできないストーリー展開する著者のフィクションながら創作の冴えに脱帽しながら「サラエボ・ハガダー」の悠久の旅を楽しく読み終えました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いくつもの時代を行きつ戻りつ、謎が少しづつ解かれていくパズルのような読み物。歴史と宗教、古書や装飾などに明るければ越したことないけど、何度かクグリながら、私でも何とかついていける、不思議にエンタメ性のある物語でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「・・・理想の街サラエボでは紛争など起きるはずがなかった・・・戦うはずが無いと思っていた。でも、紛争がはじまって最初の数日のぼくたちの行動はちょっと浮ついていた。十代の若者がピクニック気分でプラカードを持って反戦デモを行った。十人くらいの若者が狙撃手に撃たれても、ぼくたちはまだその意味をきちんと理解していなかった。国際社会がとめてくれると思ってたんだ。・・・ほんの何日か我慢していれば片がつくと思ってた。そうだな・・・世界が一致団結して助けてくれるって」 緻密な調査に基づいて書かれているので、↑のような会話からハガターの謎の推理、その他リアルで、これどこからどこまでがフィクションなの?って何度も宗教や土地について調べながら読みました。 (あとがきを読めばこれは解決することでしたが。やはり先に読まないほうがおすすめ) 色々、現在のZの国の侵略と重なる部分もあって相当読み応えありました。 ただ、ゆったりと時代を遡って、どうしてこのハガターが作られたのかという謎に迫っていくのでミステリーなのは確かですが、ダ・ヴィンチ・コードのようなスピード感とスリルあふれるタイプを期待すると物足りないかもしれません。 より現実的な歴史ミステリーは明らかにこちらです(笑) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| もうめちゃくちゃ面白い | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重厚な内容に圧倒されました。 徹夜して一気に読んでしまうというより、内容をよく理解しながらていねいに読みたくなる本で、歴史的な出来事や人名を確認したりしながら1週間もかけてちびちび読みました。 最初は、章が変わって突然始まる脈絡のない昔の物語に??となりましたが、それらは、本に残されたそれぞれの小さな痕跡の由来を語るものでした。 この部分を読みながら我々は、検証して推理するしかない主人公よりも古書を巡る正確な事実を知ることになります。それぞれのエピソードは、古い廃墟の3Dの復元ビデオを見ているようで、古書に関わった人々の姿が生き生きと蘇ります。時代がどんどん遡って古書の誕生に近づいていくのもいくのもすごく上手いところだと思います。 宗教に関係なく、美しいものを作りたい、守りたい、というたくさんの人の思いが重なって今も存在するこのサラエボ・ハガダーは、こういう時代にあって希望の象徴のようだと感じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 値段と質のバランスに満足しています。機会があればお店にも行ってみたいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本好き、歴史好きには、たまらないでしょう。 ミステリー的な面白さ以外も沢山。 楽しかった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| サラエボ・ハガターという古書をめぐるおはなし。 古書鑑定家のハンナが見つけた品々をしらべながら、 それぞれの物語を、時代をさかのぼりながら、進む。 ハンナの現在の話と交互に進む。 そこが、感情移入しやすい。 ものすごく長い年月のことが語られ、 一冊の本が多くの歴史を持っていることが貴重だと語られる。 時代、時代の辛い歴史の中で生きた人々、 そしてその中をくぐりぬけてきたこの書。 たしかにすごい。 でも、どんな運命のどんな人物でも、そこに毎日があったこと。 そこで精一杯生きたんだということを強く感じた。 古書をめぐる話だが、そんな人々を見てきた本の物語のような気がした。 読み終えてから、少し時間がたった時、そんな印象をもってこの作品を思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いかにも映画になりそうな構成。 実在する物に想像を加えるとこれだけのファンタジーを作ることができるのだ。 でも、邦訳はどうなのだろう。 もっと素敵な題名はあるはず。 もう少し突っ込んだ内容ならば、わくわくする場面は多かったな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ハガダーとは、ヘブライ語で書かれたユダヤ教の祈りや詩篇の書である。「サラエボ・ハガダー」とは19世紀にサラエボで見つかった、中世のスペインで作られた、実在する写本である。注目すべきはその本が、ユダヤ教があらゆる宗教画を禁じていた時代に書かれたにもかかわらず、キリスト教の写本に見られるような挿絵がふんだんに使われていたということである。 本書は、そのハガダーにまつわる数々の謎を、古書鑑定家のハンナが鑑定を通して解明していくという、実物をもとに作られたフィクションである。 ストーリーの面白さもさることながら、「書物」が大量生産、消耗品ではなかった時代に、いかに歴史の一翼を担い、象徴するものであったかということに気付かされる。 歴史の中で、膨大な数のの書物が禁書となり、あるいは災害などで燃やされ、失われてきた。現代私たちが触れることのできるものは、長い時間の中で、奇跡的に生き延びてきたほんの一部なのだと痛感する。 本書に登場する、中世の写本工房の親方の、こんな言葉がある。 写本製作に関ってきた多くの名も無き画家や書家たちの思いがここにある。 「ここで私たちが創っているものは、ここにいる人間の誰よりも長く世に残る。それを忘れるんじゃないぞ。どんな・・・個人的な感情より、それがはるかに重要なのだから」 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読みながら、まるでその場にいるかのような錯覚に陥りました。 現代と過去が交互に語られ15世紀にまでさかのぼるというのに、時代が古くなればなるほど目の前に鮮やかに情景が浮かんできて、ディテールの細やかさ、歴史的裏付けは圧倒的です。 ローラやイナ、ルティは読後まるで実在の人物のように心に残りました。 宗教や歴史について関連した本を読み、知識を増やして再度読みたいと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 古書鑑定家のハンナは、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争後の政情が不安定なサラエボを訪れた。訪れた理由は、稀覯本のサラエボ・ハガダーの鑑定と修復を、国連から依頼されたからだ。 ハガダーはユダヤの春の祝い事、過越(すぎこ)しの祭の聖餐で使われる書物である。祭の次第や出エジプトの物語などが書かれている。ユダヤ教徒にとって、ユダヤの教えを親から子供に伝えるために不可欠な本である。 サラエボ・ハガダーには蝶の羽が挟まっていて、ワイン染みが付いていた。塩と思われる結晶物が見つかり、絵の具には動物の毛が付着していた。これらについての科学的な鑑定が行われ、古書の来歴が明かされていく。 本書は、500年前にスペインで作られ120年前に困窮したユダヤ人にから売りに出された実在の古書に着想を得たフィクションである。 史実と著者のアイデアが巧みに絡み合わされて、古書のたどった数奇な運命と古書に関わった人々の苦悩が見事に描かれている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 図書館からもう一回読み直そうと再び借り出してきたのは、ジェラルディン・ブルックスの「古書の来歴」。キリスト教とイスラム教の狭間に揺れる時代。見つかれば焼き捨てられても不思議ではなかった中世から数百年を経て近代、そして現代にまで至り、民族紛争に燻る戦火のサラエボの博物館に奇跡的に発見されたユダヤの古書。人から人へと渡り保たれてきたこの本のページに、今はもうこの世にはいない幾人もの人々の人生が痕跡を残していく。時を違え、知り合うこともなかった人たちが一冊の本によってこんなふうに繋がれているという不思議。その繋がりをさながらCSIの科学捜査のように辿り推理し解析していく面白さは今まで味わったことのないものでした。芸術品ともいえる貴重な古書が中心に置かれた物語であるゆえに、この本そのものの装丁も、時代の移り変わりを感じさせる大変美しいものとなっています。ちょっと値がはる一冊ですが・・・お薦めですよ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書で扱われている『サラエボ・ハガター』は実在の書。 ユダヤ教の写本である。 500年前に作られたこの絵入りのきれいなユダヤ教徒の本を サラエボの戦禍から命がけで守ったのはイスラム教徒の学芸員だった。 もうそれだけでこのミステリが読みたくなる。 原題は「People of the Book」。the Bookとくれば通常、聖書であるが ここではもちろん、それだけを指すのではなく「すべての魂を持った書物」 といった意味であろう。 ハイネからの前書き 「書物が焼かれるところでは最後に人も焼かれる」 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| たった一冊の古書が、何人ものユダヤ教徒とその周囲の人々の物語を秘めていた。 いやー、こんなにおもしろく、できのいい小説はひさびさ。 翻訳家の選んだ大賞の候補にあがっていたので、読んでみた。 さすが幅広い読書と翻訳の実績を持つ人が選ぶだけあって、質が高く、しかも、おもしろかった。 緻密に書かれた小説で、しかも読みやすい。候補にあげられたのも納得。 ほんとの主人公は実在するサラエボ・ハガダ―(ハッガ―ダー)。 Sarajevo Haggadah。[...] この古書を修復するためにやってきたオーストラリア人の女性研究者、ハンナが狂言まわし、というべきか。 ハンナの視線で超お宝の古書の修復を通じ、15世紀から現代までのユダヤの歴史が体感できる。 ハガダ―の修復で、彼女の発見した、ごくごく小さな5つの「種」から、ユダヤ教徒のたどってきた歴史が語られる。 気のきいた物語の構造。真相が、別立ての連作短編のようなスタイルで語られる。しかも、読者にだけ打ち明けられる。 内容的には歴史あり、政治史ありで、不器用な書き手だと昼寝の枕になってしまうところだけど、 賢くセンスのいい著者は、やっかいな史実を整然と整理し、わかりやすいお話に展開、とても頭に入りやすい。 そこへ、さらにハンナの人生の秘密や恋愛をからませ、エンターテインメント性を増強。 えっ、どうなるんだろう、という感じでどんどんひっぱられ、ラストまで退屈しなかった。 最後はばたばたっと終わり、あらっと思ったけど、まあ、この小説に関してはどちらでもいいと思える。 物は、人間の何倍も生きる。その物語が単純であるわけがない。 余計なひとこと: 「古書の来歴」、ちょっと無骨な、近年珍しく愛想のないタイトルだけど、いい。 原題はPeople of the Book。 訳しにくかったんだろうなあと思う。 売るためのキャッチ―なタイトルじゃなく、小説の中身を伝えようという思いが伝わってきて、私は好きです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 歴史の転換の年1492年のスペイン、17世紀のイタリア、19世紀 のウィーンそして20世紀のボスニアなどと時代と場所を超えて展開する 祈祷書ハガターにまつわる物語.損傷や改造を受けつつも奇跡的に守られ てきた痕跡をたどって古書鑑定家が科学捜査を進めていく.実在の本や史 実を交えたフィクションであるせいかリアリティがあるストーリ展開を楽 しめる. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| こういうテーマが好きなので★がアップしました。 「サラエボ・ハガダー」と聞いて、ピンとくる方は、興味のある方かな?私は、全く、分からなかったが、古書という言葉の響きから、何かとてつもない重みのあるものかと想像した。 宗教感は日本人にはわかりにくい。というか宗教に対して、私が無知なのか?寛容なのか?わからないが、世界では宗教の違いで、残念ながら、戦いは当たり前にさえなっている。 かつてのサラエボには、ネオ・ゴシック様式の大聖堂があり、シナゴーグやモスクが並んでいる。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教が混在している街を中心とした物語で、500年前に作られた「サラエボ・ハガダー」を古書保存修復家のハンナが、1996年のサラエボを舞台を出発として、修復をするというストリーの中、読者は別の世界に誘われていく。 それが、古書の来歴を追う物語の始まりである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 原題People of the Book「啓典の民」。世界史教科書的意味合いでは、比較的寛容な待遇を受けていたとされるイスラーム支配下のユダヤ教徒・キリスト教徒を指す。特に、イスラーム・スペインにおいては、ユダヤ教徒・キリスト教徒・ムスリム達が比較的平和裏に共生しながらイスラーム文化黄金期を築いた、とされる。本書は、そのような文化史的経緯を前提としながらも、「共生・共存は、決して生ぬるいものではないこと」「歴史とは、宗派対立・民族対立と言った、個人的には抗うことが難しい大きなうねりの中にあっても、それでもなお、そこに息する個人によって生きられるものだ」ということを指し示しているように思われる。そこには、9/11以降強調されることの多い「○と●の対立」という構図の中で、私たち個人一人一人が、どう生きていくのか、を考える上でのヒントも含まれているように思われる。また、本書を読んで聖典を巡る3宗教間の相互理解というテーマに興味を持たれた方は、ちょっと学術的ですが「ハガルとサラ、その子どもたち ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の対話への道」もお薦めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 冒頭の献辞は 「すべての学芸員に捧げる」とあり、ページをめくる指に力が入ります。原題にある「the Book」と言うのは文字通りの「the Book」と解釈すれば「聖書」のこと。作品中で取り上げられているのは「サラエボ・ハガダー」という本で、ユダヤ教徒にとって非常に重要な「過越し祭」の正餐 の際に使う、「出エジプト記」や「式次第」を書いた本らしく広義の「聖書」ということか?物語は女流古書 鑑定家ハンナが政情不安定なサラエボに降り立ち、世紀の稀覯本サラエボ・ハガダーと出会う場面から始まります。科学的な手法を駆使して鑑定を進める内に判明した様々な 「謎」、その真相を探り、解き明かされた過去の事実からサラエボ・ハガダーを造り護ってきた過去の人々の切実な「物語」が紡ぎ出されていく・・・。7 編の現代におけるハンナの日々、そしてその間に6編の「物語」が挿入されていきます。サラエボ・ハガダーにまつわる19世紀末以降の記述 は、大まかな点については事実らしいが、それ以前についてはフィクションのようです。エキゾチックとも思える過去の世界の描写と、宗教対立による悲劇の描写が交互に描かれていき、知らず知らずの内にユダヤの民の歴史を学ぶことにもなって興味深く読み進められます。また、ハ ガダーを巡る人々の欲望や無私の行為、過去から延々と続くユダヤ人の悲劇などかなり硬派な部分と、父親を知らず、仕事一筋の母親を嫌うハンナの私生活や恋の 行方も描かれていき、結末では暖かな「家族」の「発見」や「再生」も描かれて穏やかに終わります。本にまつわる謎を解くという内容なので「歴史ミステリ」と言うにはちょっと物足りない面もありますが、サラエ ボ・ハガダーを、単なる高価な稀覯本ではなくユダヤ民族の拠り所と思う人々が、虚々実々の駆け引きの末に命懸けで護り通したという過去の「事実」を描いた内容は、単なる「小説」を超えた意義をこの本に与えていると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これは、若いオーストラリア人古書鑑定家の話です。ある日、彼女は「サラエボ・ハガター」と呼ばれる古書の鑑定を依頼され、この本が保存されている博物館へ向かいます。鑑定するにしたがってこの古書が辿った世界が、関わった人々の物語が浮かび上がって来ます。それと同時に鑑定家自身の数奇な運命も明らかにされていきます。 実在する本の謎解きに挑んだ意欲的な作品です。今まで読んだ歴史ミステリーの中で異彩を放っています。ワクワク・ドキドキの連続で一気に読んでしまいました。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!