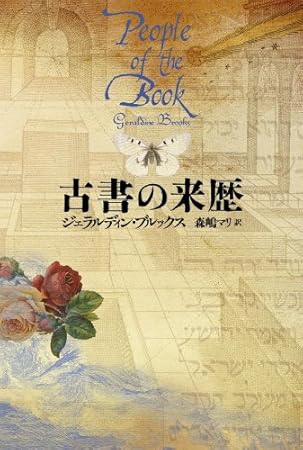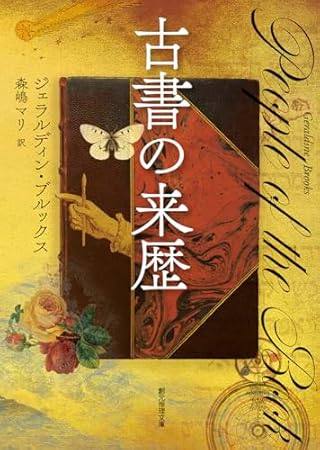■スポンサードリンク
古書の来歴
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
古書の来歴の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.44pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全25件 21~25 2/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 原題People of the Book「啓典の民」。世界史教科書的意味合いでは、比較的寛容な待遇を受けていたとされるイスラーム支配下のユダヤ教徒・キリスト教徒を指す。特に、イスラーム・スペインにおいては、ユダヤ教徒・キリスト教徒・ムスリム達が比較的平和裏に共生しながらイスラーム文化黄金期を築いた、とされる。本書は、そのような文化史的経緯を前提としながらも、「共生・共存は、決して生ぬるいものではないこと」「歴史とは、宗派対立・民族対立と言った、個人的には抗うことが難しい大きなうねりの中にあっても、それでもなお、そこに息する個人によって生きられるものだ」ということを指し示しているように思われる。そこには、9/11以降強調されることの多い「○と●の対立」という構図の中で、私たち個人一人一人が、どう生きていくのか、を考える上でのヒントも含まれているように思われる。また、本書を読んで聖典を巡る3宗教間の相互理解というテーマに興味を持たれた方は、ちょっと学術的ですが「ハガルとサラ、その子どもたち ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の対話への道」もお薦めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 冒頭の献辞は 「すべての学芸員に捧げる」とあり、ページをめくる指に力が入ります。原題にある「the Book」と言うのは文字通りの「the Book」と解釈すれば「聖書」のこと。作品中で取り上げられているのは「サラエボ・ハガダー」という本で、ユダヤ教徒にとって非常に重要な「過越し祭」の正餐 の際に使う、「出エジプト記」や「式次第」を書いた本らしく広義の「聖書」ということか?物語は女流古書 鑑定家ハンナが政情不安定なサラエボに降り立ち、世紀の稀覯本サラエボ・ハガダーと出会う場面から始まります。科学的な手法を駆使して鑑定を進める内に判明した様々な 「謎」、その真相を探り、解き明かされた過去の事実からサラエボ・ハガダーを造り護ってきた過去の人々の切実な「物語」が紡ぎ出されていく・・・。7 編の現代におけるハンナの日々、そしてその間に6編の「物語」が挿入されていきます。サラエボ・ハガダーにまつわる19世紀末以降の記述 は、大まかな点については事実らしいが、それ以前についてはフィクションのようです。エキゾチックとも思える過去の世界の描写と、宗教対立による悲劇の描写が交互に描かれていき、知らず知らずの内にユダヤの民の歴史を学ぶことにもなって興味深く読み進められます。また、ハ ガダーを巡る人々の欲望や無私の行為、過去から延々と続くユダヤ人の悲劇などかなり硬派な部分と、父親を知らず、仕事一筋の母親を嫌うハンナの私生活や恋の 行方も描かれていき、結末では暖かな「家族」の「発見」や「再生」も描かれて穏やかに終わります。本にまつわる謎を解くという内容なので「歴史ミステリ」と言うにはちょっと物足りない面もありますが、サラエ ボ・ハガダーを、単なる高価な稀覯本ではなくユダヤ民族の拠り所と思う人々が、虚々実々の駆け引きの末に命懸けで護り通したという過去の「事実」を描いた内容は、単なる「小説」を超えた意義をこの本に与えていると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これは、若いオーストラリア人古書鑑定家の話です。ある日、彼女は「サラエボ・ハガター」と呼ばれる古書の鑑定を依頼され、この本が保存されている博物館へ向かいます。鑑定するにしたがってこの古書が辿った世界が、関わった人々の物語が浮かび上がって来ます。それと同時に鑑定家自身の数奇な運命も明らかにされていきます。 実在する本の謎解きに挑んだ意欲的な作品です。今まで読んだ歴史ミステリーの中で異彩を放っています。ワクワク・ドキドキの連続で一気に読んでしまいました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| なんとなく敬遠していた翻訳モノ、久々に読みましたがこれは面白かった。「完璧な世界観」のファンタジーより虚実とりまぜての歴史ミステリーが好きな方、お勧めです。 戦争、ナチスの脅威、異端審問、などの困難を乗り越えて500年以上も存在する本、それにかかわった人々のお話です。最終的にはサラエボ・ハガダーが作られた時代までさかのぼります。本文に「最後はハッピーエンドと思ったらおおまちがい」とありますが、だからこそ心に残るものもあります。フィクションとは知りつつも、ローラやステラ、ザーラのこの先(書かれていない部分の人生)がせめて穏やかなものであってほしいと思いつつ、本を閉じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ちょっと予想していた内容とは違ったんだけど、ヒストリカル・ミステリとして十二分に楽しめた。 修復の過程でハンナが見つけた謎。蝶の羽、今はない留め金の痕跡、ワインの浸み、塩の結晶、白い毛……古書は500年もの間、どのような旅をしてきたのか? そして、ハガダーとしては珍しい細密画を描かれた理由は? 無論、ハンナはそのサンプルから推測と想像しかできない。しかし、我らはその旅を遡ることが出来る。 そこに現れるのは、ユダヤ迫害の歴史、命を賭けて本を守ろうとする精神、帰属する場所の発見…… 戦火・破壊に追われながらも、運と人々の献身によって現代まで生き延びた一冊の書物。それを通じて、500年の時を隔てた二人の女性が自分の居場所を見つけ、邂逅する一瞬は感動的。 ここに出てくるサラエボ・ハガダーは実在していて、ネットでその画像を見ながら読むのも楽しい。 また『古書修復の愉しみ』『西洋製本図鑑』あたりを副読本とすると何をやっているのかイメージしやすいかも。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!