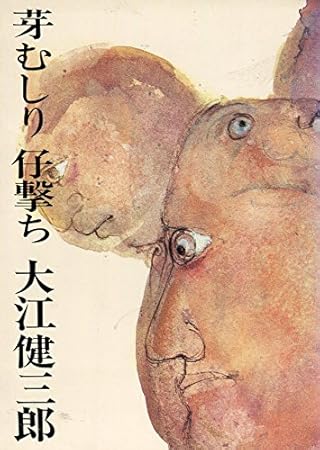■スポンサードリンク
芽むしり仔撃ち
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
芽むしり仔撃ちの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.28pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全40件 21~40 2/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 差別、憎悪の渦巻く崩壊寸前の共同体を複合的な視点で捉えつつ、緻密な情景描写と切迫した感情の叙述とで描く、珠玉の長編。 これは凄まじい。『蝿の王』に匹敵する壮絶な読書体験になるでしょう、、、。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 戦争末期,感化院の少年たちが山村へ疎開することになった。厳寒の中、ひもじく苦しい道中が続く。 村人たちの視線は冷たく、ほとんど人間扱いされない。 朝鮮人の少年や疎開してきた少女とつかの間の友情が芽生えるが、残酷な現実に踏みつぶされる。 弱い立場の人間が徹底的に疎外され、痛めつけられる。何の救いもない。 主人公が最後まで誇り高く振舞うのが救いと言えなくもないが、なんと無力で悲しいプライドであることか。 本作は特定の時代を批判しているのではなく、普遍的な村落共同体のありようを容赦なく描いているのだ。 田舎が牧歌的なんて、大ウソだ。 互いの協力が不可欠な貧しい閉鎖社会は、余所者や脱落者に対して徹底的に残酷になる。 日本型ムラ社会、というよりは人間社会そのものの凶悪さが身に沁みる。 嫌な話なのだけど、こういう嫌さは誰かが書くべきだ。 文章の迫力は、今どきのエンタメの比ではない。文学の威力を思い知らされた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| かの大江健三郎先生による、闇の歴史の大暴露が繰り広げられた作品です。なぜ迫害されても少年たちは強く生き続けねばならなかったのか?貧しさと飢えで苦しむ非行少年が綴る、大人の過ちを糾弾した直訴状。もっと読まれるべきです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 物語の中盤が・・・。あまりおもしろく無く興味を失いかけたがなんとか読めた。自選短編が、大変よかっただけに残念な気がする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 戦争小説として読むと、状況設定のおかしさが気になるところではある。ただ、この小説の本質はそんなものではなく、社会から除け者にされた人間たちが生み出した連帯と崩壊の中に何を見いだすのかが大切なのだと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 激流のごとし流れで文章が体を通り過ぎ、先へ先へと進みたくなるような文章。 細かな表現描写が読者を現実から読書の世界へと引きずり込む。 と、読んでいる間、そんな印象が絶えず付きまといました。 読んでいてもっとも心震えたのは、戦時中に朝鮮人がどんな扱いだったのか、 そして主人公と心通わせる中でいかに人間らしいと思えたか、そして 村人と言うなの大人たちがいかに冷酷で、それは結局国境を越えて 日本人にさえもどれほどひどく当たったかを痛切に感じさせる内容でした。 戦争が起きれば人はいかに冷酷になれるか、それがわかるとともに、読んでいて二度とこんなことが起きてほしくない、今の日本人らしい人にやさしい日本人のままでいてほしいと願う本です。 またいろいろな因果関係についても考えてもらいたいですし、周囲の人間の作りこみも素晴らしいので、そこらへんも考えてもらえたら、本書の奥深さをより味わえるのではないかと。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大江健三郎の「芽むしり仔撃ち」を読んだ。 物語に引きつけられどんどん読み進んだ。雪が降った山で鳥を捕らえてお祭りをする場面は最高潮だった。そして一挙にラストへ続く。 読了後まず感じたのは「なんとも救いのない暗い物語だ」ということ。ラストシーンの主人公は絶体絶命に思われるのだ。 しかし他の人のレビューも読み、つらつら考えてみると主人公の『僕』と現在の我々が重なってきた。ひとごとではなかったのだ。同時に『僕』は著者でもあり、大江はその後長年にわたって自分の尊厳を貫いて信じることを書き続けてきたのだ。そういえばラストシーンの主人公は、逃げ回るだけではなく、戦うために凍えたこぶしに石をつかんでいたのだった。 もうひとつ感じたのは「蝿の王」に似ているということ。とくに捕らえた鳥を焼いて食べる場面は、豚を捕まえて食べる場面を思わせる。そもそも少年たちが閉じられた空間で「子どもの王国」を作り出すというのが共通している。ネットで検索したところ、このことは既に指摘されていた。もちろん単なる模倣に終わっているわけではない。 痛みや臭いや寒さなど、大いに五感を刺激される物語だった。扱っているテーマは多岐にわたる。子ども、大人、秩序、欺瞞、無責任、大人の都合、非情、暴力、差別、性、社会、エゴイズム、森、戦争など。物語としての完成度が高いと思う。残酷な表現には好みがあるだろうが、再読していろいろと楽しみたいと考えている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大江健三郎のこの小説を読んだ。筋は完璧に忘れていた。ただ、冒頭の「夜更けに仲間の少年が脱走したので、夜明けになっても僕らは出発しなかった。」だけは覚えていた。当時、小説の記憶を暗唱することをしていたからだ。 話は戦争末期、感化院の15人の少年が山奥の陸の孤島とでもいうという村に疎開するが、疫病が流行するとの判断で村人たちが少年たちを置き去りして村を脱出。取り残された少年たちは、村人の家、村長の土蔵などに侵入して食糧などを盗み、したい放題の生活をする。いわば、感化院の少年たちがひとときこの村を占領し、王国をうちたてる。王国では、主人公の「僕」の他に、感化院にいたわけではないが疎開のおりに父親に連れられて疎開にくわわった弟、南というかつての感化院脱走経験者、李という朝鮮人、疎開者の娘たちが登場し、暴力沙汰をおこしたり、愛がうまれたり、小鳥などの捕獲をし、祭りをもったりする。しかし、娘が疫病で倒れ、それを伝染させた犬(弟がかわいがっていた)が撲殺されたり、暗雲が襲ってくる。ついに村人たちが帰村し、子どもたちは窃盗などの罪で糾弾され、王国は崩壊する。子どもたちは懐柔され、主人公の「僕」だけが村からの脱走を試みる。 山村の強制された監禁状態のなかでの、自由の空間、そこでの連帯と愛。そのいく付く先の死、裏切り、連帯の瓦解。著者の得意の状況設定と新鮮な想像力が独特の文体で展開される。表題の「芽むしり仔撃ち」は、村に取り残された子どもたちは脱出を試みても、病気の仔牛が殺されるときのように「半殺し」の目にあうだけだという南の言葉(p.78)、あるいは村長が子どもたちを罵る言葉(「・・・お前のような奴は、子供の時分に締め殺したほうがいいんだ。出来ぞこないは小さいときにひねりつぶす。・・・悪い芽は始めにむしりとってしまう」(p.206)による。 高校生の頃にはこの小説が最高と思っていたが、もちろん今はそうは思わない。しかし、類稀な、日本文学の系譜のなかで新基軸を打ち出した小説だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大江健三郎は「万延元年のフットボール」なんかは凄いと思うけど、その他の作品は格別好きでもありません。「飼育」なんかはまあまあな方です。「洪水はわが魂に及び」は嫌いな方です。「洪水」なんかは、思いこみで書いてる感じがするからです。自分で思いこんでいることを現実と区別していないというやり方は、意識的なのか、実際的に効果的なのかどうか。「個人的な体験」は話の変化が乏しいし終わり方が納得できない。「新しい人よ眼ざめよ」はわりとグロなところが少なくて、全体的に澄み切った感じがして、まあ好感の持てる方です。 この「芽むしり仔撃ち」だけど、こういうプロットだったら、現在の作家だったらもう少し取材して、もっとその取材を生かしたリアリティ描写に力を注ぐでしょう。しかるに、本作はどうも作者の少年体験をもとにして妄想を展開したという感じです。まあ、デビューしたばかりだったわけだから仕方ないとも言えるし、こう妄想で原稿を埋めるというのも、溢れる才能なのかもしれません。 話の内容は、暗中にも少々光ありというようなものです。構成は、先に言ったこともあってやや生硬というか変化に乏しいようなところもあるけど、文章はつねに独特な熱を、奇妙な執念深さを持った感じです。 「万延元年」にいたって作者は自分の存在の根拠とはじめて本格的に向き合うと言われますが、すでに「飼育」や本作ではそのはしりが確認できるわけです。 大江健三郎の小説にはどこか読者を試すところがあります。それはしばしば嫌味な感じがあります。批評家に言わせれば、それが壮絶な精神の戦いとも言われますが、私はあまり好きにはなれません、正直。それでもそれなりに読み甲斐はあるし、この作者のうねうねする文体には、芸術的なものがあります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| こんなに自分の五感が、活字に乗せられていくのを感じた事はないかもしれません。 閉じ込められた小屋の中での小便の匂い、病気で死んだ動物達が山積みされている光景と、誰も語らないけれど蔓延するのだろうという恐怖、干し魚と野菜と米で作った雑炊の味。 最初から最後まで、ずっと怒りながら読んでいました。閉鎖された環境や、人が人を殺すのが珍しくない時代には、人間同士のルールはこんなにもねじ曲がってしまうのか。 主人公の少年達は子供であるが故のたくましさも持っているけれど、子供であるが故に、どうしていいかわからず大人を見てどうしても安堵してしまう面もある。その度に、騙されるな、もう信じるな、と思っていました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 19年も前のことなのに、 読み終わったときの興奮を 今でもありありと思い出すことができる。 文学はこれほど面白いのか!と震えるような気持ちで思った。 純文学の面白さを堪能したい方に、 ぜひオススメしたい。 大江文学を読破しようとお考えの方も、 まずはこの1冊からどうぞ。 大江文学の入門書としてもオススメ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大戦末期、感化院の少年たちは山奥の村へ疎開させられるが、そこで疫病が発生したため、 少年たちは村人達から見棄てられ、山奥に閉じ込められる。 疎外された少年たちは、朝鮮人の少年、疫病で母を失った少女、山狩りから逃れた脱走兵らと隔離された村の中での束の間の自由生活を獲得し、厳しい戦時下での不思議な理想郷を実現したかに思えたが・・・ 少年達は大人たちの身勝手な都合で束縛されたり、見棄てられたり、また時には懐柔させられようとする。 そして、村の大人たちの狡猾さ、残酷さ、理不尽さが強烈に印象に残る。 これは、戦争という狂気によって作られたものなのか、それとも利己的な人間本来の姿なのだろうか。 私は、戦時中に少年時代を過ごした大江氏が、戦時中に感じた大人たちへの怒りにも思えたのだが、どうだろうか。 ちなみに本書は大江氏が23歳の時に発表された処女長編であり、その完成度の高さに感嘆した。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説でいちばんすばらしいのはタイトルです。意味は小説を最後のほうまで読めばわかります。二百ページほどの短めの長編ですが、なかなかに読み応えのあるものになっています。ほとんどリアリティはないらしく、一種のファンタジーになっているらしいのですが、そんなこと当時を知らない私にとってはわかりようがありません。 大江健三郎がデビュー当初からモチーフにしている、「内」と「外」の話です。閉じこめられたのか農村で自由の王国を建設する子供達。閉ざされているのに彼らは自由と感じています。しかし、いざ外にでて大人達と邂逅すると、彼らはもう思い通りにはふるまえません。大人たちの力によって挫折し、涙を流します。外にあるのに自由はないのです。閉ざされた空間と閉ざされていない空間、私たちはそのふたつの概念を前にすると自由という概念さえ失ってしまうのです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ノーベル文学賞だとか、大江だとか、そういうものではない。 1センチにも満たないこの文庫本だが、非常に重厚かつ濃厚な味わいを内包している。 言葉の端々に現れる大江ならではの節回し。 情景あろうと感情だろうと五感だろうと一気に叩き込んでくる濃密な筆致。 めまいすら覚えるほど、甘美である。 感化院の少年たちがとある山村に取り残される。 唯一の抜け道は閉鎖され、山村では疫病が蔓延していることがわかる。 それでもそこは、少年たちにとってはじめて手に入れた「自由」を孕む王国であった。 「自由」を体いっぱい体感してゆくサマは、戦争小説である本作をみずみずしいジュヴナイルにさえ仕上げている。 大江の、一般に読みにくく難解とされ敬遠されがちな文章ではあるが、分量的に少なく、近作とことなり、処女長編であるがゆえエネルギッシュであるし、比較的読みやすくなっている。 この本を手始めに、エンターテインメントとしての小説=娯楽のみでなく、文学としての小説=芸術という世界を垣間見てはいかがだろうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 普段こういった純文学に属する書物は読まないのですが、僕の好きなユヤタンが推薦していたので読んでみることにしました。('-,_ω-`)プッ 最初の何ページか読んで、抱いた印象は「なんだか表現がいちいち難しくて読みにくいなぁ」といったものでした。ラノベ脳の僕には難しかったです、はい。('-,_ω-`)プッ しかし、それも読み進めていくうちに慣れ、作品の世界に没頭していきました。健気に生き抜こうとする少年たちの緊迫した様相や心情を圧倒的な筆力で綴って行く著者に感嘆すら覚えました。 純文学だと敬遠されがちな作品かもしれませんが、これを500円以下で読めるのに読まないのはちょっと勿体無い気がしてなりません。 ページ数は200ページちょいと本当に少ないのですが、内容自体は重厚すぎるほど重厚です。 大江健三郎はすごいなぁ。('-,_ω-`)プッ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| さんも若い頃感銘を受けたと 言っていましたよ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者はこれを20台前半で書いたそうだが、すげえの一言。 ジトッとした描写が多い。それが重厚な印象をこの本に与える。 閉塞的な村、感化院の少年、疫病、脱走兵と戦時中特有の要素をふんだんに盛り込んでいるのに、戦争小説にとどまらずその範疇を大きく超越する。 感化院の少年達が取り残された村で抱く解放感、焦燥そして裏切り、友情、異性との交わりによる高揚感に重厚な印象が加わり、押し寄せるエネルギーに呑み込まれる。 この作品だけでなく、初期の大江健三郎の描く作品のパワーにはすげえの一言。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 隙間はあれども決して逃げ切れない閉塞感が、戦時下の山村に追われた少年たちを中心に描かれています。あくまでも個人的にですが、大江氏の文章は誠に読みにくく感じます。ただそれは、五感や情景が一気に文章に盛り込まれているからだと考えます。読みながら切り張りされて状況を把握するのではなく、体感する速度で把握していく小説だと思います(体感ですから、あいまいな部分も出てくるはずです)。グイグイと物語世界に引き込まれていくのも、そういった文体によるものなのではないでしょうか。一見、細微な説明的文章も感覚を重視したものだと感じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人の傲慢さと利己的な部分をいやというほど見せ付けられた。 異形を拒み、卑しい者を排斥する、人の根幹から生まれる悲劇に怒りすら覚えた。 唯一、幼い兄弟がお互いを労わる絆に救済されるが、それも大人たちが彼らを懐柔しようとする狡猾さに踏みにじられる。 これらは、戦時下という特異な時代背景で生み出されるものなのだろうか。 殺伐とした現代にあっても、その考えは心の奥深くに息づいているように思えてならない。 ページ数は決して多くないが、非常に多くの疑問を読者に投げかける、大江作品の原点とも言える傑作である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 前後して、中沢啓司のコミック「はだしのゲン」を読んだ。両作品とも言える事は、良心をもった人間と良心を持たない人間、それと無関心な人間、これらの人間で社会は構成されているのだと改めて実感した。迫害される人間の抵抗とはどうあるべきなのか?死と隣り合わせで抵抗する人間像に励まされるとともに、自分の生を振り返り、生きていく指針のようなものをつかんだようような気がする。「われわれは滅びさる存在なのかもしれない。しかし、抵抗しながら滅びようではないか」この言葉の意味を深く感じ取れる作品である。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!