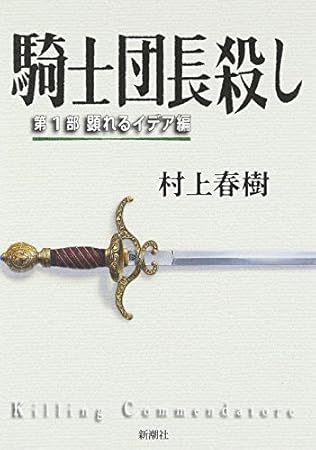■スポンサードリンク
騎士団長殺し
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
騎士団長殺しの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.46pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全211件 141~160 8/11ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初期から愛読していましたが、小説はすっかり受けつけなくなりました。 登場人物すべてがスーパーマン&スーパーウーマン…人物描写が鼻につく…ダメですわ。 免色のような高尚なヤツどこにおるねん?(目の前の家に住んどった) かといってギャツビーのようなスケール感はない。 知的で品のいいセフレ主婦なんかおらんやろ?(駅前の絵画教室に二人もおった) 国内外の著名な作家に音楽家に画家…他人のふんどし自慢してどないするの? 格好つけずにたまには料理とアルコール抜きで書いてみなはれ。 そんな感想を述べるとハルキストは そういうところは枝葉であって物語の本質はもっと深いところにある…なんてことを言う。 騎士団長の造形も過去の作品に似たようなのがあったような… イデアは手がつけられない邪悪な概念として描くべきだったのでは? 関西人特有のユーモアのセンスとサービス精神。 丁寧な仕事をする人なので翻訳は買い、エッセイも面白い。 好人物だとは思うけど、有能な技術者ではあるが芸術家ではない。 そういうところが物足りない。 小説は「もうたくさん」という感じですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| フィクションとはいえ、南京大虐殺のくだりにがっかりです。しかも40万人に増えてるとは日本人として有り得ません。 ネットのおかげで、やっと日本が自虐史観から立ち直ろうとしているこのタイミングに。 新聞記事等では左翼思想だと感じていましたが、作品にするというのはノーベル賞取るために中国からの賛美を獲たかったのでしょうか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| はっきり言ってノーベル賞がほしいだけの売名行為にしか思えない作品。内容がなさ過ぎて2部の途中でギブアップ。星ゼロに近い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ねじ巻き鳥のクロニクルを思い出す所あり、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドを思い出す所あり、1Q84を…と、今までの村上ワールド全開です。 ただ、1Q84もそうでしたが終盤は失速する感は否めません。 村上氏は、テロや地震等を目の当たりにして、普通に生きることの大切さを感じるようになったのかな、とも思いました。 主人公の男性はメタファーの世界に行って産まれ直したのでしょう。 暗くて狭いところを通り抜けて…なんてまさに暗喩ですよね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 歴史に無知な人は小説を書くべきではないとつくづく思いました。南京戦を取り上げるんなら、最低限、それに参加していた元日本軍兵士たちに取材すべきでしょう。YouTubeにも南京攻略戦に参加した元兵士の証言動画が何本も上がっているので、せめてそれを視てから執筆すべきだったと思います。そうすれば、全然違う内容になったはずなので。中共の独裁政権に媚びてまでノーベル賞が欲しいのか?と勘ぐってしまいます。独裁政権は狂喜したでしょうね。ノーベル賞欲しさのあまり「最後の賭け」みたいな気持ちで書いたのかもしれませんが、「知らないことについては書かない」という選択もあったはず。心根の卑しさを感じますね。ともあれ、歴史オンチが歴史にコミットするとロクなことにはならないと考えます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京大空襲、あの焼野原の犠牲者が約10万人と言われています。 どうやったら”南京大虐殺40万人”など出てくるのでしょう? 中国人による南京虐殺は大正時代から何回かあったと新聞報道があるとの話も聞きますが それを全部日本軍のせいにしているのですか? 村上氏は歴史資料を真面目に調査したとはとても思えません。 デタラメを書いて世界に発信させて 将来を担う日本の子供達にどう責任を取るおつもりでしょうか? こんな本を通した出版社も何を考えているのでしょうか? 新潮社の責任も重いと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 羊3部作位の頃は最高の作家だと思ってましたが、今や過去作の焼き直しばかり | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 村上春樹、彼は世界で最も過大評価された作家のひとりでは無く、最も過大評価された作家そのものである。本作を読んで確信した。時間と金の無駄である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ストーリとしては、相変わらずの読むものを引き込む卓越した文章力を感じるが、村上春樹独特の奇抜さは目新しいものがなくなった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 南京大虐殺などありもしない事を書いて、この本は中国に利用される事は間違いない。「あの村上 春樹が本に南京大虐殺が有ったって書いてるじゃないか」っていって来るでしょう。そんなでっち上げまで書いて本を売りたいのか、中国ではベストセラーになることでしょうね。こんな作家にノーベル文学賞なんてありえません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ストーリとしては、相変わらずの読むものを引き込む卓越した文章力を感じるが、村上春樹独特の奇抜さは目新しいものがなくなった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中学生で『羊三部作』と『世界の終わり』にはまりリアルタイムで新作が出る度に読み続けてきました。 どんどん読みやすくなっているし、書かれている世界もリアルに近づいており新しく手に取る人には受け入れやすいかも知れません。 また今回はある程度結末があり物語が完結しているのも良い。 ただ、書かれているものは今までの春樹さんの題材寄せ集めで何の進展も真新しいものも無く、、、これからも読み続けると思いますが、中学生のときに抱いた震えるような読後感にはもう出会えないのかなと思います。 そろそろ、全く違う話を書いて欲しい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 村上春樹の新作長編「騎士団長殺し」をおおむね楽しみながら読んでいます。 主人公が36歳の画家であり、その作品制作過程などがいかにもそうなのだろうなと思わせる巧さで描かれていて感心しています。 またミステリー小説を読むような仕掛け方も巧いなと思いながら読んでいます。 第1部「イデア編」を読み終え、第2部「メタファー編」に入りました。 そこで問題の箇所に至りました。 南京虐殺についての記述 第2部 81Pです。 その前に要点を整理します。 ・主人公が今借りて住んでいるのは日本画の大家である雨田具彦の家である。(具彦はすっかり老いて施設に入っている) ・その屋根裏部屋から「騎士団長殺し」と題された絵を発見する。 ・一方主人公は隣人(といっても山一つ向こうなのだが)の免色(めんしき)という謎の多い男から肖像画を依頼される。(高額の報酬で) ・免色の肖像画を描いた後、引き続きある少女の肖像画を描くことを依頼される。 ・雨田具彦は日本画家に転向する前ウィーンに留学していた。 時代はナチスによるオーストリア侵攻、アンシュルス(独墺合併)の時だった。 ・雨田具彦には継彦という弟がいた。当時(1937年)20歳で東京音楽学校(今の東京藝大)でピアノを学んでいた。 ところが手続上の間違いで徴兵され、南京攻略戦に一兵卒として加わっていた。 ・雨田継彦は翌年(1938年)除隊され学校に戻ったが、復学して間もなく屋根裏部屋で手首を切って自殺している。 大体以上のような設定になっています。 で、問題のP81ですが免色から主人公に電話があります。 免色は雨田具彦の昔のことなどを色々と調べています。 新しく分かったことがあると言って電話をかけてくるのです。 引用します。 その年(1937年)の十二月に何があったか? 「南京入城」と私は言った。 「そうです。いわゆる南京虐殺事件です。日本軍が激しい戦闘の末に南京市内を占領し、そこで大量の殺人が行われました。戦闘に関連した殺人があり、戦闘が終わったあとの殺人がありました。日本軍には捕虜を管理する余裕がなかったので、降伏した兵隊や市民の大方を殺害してしまいました。正確に何人が殺害されたか、細部については歴史学者のあいだにも異論がありますが、とにかくおびただしい数の市民が戦闘の巻き添えになって殺されたことは、打ち消しがたい事実です。中国人死者の数を四十万人というものもいれば、十万人というものもいます。」 一読して、村上春樹ともあろうものが粗雑な文章を書いたものだと思いました。小説の一登場人物、免色の発言という設定だとしてもです。 基本的に小説家はフィクションの中では何をどのように書こうと自由です。 しかし、このように歴史的事実に言及する場合、もっと慎重であるべきです。 上記引用文を、歴史を余り知らない若い読者が読んだ場合、免色の発言をそのまま「正しいこと」と受け取る可能性が強いことに注意すべきです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◎この本は予約注文だけですでに130万部売れています。 そして、将来的にはもっと売れ、また多数の言語に翻訳されて、世界の50ヶ国以上の国で読まれることを著者は自覚しているはずです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 特に「南京事件」のような微妙であり、ねつ造や噂に類する情報が多いことがらを書く場合、このように軽々しく、あたかも事実のように書くべきではありません。 殺人、殺人と繰り返している書きかたも問題です。戦闘行為と殺人は違います。春樹氏は免色氏の言葉として民間人の虐殺があったことを規定事実としてしまっています。 引用文の中でも「細部については歴史学者のあいだにも異論がありますが」と断っていますが、その認識があるならこのように断定的に書くべきではありません。 特に数の問題は重要です。 中国人死者の数が40万人という説は筆者は初めて聞きました。 *広島、長崎の原爆での直接の死者数でも合わせて23万人だったと思います。40万という数字がどれほど突飛なものであるか、著者なら分るはずです。こんな数字を書くことが信じられません。 中国の見解でも最大30万人という数だったと記憶しています。 当時の南京市の人口が20万人程度であり、20万を超える数はあり得ないという説が有力だと言われています。 それどころか、そもそも南京虐殺はなかったという説もあるのです。 (何人殺せば「虐殺」になるのでしょうか?) しかも村上春樹は暗にナチによるホロコーストと関連付けるような書きかたをしています。 これは問題表現です。 このような書きかたはすべきでなかったと思います。 ここを読んだあと せっかく小説を楽しんでいた私は一気にしらけてしまいました。 このような軽率な、あるいは安易なことを書く小説家の本を読んでいるのかとがっかりしました。 しかし、気を取り直して続きを読むことにしました。 ところがまたこのことが蒸し返されます。 南京虐殺の細部について 雨田具彦の息子であり主人公の学生時代からの友人、雨田政彦(今の家に住むことを勧めてくれた人)との会話でまた南京虐殺の話になります。 政彦から電話があり、主人公は東京まで出かけ政彦に会い食事をする。その時の会話です。 政彦にとっては叔父にあたる具彦の弟、継彦の自殺の件を主人公がもちだすのです。 遺書があったという。そこには南京で経験したことが生々しく克明に書かれていたという。 (筆者注:ここで筆者はこの話には或いは取材に基づいた、実際の事実があった可能性も考えました。しかしたとえそうであっても、それは一事例であり、南京事件の全貌を伝える「事実」とは言えないと思いました) また引用します。継彦叔父の遺書の中身について、政彦が語る部分です。 P97 「これまで日本刀なんて手にしたこともない。なにしろピアニストだからね。複雑な楽譜は読めても、人斬り包丁の使い方なんて何一つ知らない。しかし上官に日本刀を手渡されて、これで捕虜の首を切れと命令されるんだ。(中略) 殺し方は銃剣で刺すか、軍刀で首をはねるか、そのどちらかだ。(中略) 屍体はまとめて揚子江に流す。揚子江にはたくさんのナマズがいて、それを片端から食べてくれる。真偽のほどはわからないが話によれば、そのおかげで当時の揚子江には子馬くらいの大きさに肥えたナマズがいたそうだ。」 これもまた恣意的な書きかたと言わざるを得ないと感じました。 「真偽のほどはわからないが話によれば」という表現が虚しく響きます。 村上春樹は何を書きたいのでしょうか? 何となく分かるような気もします。ヒューマニズム? ノーベル賞が欲しいのか?と勘繰りたくなります。 かって村上春樹はディタッチメントの作家と言われていました。 それが1995年(阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件の年です)以降 コミットメントの作家に変貌したと言われています。 こんな形でコミットメントするのならディタッチメントの作家でいて欲しかったとすら思います。 ●読み始めたのだから最後まで読みますが、安易なヒューマニズム表明の作品で終わらないことを望むばかりです。 ◎小説を半分読んだ時点でこのような文章を書くことはそれこそ「不適切」なことかもしれませんが、先を読み進めることをためらわせる程の記述があったので、私としては仕方ないのです。 ここで読むことを止める選択も私にはあるのですから。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 第2部を読んでいる途中で気分を害しました。 第1部、第2部共に そのまま焼却しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| えっ?と思うようなところがあり、 読んでてイライラするし、憤りさえ覚える。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 上記2種の人間による話題づくりのためだけに存在する本。 ストーリーとかモチーフとかなんてどうでもいいですわ。 もともとそんなん,村上だって意識してないんだから。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 左翼思想の作家さんだからこうなるのもわかってましたが、それ以前に面白くない 長い間やられてるので面白い面白くないのはあるのが当たり前ですが、今回は… 残念です | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ハルキストではありませんが、村上氏の著作はほぼ全部読んでます。 一番好きなのは、「国境の南、太陽の西」。この小説だけは何回も読み直してます。傑作だと思います。 さて、「騎士団長殺し」。さすがに手練れの春樹氏だけあって、第一巻はぐいぐいと読ませますね。 絵画についてもかなり勉強なさったんでしょう、なるほど絵というのはそういう成り立ちのものなのか、と絵画鑑賞のど素人の私はいろいろ関心したりしてました。 それにしても、一文無しに近いはずの主人公が妙に金持ちっぽく見えるのはなぜなんでしょう。 あまりぱっとしなさそうな中小企業経営者を親に持つ、特に裕福でもない出自の主人公が、わずか35歳にしてクラシックやオペラ、50年代、60年代ロック、しかもアナログのLPレコードのそれらに通暁しているのはなんだか違和感ありますなー。 こういう人って割といるんでしょうか。そんなことどうでもいいんしょうね、たぶん。 第二巻の穴に潜り込んでいくあたりから、お馴染み村上なんでもありワールドに突入し、まじめに読むのがバカバカしくなってきて、読了するのが苦痛です。 1Q84でも、後半は読み続けるのが苦痛になりましたが、あれと同じ感じですね。第一巻の力強さと第二巻の冗漫さの落差があまりにひどい。 著者が息切れしちゃってるんでしょうか。 たぶん、これが最後の作品になるのではないかと思うんですが、次の作品が出てももう買わないと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「海辺のカフカ」以来の久々の傑作を期待していたのですが、出てきたのはむしろ後退した、焼き直しと「老い」ばかりが目立つ小説でした。 ほとんどセルフ・カバーなんじゃないかと思うくらい、彼の著作のプロットやモチーフが多用されているし、それと同時に物語のテンポは従来よりもひどく緩慢に感じました。計1,000ページにも及ぶ長編ですが、本来はこの1/3くらいで書けてもよい内容だと思います。それを懇切丁寧なストーリーテリングと感じるか、冗長と感じるかは読み手によるでしょうが、少なくとも私には筆者の老いだけが強く感じられてなりませんでした。特に第2部後半からは読んでいて大変苦痛だった。 「色彩を持たない〜」のような失敗作を書いてしまったあとのためか、内容的にはおそらく原点回帰的な思いがこめられていて、自己をリブートし、過去の長編で繰り返し語ってきたことに再トライするような筆者の意思を読んでいて感じました(主観ですけど)。 しかし、そこに新規性はなにも感じなかったし、その冗長さからは「話が間延びして長くなってきている晩年のお笑い芸人」のような劣化や鈍化が表れているように思えました。 また、細部についてですが、南京事件に関する扱いの雑さや、2部の最後であまりにも唐突に物語を東日本大震災に絡めてくる点が非常に気になりました。この点だけで、筆者に対する不信感を深めた読者も少なくないと思います。考えたくないことですが、筆者自身が頑なに否定している「賞レースへの色気」を思わず勘繰ってしまい、背筋が寒くなりました。 主人公は30代半ばで、しかしその人物造形の時計は1980年代で止まっていて、それでいて現実に起きた3.11に絡ませるのはめちゃくちゃだと思います。いびつすぎて目眩がします。それは、きちんと「今」を書こうという誠実な態度ではない。残念ですが、その軽薄さと「ずれ具合」は新作発表のたびに深刻になってきていると思います。筆者はいつまで古い時代に留まり、「自分の内省にだけかまけ続ける」物語を綴っていくつもりなのでしょうか? これまでの出版戦略を鑑みると、第1部冒頭のプロローグを受けた「第3部」が登場する可能性もあると思います。「騎士団長殺し」が第3部で大化けする可能性はあるのでしょうか。いずれにしても、村上春樹にはもう残された時間はほとんどないと思っています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| かつての魅力は文体それ自体に加えて、 形而上の世界と卑近な欲望、物質との接合の 巧みさ、あるいはファンタジー要素と現実との 重なり合いの上手さがあったのだと思いますが、 随分色褪せましたね、と感じました。 装丁はそれなりに上質であるので、 本棚を飾るのには良いかもしれません。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!