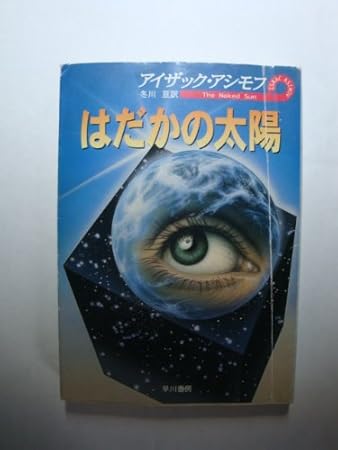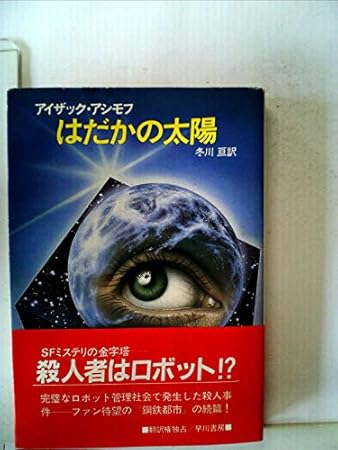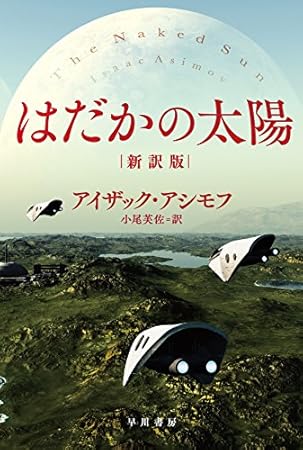■スポンサードリンク
はだかの太陽
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
はだかの太陽の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.53pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全40件 1~20 1/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 少年時代に「鋼鉄都市」を愛読し、それから40年後にようやく本書を読みました。 端的な感想としては「もしアシモフがAIが現実化しつつある現代に生きていたらロボット三原則は生み出さなかっただろうな」と終始思った。正直、3原則とはAIが現実化して様々な問題が顕在化しつつある今としては、アナログ的かつ文系的にすぎる原則で、致命的な欠陥を数多く抱えてしまっている。そして元来、三原則の綻びや悪用をテーマにしたドラマこそアシモフのロボットものSFの骨子なので、AI時代のいま読むには、謎解きとしては面白くても、二重の意味で、さすがに前提条件が時代遅れすぎて厳しいなと思った。 しかし、さすがアシモフというべきか、ラスト部分で主としてイライジャの独白だが「直接コミュニケーションを避け部族意識が失われた社会の結末には滅びしかない」というテーマは、現代も立派に通用すると思った。この結論がなければ、本書は既に時代を越えた評価を得るには厳しかったのじゃないかと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| アシモフの傑作。 夜明けのロボットや、ロボットと地球も電子ブック化してほしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 丁寧に梱包してすぐに発送して下さいました。本の状態も良かったです。ありがとうございました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| アシモフのSFを今まで何度も読みましたが、時々読み返したくなります。気負わず楽しく読めます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Facebookが2021年に社名を「メタ・プラットフォームズ」に変更したことでわかる通り、これからメタバースが広がっていくと予測されています。 そのメタバースが当たり前になった世界を初めて書いた本がこの「はだかの太陽」です。 しかも、岡田斗司夫氏が2022年になって主張されている「ホワイト革命」後の世界です。 謎もストーリーもトリックも秀逸ですが、これらの世界観を1956年に描き切っていることに驚きます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これ、実はシリーズもの。前作『鋼鉄都市』より話のテンポが程よく、中だるみなく楽しめました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 未来の人類を描きながら、実は現代人の近未来に生じるであろう課題を、見事に描き切っている。それもミステリー仕立てで、一気に読ませてしまう。素晴らしい作品です。世界観も前作の「鋼鉄都市」とのつながりで読ませるし感動的な作品。人間の心の普遍的な動きを本当に知っているアシモフらしい、深い作品と言えます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 同著者『鋼鉄都市』の続編にあたるSFミステリ小説。前作に引き続き主人公は警察署員ベイリで、相棒の外見は人間そっくりのロボット・ダニールが登場する。『鋼鉄都市』シリーズを含めて自身のロボット小説史を振り返るエッセイが序文として掲載されている。本文は約380ページ。 前作でスペーサー(宇宙に進出した地球人)殺人事件を解決したニューヨークの市警察署員のベイリは政府から出頭を命じられる。ベイリはワシントンの政府高官から、宇宙国家ソラリアの希望により当地での殺人事件の捜査を依頼されたことを聞かされる。ソラリアは通常では地球人の立ち入りを許さず、殺人事件の詳細については何も聞かされていない。自閉的な地球は発展においてスペーサーたちが建国した五十の宇宙国家から大きな後れをとっており、宇宙国家の情報を欲する政府の方針により、ベイリが任務を拒否する選択肢はなかった。 宇宙国家の総人口は地球より少ないながらも潜在的軍事力は地球の百倍、ひとりあたりのエネルギー生産量は地球の数千倍であり、かつ、地球人はだれひとり宇宙国家に足を踏み入れたことがない。力関係で地球をはるかに凌駕する宇宙国家のなかにあって、総人口がわずか二万人というソラリアの人口密度の低さと、ロボット技術の高さ・生産数は際立っている。人々は夫婦以外の人間に直接対面することはなく、一人あたりが所有するロボットは一万にものぼる。だからこそ殺人が発生したことが建国以来はじめての異常事態であり、わざわざ地球人であるベイリが召喚されたのだった。 SFとしての面白さは、ロボット技術の発展によって人と人とのつながりが極端に希薄になったソラリアの社会が描かれていることにがある。ベイリとともに徐々にソラリア社会のありかたを知るともにソラリアにとって特殊な殺人事件が、その社会との性質と不可分であることがわかる。同時にベイリの行動を通して、鉄の壁に守られて広い空間や自然に触れ合うことがなくなった地球の特殊さが描かれ、ソラリア社会とのコントラストをなす。 ミステリとしては、犯行の手段がポイントになる。人と人とがほとんど出会わない社会の特性上、殺人自体がはじめてであることから、必要な証拠が十分に残されていないという事情もベイリの捜査を難しくしている。そして、やはり人がほとんど直接対面しないという社会の事情によって、ソラリア人から見れば容疑者は明白なのだが、その点にも疑いをもつベイリが真犯人を突き止めようと奮闘しつつ、ソラリア社会の謎を暴いていく。 人が出会わなくなったソラリア社会を、ネットが発達した現代社会の今後を占うかたちで重ね合わせて読むこともできるだろう。序文を含め、アシモフ自身が『われはロボット』において示した有名な「ロボット工学三原則」が、小説のなかで重要な意味をもつ点も面白い。前作の内容を忘れていても楽しめたので、本作から入る方でも問題ないと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 太陽の意味が説明されないんですよね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 近所の本屋で前作『鋼鉄都市』がオススメされてまして面白かったので続編を…と思ったのに店舗に置いてなかったのでAmazonに頼りました。 コロナ禍のなかで読んだので、地球人は病原菌だらけだからと消毒や隔離期間が設けられたり、リモート会議のシーン(作中のはもっと進んだ技術ですが)があったり、ソーシャルディスタンスを取られたり(理由は違いますが)と、身近に思えるシーンがあり読みやすいと感じました。地球とソラリアの対比に見られるコンピューターと人、自然と人工物、三密(コロナ禍の)と隔離、自由と統制などは今まさに問題になっていて、これからさらに迫りくる時代を予感させます。 この作品にも続編があるようですが日本語版は絶版のようで残念です。 また前作にも共通しますが、ミステリー小説ではないんですが推理物のような部分も楽しめました。 知識がないのでロボット三原則などは名前は聞いたことがあるけどよく理解してない部分もありますがそれでも肩肘張らずに面白く読めました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| テレビ電話で通話し、お互いの接触を避けるという、生活基準はほとんど2020-2021年までの我々の生活とほぼ変わらない。一人ひとりが孤独に生き、それぞれが自らの仕事に没頭するものの、何一つとして成し遂げられていないのも似ているだろう。 もし、ベイリがいると、くたびれた、けれどギラギラした目で喝破されるに違いない。 個人的には、鋼鉄都市との訳の整合性はとってほしかった。 鋼鉄都市のベイリは「よしゃぱて」とか言わない(笑) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 非常に良いと書かれていたので購入しましたが本にべったりと料金か何かのステッカーみたいなものがついていたり、品質も一般的には「良い」と表現すべきものではないかと思います。この本は持っており、本棚に飾っておくためにもう少し良い状態のものが欲しかったので購入しましたが、現在持っているものより少し良い程度のものでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| アシモフはすごいです。これが、今のロボット三原則のもとです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容は皆さんレビューされているので、装丁というかカバー絵ですかね。 カバー絵に関しては冬川亘氏訳の版のときの、”野中昇"氏のものの方が個人的には好きです。 NAKED EYE が THE NAKED SUNを見上げるみたいな感じでしょうか(笑) "ニューロマンサー"なんかも前の版の絵の方が良いでしょ?みなさんいかがですか。 SFのカバー絵って自分は好きなんですね。SFロマンみたいなのをピシっと表紙から感じたい。 新版で良い点は字が大きくなった点ですね。おっさん以上に優しいと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本作『はだかの太陽』はいま読むべき作品です。なぜなら、この作品に書かれているソラリア人の生活とほぼ同じ生活を、いまの私たちが強いられているからです。 病気の感染を恐れて人との接触をさけ、どうしても会って話をする必要のあるときは、テレビ映像によるオンライン会話 (※) って、いまやっている自分たちの生活そのままじゃないですか。 (※)惑星ソラリアでは3D映像 私は本作を30年くらい前に読んだことがあるけど、3D映像によるオンライン会話や多くのロボットにかしずかれた快適な生活はいかにも未来SFらしくて違和感がなかったものの、人と人とが直接対面したり触れあったりすることのない生活習慣については、かなり突飛な (よく言えば独創的な) 設定に思われたものでした。 あれから30年・・・・。 ホームワーク、テレビ会議、オンライン飲み会、オンライン授業等々、まさか架空の未来宇宙人類 (スペーサー) ソラリア人に近い市民生活を、自分自身が強いられることになろうとは・・・・。 (→ちなみにアシモフが本作を発表したのは今から63年前の1957年) 世のなかコロナ禍で、カミュの『ペスト』が累計100万部突破のベストセラーになっているようですが、本作『はだかの太陽』も、もっと話題になってもいいのではないか。 というのは、本作は、人と人とが接触しない設定ゆえの不便さや不合理さが非常によく描かれているからです。 内容は人と人とが触れ合うはずのない惑星ソラリアで発生した殺人事件 (どだい不可能な殺人) を追うSFミステリーですが、刑事イライジア・ベイリは、結局はソラリアの慣習に逆らってまでも自分の足で歩き回り、関係者との直接対面と聞き込みで捜査を進めます。 このストーリーの流れはコロナ後の社会を示唆していると思われます。 テレビ会議やオンライン飲み会、オンライン授業等がいかに便利であろうとも、新型コロナウィルス感染症が終息したあと、会議や飲み会や授業がオンライ化の方向にどんどん進むことは多分ないのではないか。 読後、そんなことを考えさせられた本作でした。 (読後の感想/補足) 殺されたリケイン・デルマーの妻グレディアこそが下手人―――すべての状況証拠がそう語り掛け、リケインの友人/知人/助手等もそう信じて疑わない中での捜査。オーロラ人(?)ダニール・オリヴォーとともに惑星ソラリアへと乗り込んだイライジア・ベイリを待ち受けていたのは、ざっとそんな状況だった。ただし犯行現場から凶器が見つからないのが難点。 主な登場人物は以下のとおり。 ・グレディア・デルマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リケイン・デルマーの妻 ・コーウィン・アトルビッシュ・・・・・・・・・・・・・・グルアー安全保障局長の補佐官でグルアーが 毒殺未遂にあった後の安全保障局長代行 ・ジョサン・リービッグ博士・・・・・・・・・・・・・・・・ロボット工学者 ・クエモット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソラリアの社会学者 ・クロリッサ・カントロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リケインのセクシーな助手 ・スール医師・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実はグレディアの実父 ・ハニス・グルアー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソラリアの安全保障局長(→毒殺未遂にあう) ・アルバート・ミニム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地球の司法次官 最初のほう、ミニム司法次官とのやり取りの中で出た、「・・・・彼ら(スペーサー)は地球人に何を期待しているんです? 感謝ですか?」というベイリの台詞はすごく気に入った。 さまざまな紆余曲折があり、地球の私服刑事イライジア・ベイリがソラリアで捜査する過程で会った上記の人物たちのほとんど (→ただしアルバート・ミニム除く) が、一時的にもせよ犯人と疑われる推論が行われるのだが、最終的な犯人はロボット工学者のリービッグ博士だった。(※) (※)厳密に言うと、リービックが開発した着脱可能な腕を有するロボットにそそのかされてグレディアが夫リケインを殺害したというのが真相。 にもかかわらず、イライジア・ベイリ的には、主犯はあくまでもロボットによる殺人の周到なおぜん立てをしたロボット工学者リービッグである。なお、「実行犯」のグレディアに対しては寛容にも惑星オーロラで第二の人生を送ることを見過ごしてあげている。少しグレディァに甘すぎないか、とも思うが、このグレディアこそは「はだかの太陽」から26年後に書かれた続編「夜明けのロボット」で重要な役割を担う人物なのである。 さて、作中、リービッグの魔の手は主人公ベイリにもおよび、彼自身、クロリッサ・カントロの勤める養育所(ファーム)において、可愛い少年の射た毒矢によって危うく殺されかける。 物語の最後のほう、立体画像の会議を招集して真犯人を突きとめるところは、本作の5年前(1952年)に発刊された『宇宙気流』に似ている。 ソラリアの産児制限制度と新生児集中治療室に似た施設の様子は秀逸だった。 また、最後まで読むと、ソラリアのような人と人との触れ合いやコミュニケーションのない超個人主義は、けっきょく2020年の現代社会(オタク文化およびSNSでしか繋がっていない現実)の予言とも問題提起ともなっている。 63年前に本作を書いたアシモフはやっぱり凄い、のひと言に尽きる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本作『はだかの太陽』は、まさにいま読むべき作品です。なぜなら、この作品に書かれているソラリア人の生活とほぼ同じ生活を、いまの私たちが強いられているからです。 病気の感染を恐れて人との接触をさけ、どうしても会って話をする必要のあるときは、テレビ映像によるオンライン会話 (※) って、いまやっている自分たちの生活そのままじゃないですか。 (※)惑星ソラリアでは3D映像 私は本作を30年くらい前に読んだことがあるけど、3D映像によるオンライン会話や多くのロボットにかしずかれた快適な生活はいかにも未来SFらしくて違和感がなかったものの、人と人とが直接対面したり触れあったりすることのない生活様式については、かなり突飛な (よく言えば独創的な) 設定に思われたものでした。 あれから30年・・・・。 ホームワーク、テレビ会議、オンライン飲み会、オンライン授業等々、まさか架空の未来宇宙人類 (スペーサー)であるソラリア人に近い市民生活を、自分自身が強いられることになろうとは・・・・。 (→ちなみにアシモフが本作を発表したのは今から63年前の1957年) 世のなかコロナ禍で、カミュの『ペスト』が累計100万部突破のベストセラーになっているようですが、本作『はだかの太陽』も、もっと話題になってもいいのではないか。 というのは、本作は、人と人とが接触しない設定ゆえの不便さや不合理さが非常によく描かれているからです。 内容は人と人とが触れ合うはずのない惑星ソラリアで発生した殺人事件 (どだい不可能な殺人) を追うSFミステリーですが、刑事イライジア・ベイリは、結局はソラリアの慣習に逆らってまでも自分の足で歩き回り、関係者との直接対面と聞き込みで捜査を進めます。 このストーリーの流れはコロナ後の社会を示唆しているようにも見えます。 テレビ会議やオンライン飲み会、オンライン授業等がいかに便利であろうとも、新型コロナウィルス感染症が終息したあと、会議や飲み会や授業がオンライ化の方向にどんどん進むことは多分ないのではないか。 読後、そんなことを考えさせられた本作でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 小学校4年生の時に姉の書棚から勝手に取り出して読んだ。 因みに姉は本には手をつけていなかったようだったが。 少年少女世界科学小説とか言う全集のなかの一冊だったと思う。 他に少年火星探検隊というのもあって、全部で10冊くらいの全集だったと思うが、 読んだのは、上記二冊だ。 本の題名は、ロボット国ソラリア、だった。 まさに今の世界の先にある究極の不接触社会を描いた作品だった。 まさか、ソラリアの世界の入り口に、生きている間に踏み入れることになるとは思わなかったが、 逆に、少年時代に本書で擬似体験してしまった小生にとっては、今の世界はそれほど違和感はない。 社会に出て、営業職についた小生は、事あるごとに、ソラリアのような社会を夢想していた。 ご機嫌伺い、接待、贈答、挙げ句の果てには、週末の旅行までお供させられた。 仕事自体は、値段と納期の問題で、その調整が全てだった。非常にシンプル。 しかし、現実は何故か複雑w 40年前に感じだジレンマの解が今ようやく見えてきた。それも突然に。 なんか、少年期のワクワク感、青年期の鬱屈感が蘇ってきた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019年は「1984」が現実になっていると騒がれた年ですが、 2020年はコロナウイルスの騒動で、この本の内容が現実になっています。 徹底管理された星で、ウイルスを運んできたかもしれない地球人が怖がられて、直接対面を避けられ、常にテレビ電話越しで会話や仕事を行う。 夏になれば、オリンピックのランナーが灼熱の太陽で焼かれ、人々は熱中症を恐れてアンドロイド入りの携帯電話とすごすことになる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 未来の地球では増えすぎた人口を養うため、人々は「シティ」と呼ばれる巨大な鉄とコンクリートで覆われた都市の中に集合住宅を築き、食料とエネルギーを効率的に使うことで生き延びていた。一方、シティが完成する前に宇宙移民した人類は宇宙人と呼ばれ、人口では地球にはるか及ばないものの、ロボットを利用し、非常に高い科学技術文明を築いていた。 ある日、ニューヨーク市警の私服刑事イライジャ・ベイリは、宇宙人の植民惑星のひとつ、ソラリアで起きた史上初の殺人事件を捜査するため、宇宙船に乗って現地へ赴いた。ベイリは、再びロボット・ダニール・オリヴォーとパートナーを組み、事件の捜査に当たる。 だが今回は、事件現場の一切合切が原状復帰されてしまっており、他人との接触を極端に嫌うソラリアの習俗がために、直接参考人に会ってインタビューすることもままならない。そして、なぜかダニールは、自身がロボットであることを積極的に開示しようとしない。 閉鎖空間で暮らしてきたベイリにとって、ソラリアの解放された大地に立つことは、ベイリにとって苦痛でしなかった。 だが、彼は持ち前の使命感に突き動かされ、ついに真犯人を突き止める。そして、その裏に隠された陰謀を知ってしまった。そしてソラリア人女性グレディアとの 本書は、『鋼鉄都市』の続編だが、もちろん独立した小説として楽しめる。 初めて読んだのは、『鋼鉄都市』と同じ中学生の時だ。この歳になって読み直すと、違う感想を持つ――。 ソラリアは、人々が直接会って話をする必要がないほど通信インフラが充実し、仕事や家事を賄う大勢のロボットがいる。これは、現代社会そのものではないか。コミュニケーションはネットに頼り、コンピュータに向かって仕事をする毎日――直接会うことはあるものの、ネット・コミュニケーションの方が気楽だと考えている人がいるのではないか。 だがしかし、ソラリア人の人間性は幼稚である。誰もが自分がその分野での第一人者だと信じているのである。共同研究などということを思いつかない。現代を活きる我々は、同じことになっていないか。相手の話をよく聞き、自分の考えをまとめることができるだろうか。 さて、最後にソラリアの陰謀の正体が明かされるわけだが、大艦巨砲主義ではなくロボットを愛するオタクの皆さんには、たいへん感動的なラストになっている。そして、ここからアシモフの銀河帝国(ファウンデーション)シリーズに至るまで、1万年に及ぶロボット愛の大河SFがスタートするのである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| またまたまた読んだ。 旧訳を再読した直後の新訳だからか、kindleだから読みやすかったのか。 あっという間に読めた。 ここから「銀河帝国」が始まるのだな、という感慨が深い。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!