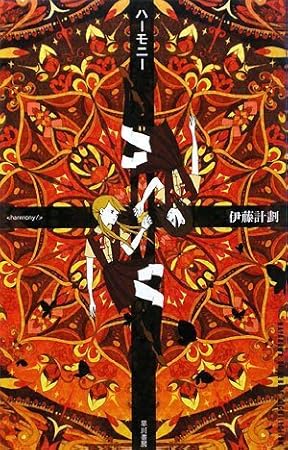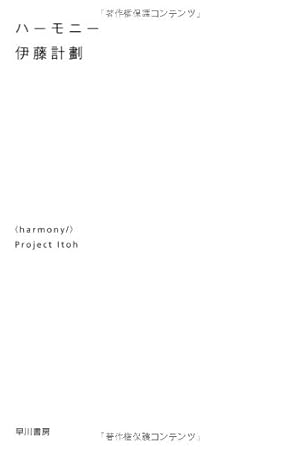■スポンサードリンク
ハーモニー
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ハーモニーの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.15pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全198件 21~40 2/10ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人間は残酷な生き物で、お互いに憎しみ殺し合う。 暴力の連鎖に終止符を打とうとして生み出した解決策、それが「意識」=「わたし」の消失。 「わたし」の喪失は、すなわち暴力を行使する主体の喪失である。 その世界では自己と他者との境がなくなり、(劇中キャラの台詞によると)ぼんやりとした幸福感だけが残る。 憎しみあうことができない代わりに愛し合うこともできない。 社会はただのシステムになる。 もはや、認識する主体もいないということであれば存在していないのと同義ではないのだろうか。 本作を読んでいてエヴァンゲリオン旧劇場版を何度も思いだしてしまった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 虐殺器官があまりにも面白かったので、続けてこちらも購入しました。 病気やストレスが駆逐されたならば?戦争がある程度自動化されたならば?大衆をコントロールする力が生まれたならば?という現代では倫理的、技術的にありえない事柄が次々と前提条件として表れて、そこにおかれた人々の気持ちや駆け引きの描写がとても素晴らしかったです。思想や迷い、判断を手放したら本当に健康で幸せですか?と終始語り掛けられているような物語でした。 今、この時代に読むことで本当にあり得ない話ではないな、といい意味で怖がれるストーリーでした。リアリティを求める人にはあまり響かない作品かもしれませんが、私個人的にはディストピアにどっぷり浸かって楽しませて頂きました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界的な核戦争「大災禍」によって、人口が大幅に減り、一人一人の人間が公共財となり大切にされる世界。 人間の身体を常に健康な状態に維持してくれる医療システム「WatchMe」。人々は、それを体内にインストールすることで、ほとんどの病気から解放された。また、他者への思いやりと優しさを前提とした文化が形成され、世界からは様々な「害悪」が排除された。 健康と思いやりに溢れた平和な世界の中で、閉塞感を感じる少女たちの抵抗と、そこから始まる物語。 -------- 健康や思いやりといった、一般的に「善」とされるものが普及して当たり前となった世界。 物語前半は、少女(と、その成長後の女性)の視点で、この世界の息苦しさについて描かれています。その中で、現在の社会と通ずる部分や現在の延長として想像に難くない姿に対して、「善」の在り方について考えさせられました。 例えば、「健康管理の外注」としての「WatchMe」。現在、多くの人がウェアラブルデバイスや健康アプリで、身体状態をモニタリングしたりアドバイスを受けたりするようになりつつあり、それがより精緻化した未来の姿として有り得るように感じます。また、「思いやりの普及」という観点では、現在においても、ポリティカル・コレクトネスのように、他者への配慮が義務的になりつつあり、同時に、その中で広がる疲弊や閉塞感も話題となっています。 今後、健康管理の外注や思いやりの普及という、ある種の「善」が拡がっていった際に、何が閉塞感を生み、どうしたら息苦しさを免れることができるのだろう、と考えさせられるものがありました。 他方、物語後半は、テーマが少しシフトしたように感じました(いずれにせよ興味深いテーマでしたが)。 上記の世界観や前半の物語から滑らかに繋がりながらも、前半からは想像しなかったような展開で、強く惹き込まれていきました。(後半については、この程度の言及に留めておきます。) 世界観、テーマ、ストーリー、どれもとても刺激的で面白い作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 独特の透明感、近未来&思考実験系SFの形を借りた社会派的な小説。今となっては描かれてる技術はチープに映るが、2022年にどんな作品を書いていたかと思うと早逝が惜しまれる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| SFが好きな人は、好きになれる本です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これはまさに人類補完計画そのもの。エバンゲリオンのそれとは目的も方法も違うけど、個人的にはこっちのほうが近未来的で現実味がある。読み終えた後、考えさせられるものがあり余韻が残った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 虐殺器官の続編となっているため、もしどちらも未読ならば、まずは虐殺器官から読んでいただきたい。 が、前作を読まないと今作が分からない訳ではないので安心してよい。 内容はディストピア系SF小説 設定的にはよくある「機械により管理された社会」ではあるが作り込みがすごい 終始出てくる謎のHTMLのようなタグが意味するものが分かったときに、作者の凄さを自分でもやっと理解できた | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 高2娘が作家さんのとってもオシでして購入代行しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 10数年ぶりにSFの世界に戻ってきて、今更ながら伊藤計劃を読んでいる。今回は先日読んだ「虐殺器官」に続き「ハーモニー」を読む。こちら、「虐殺器官」の世界線の延長なのね。MRSユージン&クリップス社の名前も出てきてちょっと懐かしい笑 物語全体を通じて、etml(Emotion-in-text Markup Language)なる架空のマークアップ言語で記述されている。一見難解なれど、htmlをかじったことがある人なら、タグの英語の意味さえ分かれば逆に理解しやすいと思う。 最後まで読んでの感想は、エヴァに引っ掛けて恐縮だけど、ナノバイオテクノロジーによる人類補完計画だなーと。 しかし作者ご存命のうちに出会いたかったなー。SFから離れていた10数年が本当に悔やまれる泣 それでは次「屍者の帝国」いきまーす。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あっという間だった。 読み始め、ギュッと掴まれてから、最後まで一気に連れて行かれた。 読み終わった後のこの虚脱感は、本当に素晴らしい作品を味わったにしか味わえない。 この著者の新作をもう味わえないのかと思うと、いたたまれなくなる。 それぐらい、いい匂いのする作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最高のSF作品です。なかなかこれ以上の作品に巡り会えません。虐殺機関とセットでどうぞ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 小説でここまで満足感を得られた作品は初めての事だと思います。そして、作者の方はもうこの世にはおられなかったのですね……。とても残念です。 「誰しもがグッドエンドとは言わないだろうが、バットとも言わない」と言う意味の話をインタビューでされていたように、私にも本作がどちらなのか判断しかねます。ただ、主人公は最後まで人であったことに違いありません。 それこそ、本当に最期の時まで純粋に人であったと思います。 友を撃ったことも、もう彼女は何も思わないのでしょうね……。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 面白かった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品で著者のやりたい事ははっきりとしている。薄っぺらい、と言っている人はどこが薄っぺらいのか言って欲しいが、それを言うと本人の薄っぺらさが暴露されるので言えないのだろう。あらゆるものをつまらないと言ったからと言って、本人がつまらなくない人間とは限らない。 著者がやりたいのは自己意識の消失について描く事で、著者はオーソドックスな、古風と言っていいほどの文学的理念を持っている。彼が坂口安吾なんかを引いて、自死の問題なんかを持ってくるのはそのいい例だ。 伊藤計劃が現代作家であるのは、その古風な文学的理念を、現代の物質化社会にぶつけているという事にある。立川談志は「現代ではもはや苦痛だけが楽しみではないか」という逆説的な真実を彼らしく語っていたが、それと通じるものがある。 意識とは物に対する一種の抵抗である。だからそこには苦痛がある。自己の存在を感じる事は、必ず苦悩の影を負っている。しかしこの影を背負わなければ文学にもなんにもならない。 作品の最後では、ハーモニーが勝利する。それはハッピーエンドであるが、作者はそこに苦い真実を見ている。人間が融和され、幸福になった時、失われるものは何か。伊藤計劃はそれを問いたいのだ。 ミシェル・ウエルベックと同じく、伊藤計劃は一人称・ニヒリズムによって世界に抵抗しようとする現代的な作家だ。現代は閉ざされた世界であり、ニヒリズムによって、自己に閉じこもる事によって、何かを守らなければならない。仮に世界の側に幸福があるとしても、自身の不幸を大切にしなければならない宿命がある。かつて生物は、海から陸に上がってきたが、その最初の生物らは実に苦しかったろう、と私は想像する。 共同体から離れて前進しようとする存在は自分の存在そのものを痛みとして感じる。しかし、幸福な共同体に包まれている人はそれは通じない。伊藤計劃という人は今の日本では珍しく、自分の追い求める課題を持っている稀有な作家だった。彼は若年の内に死んだが、彼のたどり着いた苦い真実は後に続く者になんらかの影響を与えるだろう。それに比べて、世界に溶けている著者らは世界とともに流れ去っていく。 私はミァハの、最後のステップを思い出す。その擬音を。また、最後の「とても」のリフレインを。それは意味の世界から外れて音調だけになったあるものであって、伊藤計劃が、幸福だけがすべてではないと言わんとする最後の抵抗の形式だった。最後には音調だけが残り、意味は消える。例えば降り積もる雪の風景のように、伊藤計劃が死んだ後もなんらかの音、自然、形式がこの世界に残っているのではないか、と私は深夜にふと考えてみる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「虐殺器官」は全く楽しめなかったので、こちらも期待せずに読み始めたのですが……本当に同じ著者なの?というくらい、どっぷりハマってしまいました。 主人公はこの作品内の社会では異端の思考の持ち主ですが、現代社会から見ると通常の思考であり、この作品を読んで感じた私の気持ちの代弁者でもあるので、この息も詰まる世界観においては感情移入が容易でした。 そして世界を救うことより、個人的な欲求と復讐で動くところも、この世界の人間らしくない、でも彼女らしい人間くささがあって、非常に好感が持てました。 虐殺は主人公が受け付けなかったので、当たり前ですが主人公って大事だなと感じました。 アニメ映画とコミカライズされているとのことで、普段はアニメや漫画にはあまり興味がないのですが、こちらの作品は手を出してみようかと考えるくらい衝撃でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| コロナウィルス感染症拡大の今こそ、この本から伊藤計劃の凄さを感じます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 世のほぼすべての作家は「人間性」に関心があってその「意識」も実は「動物」としての必要性から生まれたものに過ぎない。その根源からものを考えるべきとする著者「の態度はどこまでも科学的、唯物論的なものである」(佐々木敦解説)。と同時に、「ロジック」にあくまでこだわる著者はある特定のそれが絶対に正しいと言えない限り複数の人物を登場させざるを得ない。本書でも3人の少女⇒女性、主人公の父親などなどに思想=「ロジック」を語らせているのはそのためである。これは言い換えれば「弁証法」に他ならない。 ただし、本書のテーマは重過ぎてこの著者にしても最終回答は「やはり今回は見つかりませんでした」(佐々木氏との対談)なので、弁証法は正-反-合の完成形に至っていない。本書を著者自身、「途中経過報告」(同)と言わざるを得ないのはこのためである。 では、どのように「正-反-合」を考えねばならなかったのか、どういう問題として考えなければならなかったのかといえば、やはり「現在を招来より過大に見積もる双曲線の問題」という問題ではなく、動物がそれこそ本能的に持っている「他者」より「自己」を重視していること言うこと、言い換えれば、他人と自分との間の利害の矛盾の方がより根源的、一般的な問題ではなかったかと思うのである。「万人が万人を思いやる社会」といっても自分、家族や友人とその外部の人間とを同じように扱うということは「動物」としても不可能である。それが「ハーモニー」という理想社会の実現可能性の問題だとどうしても思えるからである。 本書を読んでいろんな感想をもったが、コアたるべき感想のみを書いた。参考にされたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とてもいい作品でしたが、表紙が違っていました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人間が望むユートピアは、究極にはデストピアになってしまうというように物語は展開しているようだ。非常に難解な小説なので、折をみて読み返すつもりである。トァンとミャハとの間に横たわる、友情と憎しみ存在がこの小説に深みを醸し出している。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あらすじ:病気も差別もなく、誰もが幸福に暮らす理想社会。しかし主人公たち3人は息苦しさを感じ、自殺をしようとしてしまいます。 そして自殺に失敗した主人公は、時を経てWHOの準軍事組織に所属し、紛争地帯を駆け巡りながら社会から逃げる日々を送っていました。 だがある日を境に、一緒に自殺しようとした友人の一人が関わっているとされる世界規模の大事件が起こり、主人公はその犯罪を捜査することになります。 僕はこの本を読んで、誰も争うこともなく、差別もなく、平和な世界になるためには〝共感〟そのものを抹消するしかないんだなと思いました。 人は〝共感〟を持ってるが故に差別をしたり、犯罪を犯したりします。たとえどんなに立派な思想の持ち主だとしても、歪められて過激になるのもそうでしょう。 この作者はきっと、究極の平和とは、全人類が〝情に流されない完璧な人間(サイコパス)〟になるしかないと考えているのかもしれません。僕はそこにすごく共感しているし、だからこそ人間の欠陥部分を許容しながらも平和を目指していかなければいけないと思います。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!