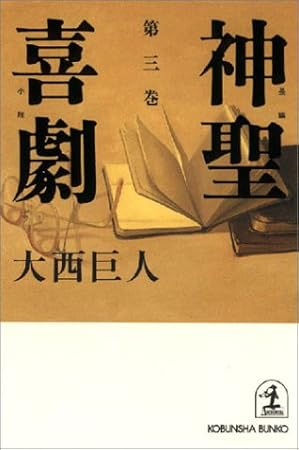■スポンサードリンク
(短編集)
神聖喜劇
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
神聖喜劇の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.51pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全51件 21~40 2/3ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人間のエゴや規則が入り混じっており、人の嫌なところやヅル賢いものは現代にも当てはまる | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| すごい。これは一体、漫画なのか。漫画の臨界点をほとんど突破しようとしている。 この物語は「この世は真剣に生きるに値しない」というニヒリズムを心に抱いた主人公、東堂太郎が、対馬の重砲兵連隊に入営するところから幕を開ける。 しかし、少なくとも漫画版では、そのニヒリズムは、物語の通奏低音とはなっていない。 むしろ主人公の「法的思考」による戦いが、はじめはユーモラスに、やがてはヒロイックなものとして描かれ、それが物語の中心をなしている。 物語中、「軍法会議」なるものが登場する。 軍法会議というのは戦前における一種の司法機関(すなわち裁判所)であり、判例も残っている。 ただし、それは軍隊内の裁判機関である。 (日本国憲法は「特別裁判所」の設置を禁じているが(76条2項)、これは軍法会議を狙い撃ちにした規定だ。) 主人公が法的思考を戦わせる舞台は、この軍法会議においてである。 この物語はいわゆる「法廷物」ではない。 しかし、「法的思考」というものをここまで物語化し得たという意味では、凡百の「法廷物」を抑えて稀有の存在だ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「神聖喜劇」では被差別部落民のことが大きなテーマの一つになっている。主人公東堂は当時極めてめずらしく自由平等思想と近代科学知識を十全に身につけた教養人であったから、部隊内で隠然と、時には公然と行われる差別に憤懣を覚えている。なかでも上級者やそれに阿る兵卒たちの意図的で感情的な嘲弄と侮蔑を心の中で糾弾する。 ただ、そういった意図的な差別ではなく、世間の中で自然と受け入れてしまっている無教養な同報たちの無邪気な、無意識的な差別を哀しくは思いつつ、諫めることの困難さに無力感を覚えてもいる。床屋が職業として蔑視されていることに反発して。自分はまっとうな人間であることの例として「四つじゃあるまいし」と言い放つが、その「四つ」としてさげすまされている者が実はすぐ近くにいることに、気がつき。口をつぐんでしまうのは、むしろ彼が世間の中では善良な人間であることを証明している。 彼ら「穢多」あるいは「非人」は江戸時代に支配制度の一環として固定された。あくまでも支配、統治のための都合にすぎない。農工商の市民はその「お上」の都合にまんまと乗ってしまった。 身分制度のらち外の彼らを踏み付けること、自分たちより「下」がいることで溜飲を下げていた。と畜を生業とする者も多く「四つ」ともよばれ忌み嫌われることになっていった。 江戸時代がおわって一世紀半になろうとしているのに、この差別・選民意識は、風土として世間にこびりついてしまっている。 差別意識は人間がそもそも生理、体質として身に付いてしまっているわけではないが、一度すり込まれるとぬぐい去ることが極めて困難でもある。文明も教育も教養も無力というわけではないが、その力はとても弱くつたない。 「けがれ」という意識。未開社会から現代まで絶えることなく継がれ続けてきた忌まわしさへの恐れ。部落民へのアイヌへの在日への差別もけがれ意識と分かちがたい社会の表面すぐ下に流れる汚れた地下水のような流れ。ハンセン病など病へのけがれ意識。同性愛へのけがれ意識など連綿と続く古来からのけがれ意識。そしてそこから差別が始まる。 そして、いまや放射能が世間を最も震え上がらせる恐怖となり、科学的な説明を受け付けない、ひとびとはそれを恐れ、遠ざかろうとする。それもまたけがれ意識である。ここにまた差別が始まっている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 原作の渾身の大作を、漫画にしようとする苛烈な挑戦に、驚きを禁じ得ないまま3巻目にやってきた。 この巻は、全体の構成の中で、唯一特異な場面構成を見せている。 それは、主人公と、「安芸の彼女」とが織りなす、濃密な男女関係であったり、その彼女の人生の謎を解いてゆく、つきつめた情景であったり、その回想の場面が、現実には、兵営で繰り広げられる昼食前の、できごとに端を発していて、その途中に思い出しているという、小説の構成上は、少なからず問題ではあるかもしれないが、実際の人の記憶の再現という意味では、普通の記憶再生の動きのような、そういった、他に類例のない場面が、この3巻で描くところなのだ。 これを絵に落とすとなると、とても困難だと思う。 だが、作者はそれをやってのけ、読者がとても期待する、「安芸の彼女」の描画についても、なっとくがゆく、知的で官能的な美を再現できていると思う。 村上少尉の「戦争の本義」が、宙に彷徨った瞬間や、「安芸の彼女」を剃毛する場面など、このシリーズの代表的なカットも、多く描かれている点でも、前半の見せ場といってもよい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大前田軍曹の訓話で終わる第2巻。前半最大の山場である。 奇想天外な論理と体験で語られる戦争の本質。この本能的な論理を打ち崩すことは難しい。次巻に続く、最大の山といってもいい。 原作を読み終え、あの世界を体験したものとしては、漫画化した作品を楽しむために勇気を必要とする。 というのも、自分なりに、登場人物の設定=映像が、頭の中でできあがっているからだ。 下手をすれば、自分の映像世界を破壊されることにもなるからだ。 だが、この漫画は、そうではなかった。原作に傾倒し、原作が持つ世界観を、いかに誠実に絵に落としてゆくのか、その命の賭け方が半端ではないからだ。 その迫力に押されたせいもあるだろう。文字以外では再現しにくいと思われる世界を、漫画という舞台で、みごとに再現してみせた、というべきか。 しかも、38式野砲などの具体像を把握するには、原作よりも漫画のほうが優れていることは、言うまでもない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 数年前、某フリーターが発表した『丸山眞男をひっぱたきたい』というエッセイが評判になったことがある。 戦時下や軍隊内においてこそ、格差・階級・差別が、転倒もしくはリセットされるという趣旨の、きわめて 単純で幼稚な戦争待望論であった。 上記某フリーターはじめ、上記エッセイに賛同した人々に、ぜひ本書を読んでもらいたい。 例えば、被差別部落出身かつ犯罪者の一兵隊 冬木の発する以下の一節をどう考えるか。 ― 「いやになる。」 (中略) 「営門をくぐって軍服を着れば、裸の人間同士の暮らしかと思うとったら、 ここにも世の中の何やかんやがひっついて来とる。ちっとも変わりはありゃせん」 漢文調の文体、知的な言説、鋭く冷徹な洞察力など、表面上は男性的でハードな作品なのだが、 そのじつ、他者への「優しさ」「共感」に満ち溢れた、愛すべき傑作である。 以下余談だが― 映画 『戦場のメリークリスマス』 (あるいはヴァン・デル・ポストの『影の獄にて』) が好きな人は きっとこの作品も気に入ると思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あまりの面白さに、読み終えるのが惜しくなり、意図的に遅読している。 対馬要塞を守る砲兵部隊に配属された主人公の東堂二等兵。驚異的な記憶力を駆使して、軍隊という日常が極度に制約された場所で、知力を発揮する。物語は、その山場にさしかかっている。 軍隊に身を投じることで、己を終わりにしたい。そういう動機で入隊したはずなのに、東堂二等兵が、この極めて不自由な空間と時間の制約の中で、いきいきと個性を発揮している痛快を、この4巻目で味わうことができる。 人間の思考の自由を再現したかのような、東堂の記憶再生の旅もまた楽しい。本筋を追っているかと思えば、過去に読んだ書籍、過去に思い描いた記憶、とめどなく連なっている、筆者の博識にも導かれて、まるで智の山脈を歩いているようだ。 遅く読むにも限度があるので、別の本に寄り道してでも、この世界とともに、少しでも長く過ごしていたい。そういう気持ちにさえなっている。読んでいる時も、読まないでいるときも、この本が描く世界とともに過ごせる幸せ。そういう体験を味わっている。幸福である。 東堂二等兵。彼は戦争にも、軍隊にも積極的に加担するつもりはない。 それは、そうなのだが、軍隊という「神聖なくだらなさ」で満ちているはずのその場所。そう思いながら、東堂二等兵が惹かれてゆく、38式野砲への美意識。 あるいは、自分に対して敵対的とも思えるほどに、とりわけ厳しく教練する大前田軍曹の野砲操作を強い憧れを抱く東堂二等兵の撞着。発射姿勢を行う大前田軍曹。照準を合わせる大前田軍曹。 東堂二等兵と、知性の点でも、行動の点でも、対極にある上官の軍事的な所作に美を見出してしまう、そういう心情を告白するくだりでは、今はもう、永遠に失われた時間のことを、東堂二等兵と同じように回想し、理不尽な日常の中にさえ、美を感じる時間があるのだと、強く共感する。 東堂二等兵の大前田軍曹に対する決して口にできない畏敬は、いつか相手に伝わるのか、あるいは、同僚の誰かが見抜くことがあるのだろうか。まるで恋愛小説の結末を切望するかのような気持ちである。 私もまた、東堂二等兵のように、38式野砲の2番砲手として躍動する教官・大前田軍曹の所作に美を感じてみたい。読者たる私は、文字による再現でしか味わうことができないだけに、おそらくは、それを現実に視認した著者を、羨ましく思うのだった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1巻から第5巻まで全巻を通してのレビューになりますが、この大長編小説に関しては様々な研究論文も書かれているようですが、一切読んでおりませんので、あくまでも私個人の感想に過ぎませんが、「これは、吉川英治の「宮本武蔵」のパロディなのではないか」との印象を強く持ちました。作者は、戦中の代表的な教養小説である「宮本武蔵」をパロディ化することで、日本人の情緒に支配された「非論理性」を乗り越えようとしたのでしょう。 主人公である東堂太郎は、宮本武蔵の「剣」を、「知識」と「教養」とに持ち替えています。東堂以外の登場人物についても、「宮本武蔵」の登場人物に当てはめてみると面白いです。たとえば、村上という人物は、佐々木小次郎。作中もっとも魅力的な登場人物である大前田は、沢庵和尚と宍戸梅軒ですね。 そこで思い出したんですが、内田吐夢監督の映画「宮本武蔵」5部作(1961〜1965年)で沢庵を演じていたのは三國連太郎さん、同じく吐夢監督の遺作であり「宮本武蔵」番外編でもある「真剣勝負」(1970年制作、1971年公開)で宍戸梅軒を演じていたのも三國さん。大前田は、若い頃の三國さんのイメージです。勝手な解釈で申し訳ありませんが、作者の大西巨人さんも、HP「巨人館」での「映画よもやま話」の中で、「内田吐夢の映画が好きだ」と発言しておられましたので。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 原作「神聖喜劇 (光文社文庫)」を損なうことなく、漫画で再現する。この困難な道に乗り入れた作者2人の勇気と根性に感動を禁じ得ない。原作を映像化すること。舞台化すること。絵で表現すること。いずれも困難な挑戦だと思うが、挑みたくなる気持ちは理解できる。 私は、原作から先に読んでいるので、絵画で再現されたいろいろな場面、登場人物の表情などが、私自身の頭の中で再現していた映像と、異なる部分は当然にある。 大前田軍曹は、これでよいのか。神山上等兵は、これでよいのか。冬木照美二等兵は、これでよいのか。いちいち確かめながら、ページを繰る。 作者の心の中から湧き出てきた絵画と、私自身が描いていた映像が、不一致だったとしても、この作品に違和感を感じることはない。 原作に最大限の感動を覚え、原作をいかに伝えるか。その精神のぎりぎりのところまで追及している点において、原作を描こうとする、真剣必死の心もちに於いて、この漫画作品の作者と、私との間に、隔たりはほとんどない。 原作が持つ、比類ない日々の世界。軍隊という特殊閉鎖な環境に置かれた、主人公の日常。同じ空気を、描いた作者も、読んで頭の中に再現していた私も、その気持ちにおいて、まったく共感できる。 素晴らしい原作。その世界を違う形で伝えたいと描いた、入魂の漫画作品。どちらも楽しむことができる。 原作を読み終わるのが惜しい。このために、購読した本書だが、この世界もまた楽しい。「神聖喜劇」を手にした数か月。とても幸せな時間を、送っている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 3巻目を半ばまで読んだところで感想を書きたくなった。 徴兵され、陸軍の対馬要塞に配属された東堂二等兵。軍隊という日常の自由を極端に制限された場所に置かれると、与えられる情報は、わずかな断片にすぎなくなるし、挙動すべてに軍隊の決まりと習慣を強要される。 その行動と生活そのものが第三者には、滑稽にすら思えても、当事者が、軍隊内部で、滑稽を表明することは決して許されない。 まさに、神聖にして喜劇。この本の題名「神聖喜劇」とは、軍隊生活=内務班生活を表現する造語として、極めて秀逸な命名だ。 漢籍から左翼雑誌、文芸誌、民俗学に至る、あらゆる文献に精通している筆者の知性は、主人公の東堂二等兵の博識として作中に生かされ、かつ軍隊の規則の法解釈まで加えながら、実に多様な文章世界を横断しつつ、物語は進む。 冬木二等兵は何者なのか。大前田軍曹の発言の真意はなんなのか。隊内に巻き起こりつつある「事件」は、いったい何なのか。推理小説とは、もっとも遠隔にあるはずの、この小説は、実際のところ、読者である私の中で、どんな推理小説よりも、推理する楽しみと知的好奇心を引き起こす。 なんという形式。なんという文学なのだろう。この博識饒舌な文体に、類似点があるとすれば、作品の中に、多様な過去の文献を織り交ぜて進行する、中国古典文学か日本の古典文学なのだろう。少なくとも現代文学の範疇には、同一のものがない希少かつ特異な形式だ。 この作品を読み進みたい好奇心を自制し、少しでも長く、この世界にとどまりたいがために、毎日少しづつ読んでいる。読書にひたる陶酔を味わうことができる素晴らしい作品だ。この作品を読むことができる時間に、生きているなんて、私は、なんという幸福者なんだろう! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2巻目に入った。長編を読む楽しみのひとつが、読んでいる期間中。本を閉じているときでさえ、その本で描かれた世界を思い描き、描かれた世界にともにいることだ。現実は本とともにあり、実際生きているここにはない。そういう不思議な陶酔状態を延々と続けることができる。読んでいる間だけ。 2巻目なのに、読み終わるのが惜しくなっている。意図的に読書速度を落として、この世界とともに過ごす時間が、少しでも長くしたいと考えつつある。 この小説の感想を述べてゆくことは、極めて困難だ。少なくとも現代小説には類例をみない。強いて例えるなら、昭和16年から昭和20年に起きた、軍隊生活内部での、できごとを、古文の表現手法で描き出した世界なのだろうか。 軍隊内部で行われる日常を通じて、主人公の内面は、古典から政治、文学、漢文、詩作にいたる自分自身の知的蓄積の内部を目まぐるしく文献を検索し、相手の発言や意図を予測する。 その思考の面白さと、博識さ、ついでに学べてしまう、あらゆる分野の文献の楽しみ方、そういうものをいっしょくたにして、展開してゆく。 誰も真似ができない。類似のものを書いたとしても、この筆者以外の筆力と知力では、それは必ず破綻するだろう。 そうして、この2巻目。1巻目とは趣を異にして、入営前の愛人との濃密な関係についての秘密が解き明かされてくる。主人公の頭脳の中を泳いでいるような心持ちだ。 そして、この巻の重要な登場人物、主人公の東堂二等兵でさえ、つかみかねている大前田軍曹。彼の口から出てくる、でまかせのような奇怪なとめどもない話の先は、どこに向かっているのだろうか。好奇心を掻き立てられつつ、3巻目を購入した。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中学生時代から本書の存在を承知していたが、読まないと決めていた。 その後、個人的趣味の赴くままに、大量の戦史と戦記を読み、軍隊という場所の想像が容易につくようになってから、読み始めたい、そう考えはじめてさらに数十年、今日に至る。 いわば数十年がかりの準備を、この本を読むために行っていたようなものだ。 読み始めて88ページになった。 その感想は、「中学生時代に読まずに正解だった。時間をかけて、今読む。その楽しみに値する本だ」である。 軍隊の経験者なら、誰もが懐かしく思い出される所属軍隊の「聯隊歌」。歌詞全文を紹介したあと。筆者は、「この稚拙な歌詞は、対馬要塞重砲兵聯隊歌である」と、いきなり「稚拙」と切り捨ててから始まる! そうだ。軍歌の歌詞はたいていが稚拙な漢語調だ。しかし、軍隊に所属した元軍人が、そうではないかと思っていた本心を発言することはない。本心だとしても、懐かしさのあまり、自分たちが歌い、歌わされた歌を、「稚拙」と切り捨てることは、なかなかできるものではない。 主人公の視点で描かれた、軍隊生活における兵士個人の感情の推移。体験からもたらされた感情の記録を、読み物として、ここまでまとめあげた力には感服するしかない。いや、感服などではない。これほど類似のものが存在しない、不思議な戦記(記録)が、今まであっただろうか。 主人公の軍隊生活とともに、これから数か月あるいは1年がかりで、この本を楽しみたいと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読もう読もうと思いつつそのボリュームなど様々な理由で躊躇している方。迷っている場合ではありません。傑作ですから今すぐ手に取ってください。驚くべき記憶力をもつ主人公が、軍隊内の不条理に合法的に、軍規を盾にとって闘争する3ヶ月。あっちこっちに飛んでいく記憶のままに、東西の古典文学から豊饒に引用し、重苦しくもあり、おかしくもある「ザ・小説」。召集以前の生活、特に恋愛関係も珠玉の出来栄えです。 こんな世界は生きるに値しないと思っているニヒリストの主人公が、そのつもりもなかったのに、不条理な支配関係や差別問題に抵抗していくなか、周囲の一般兵たちと奇妙な連帯意識が芽生え、生きる希望を見出していく、という中心的なストーリーだけでも気持ちいい。軍隊でこそ見出す逆説的な希望。 もちろん、作品舞台が対米開戦直後の1942年1月から4月であり、敗戦濃厚になって兵隊たち自身が威圧的で堅苦しい雰囲気を内面化する前だからこそ、軍隊内にまだわずかに民主的法律的な空気が残っていることになっています。主人公の合法的な訴えを聞き入れて戸惑う上官たちは、決して問答無用の鉄拳制裁をしない。 ト書き風、一人語り風、三人称、引用のみ、など節ごとに文体を自在に変化させているのもおもしろい。九州方言の語尾「ごたぁる」の心地よいリズムが耳を離れません。至福の読書体験をぜひ! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 表紙で大きく口を開けて怒鳴っている人物は主人公東堂太郎ではなく、言わば敵役の内務班長大前田文七である。そしてこの場面は第1巻でのハイライトシーンの一つで、彼のセリフは 「職業軍人でもない俺達の 誰が好き好んで五年も七年も こげな妙ちきりんな 洋服ば着て暮らすか うんにゃ、何のためか ようと考えてみよ ・・・」 1頁まるまる使った大コマで次のページは後姿でセリフの続き。本の裏表紙にはその後姿。その白黒画面に紫の明朝縦書きで「第一巻 神聖喜劇 大西巨人のぞゑのぶひさ岩田和博」名匠鈴木成一デザイン室の面目躍如である。本編の当該場面に至ってこの装丁の素晴らしさを実感した。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大西巨人の原作を紐解いた事のある人ならこの作品の漫画化という作業がどれほどの大仕事だったかが分かるだろう。事実この作品は十年という歳月をかけて作り上げられ(原作は二十五年)、その仕事は見事に成功の域に達している。しかしこれを読んで原作を知った気になってはいけない。原作に忠実に描かれてはいるけれどやはり奥行きに限界はある。それはまったくこの漫画の評価を落とすものではないし、原作者もこれらの作品は別々の独立した作品として読まれるべきだとも言っているが、やはり原作あっての本書、原作を知っているがゆえに楽しめた部分は少なくない。原作への最良のガイドにもなると解説で中条氏は語っているが、僕としてはやはり原作の後に本書を読まれる事をおすすめする。もちろんガイドとしても一向に問題はない。つまりは、原作を読んでみて欲しいという一言につきる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| このマンガ、みんな褒めてるのは知ってたけど、かなり値が張るでしょ。だから購入を躊躇ってたんです。でも、たまたま第1巻を古書で見つけて読んでしまったら、残りの5巻新本で買っちゃいました…ううん。 物語はゆっくりゆっくり進んでいくんですが、やっぱり5巻から6巻の大団円の部分に、すべてが凝縮されて流れ込んでいる感じですね。長さに意味のある物語なんですよね。いいですよ。なんか版元の幻冬舎には一抹の悔しさも感じますけど。 先頃、手塚治虫文化賞新生賞と日本漫画家協会賞大賞を受賞しましたね。しかし、背表紙に3人も名前が並んでいたのは、最初はかなり違和感ありましたけどね。 各巻の終わりに収められている「解題」では、第2巻の三浦しをんの文章が面白かった。三浦しをん、読んでみたくなりました、関係ないけど… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読後、さわやか。第一巻から読んできた者は十分な満足と充実感、そしてえも言えぬさわやかな気持ちをえる。 この第六巻(第八部永劫の章)で、読者は大日本帝国陸軍の中の一兵卒として在る自分に気付く。軍隊内部で錯綜する悲喜劇。 緊迫した状況下でドラマは予想もしない展開をする。感動につぐ感動。そしてあっというエピソード。ああ、大前田軍曹。 ああ、漫画はこのようなことが可能なのか。 「“一匹の犬'”から“一個の人間”へ実践的な回生・・・そのような物事のため全力的な精進の物語 ―別の長い物語でなければなければならない」(最後の248頁)と、いう言葉通り。 己の生き方を問われる書である。 この書を完成させた人たちに感謝。第11回手塚治虫文化賞 新生賞、第36回日本漫画家協会賞 大賞おめでとう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この巻の最も印象的な、また共感を持つ部分は、後半中国大陸での戦闘を経験してきた「大前田」氏が「戦争のなんたるか」を力説する部分です。 彼は戦争とはより多く敵を殺し、より多く陣地をぶんどった方が勝つ、ただそれだけが本質の、上品でも高等でもなんでもないものなのだと喝破、 軍の高官や国のお偉方にいまさらキレイ事は言わせない!と主張します。 戦争の現実、本質はその通りなのだと思います。 結局、それ以上ではないのでしょう。 なんと非難されようと、より多く残虐にヒトを殺した方が勝ちなのです。 そして殺し、殺される役回りをさせられるのタダのヒト(私や私の家族。 先の大戦では父の従兄は沖縄で、義父の兄二人は南方で亡くなっています。 彼らは壮絶に殺し、殺されたのでしょう)。 憲法9条の改正や再軍備(=徴兵制の復活?)、核保有の是非はともかく、 それを声高に主張する方は是非有事の際に最前線で捨て駒となる覚悟でお願いしたいものです。 (安全無害な司令室での作戦会議を担当するなどという想定はゴメンです。) 史実や映画、こんなマンガを読むたびに、人間の残虐さを思い知らされますが(きっと私もなんでもやるのでしょう)、 そんな人間の残虐さが現れる状況を避ける、 つまり戦争状態を避ける事がとても大切なこと!だと思います。 やはり再軍備より手練手管、優秀な外交官の人数を増やす事のほうが大事だという思いを新たにしました。 (こどもにも読ませようか、と思っての購入でしたが、 第一巻とも中国人捕虜・日本人在中女性へのすざましい暴挙の描写で取り止めました。 いつかはそんな事も知らしめなければならないのですが。) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| なんの予備情報もなく、「とにかくすごいらしいよ」というだけの噂を頼りに、一巻を読みました。 読み終わった後も、自分が読んだのが「何」であるのか、よく分かりません。 とにかくものすごい言葉の量でした。 作中の主人公、東堂はあらゆる書物を読破し、その一言一句を全て頭にいれいる、優れた記憶力の持ち主です。「世界は真剣に生きるに値しない」と考えた彼は、徴兵検査において同郷のよしみで見逃してくれようとした医師の情けを振り切り、兵士に志願し、軍隊に入隊します。 そこで起きる様々な理不尽に、彼は言葉のみで応戦してゆきます。怒濤のようにあふれる論理に、全ての人は閉口します。 東堂は、決して声を荒げたりはしません。 軍での数々の理不尽な規律も、よくある戦争マンガのように悲劇的には描かれず、淡々と、つい読み流してしまうような調子で描かれます。 ですから、ストーリーは、全体を通して一種の静けさが漂います。 絵柄はトーンを一切使わず、画面のすみずみまで黒々とペンで覆われて、「10年かけて漫画化した」というこの情熱と、ドラマティックな描き方の一切が押さえられたストーリーは、いっそ対称的で、それがこのマンガの「凄み」を増しています。 原作者、大西巨人は、この小説を25年かけて完成させたそうです。 私は戦争体験がないし、戦争の悲劇も悲惨さも、本当の意味では理解することはできません。ただ、大西巨人と、漫画化したのぶえのぶひさの、あふれんばかりの「鬱屈さ」は、理解できるような気がします。 このマンガは、戦争という、誰が描いたのかしれない、とてつもなく大きく理不尽な物語に巻き込まれた人物の、「あれは一体なんだったのか」という理不尽を徹底して問うているものだと思います。 そのために、膨大な書籍を読破し、引用し、言葉の限りをつくして、主人公はその理不尽さに対峙するのです。これは作者の大西が戦中言いたかったことのすべてを、「これは一体何であるのか」という世間への問いを、主人公に代弁させているのではと思います。 しかしそれは、どんなに言葉を尽くしても語り尽くせるものではなく、それがいったい「何」であるかなど、断定することはできません。多くの死者と悲劇を産み出したものが「何」であるかを説明などできないのです。しかしその「説明することのできなさ」、そして「何」であるのかを誰も知らぬままにただ抑圧されてきた者たちの鬱屈、そういったものが描かれているのではないでしょうか。 私が戦争体験がないのと同様、漫画化したのぶえのぶひさにも、戦争体験はありません。それでいて、軍生活の細部までもを絵で表現するという「無謀」に挑戦するのは、抑圧された者の語り得ぬ言葉の鬱屈さを彼も抱えていて、語りたい、言葉が欲しいという、ただ一つの情熱ではないかと思います。 戦争はたくさんの人から言葉を奪いました。そして今も、たくさんの人が自分のリアリティについて、語る術を持たず、沈黙を強いられています。 そういった人々が何かを語らんとしたとき、それはダムの決壊のような勢いを持って、言葉の放流となって私たちの前に現れます。 私たちはそれにとまどい、それが「何」であるのかを理解できません。言葉はあまりに複雑で、あまりに多すぎるからです。 そして、その言葉の放流を前にしたとき、私たちは「閉口」するのです。主人公の東堂に論破される人々のように。 そして、語っている本人ですら、もはやそれが「何」であるのかなど、分かってはいないのかもしれません。ただ、その語り得ぬ「何」かを、その「説明することのできなさ」を、他者に言葉を尽くして「説明している」のだと思います。 オマエはこれを知っているのか、知っているなら語ってみよ、説明してみよ、と迫るのです。そして誰も説明できずに、言葉を飲み込むしかないのです。 これだけの言葉を尽くしても、決して説明しえない理不尽があり、これだけの言葉を用いて25年かけても昇華されない痛みと悲しみと怒りがある。 極力まで押さえた表現からにじみ出てくるもののすごさに、私はただただ、言葉を失って、圧倒されたのでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 懇切力の入った職人的描法がいいです(^^)。 また論理的に考え、話すことに快感を覚える私ですが、冷静沈着で堂に入った主人公「東堂」の振る舞いに『私もこのままガンバロウ♪』と刺激を受けました(汗)。 ちなみに第二巻はまた違った感慨を持ちます。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!