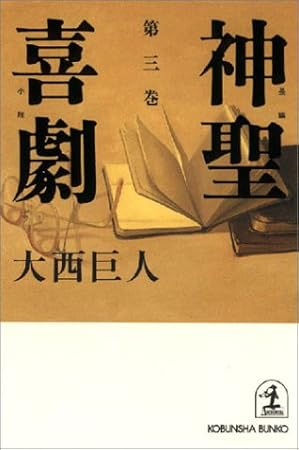■スポンサードリンク
(短編集)
神聖喜劇
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
【この小説が収録されている参考書籍】
神聖喜劇の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.51pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全51件 1~20 1/3ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容としては非常に簡素で、陸軍二等兵・東堂太郎が博覧強記をもって上官の不備をつきやり込めてゆく、という筋が主となっています。ポイントとなるのは、不備をつかせるだけの整然とした規則という論理を、守る存在があったということでしょう。現実に軍内部でそう理路整然とし正しかったとしても上が絶対だ問答無用とねじ伏せられたろうと思われますが。成り立たせたのは鬼軍曹の大前田で、彼が退場することによって本作に幕が降りるのは、必然であったでしょうね。 日本固有の、それもだいぶ古色蒼然としてきたイメージでありますが、文学と言えば小説であり純文学だというもの。そしてそのイメージにある純文学である小説とは、むつかしい漢字、言いまわしがガチガチに詰まった深刻な内容であるもの。それはある部分生きていて、例えば芥川賞受賞作品などに見られる純文学は、文章からみればへなへなすかすかしたものが多数派を占めるようになりましたが、深刻というのか胸がわるくなるようなもの、常軌を逸したものほど好まれる、高く評価される傾向が見受けられますね。その良否、好悪はおくとして、本作ほど古色蒼然とした純文学の小説の特徴をあらゆる意味で完備したものはない、ように思われます。古今東西の文学作品からの引用、執拗なまでの緻密な描写、言葉の正確さへの執念。それでいて、あまりにも突き詰めていったために、古色蒼然としたイメージを突き破ってしまっている、と感じるのは私だけでしょうか。それは文章のみならず、表現だとか取り扱いについても。主人公とおなじく徹底的に正攻法、理路整然とゆき、あまりにゆきすぎるため、そこらの軽々しい目を引くためだけにやっている奇を衒ったものをはるかに越えた威容が現れるかんじ。発表登場からだろうと思われますが、いまの(とりあえず)純文学といわれる小説のなかにおいたとき、あまりに異質すぎて戸惑いを覚える人がほぼほぼなのではと推察します。私自身、混乱しますし。軽いもの、ただ奇を衒っただけのもの、それが悪いとは思いませんが、それだけではあまりに貧しいですね。不満や疑問を感じている方、ときには失望や絶望をもたれる方もいるのではと思われます。これだから日本の小説など読んでいられないのだ、という歎きを見聞したことが実際にありますし。そんな方々に、ぜひ手にとっていただきたいものですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| きれいな本で、直ぐに読んでしまいました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あのような大作を漫画化するなんて、なんて無謀な。と思ったが、入り組んだ知の迷宮を見事に浮き上がらせ、すっかり見晴らしの良いものにしてくれている。 元祖論破王・東堂の活躍は痛快でとても面白いのだが、知の巨人が主人公を通して繰り出す古典の引用や軍隊の難しい用語などが、バカすぎるわたしの頭脳には眠気ばかりを誘い、中途断絶してしまっている原作だったが、ようやく続きを読む勇気を与えてくれた。おすすめです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 第二巻は「混沌の章」。主人公の東堂は帝国陸軍の教育応召を受けた元学生。 この巻でも兵営での新兵訓練の様子が綴られている。 「約一ヶ月(教育召集全期間の三分の一近く)が過ぎ去り、私は同年兵達ととも に屯営生活に関する一定の理解および慣れを身に付ける事ができた」。 対馬での物語。 旧帝国軍の兵隊扱いの悪さは群を抜いているが、ここでも「たかが食事内容に 文句」を手紙に書いただけで、暴力的制裁の対象になる。「大根だけが出てくる ことへの不満」はどうやら「機密事項漏洩」になるらしい。 毎日毎日の愚にもつかない言いがかりと、それに耐えねばならない新兵。当時 はこんな状況がどこにでもあったのだろう。主人公は単なる「軍隊的こだわり」 でしかない「軍隊的規範」に鋭く反応する。「教えられていない」、「どこにも根 拠がない」ことを、「忘れました」と言い換えるそのあり方に絶対に拝跪しない。 軍隊的納得や軍隊的認識に染まらないという、主人公の矜持であろうか。 混乱に混乱を重ねるような「異常な指導」としか思えぬ、班長や上官の「指導 ・教育」と称する数々のイジメ。上官達の高学歴者に対する故のない反感。 主人公はここでも驚異の記憶力を発揮し、上官の間違いの一つ一つの間違いを 指摘する。漢字の読み方一つでも揺るがせにしない。 本書では野砲の詳しい図解があるが、小説では文章で説明してあるらしい。著 者の大西も第一巻で、漫画の方が分かりやすいと記している。輜重隊としての訓 練の毎日。輜重隊にいた方の書いた本では、輜重隊の戦場での動きは独特であっ たよう。ただ主人公は「砲兵」だった。 上官のイジメには心が冷える。旧帝国軍(現自衛隊も同じだろう)では、権力 構造の上位に立つ者は、何か自分が「偉くなった」ように感じるらしい。イジメ をするその精神構造は今も昔も変わりないと実感した。 中国大陸で中国人を焼き殺したこと、凄惨な殺人を犯したことを語る上官=大 前田。「俺が殺したとは、人は人でも日本人じゃないぞ”支那人ぞ”」とわめく。 大前田の言は実は真実を言い当てている。殺すことが戦争の目的で、殺して取り 上げた土地を日本のものとする。大将がもったいぶって何を言っても同じこと。 「殺して殺し上げて…(それが)戦争じゃ」。 「隠坊」による「火葬場」での行動を思い出し、そこから「穢多」、「ちょうりん 坊」、「四ッ」、「新平民」という単語が飛び出してくる。これは第一巻に伏線があ った。同輩の橋本に対する上官の罵詈雑言から、東堂は橋本が被差別部落の出身 であることを知る。軍隊という集団内で、差別意識はさらに拡大する。 巻末のエッセイで大西は「要塞の日々2」として、教育召集された時の兵隊の 状況を語る。 「私のような第三乙種―補充兵の場合、教育召集自体は、ある意味、いつ来ても おかしくない…除隊になって…補充兵のままで過ぎる場合もあり得たし…未教育 の補充兵のまま終えることもあり得た。それは戦局次第」。 当時の召集は戦局に合わせてとにかく召集できる者は召集する、ということだ ったのだろう。 砲兵としての訓練の様子も丁寧に語られる。白兵戦をする一般の歩兵とは異な り、前線よりも後方から的を撃つ。 大西はこの「教育召集」の後は、「下関重砲兵聯隊」に配属された。 その「約四年間に、私たちの後からも兵隊は加わってきたよ。…初めから臨時 召集を受けた年上の大人たち」。 兵隊として暮らした年月で、「軍隊に入って何よりも一番いやだったことは、や っぱり<絶対服従>だった」。 「解題」で三浦しをんが書いている。古本屋のアルバイトをした時は、結構「神 聖喜劇」が売れていたこと。三浦自身も気に入って、旅先で夢中で読んだこと。 面白いことが書いてある。 「東堂(主人公)が大変素敵な男性であることは間違いないが、情事のあいだす ら捨て去らぬ生真面目さと分析癖を見るにつけ、つきあうのはなかなか大変そう だ」。なるほど。 読みやすく面白いです。おすすめ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| すごいとは聞いてはいましたが、ここまですごいと思いませんでした。 ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』のレベルだと思います。 つまり、日本文学の不滅の長編の一つに入ると思います。 もっと早く読んでいればよかったと思いました。 この本がすごいのは、戦争小説というジャンルを軽く飛び越えた普遍性にあります。 日本人をここまで徹底的に描いた作品を私は知りません。 旧日本軍の不条理といじめが徹底して描かれています。 日本軍がアメリカによる攻撃にかかわらず、遅かれ早かれ自壊するのは時間の問題だったことがわかります。 そしてこの、組織の不条理といじめの体質は、日本の会社や学校などに根強く残っているのです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| きれいな状態でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 全5巻を読み終えての感想だが、これは凄い小説だ。日本にこんな小説があり得たとは! 人間に対する深い洞察、緻密なストーリー展開、スリル、ユーモア、個性的で魅力的な登場人物達(主人公東堂は勿論、大前田軍曹、安芸の彼女、村崎古兵、冬木、曾根田、橋本、吉原 等々)どれを取っても、これだけのものはなかなかない。私の文学体験(極めて浅薄なものだが)からすれば、これに比肩し得るのは「カラマーゾフ」くらいしか思い浮かばない。第二巻目で解説者が書いていたが、「迷わず全巻買い揃えるべきだ」という意見には全く同感である。昨今のラノベのような軽い作品に馴れている人達にも、たまにはこういう骨太で重厚なものを読んでみることを強く薦める。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 原作が日本の20世紀後半の文学・小説を代表する作品であることは筆者が言うまでもない。この作品を映画化を想定した?「シナリオ 神聖喜劇 」大西 巨人 (著), 荒井 晴彦 太田出版 を読んだ時に、原作にあった膨大な引用部分の映像化は難しいんだろうなと感じた。その点では本作品も同様。それでも最終巻の主人公が配属先に向かう船上の描写などは原作を読んだ時のイメージに近く再現されていたし、「集団抗命」の場面は的確に映像化されていて感動を新たにした。映画で言えば大道具、小道具にあたる細部の描写も相当な現実感をもって描かれているのだろうと感じられた。 とはいえ、また今回改めてkindle版で読んで、本作品のセリフの文字の多さが気になってしまった。その点で言えば原作はやはり「小説」という表現形式に最適化されていたのでは、と感じた。さらに付け加えれば、本作品245〜248ページにあたる部分を原作で読んだ時に脳裏に広がったイメージはもっと明暗のコントラストが強く、鮮やかな色彩で、かつ爽快だった。 小説がマンガ化、映像化される際には原作小説ではできなかったマンガ・映像ならではの表現がされたと感じられるか否かを目安に、その成功・失敗を判断するのだけれど、本作品で前述の細部の現実感以外の点で「ここは原作を凌駕する」という部分を見出すことは筆者の読力ではだいぶ難しい。それでは本作品が「神聖喜劇のマンガ化」として無意味だったかと言うと、そうとも思っていなくて、何故かと言えばやはり「書き言葉」による表現としてこれだけ完成された作品をマンガ化しようと言う意図そのものが偉大だからだ。ものすごい小説を漫画化する企てについて「失われた時を求めて フランスコミック版」 ステファヌ ウエ (著), マルセル プルースト (著), 中条 省平 (翻訳) があるが、こちらの方が「神聖喜劇」よりは映像化しやすそうに思えてしまう。それでも翻訳版は10年前に2巻で止まったままであるが、原著版はどうなっているのだろうか?と思って検索したら、続きの分が少しだけ翻訳・出版されているらしい。 そう考えてみると本作品が完結に至ったことの意義がわかる。さらに本作品を乗り越えようとする未来の表現者のことを思い、本作品が存在することの有り難みが実感できる。 もう一つおまけに言えば、本作品冒頭では東堂は「我流虚無主義」にとらわれ「この戦争で死ぬべき」と思っている状態にあり、作品内の経過中に徐々に・時に一気にそのような状態から抜け出すきっかけを得たとの過程と比較して作品中の東堂の相貌・表情が最初からすっきりと屈託がない。もうちょっとひねた顔貌でも良かったのではないか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 原作の感じがけっこう上手く表現されていて悪くないと思う。ただ、キーパーソンの神山上等兵の絵があまりにイメージとかけ離れているのがちょっと・・・・。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ある青年が軍隊に入り・・・というお話。 と上記しましたが、それだけでは何の要約にもなっていない大長編。一応戦争中の軍隊内のお話しなので、戦記文学の系譜に連なる作品かと思いますが、なにしろ文庫五分冊でそれぞれ500ページあり、合計2500ページに上る大長編という言葉でも包括出来ない長さの巨編であります。書き始めから終わりまで、25年掛かったのも納得の一大巨編。 主人公が軍隊内で様々なキャラクターと出会い、そのキャラクターそれぞれにいわくや過去があり、それが日本の歴史を総浚えする挿話になっていて、日本史を小説で再現したかの如き作品。その挿話が日本の共産主義、部落差別、軍事史、男尊女卑の歴史、貧富の格差等、あまり他の国に知られたくない日本史の恥部を描いていて、故に世界で日本の歴史を知る為に読んでもらいたい内容になっていて、これだけの情報量、情緒量を一作の纏めた著者の筆力に感銘を受けました。これはもう、日本の文学史どころか、世界の文学史に残る偉業だと思いました。 書名の「神聖喜劇」とはダンテの「神曲」の正確なタイトルだそうで、「神曲」が地獄巡りの小説だったと記憶しますが、この小説はさしずめ日本の地獄巡りの小説と言えそうな作品だと思います。正に神聖なる喜劇というか。 特に、部落の問題は日本で一番デリケートな問題で、ほんの少し語弊を招く、或いは誤解を招く表現があると圧力団体から凄いクレームが来るという、あまり触れたくない、或いは相当に神経を使う問題の為に、多くの人が避けて通る問題なので、ここまで突っ込んだ内容の小説のネタにした著者の勇気に恐れ入りました。実際に色々な方面からクレームや批判もあったかと思いますが、そういう事も覚悟の上でここまで踏み込んだ見識と尽力に脱帽です。 トマス・ピンチョン氏の超大作「重力の虹」に比肩する小説はあまり無いと思いますが、この作品はその数少ない作品だと思います。 広く世界に読まれたい、世界文学史に残る偉業。必読。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これほど骨太の男性的な文学作品が日本文学にあろうとは本当に驚きです。この作品は今こそ日本人にもっと読まれるべき傑作だと思います。それにしても、文庫で小さな文字を追うのはいささかつらいものがあります。是非、単行本での再刊を出版社にお願いしたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今まで読んでいませんでした。 初めて読んで新鮮なので感激。 知人にすすめましたが結果はわからない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 長らく探していた希望通りの本がそれなりの値段で手に入り、満足しています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まず、今の日本の社会では明らかにベストセラーにはならないであろう、このような文学作品を、 美しい装丁で文庫化して世に問うている出版社に、大いなる敬意を表したいと思います。 巻末の初版当時の書評で、いみじくも寂聴さんが仰っている様に、非常に男性的で骨太な論理的文体に、 まずもって圧倒されつつ、旧軍隊という閉じられた不合理な組織における笑止の沙汰を、 人間社会の普遍的な相へともたらして行く筆力構想力に、 日本人として望外の瞠目を強いられた、と言ったところでしょうか。 今回の選挙の投票率を見ても分かるように、日本はもう半分終わっていると思わざるを得ない昨今、 この作品が、もし若い人を中心に広く読まれるような日が来ることがあったら・・・・。 まぁ、そんな日は来ないんでしょうね、所詮人間は、多数決的な総体としては、少しだけ自然を操ることを覚えた、 類人猿よりは手先の器用な、驕り高ぶってスポイルされたサルの群れに過ぎないんだから。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初に、コミック3巻まで読んだところで小説を購入して読了。 このたびキンドル版コミック4から6まで読みましたが、 こんなあっさりしてましたっけ? という感じです。小説にあった、本筋とは関連のない引用や詩がないからかな? この感覚は、『指輪物語』を読んでから映画『ロード・オブ・ザ・リング』を見たときと似ています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| およそ四半世紀かけて書き上げられた小説、 全5巻読み終えるのに約2か月かかりました。 至福の時間でした。 物語の緊張感、軍隊生活のディティール、厖大な引用、 偏執狂かとも思える描写の細かさ、試される様々な文章 様式・・・稀有で濃密な読書体験を約束してくれます。 「キャラクター」なんてことばで表現できない人間の 多義性、測りがたさが見事に造形されていて、 特に大前田班長は比類なく魅力的。 日本での社会、組織の本質として、その規則や論理が 純粋化、先鋭化したものとして軍隊が描かれている。 ある意味で現代のサラリーマンにとってもきわめて 面白い読み物になっている。 再読にたえ、他人へ是非よむべしと勧められる小説。 物語の狭間に主人公の思念に沿って展開されるペダン ティックな引用や考証はそれはそれで面白く、時勢を 多重化する契機にもなっているが、一般人にはほとん ど予備知識がないであろうものが多いので、よみづら ければ流してもよし。 ボリュームや題材に尻込して手にしないのは、あまりに 惜しいと思います。こうした密度の小説はもうおそらく 二度と書かれることはない、という解説も納得。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 昔読んだ時は、晦渋な文章を理解するのがなかなか難しかった。最近あるきっかけで読み直してみたが、少しは理解出来る様になった。第4巻が行方不明で、これだけ注文。古いがきれいに保存されていて満足です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 偉大な原作の漫画版を、全巻読み終わった。 この漫画版を読む楽しみは、小説として書かれた原作世界を、写真を見るように手に取る形で追憶し、新しい感動を刻めたということだった。 原作の小説を読み始めて読み終えるまで、10か月間を要した。それは、小説「神聖喜劇 (光文社文庫)」に出会えた幸福と、その時間が過ぎ去るのが惜しくてたまらないという時間だった。 永遠に小説世界を彷徨っていたい。そんな願望とともに、当然、そんなことが果たされるはずはなく、読み終えて、小説とともにいた時間のことがたまらなく懐かしく思い出されるのだった。 この漫画版では、原作が描いていた世界を記録し、新しい感動を得ているような気持ちでいた。 原作の小説にとっても、この漫画にとっても、主役・東堂太郎とともに、骨格を構成する最大の脇役は、誰だろうか。 それは、東堂が心を許した冬木でもなく、思考と知識で共感していた生源寺でもなく、むろん心を許した「食卓末席組」の同僚兵士の誰でもない。 最大の脇役は、東堂と対極をなす大前田文七であったはずだ。 東堂とは、思考行動すべての点で不一致をなすとともに、その実、東堂が大前田の挙手言動の中に、真実や美を見出していた点は間違いない。 「人非人であり、偉大な日本農民兵士」という大前田軍曹への形容を、この場面で再度目にするとき、原作が持っている圧倒的な場面を読んだ時の感動がよみがえった。 素晴らしい原作の世界を損なうことなく、尋常ではない情念で作画した、作者お二人の労をたたえると同時に、唯一無二の原作の価値を、このような形で再現し、それに巡り合えた幸福を、かみしめながら読了したのであった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 登場人物のほとんどにリアリティを感じない不思議な小説。 名作・佳作というよりもしかしたら奇作かも知れない。 主人公・東堂太郎の異常な記憶力 にリアリティがないのは良いとして、 一兵卒が軍隊内で延々と「正論」を述べることなど可能だったのか? でもそんな詮索を乗り越えてやはり面白 い。 確かに大作だが、司馬遼太郎の長編をたくさん読むなら、 一度でいいからこっちも覗いて損はない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人間のエゴや規則が入り混じっており、人の嫌なところやヅル賢いものは現代にも当てはまる | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!