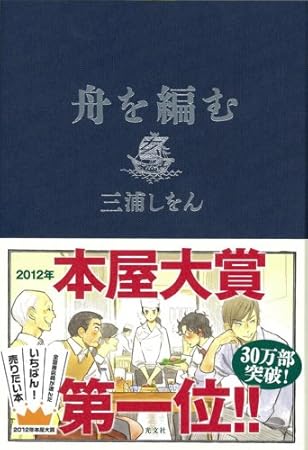■スポンサードリンク
舟を編む
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
舟を編むの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.14pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全73件 41~60 3/4ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書、言葉への愛は感じる。でも、ストーリーの展開は予定調和の範囲内か? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 映画の出来映えに比べて、本書には正直がっかりした。「原作を越えた」というのが映画に対する最大のほめ言葉なら、映画の素晴らしさにはるかに及ばない原作はなんと呼べば良いのだろう。 映画で最も感心したのは、馬締が(会社で仕事の合間に書いた15枚の便箋ではなく)巻紙に毛筆で丁寧に書いた恋文を香具矢に渡し、それを受け取った香具矢が「私を本当に好きなら、あなたの口から言って欲しい」というシーン。ここには、愛の告白は、百万言の美辞麗句も、相手を見ながら発するたどたどしい言葉に劣る、という言語上の重要なポイントがあるのだが、原作ではあろうことか、香具矢に「夜這い」をさせる。「近頃の女性はその位のことは常識」と訳知り顔に解説する向きもあるが、問題は「男の部屋に押し入っての初体験」という、あばずれた行為の是非ではなく、それが辞書作りと料理修行に命をかけている折り目正しいキャラクターの特性に全く似合っていないと言うことだ。このように登場人物の性格描写が安易な点がこの本の第一の難点。 これ以上にひどい第二の難点は、辞書を作るというテーマに反して、言葉遣いに全く配慮が欠けていることである。馬締も西岡も自分を「俺」と呼ぶ。例えば、馬締は大先輩の荒木公平に、「俺は1時半から、渋谷の書店さんをまわらないといけないんでした」(p.22)と言い。西岡も教授に「俺は愛人の存在を知っている」(p.138)と脅す。「俺」は一流出版社エリートが目上に使う呼称ではあるまい。香具矢との初対面のシーンでの、馬締「あの、どちらさまでしょうか」。香具矢「かぐやだよ…….」という乱暴な受け答えにもあきれる。 同様の下司な表現や意味不明の表現には事欠かない。少し例を挙げると、「馬締は、高速で白菜の浅漬けを咀嚼した」(p.79)。この「咀嚼」という食欲を失わせる医学用語は他の食事シーンでも頻出する。例の夜這いのシーンでも、「香具矢が本格的に馬締の腹に乗り上げていたからだ」(p.92)。香具矢「どうして硬直している?」(p.92)。西岡「こりゃまた途絶にうだつがあがらなそうだな」(p.98)。「その時理性の指令が稲妻のごとく体を走り」(p.137)。「西岡はあわてて表情筋をひきしめ」(p.144)。若い女性の「岸辺[みどり]は定食をたいらげ」(p.178)。「岸辺は頬の裏側の粘膜を軽く噛み」(p.213)。どうしてこうまで生硬で洗練されない言葉がストーリーを埋めるのだろう。 第3の難点は、少し学問じみてしまうが、作者は20世紀の言語学・哲学に著しい影響を与えた「言語論的転回」を意識しているかどうかが疑わしい点である。作者がそれを承知していると感じるのは、「一つの言葉を定義し、説明するには、かならず別の言葉を用いなければならない」(p.62)という文章や「記録とは言葉なのだそうです」(p.212)と言った部分だが、反対に「[言葉]の真理に迫るために」(P.145)とか、「ゆがみの少ない鏡を手に入れることだ」(p.186)などを読むと、言葉をつなぎ止めることができると信じているらしい素朴な明快さに、ソシュールを知らないのではないかとも疑ってしまう。小説は論文とは違うから、軽く書くのはよいが、言語の「嘘」を書いてはいけないと思う。 販促を目的とする「本屋大賞」なんだから、お手軽さは仕方ない、と、ここでもまたしたり顔に述べる向きもあるが、それは原因と結果を逆転させた物言いだ。作者は最初から本屋大賞を狙って書いたのではないだろうし、それに本書は「辞書造り」という、言語の根幹をつかさどる重大な問題だが、その反面で地味で専門的な難しいテーマに取り組んでいるのだ。読者の笑いを取るために、あえていい加減な言葉遣いで書くという戦略はあり得るが、内容と言い方の乖離が激しすぎては笑いも誘えない。 将来を期待されるといえるほどの資質を有する作家だけに、この「書き殴り」が惜しまれる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 帯がある状態で紹介されているので、帯がついているものだと思っていました。良く見ると帯等は付いていませんと書かれているので気がつかなかった自分が悪いのですが、、、表紙もあまりきれいな状態ではなかったので残念。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書というものを作る苦労、その人たちの変わった性格が差もありなんというように良くわかった。並行して進展する恋愛は読者の願い通りに進む。そこがあっけない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文章は読みやすかったし、内容もつまらなくはなかった。 ただ、「本屋大賞をとるほどの本か?」というのが率直な感想。 個人的に良かった点 ・辞書の知らなかった事実が知れた ・登場人物が個性的(特に西岡さん) ・辞書に直向きに行動する人たちの姿 個人的に嫌な点 ・感情移入ができにくい(作中の人たちも感じているが、馬締さんの感覚が本当に謎) ・いきなり話が何年後と飛んだり、登場人物の視点もいちいち変わるので、せっかくの個性的な登場人物たちの心情が薄い 松本先生の死もあまり感動できなかったし、岸辺さんの恋もぶっちゃけ必要だったのか疑問。 でも、冒頭で書いたとおり文章は読みやすいし、内容もつまらなかくなかった。 本屋大賞なんて肩書きなかったら、もっと褒める感想書けたかも。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大変な評判を呼んでいる本のようなので、読んでみました。 辞書編纂という、かつてないような異色の小説素材は斬新だったと思いますが、率直に「アイディア倒れ」というか、それが全て、というのが感想です。 全般に「軽い」というか、少女漫画等の原作としては良いのかもしれませんが、男性読者は違和感をかなり感じるような気がします。 正直なところ、このレベルの作品が本屋大賞というのが信じられません。 少なくとも「文学」ではないでしょう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 三浦しをんさんの本を初めて読みました。 辞書編纂という地味なけれどもとても骨の折れる仕事に、 真摯に打ち込む青年と彼をとりまく人間関係を描いた本です。 頭の片隅に「本屋大賞」という言葉がひっかかり、 とても期待して読みました。 でもみなさんのレビューの通り、確かに人物描写も荒く ストーリー的にはグイグイ惹き付けられて読むことが できたか、といえば素直に「はい」とは言えない本です。 でもグロテスクな描写や突拍子もない露悪なストーリー展開の本が ベストセラーとなる今、この本はとてもほのぼのして そして場面場面の描写や言葉はとても素敵です。 もちろん年間の読書量が多い方にとっては 内容が薄く貴重な休日をつかって読むような本ではないかも しれません。 でも本を読み始めたばかりのひと、文学や小説を読み始めた ばかりのひとにとってはとても楽しい本ではないでしょうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読みやすいし、そこそこ面白い。ただし、それ以上でも、それ以下でもない。 あまり知られることのない辞書作りに関わる人物を主人公にしたという点が人気を得た理由だろうし、しかも本に関わる人から支持された理由でもあるのだろう。しかし、たいていの仕事に、関係者以外には分かり難い苦労や喜びがあるのは当然のことなので、“地味な仕事に隠された喜びを〜”みたいな評価をする気にはならない。 登場人物に関しては、それぞれの個性をはっきりさせるためもあるのだろうが、ある意味“類型的”な人物ばかり。特に、岸辺みどりが薄っぺら。その“改心”が、あっさり過ぎるのだ。西岡正志にのみ、やや膨らみが感じられるだけ。 ★3個は、かなり甘めの評価である。 本書が売れることで、多少なりとも“言葉”に注意を払う人が増えることを祈る。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| それほど楽しいとは思えないがまじめな本だ。1回は読んで孫はない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| せっかく辞書編纂という、いいテーマを扱っている割には 内容が軽く、さらっとしすぎているとこが気になります。 まさにライトノベル感覚の小説。 疲れているときにちょうどいい読み応えという感じ。 それに各登場人物の描き方が非常に中途半端ですね。 特に主役の馬締くん。 変人キャラで友達も恋人もいない…という設定の割には すぐ理解者が現れて、恋人までさっさと出来ちゃって、 どこが変人なんだとツッコミを入れたくなりました。 特に香具矢さんと関係を築く部分は、出会いから告白まで せめて3年くらいは時間をかけるべきでは? しかも理解者の西岡さんが去ってからあっという間すぎる13年! 唯一の正社員になった馬締くんが、 あの後どうやって部署を仕切れるくらいに成長したのか? そういう部分こそ、この小説の肝の部分だと思うのに そこを省略して、いきなり成長した馬締くんが出てくるのは反則です。 それから、ラストの山場「血潮」が抜けていた部分。 徹夜で原因究明をしなければ!と意気込んでいた割には 原因は特に描写されず。 他に抜けている箇所はなかった…ってそれだけ?とがっかりしました。 不明なら不明ってちゃんと書いて欲しいです。 正直本屋大賞って余り期待してないですが、 やっぱり期待通りだったいうのが正直な感想です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書の編纂がそんなに大変なことだとは思わなかった。小説の話と辞書の編纂の大変さは違う。 人生を掛けた人がどの様に生きたのか、こころを知りたかった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 三浦氏の小説は初めてです。 文章のグルーヴ感、ストーリーテリングの才、さすが今売れっ子の作家だな、と感じました。 読みはじめに、あれれ、と困ったのが、 読んでいくのと同時進行で、頭の中に漫画のコマがつぎつぎ展開していくこと。 ほんとうに、まるで自分の頭が自動翻訳機械になったみたいに、小説の場面場面でコマがつぎつぎ浮かび流れていく―。こんな経験は初めてなので、なんだこりゃ、と最初は戸惑いました。 わたしは小学校の頃は「少女フレンド」や「マーガレット」で育った世代。 ちょうどわたなべまさこや水野ひで子(だったっけ…)が大活躍していた頃で、昭和40年頃でしょうか。なぜか中学入学と同時にぱたりと読まなくなり、以降はもっぱら読書といえば活字でした。それでも大人になってから大人の漫画はときどき読みます。まあ、自動翻訳機械になってしまう下地はあるのです。 (漫画をほとんど読まない人って、どういう順番で読み進んでいいか分からないという人、いますよ、ほんとに。わたしの連れ合いがそうです) 三浦氏は大変な読書家のようですね。と同時に、恐らく、小説と同じぐらい沢山の漫画を読んでこられたのではないでしょうか。ストーリーの展開などは、むしろ後者から多くを学ばれたのかもしれません。とりわけ、氏のユーモア感覚は、ここだけ悪い意味で使うのですが、漫画そのものです。 (悪い意味で漫画みたい、というとき、具体的にそれがなにを意味するのか、あまり熟考せずに使っています。今度暇なときにじっくり考えてみようっと) でも多くの読者が、読みやすい、おもしろい、と感じるのですから、まあ、これでいいのかなぁ…。 勿論、漫画のコマには翻訳できない文章もありますよね。私は以下の箇所がとても好きです。 「なにかを生みだすためには、言葉がいる。岸部はふと、はるか昔に地球上を覆っていたという、生命が誕生するまえの海を想像した。混沌とし、ただ蠢くばかりだった濃厚な液体を。ひとのなかにも、同じような海がある。そこに言葉という落雷があってはじめて、すべては生まれてくる。愛も、心も。言葉によって象られ、昏い海から浮かべあがってくる」 …いいなぁ。こんな表現ができる人と、あのユーモア感覚と、どうして同居しているのかしらん。 辞書づくりという未知の世界、自分の知らない仕事の分野を読む面白さはありました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| たくさんの宣伝・広告に負けてしまい,読んでみました。 辞書を編纂するという作業を通して,1つの物事にかける情熱が 小さな灯のように登場人物を照らし続けます。 秋の夜長に読みたいような本ですね。読後は爽やかな気持ちに なりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本屋大賞ということで、万人受けするエンターテイメントなのかなと思って読んでいくと、物語としては、登場人物同士のぶつかりあいや葛藤もなく、淡々とあっさり進んでいきます。 キャラクターも三浦さんお得意の少女漫画調のさわやかな人たちで、辞書編纂の壮絶な苦労、という感じでもないし、語り手の視点も中盤から急に変わったり、物語としては物足りないです。 辞書編纂やことばに関して彼女が取材したり日頃思うところのエッセイを物語仕立てで味わうという感覚なら、彼女の視点や文章が好きな人には楽しめると思います。(私は好きです) 辞書にたずさわる人たちへのリスペクトがある点も、気持ちよく読めます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 辞書作りという面白いテーマは、読んでいて勉強にもなったが、各章の恋愛話はいらなかった。恋愛話のせいで物語全体が軽い印象になってしまっている。 辞書作りの過程で起こるトラブルや編集部内の人間関係を中心に物語を進めてほしかった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大雑把なわたしには、ここまで色々考えながら物事を進めたことはなく尊敬してしまいます | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説の面白さはなんと言っても辞書の編纂の舞台裏を発見するスリルと、三浦さんの言葉に対する愛情の表現の仕方だろう。また話が進むにつれ、視点が別々の登場人物に変わっていく書き手としての技量にも感服できる。さらに、とても読みやすい文体になっている。しかし魅力はそこまでで、恋愛が生まれると期待が湧く部分では恋愛が充分に描かれておらず、編纂チームが問題に直面していると書かれても本物の危機感が伝わらず、伏線もなければ展開の意外性もない。すべてが予定調和的に捗るストーリーにある種のもどかしさが生まれ、NHKの「プロジェクトX」を連想させる作品と言える。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| しりつぼみの作品のような気がしました。本の内容は主人公二人によって、大きく前半・後半に分けられていますが、後半で一気にレベルを落としました。といっても物語の展開上、後半は必要なのでしょうが、正直言って「筆者が楽をした」としか感じられませんでした。何故今まで影も形も匂いすらなかった新しい主人公を登場させたのか。例え登場させるにしても、もっと何かしらの上手い方法があったはずだと感じられました。 前半があまり親しみのない「辞書」という世界に自分を上手に導いてくれていただけに、後半の落胆は大きい。 完全に好みの問題なのでしょうが、スケール、筆力、展開、すべてにおいて『ジェノサイド』が大きく上回っていると感じる自分にとっては、前回の『謎解きは〜』に続き、本屋賞大賞の選考にかかわる人は本慣れしていない若年層なのではと思ってしまいます。過激に言ってしまえば出来レースの匂いも気のせいかもしれませんが少し感じてしまいます。 辛口になってしまいましたが、売り出し方、世間の評価と本の中身がマッチしない作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| CLASSY.という雑誌に連載されていた小説であることからも、本書の想定読者は20代の女性なのでしょう。 主人公は、20代のまじめで、高学歴(院卒)、堅い職業に就いていて、奥手でスリムな男性。お相手も、20代の美しく、手に職を持った(板前)女性。20代OLにとって、理想のカップルなんだろうな、と思います。 古い下宿、気のいいおばあちゃん、変わったネコ…、宮崎アニメや高橋留美子のマンガを彷彿とさせるような設定です。 このように、ストーリーのセンターラインはよく言えば王道、わるく言えば陳腐。そこに、未知の要素として、「辞書の編集」というスパイスを利かせた小説だと言えるでしょう。 私のような中高年の男としては、この「スパイス」の部分をもっと描いてほしかった、というのが正直なところです。 飲み会の席でも、「用例採取カード」と鉛筆を放さない松本先生(老学者)や、編集者人生を辞書づくりに捧げたベテラン編集者の荒木といった、言葉の「偏執者」に、もっと光を当ててほしかったですね。 まあ、英語英語と言われ続け、また紙の辞書を引かずググって済ませがちな若者が、日本語と紙の辞書に目を向ける、そのきっかけになる本ではあると思います。 なお、本書には、「日本では、公的機関が主導して編んだ国語辞典は皆無です。日本における近代的辞書の嚆矢となった、大槻文彦の『言海』。これすらも、大槻が生涯にわたり私的に編集し、私費で刊行されました」とあります。 ここだけ読めば、大槻文彦が権力とは何の関係もなく、私的に辞書を編んで出版したと思うでしょうが、実は違います。 『言海』は、明治8年、文部省に勤務していた大槻が、上司(課長)の西村茂樹に国語辞典の編纂を命ぜられ、編さんを開始したものであり、元々は文部省から刊行される予定のところ、出版が立ち消えそうになったため、明治24年に自費出版することになった、というのが正確なところです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ヒットメーカー、三浦しをんの評判作。本屋大賞を取ったのですごく期待して読んだが。結果は、まあまあ。三浦作品としては、標準的水準では。 辞書を作ることがどういうことか、どんなに労力が必要で、作るのに金がかかり、売れないと儲からないか、良く分かったけれど、「風が強く吹いている」「仏果を得ず」のような疾走感、高揚感、上昇感はなく、淡々と話が進む。辞書の編纂という地味な主題なので、しょうがない面もあるのだけれど、少々期待外れ。 主人公夫婦が魅力的で、友達になりたい気もするけれど、生活感の点で、いまひとつかもしれない。 早期にTVか、映画化されることを期待。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!