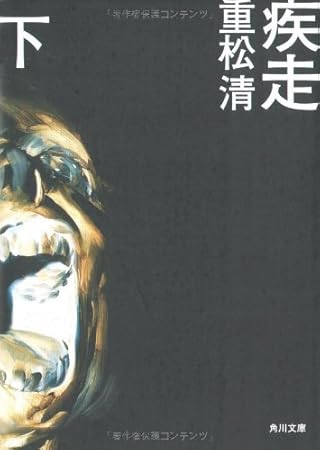■スポンサードリンク
疾走
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
疾走の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.13pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全212件 81~100 5/11ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公シュウジの周りからみんな離れ、死んで、消え、壊れてしまい、シュウジは「ひとり」になっていく 人は絶望し、からっぽになると穴ぼこのように暗い目になるという シュウジは「ひとり」であること、絶望、その人生から逃げようとする そして疾走る つながりを求める「ひとり」はどうなるのだろうか そんな物語は神父を語り部として終焉を迎える 人はなぜ生きるのか 考えさせる本です | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| こんなに読んでいて気分が悪くなった小説はない。 なのに、ページをめくる手が止まらず、一気に読んでしまった。 読み終わった後は体が重く、一人で1日考え込み落ち込んでしまった。 主人公のシュウジに次から次に訪れる不幸。 あまりに救いようがなくて、ただひたすらかわいそうだった。 頑張れなんて思うことはできなかった。 睡眠薬とか飲んで眠るように死んだほうが彼のためなんじゃないか・・・ とか半分読んだ時点で考えてしまった。だって、彼に訪れる試練の数々は壮絶すぎる。 最後に希望が・・・とかいうレビューもあるようだが、私にはそう思えなかった。 『人間は公平に不平等』 本当にそうだと思った。 10代におすすめとか本の帯に書いてあったが、なるべく15歳以上の人に読んでほしいと思う。中学生には重過ぎるだろ〜。 あと、女性にはあまり好まれないかなとも感じた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とにかく読み出したら止まらない。ずっとドキドキしていた。 考えさせられるよりも、共感した。 上下とも読み終えた今思うと、話の展開が読めたりで、ベタなのかもしれない。ありえないだろ?と思ってイライラするかもしれない。 しかし、現実的な部分は作者の体験談か?と思うほど、的確でもある。 それぞれの登場人物は実際にどこにでもいるだろう。 例をあげれば、徹夫のような奴に学生時代に出会った、もしくは、なってしまった人もいるのでは。 それを含めて学校のシーンがやけにリアルだったのが忘れられない。 傷ついているのに、なにをされても折れないシュウジがかっこいい。 なんでこんなに?と思うほど辛いことばかりだけれど、なぜか絶望感があまりない。 非現実的でもあり、現実的でもあるからだろうか? 少年の物語が終わるあたりは神父さんにほんの少し会ってからにして欲しかった。 白と黒に分かれた車が来たあたりから、覚悟を決めたシュウジならこうするだろうな、と想像できるような終わり方の方がよかったような気もする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 自分の読みたい小説を選ぶポイントは大きく分けて3つあると思う。 “タイトル”、“作者名”、“設定・テーマ”の3つだ。 僕がこの小説を手にした理由は間違いなく“設定”である。 普段作者名やタイトルやエンターテインメントを考慮して 選んできた僕にとってこの小説との出会いは“設定”であった。 下巻のキャッチに書かれた“誰か一緒に生きてください”の文を見つけたときに 上下巻ともに買うに至ったのである。 上巻は家族それぞれの心理描写が中心に描かれている。 不思議なことにシュウジに、そしてシュウイチにも感情移入することができた。 文章の一文一文が鋭く、キラキラと光り輝いています。 重いテーマですがタイトルの疾走の如くリズム感をもって読むことができた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 下巻ではシュウジが動き出します。 タイトルの疾走の如く怒涛の展開がシュウジに待ち受けています。 ラストの数ページではむせび泣きました。 僕の読書経験の中で「疾走」は大きな点になりました。 本当にこの小説に出会えたことに感謝しています。 真実を持って生きるということは辛いことなのかもしれません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 淡々とした語り通りの重い話だった。誰にも頼らずひとりを選択したシュウジの言葉、強さが印象的だった。シュウジの周りの人間はみんな人の顔色を伺って生きるような弱い人間だった。シュウジも弱い人間だったのだが、不幸な家族のせいで苦しみ、誰にも弱音を吐くこともできず強いひとりの人間、そして寂しい人間になっていく様子がとても悲しかった。人間、こんな状態になると猛烈に走りたくなる心情もよく伝わってきた。性行為に対する描写も具体的でちょっと気持ち悪くなるほどだった。最後は好きになった人を立ち直らせるため、自らを犠牲にした生き様は立派だったと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 上巻を読んだ限りでは、夢も希望もない感じ。 家庭内暴力を振るう引きこもりの兄、その兄を叱れないダメな親、能書きを垂れ続ける偉そうな神父、醜いいじめっ子に変わる友人、そして周りに流されているだけの主人公、とこの本に出てくるのは腹が立つ人間ばかりだ。 特に兄貴は最悪で、挫折をしたからってそこから努力もせずに堕落を続け最後は・・・、と救いようのないダメ人間だ。 なぜこんな奴を家族は甘やかしておくのかが、正直わからなかった。 ここまではイライラさせられることばかりなので、下巻を読まなければ何とも評価できません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 先日秋葉原で起きた通り魔事件。その容疑者を見たとき、この本の主人公が思い浮かんだ。家庭が崩壊し、愛情を与えらずに育つ。「誰か一緒に生きてください。」シュウジの叫びは容疑者の思いと同じだったのではないだろうか。 友達もいなく、女にも相手にされなかった容疑者。ひとりでいるのが寂しい「孤独」。それに押しつぶされて壊れていく自分。手を差し伸べることをしない社会。何かが歪んでいて、疾走できなかった容疑者。もちろん通り魔事件はひどく身勝手な事件であち、被害者は本当にやりきれない思いだろう。しかし、シュウジを生んだ社会、容疑者を生み出した社会を私たちは見て見ぬふりはできないのではないだろうか。 この作品はハッピーエンドでは終わらない、社会の歪みを見つめた作品であると思う。読んでて暗い気持ちになるが、だからと言って目を背けることは出来ない。フィクションであるが、本質的にノンフィクションなのだから。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最後はやりきれない気持になった。 泣きたいんだけれど泣けない、みたいな。 でも、なんとなくこういうラストは 予想できたのかもしれない。 前半、なかなか読み進まなかった。 内容の重さもさることながら、本の重さもネックだと思った。 (ハードカバーで読んだので) でも、後半は途中でやめることができなくなって一気に読めた。 シュウジの生き方は 可哀相、だとか、悲惨なんて言葉で片付けられない。 周りの環境のせいで、何もかもが崩れていく そんな中、シュウジ自身はきちんと自分自身を生きてたと思う。 孤独、孤立、孤高。 「ひとり」 という意味を色々と考えさせられる そんな作品だったと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重松清は、小説家としてではなく、ライターとしてこの物語を書かざるを得なかったのだろう。疾走していたのは、シュウジではなく、作者自身ではなかったのか。 それほどまでに彼を追い詰めたのはなんだったんだろう。 ある人は、彼の暗黒面といい、ある人はジャーナリスト魂という。 私は、彼の持つ人間に対する苛立ちではなかったかと思う。 これを書いたことでつき物が落ちたような感じではないか。 これが、真の重松清であり、流星ワゴンなんかはシゲマツなんだろう。 そういう意味で、主人公の名前はカタカナではなく、感じでよかったような気がするのだが。 今までのファンを裏切りかねない冒険と思うが、他のペンネームではなく、 重松清として本作を送り出した勇気をたたえたい。 文庫版に解説がないのは、誰も書いてくれなかったからなのか、作者が拒否したのか。 「文庫版のためのあとがき」がないことからして、後者かな。 そこに、重松清の作家としての矜持と本作への意欲を見る。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まさに疾走するが如く15歳の人生を駆け抜けた少年シュウジ。多分岡山県と思われる郷土で優秀なはずの兄が結局は落ちこぼれて放火犯になり、町や学校で孤立するシュウジ。父は失踪、母はギャンブルに走り、何のいいこともなかった郷土を出て、やくざの情婦アカネの元に行くシュウジ。しかし、そこでやくざにおぞましい行為を強制され、そのやくざを殺してしまう。東京に出たシュウジは ここでも裏切られていく。唯一心の通じる友、エリ、しかし、彼女の叔父を刺してしまう彼。やがて警官に射殺されて何のいいこともなかった人生を終えるシュウジ。常に一人であり、一人で強く生きることを目指した彼だが、彼が求めていたのは人とのつながりであり、誰か一緒に生きる人を探すことであった。若くして煉獄の道を歩まされるシュウジ。彼が求めた人とのつながりは結局彼には来なかった。あまりにも悲しい人生。彼が残した小さな命は本当に幸せな道を歩んでくれるのだろうか。本当に希望はあるのだろうか。誰か一緒に生きて下さいというシュウジの叫びだけがいつまでも心に残る。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| “ひとり”で背負うのには、あまりに重く、そしてあまりにも残酷な運命を背負わされてしまったシュウジ。 逃げ遅れたがために、家族全員の罪と不幸を背負うことになってしまったシュウジ。 本を読んでいて、こんなにも辛いと思ったことは初めてのことでした。 最後の最後で、物語に一筋の光が差し込みますが、それすらも闇を強調しているように思え、心がふるえました。 今でも表紙を見るだけで、シュウジの心の慟哭が聞こえてくるような気がします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 孤独が生み出す悪循環と悲劇。 誰かと繋がりたいという声にならない主人公の少年の嘆きに胸が締め付けられるような痛みに襲われます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 疾走する思春期の破壊的な人間模様が巧みに描かれています。 主人公の少年を通して、人間の儚さや脆さや卑しさを見ることができるシリアスで重い作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 痛くて苦しい。 読んでいてこんなに痛い話は初めてです。 心臓を少しずつ握りしめられていくようなじわじわとした感覚。。 人はいつだって「弱い」し「ひとり」、 だから「強い」ようにふるまうし「だれか」と繋がりたいと思う。 繋がりをただひたすらに求める少年の話。 聖書の引用の仕方と、話全体に漂うもの悲しい雰囲気が素晴らしいです。 私にとっては文句なしの5ツ星。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公の少年が家族に起こった出来事をきっかけに、自分の意図しない・望んでもいないところで事件に巻き込まれ、迷える道を疾走していってしまう。 そこには暗い闇が広がり、主人公はそこからわずかな光を見出しそこから抜け出ようと疾走する・・・。 僕はメッセージしていきたい。 自分の意図しない・望んでいないところで、「家族」「親」を失ったり、過酷な状況に追いこまれてしまう子供たちのことを。 この小説で「ひとり」という表現が頻繁に使われる。そして、その「ひとり」はこう言う。 「いつか走ろう・・・ふたりで」 「ただ、ひととつながりたい」 「誰か一緒に生きてください」 「ひとり」でさ迷う子供には誰か「家族」となれる人が一人でも居ることが必要だ。 たった一人でもいいのだ。 「小説の主人公の話」「小説の街の話」ではない。現実にこの主人公のような体験をし、疾走している子供たちはいるのだ。 闇を避けるのではなく、見ないのではなく、あえてその闇に入り光を与えたい。 そういう活動がしたい。 この小説を読んで社会の闇から発せられたメッセージを考えてほしい。 そう思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この物語では5人の命が失われてしまう。 どれもその人が望んだことではないのに。 まるで宿命なのかのように。 絶たれる命がなければ人の悲しみ、憎悪、絶望、孤独を表現できなかったのかも知れない。 だから、この物語に引き込まれたのだと思う。 死んで良かったと思える人間も中には居た。 そうすれば「ひとり」だった者が「ふたりのひとつ」になれる。 でも、やはり人が死ぬのは見たくないです。 微かな救いは最後に「望」が残されたこと。 この人達の宿命はたった一つの「望」を残すために存在していた気もする。 今から言っても遅いけど、重松さん、命が絶たれる物語はこれで十分です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 仲間がほしいのに誰もいない「ひとり」が、「孤立」 「ひとり」でいるのが寂しい「ひとり」が、「孤独」 誇りのある「ひとり」が、「孤高」 なるほどなあ〜〜と思った作中の文章であります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 現在角川文庫で上下巻に分かれて発行されている方を読んだ。 胸を深くえぐられるような衝撃的作品だった。 この本を読んでテンション上がる奴の顔を見てみたい。 人は強くもあり、弱くもある。ぜひ読むべき作品。 僕にとって、重松清最高傑作です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 救いのない物語だ、と思った。 偉大な物語だ、と思った。 誤魔化していない、向き合っている物語だ、と。 悲劇を書くのは簡単なことで、悲惨さを謳うのも容易ではあるのだろうけれども、一つの線を貫いて、抑制を効かせた文体は、悲劇を黙示録へと昇華させている。 いや、批評はいいや。 この作品に、こういうことはくだらない。 エリとシュウジの終盤を読みながら、本当に暗澹たる気持ちになっていたのだけれど、実は読み終わって仕事をしながら、 「これは、救いの物語なのではないか」 と思い始めた。 シュウジは、エリが変わってしまい、損なわれてしまっても、自分勝手にエリを操作しようとしなかった。 全てを含めて、エリと、エリに連なる世界とを、受け容れて、大切に思った。それは、作中では出てこない言葉であり、手垢の付き過ぎた述語ではあるけれども、シュウジなりの愛という姿勢であったのだろうと思う。 極限の苦難の中。 全ての救いと支えはエリだった。 そのエリが、変質した。 それは微妙でありながら、やはり決定的な変質だった。 救いは、喪われた、はずだった。 外部に、信じられるものは、無くなった、はずだった。 シュウジは、しかし走り続けた。 シュウジの態度が、黙示録なのだと思う。 ・・・言葉にしにくい。 けれども逃げないで、何度も読み返して、何度も味わって、何度も考えて、そして生きよう。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!