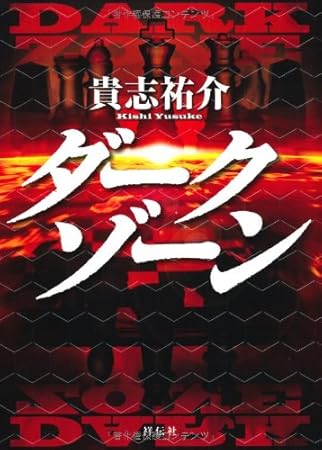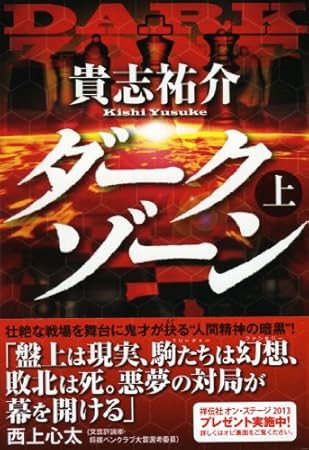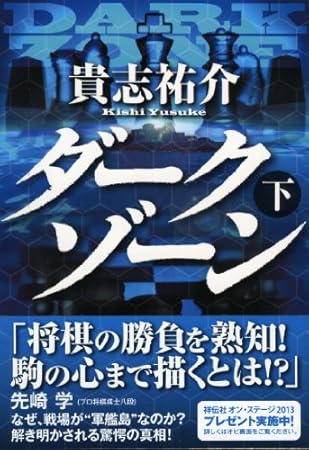■スポンサードリンク
ダークゾーン
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ダークゾーンの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.49pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全74件 61~74 4/4ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| このオチにするくらいなら、現実世界での描写はいらなかったと思う。 ダークゾーンでの不条理なバトルをもっと濃密に描いて欲しかった。 現実世界での話は何の意外性もなく、いかにもありがちなエピソード。ダークゾーンへの絡め方もいまいち。 もやもやとする読後感で、なんだかなぁ、という感じ。 ただ、ダークゾーンでのバトルは最高に面白かった。 フォントの使い分けには、若干のあざとさを感じたが、それにより描写がわかりやすくなっていたので、まぁありかと。 将棋の知識があるとより楽しめる本である。将棋好きなら購入してみてもよいだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ダークゾーンという得体の知れない世界でいきなりバトルが始まるこの作品。 そうかと思えば次章でいきなり無関係な現実世界が描かれ出したりと序盤はかなり違和感を感じるストーリーではあるが話が進むにつれダークゾーンでのそれぞれの陣営の繰り出す様々な戦略の秀逸さや現実世界での主人公塚田の実態や過去等が明らかになっていくにつれこの相容れない2つの世界がどうつながっていくのかが気になり展開に釘付けになってしまった。 終盤ダークゾーンの正体が明らかとなった際には塚田の過去と照らし合わせてやり切れない虚しさを感じさせられる作品ではあったがダークゾーン内での局ごとにそれぞれの陣営の繰り出す戦略及び戦闘は本当に読者を惹きつけるものがあるので興味のある方は読んで損は無いと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 非常に割り切った作りで,これはこれで面白かった. 「黒い家」「新世界より」のようにストーリーを追いかけるのではなく,圧倒的な情景描写能力,世界観の作り込み方,そして知略を尽くした闘いのシーン,といった“貴志祐介のテクニック”を純粋に楽しむための作品だと思う. 例えるなら,ストーリー性のある「映画」ではなく,「フリースタイルスキーのスーパープレイムービー」を見た後のような,そんな読後感. 巻き戻して,何度でも見たくなる. 貴志作品初めての人にはオススメしないけど,ファンには是非推薦したい. あと,「眼の中に虹彩が2つずつ」というモチーフがずいぶん気に入ったんだなぁ…って思った. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 貴志祐介さんの本はほとんど読んでいて大好きな作家の1人ですが、 毎回毎回趣向の異なる世界の書き方で頭の中がぐにゅぐにゅっとねじられた ような読後感です。 今回の作品では大半が、「ダークゾーン」という不思議な場での将棋に似た ゲームを、主人公の知人たちがなぜか駒となって不気味な、そして特殊な能力を もった者として戦いを繰り広げます。 そして間に挟まれる「断章」で「ダークゾーン」と主人公との接点のヒントが 提示され……という構成であると言えばいいのでしょうか。 どうやら初出時はバトルがずっと連続的に書かれていたようで、単行本での加筆 とのことです。 これによりバトル好きな方(目次でわかるんですが、全8回のバトルがあります) の満足感は下がったのかも知れませんが、バトル・断章・バトル〜という構成は 僕としてはそれぞれに描かれているシーンの意味を考えるいいヒントであることはもちろん ちょっとグロくてハードなバトルの休憩にもなりました。 ダークゾーン、読み進めるとわかるんですが、装丁のエンボスまでも意味があって、 それが半分くらいのところで示された後は、本が一体となって指先から目から入って 脳と心に忍び込んでくる感じを受けました。 そんなところまでよく出来ているなんてさすが… 言わずもがなですが、貴志さんの新刊は(評価が定まる前に)すぐに買っても まず後悔しないですよね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 他の方々と同様、私も「クリムゾンの〜」が大好きなクチで本書を購入。 冒頭、ほぼノー説明で異世界の状況描写が始まり(主人公も私も???)、そのまま戦端が開かれる展開はたまらなくミステリアスでスリリングです。神話・伝承が好きな私には鬼土偶(ゴーレム)や金狼(ライカン)等、キャラ設定もたまりません。 未読の方の為にぼやかせた表現に留めますが、現実の日本の孤島の様な異世界で、二人の将が上記の様な伝奇的で多様な戦士達を生ける駒とし、知略・謀略を駆使して血みどろの戦いを…というパートと、現実の若き棋士の日常パートが交互に描かれ、やがて奇妙で切ないシンクロを見せていきます。その絶妙な伏線の数々は著者のファンならお馴染みでしょう。 グイグイと引き付けるエキサイティングでミステリアスなストーリーも素晴らしいですが、今更ながら著者の博学さに改めて脱帽ですm(__)m 最後に毒鶏(コカトリス)マジ怖ェ(*_*) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初から最後まで一気に読みました。 赤軍と青軍の異形の駒たちが織り成すバトルロワイヤルは、読んでいて想像力を掻き立てられました。 ダークゾーンでの異形の者たちのバトル。 主人公の将棋に対する思い。 ページをめくればハマること間違いなしです。 賛否両論あるでしょうが、私はこの作品のラストが結構好きです。 ダークゾーンは主人公にとっての地獄なのでしょうか?それとも天国なのでしょうか? あるいは… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 割と高評価のレビューが多いのが意外です。 読後の感想を一言で言うと、「疲れた」と「ゲーム化されそう」。 最後のオチは、他に仕方がないのかもしれないけど残念。賛否でいうと否です。 しかしながら、強烈に印象に残る本でした。 一気に読んでしまいました。 8戦続くなかで、1戦1戦が重たくて読むほどに疲れるのだけれど、なぜか途中で読むのを止められない。気がつくとこの世界にどっぷりとハマっていました。世界観のつくり方がハンパないのかもしれない。読むことに疲れていたのは、このダークゾーンという世界に自分が入り込んでしまったからなのかもしれない。 将棋は小学校以来指していない。駒の動かし方も覚えていない。 なのにこの小説を読んだ後、羽生さんの書籍を2冊読み、将棋盤も買ってしまった。 この小説のなかで繰り広げられる勝負師、棋士の姿に魅了されてしまったのだ。と書くと大げさだろうか。でも少なくともこの作品から強い影響を受けたのは確かだ。 僕は著者貴志祐介さんは好きな作家で、作品のほとんどが好きです。評価が分かれている悪の教典 上も、好きです。 クリムゾンの迷宮 (角川ホラー文庫)も新世界より(上) (講談社文庫)も大好きです。 本書は僕の好き嫌いでいえば、貴志祐介作品の中では好きではない方。 しかし、強烈な印象と影響を受けたという面ではトップクラス。 ちなみに読んでいてつまらない、という事は一切ありません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「クリムゾンの迷宮」や「新世界より」に含まれる<戦略性>をメインに据えた、かなり割り切った世界観のバトルものです。 一から説明しなければならない強引な設定であるにもかかわらず、そのあたりの解説とストーリー進行を兼ねた描写力はさすが。 ゲームとはいえ元人間を駒にした殺し合いの要素に好き嫌いはあると思いますが、異形の怪物を頭に描くイメージ力があれば面白く読めるんじゃないでしょうか。 目次を見れば3勝3敗1分で最終章に進むのは容易に推測できますが、「プロモーション」など徐々に明かされるルールや戦略に対する興味で飽きさせず、そして「結局この世界は何なのか」という謎で最後まで引っぱられます。 作者のこれまでの作品によくあるタイプながら微妙に人好きのしない主人公、そんな引っ掛かりを持って読んでましたが、読み終わってなるほどと。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公は、気がつくと、どこともしれない別世界にいて、そこで否応なく命を賭けたゲームが始まる。導入部の骨格は「クリムゾンの迷宮」と同じです。 プロ棋士を目指す二十歳の奨励会会員・塚田は、廃墟の一室で目覚めます。ここはダークゾーンと呼ばれる異空間に存在する出口のない孤島で、塚田も含め18の異形の人影が赤いオーラをまとって蝟集しています。島内のどこかには青いオーラに包まれた青の王将率いる一団がおり、両者はどちらかの王将が死ぬまで殺しあう。七番勝負で四勝した陣営の勝利。誰が何のためにといった口上は一切抜きで、ルール説明だけがたった数ページで怒濤のように語られ、青の軍勢の襲来によって、問答無用でバトルに突入します。 「悪の教典」や「新世界より」の後半に展開された、戦略と戦術に裏打ちされた激しい命のやりとりが、巻頭から巻尾まで、しかも第一局から第八局(なぜ七でなく八!?)まで8つも詰め込まれています。リアルに想像するとかなり陰惨な光景が全編にわたって繰り広げられていますが、描写は淡々としていてゲーム的です。また、ゲームが繰り返されるにつれ、徐々に智略が研ぎ澄まされ、戦いがヒートアップしていくのもたまりません。 プロ棋士を目指す奨励会での戦いと、ダークゾーンでの戦いがクロスオーバーし、決着がつくまでやめることすらできない戦いを強要される若者像など、教訓めいたものを拾いあげようとすればできるでしょうが、それよりなにより、読みはじめたら結末にたどりつくまでやめられない、貴志祐介ブランドの超絶、中毒的な一気読み小説である、という一点に尽きると思います。 ラストのまとめ方は毀誉褒貶ありそうですが、何度か読んでみるとかなり込み入った伏線が張られていて、ぼくはかなり好きです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 著者の特記能力である圧倒的情報量とリアルな描写が充分に活かされた一作。この能力において彼は作家の中でもトップクラスだと思います。 「悪の教典」ではかつての才能も流石に少々パワーダウンしたのか?と思わされましたが、そんなことは要らぬ心配でした。しかし個人的感想としては「まだまだこんなもんじゃないだろ」の一言。昔と比べて何かが物足りない。 もちろんこれでも充分面白い作品だが、「黒い家」「青の炎」「新世界より」から受けた様々な衝撃に比べると、もうちょい。 そりゃ誰だって常に完璧な作品が書ける訳ではない。でも十数年もファンをやってるといつだって彼の最高の作品が読みたいんですよ。貴志さん、次回作期待してます(笑) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 著者の本は、読み始めると、その世界に入ってしまい一気に 読み終えてしまう。この本も他作品と変わらず引き込まれる 内容だ。 これまでの著者の本と異なる点はバトルシーンの多さだろう。 その反面、ストーリ性は乏しく、その面白さは半減していた。 また、予想のつく終わり方であり、読んでいて驚きも少ない。 読後感も悪く全体として残念な作品である。 著者が書いた本の中では、けして高い質のものではない。それでも 面白いことは確かであり、さすが貴志佑介と感じた。 次回作が楽しみだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 傑作! みごとな世界観の創造だ。 もちろん貴志祐介作品の魅力をひとことでなど言い表せないが、おおまかに「極めつけにハイクオリティのゲーム世界/ヴァーチャルリアリティ系」と「心の深淵を切ないほどに抉り出すヒューマンドラマ/モダンホラーまで含む」という幅でとらえるとするなら、この最新作はおそらくゲーム系。『クリムゾンの迷宮』や『新世界より』が好きだという読者なら、文句なしに、夢中になって読みふけるはず。極上の読書経験を保証する。さらに、ときおり垣間見える切迫感あふれる心理や人間描写のみずみずしさにも、思わずハッとさせられる。 冒頭、ダークゾーンという異界で、赤いオーラをまとった異形のキャラクターたちが目覚め、対戦相手は「青」のチームであること、それぞれを「チェスの駒」に見たてたゲームがスタートしたのだと告げられる。このへんの文章からして実にタイトでスタイリッシュ。また、イメージ喚起力の強いことときたら。ゲーム好きであれば脳裏にゲームの映像を思い浮かべ、映画好きなら映画、幻想文学好きならその手の小説、ハリポタ好きならハリーたちのあのチェスでの戦いの場面を思い浮かべるだろう。 将棋に生命をかけた過去を持つ主人公の心の綾と、断章で語られる登場人物たちの背景とそれがダークゾーンという世界に投げかける陰影の深さに、とても切なく、惹かれるものを感じた。個人的には、鬼才ギレルモ・デル・トロ監督作品『パンズ・ラビリンス』を映画館で観たときのような、妖しくもシャープで哀しい物語世界の創造を見せてもらった、と解釈している。自分自身のなかに、よく似た心の痛みを感じて、胸を突かれる思いもした。いままでの作品同様、これからさらに何度も読み返して味わうことになりそうだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 著者が狙ってそう書いたのかは解りませんが、将棋とロールプレイングゲームの融合は、ありそうで無かった設定ではないでしょうか。そこにミステリーの要素が加わり、全く斬新なエンターテイメントが生まれました。 この作品に於ける最大の見せ場は、帯にある謎めいた言葉に非ず。ヘックス(六角形の升目)を用いた戦闘シーンに他なりません。いくら優れた小説でも、平面的な描写に留まるのが殆どですが、この著者にかかればそれさえも覆ってしまうようです。三次元となって迫り来るリアリティに、気が付けば徹夜読み。王将の策略に嵌まってしまう自分がいました。今年、これを超える小説に出会う自信がありません。 唯一悔やまれたのは、ミステリーの部分の結末が、途中である程度読めてしまう事。ただ、それを差し引いても読む価値は十分です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「ダークゾーン」で目覚めたら異世界でいきなり戦闘! ……という、わけのわからない不条理なゲーム的状況から突然物語は始まります。 「赤の王将(キング)」として塚田は「鬼土偶・火蜥蜴・死の手・皮翼猿・一つ眼」という5人の役駒と6人の歩兵、6人のディフェンダーを従えて、青の軍勢と闘わなければならない。 敵方にも「青銅人・毒蜥蜴・蛇女・始祖鳥・聖幼虫」という特殊能力を持つ役駒があり、殺した敵駒は自軍の持ち駒として再生し活用できる。 ゲームのキャラクターのように異様な姿の駒たちは、どうも塚田の知っている人たちのよう。 「青の王将」を4回殺せば赤の軍勢の勝ち、「赤の王将」である塚田が4回殺されれば赤軍の負け。 塚田自身も、虹彩が4つある姿に変容し、戦いに負けるたびに4つの視力が一つずつ奪われていく。 味方の一人「死の手」は塚田の恋人であり、敵軍の大将である「青の王将」は塚田がプロになるための将棋のライバル。 そして、小さな島のようなこの異世界は、塚田が過去に来たことのある軍艦島に酷似している…… ダークゾーンにおける塚田の8つの凄惨な「対局」と、ダークゾーンにくる前の世界の8つの「断章」とが交互に語られます。 短い断章では、棋士を目指す塚田の日常生活を描きながら、ある事件の真相が少しずつ明らかにされていきます。 なぜ自分たちはこんな不条理な世界にいるのか?……という謎に対するオチは好き嫌いが分かれるかもしれませんが、それよりも、手に汗握る頭脳戦こそが本書の醍醐味。 まさに『クリムゾンの迷宮』『悪の経典』『新世界より』のバトル場面だけを抽出したような感じです。 なにかのインタビューで好きな作家と作品として、山田風太郎の『甲賀忍法帖』を挙げていた作者。 『甲賀忍法帖』も伊賀vs甲賀、両陣営の異能力を持つ忍者たちのチーム戦。 『悪の経典』で山田風太郎賞を受賞した作者の「忍法帖」へのオマージュのようにも感じられました。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!