■スポンサードリンク
薔薇の名前
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
薔薇の名前の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.19pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全117件 61~80 4/6ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| キリスト教を信仰している方や、聖書の知識・キリスト教史の知識がある方は問題ないかもしれませんが、その辺りの内容が分かりづらいです。 しかし、とても面白かった。 その時代に思いをはせながら、じっくり腰を据えて読みた1冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私には上下巻で長かった物語でした。 描かれている世界観、僧院の風景等、いろいろとイマジネーションがわく作品でした。 映像化されているので、そちらを見てみたくなりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説の背景がキリスト教神学と修道院でありとても難解且つ複雑であったが、当時の社会情勢も懇切丁寧に 描かれており良かった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 上巻の感想と同様であったが、DVDを見れば理解し易いと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ”全宇宙とは、神の指でかかれた一巻の書物である・・” ウンベルト・エーコが、古書店で見つけた書物(メルクのアドソの手記を、ある修道院長が書き写したもの)をイタリア語に翻訳したもの、という体裁である。手記の内容は、年老いたメルクのアドソが、見習い修道士だった頃に、北イタリアの修道院で起こった事件、名も知らぬ農家の娘との一夜などを回想するものとなっている。 物語は中世。日本の南北朝時代に、朝廷が南朝と北朝に分裂したように、ヨーロッパでも、カトリック教会が分裂した時代があった。ローマとアヴィニヨンで別々の教皇が立てられ(その後。3人に教皇が増えたりするが、1417年マルティヌス5世の選出で終息する)、異端審問や魔女狩り、宗派論争で混沌とした時代があった。それらを超克して、ヨーロッパはようやくルネサンスを迎えるが、物語は、分裂以前の疑心暗鬼な時代を描いている。 パスカヴィルのウィリアム(フランチェスコ会修道士)とメルクのアドソ(ベネディクト会の見習い修道士)は、ホームズとワトソンの役柄である。ローマ教皇庁と皇帝派は、かねて世俗の権利をめぐって争っていた。教会の清貧を説くフランチェスコ会は、皇帝側の支持を得ており、教皇から危険な存在と思われる一方で、同じカトリック宗派として、ローマ教皇庁との関係悪化を避けたいとも考えていた。アヴィニヨンのローマ教皇庁で、フランチェスコ会の総長ミケーレと教皇側との会談が組まれることになったが、アヴィニヨンでのミケーレの身の安全を確認する(最悪の場合、そのままミケーレは捕縛され、異端者として処刑される危険があった)ために、両派に中立な場所にて、予備会談をする必要があった。北イタリアのベネディクト会修道院が選ばれ、フランチェスコ会総長ミケーレとベルトランド枢機卿が会談をすることになった。その準備として、フランチェスコ会からパスカヴィルのウィリアムが派遣されたのだが、到着の前日に、修道院では修道士が死亡していた。何しろ大事な時期である。その死亡事故の調査を、修道院長から依頼され、ウィリアムは引き受けることになったが、事件は止まらず、修道士の怪死が続く。 やがて、修道院に教皇側の一行が到着。枢機卿のほか、冷酷な異端審問で名をはせたドミニコ会修道士ベルナール・ギー、枢機卿の護衛と称して、精強なフランスの弓兵隊などを連ねていた。予備会談の最中にも事件が起こる。異端者の発覚と”告白”、修道士の怪死が結びつき、フランチェスコ会と教皇との調停は失敗する。ついにミケーレの身の安全は保証されなかった。教皇側一行が修道院を去った後、ウィリアムは殺人事件の調査に本腰をいれていく。迷宮構造となっている文書室の秘密の部屋。キリスト教世界では到底受けいられないような内容が記された書物をめぐり、事件が繰り返されていく。謎解きは、記号だらけ。 映画版よりも当然、活字の方が内容は濃い。特に、異端審問で裁かれる側は哀れである。多くの平信徒は、異端と正統の区別が付かない。苦しい日々をなんとか過ごしている人の素朴な信仰と、教会の財産や権威は、どこかで対立するものなのだ。その対立軸において、「笑い」がひとつの鍵である。写字室での、ホルヘとウィリアムの会話が、その後の展開(というか、もっと言えば、中世の暗黒から、ルネサンスへの道筋)を暗示している気がした。異端審問がそうであるように、「恐怖」を煽り、支配するためのツールとして利用する。一方、「笑い」の背景にあるものは、もっと自由な批評精神である。権威とかではなくて、社会風刺のような「笑い」にこそ、開かれた人間の進歩がある。ウィリアムは、文書を読むために老眼鏡を利用している。迷信だらけの世の中で、とてもユーモアがあり、科学的である。世の中が暗く感じるときに、「恐怖」からは何も解決はされず、むしろ、その状況を「笑い」で克服することが、大切なのだ。「笑い」とは科学的手法の源泉なのかも。物語の後半クライマックス。<アフリカノ果テ>で、一連の怪死事件の黒幕と対峙した際の会話シーンで、なぜかマイケル・ムーアのドキュメンタリー映画『華氏911』や『シッコ』などを思い出した。ドキュメンタリーとはいえ、かなり風刺が効いている。(映画の内容はホントだとしたら、)悲惨な現実を跳ね返すには、「笑い」は強力なツールになる。そして、為政者が、いかに国民に「恐怖」を植え付けるのかが描かれる。現代も、中世と構造は変わらないのだなぁと感じた。スターリン時代然り、北朝鮮然り。それと比べれば、アメリカ合衆国や日本は、ルネサンスである。多様な意見が、堂々と言え、自由な勉学が可能なのだから。とはいえ、自由すぎるのも苦痛だ。命がけで、貪るように知識を得ようとした、14世紀のカトリックの修道士たちが、今日の、情報の氾濫を目にしたら、どう感じるだろうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 友人の面白いとの薦めで読みました。 中世14世紀の僧院での怪事件をホームズ役フランシスコ会修道士とワトソン役のベネディクト会見習い修道士(物語の語り手)が解決する話。 そこに宗教的な事柄が多数絡められています。カトリックの派閥対立とか、異端とは・清貧とは何ぞや?とか。 難しい(かつ失礼ながら興味を持てない)話が多く出てくるし、登場人物が外人名だから誰が誰だかわかりにくい(だから登場人物表しおりが付いてる)ので、正直読んでてツラかった。 最初のはしがきとプロローグでいきなり挫折しそうになり、オイオイっこれ本当にオモロイのか? と心配になってアマゾン書評をみたら、評価高かったので安心したぐらい。 下巻のアマゾン書評数が上巻に比べて少ないのは、上巻で挫折した人が多いからか? 友人が最初はあえて上巻しか持って来なかったのも、挫折を予測してたから? などと邪推してしまった。(その推理は正しいのかもですが...) 宗教的な問答では、キリストが笑ったか? の論争とか。 (それなりに笑ってたに決まってるやろっとツッコミながら読んでた) それに対する言で 「きっと笑わなかっただろう。なぜなら、神の子の名にふさわしく、全て知っていれば、私たちキリスト教徒が後年にどのような事をするのかぐらいはお見通しであっただろうから...」 なんてのは深いなぁと感じた。 上巻2/3頃からやっと面白くなってきた...と思ったら、下巻でカトリックの派閥対立話等でまたやや辛くなり、 なんかよくわからん動機(中世キリスト教の世界では十分に動機たりえるそうです)の主犯との攻防でやや盛り上がって終了。 「最も残酷なのは、自分の事を正しいと信じて疑わない人である」なんて言葉を強く思い出す内容でした。 薦めてくれた友人に対してもね... 推理小説はあまり好きでないし、キリスト教にも興味ないから、通常であれば120%読むことはない本なので、 そういうの読んで視野を広げれたという点は良かったです。 それにしても色々な事柄に対する表現がくどいなぁ〜と感じました。 まぁ正直なところ、 オモロイ箇所 <<<・・・<<< ツライ箇所 ということで、★★☆☆☆ とさせて頂きます。 理系・日本史専攻・仏教徒の評価とお考え下さい。 それから、この作品はショーン・コネリー主演で映画化されてるそうです。 ショーン・コネリーは好きなんでちょっと見てみたくなりました。 あと、解らない言葉や読み不明の漢字が多数だったんで調べながら読みました。 解らないことをWikiで調べたらドンドン派生して、そっちが止まらなくなったりしてました...。 まぁ勉強にはなったけど。 以下が調べた語の一部です。 ---ティンパヌム--- 建物入口上にあり、横木とアーチによって区画された装飾的な壁面のことで、半円形か三角形をしている。 ギリシャ・キリスト教建築においては、ティンパヌムに宗教的情景が描かれているのが通例。 (上巻最初のティンパヌム描写がやたらくどくて辟易した...) ---修道会--- キリスト教の西方教会における組織。カトリック教会においては教皇庁の認可を受けて、キリスト教精神を共同生活の中で生きる、誓願によって結ばれた信徒の組織。修道会の会員は修道者といわれる。 ---フランシスコ会--- 13世紀イタリアで、アッシジのフランチェスコによってはじめられたカトリック教会の修道会の総称。無所有と清貧を主張したフランチェスコの精神にもとづき、染色を施さない修道服をまとって活動。 居住する家屋も食物ももたず、人びとの施しにたよったところから「托鉢修道会」ないし「乞食僧団」とよばれ、どの教会管区にも属さず、ただローマ教皇にのみ属した。 ---ベネディクト会--- 現代も活動するカトリック教会最古の修道会。戒律は「服従」「清貧」「童貞(純潔)」。ベネディクト会士は黒い修道服を着たことから「黒い修道士」とも呼ばれた。 ---癩病人(らいびょうにん)--- ハンセン病患者のこと。この名称は差別的と感じる人が多いために、歴史的文脈以外では、一般的に避けられている。 この本では病気により社会から隔絶された人々を示して使われています。 聖書にでてくる皮膚病がどの病気を指しているのかは諸説あるそうで、聖書での最近の訳はこの語を使わずに「重い皮膚病」としているそうです。 ちなみに、ハンセン病の伝染力は非常に低く、治療法が確立しており、重篤な後遺症を残すことも自らが感染源になることもないとの事。 ---枢機卿--- カトリック教会において、教皇の助言者たる高位聖職者。教皇選挙権を持つ。 ---アナーニ事件--- 1303年、フランス国王フィリップ4世がローマ教皇ボニファティウス8世をイタリアの山間都市アナーニで捕らえた事件。 アヴィニョン捕囚を引き起こして教皇権に対する王権の優位を確立した。 この事件・結果は教皇権力の衰退と王権の伸張を印象づけ、近世絶対王政にいたる重大な一里塚となった。 ---アビニョン捕囚--- キリスト教のカトリック・ローマ教皇の座が、ローマからアヴィニョン(フランスの南東部に位置する都市)に移されていた時期(1309〜1377年)を指す。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 下巻はさすがに読ませどころが多い。いや、読む人が読めば読ませどころは全編に横溢しているわけだが、ひたすらエンターテインメントを求める向きには、その仕掛けがもどかしい。そんな僕のようなけしからん(?)読者にとっても、下巻は読ませどころが多いのだ。 実在した異端審問官ベルナール・ギーとの対決、徐々に全貌を現す玉虫色の真相、そしてカタストロフィー。最後のそれに、俗人である僕は横溝正史の『八つ墓村』を思い出さずにはいられない。うん、ストーリーだけ見るとこれは『八つ墓村』だな。記述者アドソのビルドゥングスロマンであり、師となるウィリアムはホームズというより金田一耕助だ。 つまり、ミステリとしての仕立ては実に“記号的”である。分かりやすい。その砂糖菓子のような骨組みに、目が眩むような知のデコレーションが重層的に施されている。作者のたくらみには文字通り「舌を巻く」が、それを味わい尽くすほどの肥えた舌を僕は残念ながら持っていなかった。だからせめて、「こういうものを面白がる人たちもいるんだ」という理解は示しながら、読み飛ばしていった。例えるならそれは「現代音楽を鑑賞する姿勢」に近かったろう。 読了後、ジャン=ジャック・アノーの映画をあらためて観ると、難解な現代音楽を実に要領よく咀嚼しているなあと感心した。もちろんそこに物足りなさを覚える原作ファンはあるだろうが、これだけの作品世界をいちいち具体的な「画」に置き換えていった丁寧な仕事には、頭が下がる。なんてことは映画のレビューに書くべきですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 好みでいえば、好きなタイプの小説ではない。現代アメリカ文学の大家ジョン・アーヴィングを枕頭の書とする僕は、圧倒的な物語が展開するディケンズ的な小説が好みだ。だから、モダニズム文学の首魁ジェイムズ・ジョイスみたいな「知の叙事詩」ともいうべき小説は、好みではないのである。本書をジョイス的と呼ぶのはいささか乱暴という気もするが、エーコはジョイスに大きな影響を受けているらしいので。 それでも本書を読もうと思ったのは、ミステリファンとして踏破しないわけにはいかないひとつの高峰であることは確かだから。そしてシャーロキアンとしては、ホームズもののパスティーシュにやはり関心を持たないわけにはいかなかったから。もちろんパスティーシュとか、あるいはメタミステリとか、そういう分かりのいいレッテルを貼って片付けるにはあまりに手ごわい小説であることは、充分承知している。 今、上巻を読み終えてこのレビューを書いている。キリスト教史や中世の西洋史、哲学、思想などの知識があるほうが楽しめる、というのは多くの方がここで書いておられる通り。もちろん知らなくてもミステリとして楽しめる、というのもまあその通りだろう。しかし予備知識はいらないにしても、それらに対する興味、関心、好奇心はあったほうがいい。僕には正直それらが欠如していた。「分からないことは分からないでいいや」というスタンスで読んで、結局少々退屈なまま上巻終了。 でもひとつ思ったのは、宗教上の相克において何が異端で何が正統か、また何が善で何が悪かというようなことは、何が残って何が残らなかったかという問題に過ぎないのではないか、ということ。圧倒的な情報量に触れながら、たったそれだけのことに感心しているのは情けない気もするけれど、下巻のミステリとしての面白さに期待しつつこのへんで―― | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 映画はずいぶん前に見ていたのですが、本は難解そうで敬遠してました。 知り合いのイタリア人が「絶対読むべき本、エーコは読者を選ぼうとして最初の数ページはわざと難解に書いている」と聞き、挑戦しました。 これを聞いてなかったら、最初の数ページで本当に振り落とされそうに。 でもそれをこれをのり超えると、これでもかというほどの、知的な会話が展開されもう夢中になりました。 それは禅問答にもつうじるものがあります。 読んでいるというよりは、ウイリアムの傍らで聞いている・・自分も参加している臨場感! 中世ヨーロッパや宗教論に興味がなくとも充分楽しめます。 読んでる途中から、再読したくなる本、一度目はこの会話を楽しみ、次は実際に議論されてることを学びたい気持ちに。 借りるのではなく、蔵書したい本です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本を読む楽しみをこれほどまでに、味わえる書はざらにないだろう。しかも、サブテーマとなっているのも、書に対する愛である。恐れ入りました。しかし、いかんせん、この作者は作家としての活動が短すぎた。惜しまれる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私も含めて日本人はあまり深く知り得ない時代背景がとても楽しいです。 「磁力と重力の発見」の全3冊の中の2巻にルネサンス初動期の話もあわせてお勧めします。 この物語の背景になっている、ヨーロッパでは失われアラブ世界で保存されていた アリストテレスのなどギリシヤ哲学の知とアラブ世界の技術的な知などを いっきに吸収しはじめた、まさに知の変革期です。 この事件の起きた理由、時代に反発する黒い影が何故そんなに抵抗したのかも納得できます。 物語の主人公の師ウィリアムはシャーロックホームズばりの 実証的な捜査方法を取りますがこれは、この時代に初めてあらわれた実験で 物事を検証しようという科学的な姿勢と深くかかわってます。 何がいいたいかと言うと、時代背景がわかると何十倍もおもしろく エーコがまさに「私はこの時代で描いた」と言った意味もズシンとくると思います。 手始めに「磁力と重力の発見」山本義隆著はものすごくお勧めですっ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| オリジナルは1980年リリース。邦訳はかなり遅くて1990年1月25日リリース。ミステリーの世界で孤高の存在である本作は、ミステリー読破を目指す者にとっては百名山の如く、踏破せずには死ねない一冊とされ、読了後、その思いはますます深まった。作者ウンベルト・エーコは、イタリアの記号論哲学者、小説家、中世研究者として有名だが、もういくつか加えて説明しておくと、エーコの卒業論文は『聖トマスの美的問題』であって、この作品の時代である1327年というのは彼の最も専門とするところである。そしてもう一つ、『三人の記号 デュパン、ホームズ、パース』という本をトマス・シービオクと共著していて生粋のシャーロキアンでもある。 何と言っても圧巻なのはその構造だと思う。生粋のシャーロキアンらしく、主人公に『バスカヴィル』のウイリアムとその弟子(助手)アドソを配しているが、誰しも連想するのはシャーロック・ホームズとワトソン博士だろう。そして長老には、『幻獣辞典』等で有名なホルヘ・ルイス・ボルヘスから取ったと思える盲目の師ブルゴスのホルヘを設定している。また、実在の人物である有名な異端審問官ベルナール・ギー(ドミニコ会士)やフランシスコ会士カサーレのウベルティーノを登場させてくる。原書はラテン語・ギリシア語・中高ドイツ語の原語のセンテンスやフレーズがその原語の表記のまま使われていて、その上に中世キリスト教の在様が重畳的に組み合わされる。正に知の迷宮とも言えそうなストーリーである。 ストーリーについては未読の方のために触れないが、強く感じるのはウンベルト・エーコの『本』に対する愛情だ。中世修道院のスクリプトリウムの文書館3階の構造などは正にエーコの想像した『本の宇宙』のようですらある。その本の宇宙を彷徨うウイリアムとアドソはまるでその宇宙を彷徨うのを楽しんでいるかのような感じすらする。『キリストの清貧』や『キリストにおける笑い』そして『薔薇の名前』の意味における謎など、仕掛けられた知の迷宮の素晴らしさに『恐るべしウンベルト・エーコ!』と唸ってしまう。やはり読まねば死ねない一冊である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 名訳との世評をずっと疑ってきた。驚くほど大量の初歩的な訳語・表記の選択ミスがあるからだ。大家といえども教養に限界はあるのだから責められないとも言えるが、最小限に抑える手はあったはず。現に、最新作『バウドリーノ』は歴史学者がチェックしたと仄聞する。それくらいのことをしないとエーコの学識には拮抗しえない。 重版のあいだに訂正はされているのだろうか。版元は早急に徹底的に手入れをした文庫版を出す義務がある。訳者が偉すぎる、あるいは偏屈にすぎるとこういう仕儀になり、読者がワリを食うという悪弊の典型である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読んでよかった! 八重洲の丸善(オアゾ)には、松丸本舗という、書店内書店がありまして、松岡正剛氏がプロデュースしているわけですけど、ときどき、ここへ行くと、めまいに襲われることがあります。まさに、知の迷宮といった様相です。 「薔薇の名前」に登場する迷宮とも、通じるような気がしました。 で、「薔薇の名前」。 書き手が名も無き女性と寝てしまう(修道士なのに!)というところから俄然、おもしろくなります(読み手が下世話だから……)。この本は宗教、善と悪の問題、富と貧困の問題、さらに男と女、そして性の問題を扱っています。その点で、「ダ・ヴィンチ・コード」も、基本は男と女、性の問題と宗教をからめたテーマだったと思い出しました。同じようなテーマだけど書き方はまったく違います。 例えが悪いですが、「ダ・ヴィンチ・コード」をダ・ヴィンチの時代の人が書く、という設定にすれば、「薔薇の名前」みたいになるだろうと思います。 面倒な「清貧論争」の部分であるとか、宗教と「笑い」の議論なども出てきて、読者はあっちこっちに振り回されます。 中世は暗黒時代というよりも、宗教と国政、階級と自由のせめぎあいが行われていたんだなあ、と感じます。異教徒と戦う以前に、同じキリスト教内での覇権争いが激しく、そこに国王(兵士を要している)との関係がからむからややこしい。 国王は法律を作り、民をおさめ、軍事力を増強し、商業を活発にします。一方、宗教は人々を安定させ、一つにさせる一方で、異端者を排除しようとします。でも、異端者を排除する一方で、異端者の力を借りて国力を増強させようと考える王もいたでしょう。そこで、宗教レベルの戦いと国レベルの戦いが、人々を巻き込んでいくわけです。 ここに登場する名も無き薔薇、つまり村の女性のように生きることに必死で無学な人々に対して宗教は開かれた存在ではなく、そうした人たちを飛び越えて、教義は、国法の上に位置していることになります。 司法が裁く前に宗教が裁くのです。「そんなことは知らない」と言っても、どうにもならない。ひどい話です。 その後、近代国家になるときに、私たちは諦めたんですね。宗教と現実を統合するわけにはいかない、と。 で、この割り切りによって、法律を中心とした法治国家が主となっていき、やがてはその法律をも人々の手によって民主的に作ることが可能になっていった。権力を国王だけに集めず(当然、宗教だけにも集めず)、分散しようとした。同時に人々は教育の重要性に気付き、幅広い教養を身につけるようになっていく……。 「わたしは記号の真実性を疑ったことはないよ、アドソ。人間がこの世界で自分の位置を定めるための手掛かりは、これしかないのだから」(下巻 P371) と、バスカヴィルのウィリアム(フランチェスコ会修道士)は言います。これは著者の言葉でもあるのでしょう。 たまたま、清貧論争にも興味があったので、この本には当時の宗教と政治の関係が、いろいろ綴られていて、そこもおもしろかったですね。1300年代にもなると「キリストは財布を持っていた」とか「キリストは笑わなかった」といったテーマで、深刻な議論が起こっていたと本書はのべています。 このあとに、ルネサンスが起こるんですね。 しかしながら、日本では私も含めて、面食らうような宗教観、歴史観によって作られた舞台で起こるミステリーですから、最初はなかなかとっつきにくいかもしれませんが、刺激的な作品です。 なお、この作品中でしばしばウィリアムが言及するロジャー・ベーコン(または、ロジャー・ベイコン、Roger Bacon)の本は、日本語ではズバリという翻訳書がなさそうです。どういう文脈で飛行機などを予言したのか、確認したいところですが……。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 1990年初版のロングセラーである本書ですが、気になる点が一つ。 相前後して上下巻を購入したのに、 上巻には【38版】、下巻には【30版】との奥付が。 8版の差が何部なのかは分かりませんが、 上巻だけで読むのを断念した方の数字が含まれていることは間違いなさそう。 だとすれば残念な話で、できれば上下巻読破してもらいたいもの。 そんなことを念頭に、本レビューを綴りました。 【やはり事前準備は必要なのでは…】 1327年にイタリアにある僧院で起きた、 奇怪な連続殺人事件の謎を巡る本書ですが、 小説の記述には、注釈はなく、 当時の政治的・宗教的な背景をある程度知っていることが 前提に書かれているように思えます。 ネット検索でも結構ですので、 軽く下調べをしてから読むことをオススメします (もちろん紙ベースの資料を当たっていただいても結構です)。 ちなみに、本書の文体そのものはそれほど難解ではないと思いました。 学術論文ではなく、あくまで「小説」として書かれていますから。 【映画を観てから読むのも一興】 本作品は映画化され、1987年に日本公開されています。 原作が翻訳されていなかった当時、私は劇場に足を運びました。 私は映画を観たうえで、小説を読んだわけですが、 映画で物語の結末を知っていても、 原作小説の面白さが損なわれるということはなかったと思います。 むしろ私は、犯人や犯行の手口は記憶していても、 肝心の「動機」を忘れてしまっていたため、 原作小説でその深い意味合いを読むことができて良かったと思います。 この「動機」、宗教的な理由に基づくものなのですが、 映像ではうまく伝わりにくかったのでは。 −−というのは、自分の記憶力の悪さを棚に上げた意見かもしれませんが。 (下巻に続く) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (上巻からの続きです) 【ある意味で膨大な無駄のある小説だが…】 本書は、下調べをしてから読んだ方がよい、と先述しましたが、 じつはこの小説、ミステリとしての筋立てを追うだけなら、 物語の社会背景など知らなくても読むことができます。 何やら難しげな宗教論争の場面を斜め読みしても、 どんな事件が起き、犯人は誰で、といった ミステリとしての骨格は読み取ることができるでしょう。 でも、それではこの作品を楽しむことはできないのではないかと思います。 歴史的には短編として誕生した推理小説ですが、 近年書かれるようになった本書のような大長編推理小説は、 ミステリとしてのストーリーとは別に、 物語の世界を構築するために、 作者が大量の言葉を尽くして記述するという傾向があるように思います。 それは、ミステリの本筋だけを楽しみたい読者にとっては 無駄な記述に映るでしょうが、 こうした作品はミステリの骨格に纏わされたかなり厚手の衣 −−作者が構築した作品世界に身をゆだねながら、 謎解きを楽しむという読み方ができると思いますし、 それも推理小説の楽しみ方の一つといえるのではないでしょうか。 日本の作家では京極夏彦の京極堂シリーズがそうした傾向の作品だと思います。 【薔薇の名前という題名について】 なぜ本作品の題名は、「薔薇の名前」なのか。 その表層的な意味(登場人物の誰かを指している)は、 すぐに理解できるところですが、 それ意外にも深い意味が隠されているようです。 その点は、「普遍論争」をキーワードに調べてみると より一層本作品を楽しめるのではないかと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 記号学の泰斗が書いたミステリとして著名な作品だが、読む前から単なる衒学的作品ではないかと言う懸念があった。初っ端からその不安が的中する。14世紀のイタリアを中心とする中世ヨーロッパ史、特に宗教史について造詣を持たない読者は門前払いと言う態度なのだ。また、探偵役の修道士ウィリアムの観察眼や推理法はホームズもののパロディで、この点でもガッカリさせられた。作者が本当にミステリを書こうとしたのか否か疑念が湧く内容で、作者自身の宗教史観・記号学の自省的考察を披瀝するために戯れに物語を捻り出した感が強い。 岩壁沿いの修道院で起きる事件の模様は殆ど語られず、代りに読者は当時のキリスト教諸派の対立や神学上の解釈の相違や院内の衆道関係等を延々と聞かされるハメになる。そして、修道院内の建物には秘密の通路が複数あったり、"魔法の薬草"や鏡で幻覚を起こす等、子供騙しの手法が堂々と使われる。表面的にはペダンティックな装いだが、内実は子供向けの冒険小説の趣きである。作者の専門を活かした筈の暗号も断片的過ぎる上にコケ脅しで、現代暗号理論からすれば幼稚極まりない。作中で強調される"迷宮"に陥っているのは読者や探偵役で無く、作者ではないかとの思いを強く覚えた。キリスト教における異端論争・教義対立などミステリ・ファンにとっては興味の埒外である事は自明だろう。 結末に到ってもミステリ的趣向が皆無で、徒労感・脱力感しか覚えない。ミステリを知らない碩学の書いた壮麗なる駄作と言えよう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 教皇とフランチェスコ会の教義をめぐる対立、会内部での暗闘。さらには皇帝を後ろ盾としたフランチェスコ会は、教皇側と、有数の文書庫で名高い修道院において、会談を持とうとする。フランチェスコ会の使節団の一人として、修道院に到着したパスカヴィルのウィリアムは、そこで一連の殺人事件に出会うことになる。 通常のミステリーならば、読み始めればたちまちのうちに、以上の事情をたやすく察するだろう。だが本書の場合には、読者はその事実を把握するためには、溢れかえる当時の著名人士の名、ヨーロッパ史いや中世教会史上に著名な事件の連呼、列挙される異端の網の目等々、の間を泳ぎまわらなければならない。相当注意して読んでいても、改めて前のページを読み返さざるを得ないことが何度もあった。 一言で言って、大変読みにくい。だが、幹から横に伸びた枝の形は美しい、鋭い。細い枝に咲いた花は香しい。 懺悔とはどのようなものとして感じられるか。修道士にとって、女とは、どのようなものとしてありえたのか。そんなことに触れた個所がある。異端とはどのような形で生じるのか。庶民にとっては、どんな形で異端と出会うことになったのか。異端であるとは当時にあってどのようなことであったか。異端審問とはどんなものであったか。人は弱さにどのように対処したかが、恐怖に支配された時どうなるのかが述べられる。会派が、修道院がどのように相争うかが考察される。 確かに殺人事件は解決される。だが読み終わって感じるのは、一つの修道院の殺人事件の記述が、キリスト教の諸相の複合的な記述に重なっているということである。キリスト教の諸相とは、ヨーロッパの精神そのものであり、目をとめた文章の端々から、(キリスト教的)人間の全体が立ち上がってくる。どのページを開いても、興趣が尽きない本である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| かなり量のある文章、上巻のみで挫折する人も多いようです。 中世のヨーロッパ、僧院、それを取り巻く景色をイメージできないと 読み進めることは難しいでしょう。 しかし読み終えた後には、中世の世界をのぞいた満足感が得られると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「それを決める明確な基準はない」 「なしうる最大のことは、もっとよく見つめることだ」 「わたしたちの精神が想像する秩序・・・手に入れたあとでは、梯子は投げ棄てなければいけない。 なぜなら、役には立ったものの、それが無意味であったことを発見するからだ。 ・・・昇りきった梯子は、すぐに棄てなければいけない」 「見せかけの秩序を追いながら、 本来ならばこの宇宙に秩序など存在しないと思い知るべきであった」 「可能性を全面的に織りこんだ必然的存在・・・ 神の絶対的全能とその選択の絶対的自由とを肯定するのは、神が存在しないことを証明するのに等しい」 「過ギニシ薔薇(=神)ハタダ名前ノミ、虚シキソノ名ガ今ニ残レリ」 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

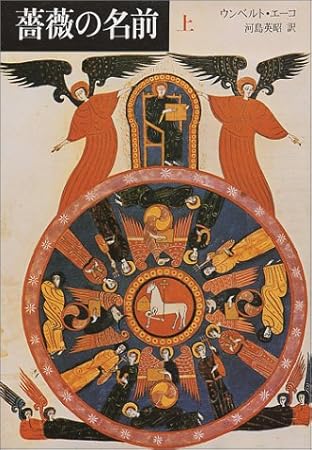



![薔薇の名前[完全版] 上 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51u3X3o71BL._SL500_._SL450_.jpg)
![薔薇の名前[完全版] 下 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51rmxbj67JL._SL500_._SL450_.jpg)
