■スポンサードリンク
薔薇の名前
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
薔薇の名前の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.19pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全117件 41~60 3/6ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 下巻に突入すると事件は連続殺人の様相を呈し始め、風雲急を告げる修道院、 100ページ付近からいよいよお待ちかねの悪役ベルナール・ギーが登場し物語りはがぜん活劇調を帯びてゆく(この娯楽性があったから映画化されたわけだ)、 異端信仰を隠し修道院に身を寄せていたサルヴァトーレの運命やいかに? ウィリアムとギーの宿命の対決に論理的決着はつくのか? 再三映画を鑑賞してしまっているので、さて、脚色と原作にどのような差があったのかばかりに注目して読み進んでしまう(読書としてはあまり健康的な読み方ではない)、 まだ途中だが小説に映画版のようなカタルシスあるクライマックスが訪れるのか楽しみでしょうがない(べつになくても何の問題もないのだが)、 冒頭の8ページに”使用人たちは十字を切って、魔よけの呪文を唱えた。”とある、 十字を切るとはキリストへの信仰だが、すると魔よけの呪文とは聖書にある言葉のはずだがそれは記されていない、 十字を切っただけでも魔よけになるはずだが、さて、魔よけの呪文はキリスト教の外、キリスト教浸透以前の古い呪術の名残か?などと考え始めるとすこしもページをめくれなくなってしまうまことに不健全で文字数は膨大だが実は中途半端な叙述ばかりにも読めてしまう、 上記のたった二十文字ほどを劇化するなら、どんな言葉を何語に発声するか決定する必要があるのである(ここで、おれは脚本家か?っと自分で突っ込んでおく)、 長い物語の大分を占める教義問答を読むと、英語の文脈で主義・主義者 -ism / -istと多用される淵源が教会にあったのだろうと想像できる、 日本の仏教でも宗派間の問答はそれなりに実施されてきたし、事実論敵を論難・論破した記録も残っているが、それが一般市民の思考なり会話なりにまで英語圏ほどには影響していない、 同じ阿弥陀如来を崇めながらも浄土宗と浄土真宗の一般の信徒・門徒達が他力と絶対他力についてあいてを強く非難するような日常をわれわれはもっていない(せいぜい、門徒物知らずと見下す程度のはなしだ)、 この稿未了、 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 梱包の袋が裂けて、中身が半分露出していました。商品に傷がなかったので受け取りましたが、以前もアマゾン便で届いた荷物の箱が破損していて、全開の状態だったことがあります。ほかの通販で梱包が破損していたことはありません。中身が見える状態で配達されるのが正常だとは思えません。傷がなければよいというのでもありません。今後アマゾンで注文をするかどうか、ためらいます。評価はゼロかマイナスでもよいぐらいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| と、P.102にある、 P.32には”神の意図はやがて聖なる自然の魔術すなわち機械の科学となって実現されていくであろう”とも記されている、 この物語の中ではウィリアムが語る予言だが、20世紀末を生きた著者が歴史を振り返った時の偽らない感想なのだろうと思える、 ロードショーで映画を見た後に一度読んで以来なので30数年ぶりに現在上巻を読んでいるが、当時感じた読みにくさを現在ではまったく感じない、 極度の衒学趣味部分もにやつきながら楽に読み進められるようになった自分にしょうしょう驚きもある、 衒学趣味を除去しても本作のミステリーとしての優秀さはいまでは古典化しているとも思う、 多くの読書家の感想に同じくシャーロック・ホームズ・ファンには必読作品だと思う、 そして映画化に際し練り上げられた脚本の素晴らしさにはいまさらながら深い感動を覚えてしまう、 訳文がめんどうな宗教用語や歴史に触れながらもとても読みやすく、14世紀が語られながらもまるで現代人が語っているようにしか読めないのは、さて、原文はどうなのだろうと疑問はあるのだが、 で、読み始めてまず驚いたのが、この物語が1968年に作者がアドソの著書を発見した体裁で書き始められている点だ、 つまり14世紀のアドソが観察した修道院の過去の出来事、それを読み解く20世紀の著者と三段構造になっているのである(より正確には17世紀の手記の発見、19世紀の手記の出版と入れ子構造がさらに複雑だが)、 映画はアドソの追憶としてのみ語られる娯楽映画らしいシンプルさだったわけだ、 1968年8月20日のソ連軍によるチェコ侵攻はハンガリー動乱に続いて共産主義の横暴を再度世界に知らしめた大事件だが、そのさなか持ち出された手記によって語られる本書の内容は?と考えると、もしやこれは「存在の耐えられない軽さ」と対を成している可能性を考えてもいいのかもしれない(存在の、、は小説も映画も未読未見なのでただの憶測だが)、 自然さえも制御してしまいたいと考える邪悪な政治思想である社会主義や共産主義がまだそれなりの支持を集めていた時代において、神の善良さを説く物語がなんらかの政治目的をもっていた可能性を読み取ることも可能だろう、 そして、笑いを封印してしまう教会の横暴さが異端審問と比べられる描写が下巻で繰り返されるのだと思う、 当時の王侯貴族が道化師を意図的に自らの傍に置き、自身を風刺させたような余裕がキリスト教にはなかったことになるのだが、この点は非キリスト教の価値観を歌ったロック・クラシックの中でも突出した名曲である"Stairway To Heaven"と"In The Court Of The Crimson King"を聞き込むべきと改めて感じてしまう、 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 28年前に、本書『薔薇の名前』を読んだ時には、ただミステリとして楽しく読んだようである。 その後、ショーン・コネリー主演の映画も観ているから、おおよそのストーリは把握していたつもりだった。 今回、再読してみて、著者エーコの才能の奥深さを思い知らされた(といっても全て理解できたわけではないが)。 理解できない理由の第一に、評者はキリスト教徒でないから聖書など読んだことなどないからである。 それに中世ヨーロッパの歴史に暗いからでもある(多少の知識はあるものの)。 今回この『薔薇の名前』を読み進みながら、事件の元凶が一冊の古書(アリストテレスの『詩学』の『第二部』)であることから閃いたのが、先に読んだ『哲学散歩』の「書物の運命 これもまた?」という章で下の・・・・・内のようなことを木田先生が述べていたからである。 少し長くなるが転載したい。 ・・・・・ <前文略>当然、しばらくのあいだは以前の著作とこの新しい著作集が共に読まれていたのであろうが、次第に「専門聴講者用」の著作に関心が集まって、こちらばかりが読まれ、以前の著作はほとんど散逸してしまったということらしい。 プラトンのように芸術的才能に恵まれていたわけでもないアリストテレスが、先生のまねをして書いた作品より、推論を積み重ねてゆく理論的著作、例えば『形而上学』などのほうが彼の本領であったにちがいない。 こうして、残るべき書物はどれほど回り道をしてでも残り、消えてしまった書物は所詮それだけの価値しかなかったのだ、書物にはそれぞれ定められた運命がある、というのがアリストテレスの著作の新旧交替劇についてのかっての定説であり、この交替劇は「書物の運命」なるものの好例とみなされてきた、と、私は長いあいだ信じこんでいた。<後文略>(『哲学散歩』P44~45) ・・・・・ このあと、このような思い込みは木田先生の思い違いだったと多くの例をあげて述べていたのですが・・・。 しかし、評者は『薔薇の名前』最後の7日目を読み進みながら、『哲学散歩』のなかで木田先生が述べてした言葉を想起してしまったのです。 蛇足ながら手練れのミステリフアンなら誰が犯人なのか?、何を使って殺したのか?、などは推理可能でしょう。 本書『薔薇の名前』は、読み手の知識があればあるほど知的好奇心を満たすだろうと思いながら読み終えたのです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 先に読んだ木田元著『哲学散歩』から触発され、もう28年も昔に読んだ単行本『薔薇の名前』を、本棚から取り出して読むことにした。 木田先生は、『哲学散歩』のなかでこのエーコの「薔薇の名前」について哲学者ならではの解説をしていたので興味深く読みました。 木田先生は、1987年に、この「薔薇の名前」が映画化され、1990年に、翻訳出版されたと語っていた。 が、評者は、この「薔薇の名前」を、本で先に読み、後から映画を観たのです。 本を読んだときには、中世末ヨーロッパの歴史的背景などほとんど知識(特にキリスト教について)がなく、ただミステリとしての興味だけで、それなりに面白く読んだのですが、映画も何度か観てから、本では理解できなかったことも多少知ることができたような記憶です。 木田先生の『哲学散歩』のなかの「『薔薇の名前』遺聞」の章を読んでから、この本を再読したのですが、なるほど碩学ならではの解説なので上巻を、より興味深く読み進むことになりました。 ルートヴィヒ4世 (神聖ローマ皇帝)、オッカムのウィリアム、ヨハネス22世 (ローマ教皇)、ロジァー・ベーコン、などなど歴史に実在した人物像なども調べながら再読すると興味津々で読み進むことになる。 ウンベルト・エーコの「隠し玉」には、木田先生も瞠目していたが、さすが記号学の権威と思えば納得です。 ただ、エーコの叙述の饒舌さに多少戸惑うところもあり、訳者がもう少し易しい同義語(単語の)を、選択してほしいと思ったのは評者だけだろうか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ・骨子は単純なのに修飾だらけでカオス状態 ・他の僧との宗教論争が多い ・中世暗黒時代の雰囲気は映画が上 ・迷宮図書館の構造と設計意図がよくわかる | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ダンブラウンが好きで、新作が出るまでの繋ぎにと読み始めたものの…難し過ぎる説明が延々と続く為、頭の良くない私的にはその時点で眠くなってしまう。誰かもっと簡単に説明して!そもそもこの長ったらしい説明とか必要?と思ってしまう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 記号論者であり思想家であるエーコは、メディアのディテールを惜しみなく披露するので、読んでいて興味深いです。 本書は主に西洋に関する宗教史を追っている言語のメディア性について論じていると思うのですが、 それはすでに崩壊され、再生するのは困難で、再生などしない方がいいとエーコは言っていると思います。 日本の無宗教の家に生まれた私からみると、カオスな状態が当たり前なのですが、世界はまだ宗教戦争が終わっていないとも言えると思います。 ですから、本書はすごく真っ当で、読み継がれてほしいとも思うのですが、思想史や言語学の分野は堅苦しい用語を覚えることから始まりますので、このように文学として読まれた方が面白いかもしれません。 本書はエーコの中世言語エンタメワールドを感じるにふさわしい一冊であり、私は中世を思い浮かべる時に、いつもエーコのこの世界にタイムスリップしてしまうほどトラウマになりました。 エーコの厄介な文章に中毒性を持ってしまった方、エンタメ性よりもよりエーコのエッセンスを感じたい方は「完全言語の探求」も読まれることをおすすめします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 記号論者であり思想家であるエーコは、メディアのディテールを惜しみなく披露するので、読んでいて興味深いです。 本書は主に西洋に関する宗教史を追っている言語のメディア性について論じていると思うのですが、 それはすでに崩壊され、再生するのは困難で、再生などしない方がいいとエーコは言っていると思います。 日本の無宗教の家に生まれた私からみると、カオスな状態が当たり前なのですが、世界はまだ宗教戦争が終わっていないとも言えると思います。 ですから、本書はすごく真っ当で、読み継がれてほしいとも思うのですが、思想史や言語学の分野は堅苦しい用語を覚えることから始まりますので、このように文学として読まれた方が面白いかもしれません。 本書はエーコの中世言語エンタメワールドを感じるにふさわしい一冊であり、私は中世を思い浮かべる時に、いつもエーコのこの世界にタイムスリップしてしまうほどトラウマになりました。 エーコの厄介な文章に中毒性を持ってしまった方、エンタメ性よりもよりエーコのエッセンスを感じたい方は「完全言語の探求」も読まれることをおすすめします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 記号論の勉強を始めようという矢先に読んだ。正直なところ私は彼の論述スタイルを存分に楽しめる性分ではない。彼の文章は以前に一度だけ触れたことがあるがその時も同様に感じた。それはつまり、固有名詞の列挙を楽しめないことだ。本当にそれを味わおうとすれば一語一語検索していかねばならない。その観点から見て、翻訳にも若干の不満が残る。例えばいくつかの漢字に対して、3回目の登場の個所ではふりがなをふっているのに、最初の登場箇所にはふりがなをふっていなかったりする。もちろんこれは、それらの事物をよく知っている教養豊な人々なら存分に楽しめるということを意味する。 まだ一読した限りであり、一体なにを受け取ったのか、判然としない段階で言うとすれば、私が最も興味を持った側面はおそらく異端審問だ。現代にも異端審問は広く行われていると言ってもいいだろう。いや、むしろ異端審問が行えなくなってしまった時代だともいう方が正確かもしれない。もはや赤狩りは存在しない。次なる異端を探し求める欲望が渦巻いているように思えてならない。そこで笑いはある閾を通り越し、ほとんど嘲笑と暴力の道具と化す。本当に歴史は単に繰り返されるのか。 こうして私にさらなる書物を求めさせるという点において、この書物は成功していると言えるだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『薔薇の名前』というのは20世紀を代表する小説らしい。らしい、というのはそれほどの作品なのならば私はとうの昔に知っていたはずなのだが、文学を読み始めて10年近く経ったにも関わらず、知ったのはつい最近だからである。確かに読み手は海外文学であるにも関わらずかなりいる。にも関わらず知らなかったのは、作品は20世紀の中でも後半に位置づけされるからか、とも考えた。あと、英独仏ではなく比較的マイナーなイタリア文学に分類されるから、というのもあるのかもしれない。 まあ、そう色々考えながら私はこの作品を手に取り、最後まで読んだ。 読み終わってみると、私は何とも言えない気持ちになった。この作品をどう評していいのかわからないのである。作品の基底にあるのは、推理小説的なものである。ある僧院において誰かが殺された。そしてその犯人は誰なのか、ということを推理していくものである。しかし、この作品は推理小説に単純に分類していいものではないこと位、読めば誰でもわかるだろう。歴史的な話が加わり、なにやら神学的な話、植物学的な話、といった学術的な話が色々と加わっていく。 この作品は歴史的背景を知っておかなければ楽しめないだろう作品なのだが、私は歴史的背景をつぶさに知っておかなければならない作品をそんなに評価したくない。確かにそういった背景を知らない非は私にもあるだろうがそういう歴史的な説明が必要なものを高評価下すことはどうしてもできない。いや、正確には作中においても説明されている(かもしれない)。だがあまりにも長々としておりとても頭に入ってこない。他の学術的な話も多々入るが、私は物語上の必要性はあるのか、と疑問に思った。 確かにこの作品は全く持って凡庸ではない。才能を持った人間でなければ決してこの作品を書くことができず、それ故天才の作品であるといっていいだろう。だが、私は正直楽しめなかった。脱線としか思えない学術的な話が多いし、結局なんで殺人が起きたのか私には把握できなかった。前衛的な作品でその意味で現代的な作品、といえよう。 だがネットのレビューをみるとかなり評価は高い。それ故私の感性がずれているのかと自分に疑問を呈する。まあ別にずれているのならばずれているので構わない。私のレビューもまた一人の読み手のレビューということで。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 改めて、あの映画はこの結構な長編を素晴らしい映像に描き出したと感服。そしてこの名作。何度も何度も、深く多彩に、広く幾重にも思考が伸びていく。ハリー・ポッターならなんとか…の私の英語力では、こちらは今はない言葉遣いや習慣、宗教の専門用語が多く、原作読破は厳しかったので、真摯な翻訳には感謝。 この時代は…と思いかけて気付く。 いや、問題の本質は、現在もたいして変わりはしないことに…。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中世のイタリアの修道院で謎の連続殺人が起こり・・・といいうお話。 この小説に関しては原著刊行や日本に翻訳されてから色々散々言われてきてそのどれもが適切な論評だと思うので個人的な感想を書かせて頂く事にしたいと思います。 まず、推理小説としてはその枠組みを利用してはいますが、厳密に言えば推理小説とは言えない、というかアンチ・ミステリーに分類されるべき作品ではないかと思いました。日本で言えば中井英夫の「虚無への供物」に当たる様な作品だと思いました。勿論、推理小説としても良く出来ていて殺人の動機や謎の手がかりである「アフリカの果て」を巡る暗号の解読、迷宮の文書館等はスリリングで知的興奮を煽りますが、一般の推理小説とは位相の異な推理小説風哲学小説に思えました。 次に作品の骨子になる「キリストの清貧」に関する論考は興味深くはありますが、個人的に私が信仰心が無く、キリスト教もあまりよく知らないので些か読むのに苦労したことを告白しておきます。著者がこの小説で一番言いたかった部分であろう事はよく判りますし、その熱気には強く心を揺さぶる所ではありますが、私や私を育んだ日本がキリスト教と距離を置いている事を鑑みればこういう感想になったのもしょうがないという事で・・・すいません。 更に、著者は記号論の学者だそうですが、あまり小難しくならずに平易に読める所は素晴らしいと思いました。その作品世界の構築度は凄まじく、実際にこの時代に生きた人が書いたのではないかと錯覚しそうな完成度でした。あと、あまり言われませんが、舞台の僧院が巨大な館だと思えば、所謂「館ミステリー」に分類出来るかもとか思いました。 最後に私事ですが、一番最初に日本で翻訳された時は嬉しくて版元に電話して発売日を聞いて買いに行ったのが懐かしいです(確か上巻と下巻で発売日が異なった様に記憶しております)。その後にこの版元で一番金蔓なのか、私の知る限り未だに文庫にしてもらえないのがむかつきますが、それ以外は今読んでも十分読み応えのある作品でした。☆五つにしなかったのは上記の理由を色々鑑みた結果であまり気にしないでください。 キリスト教の教義問答を推理小説の形に当てはめて読ませる力作。機会があったら是非。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 浅学な私にとっては、皮肉と破滅の伝奇ミステリの良作。 著者が昔入手した中世の写本に書かれていた事件というプロローグから引き込まれます。 イタリアにあった特殊な建築の大図書館を舞台にした連続殺人、真相は禁断の古書にまつわる、というのが、本好きにはたまりません。 探偵、推理や事件解決の行為を嘲笑ってるかのよう。 事件の真相も、エーコ氏がよく笑う人というエピソードを読んで納得。 映画版は、原作の面白さがロクにないので、そもそも観る意味がないかと。 原作は、現実的に、迷宮は迷いやすいようにどう作られてるか描かれています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| イタリア語のような、どちらかというとマイナーな言語の世界(業界)では、 この程度の、できの悪い学生の訳としか考えられないものでも、出版されてしまうのか! とにかく、日本語が酷い! 著者のウンベルト エーコに失礼な翻訳である。 これが日本翻訳文化賞を獲ったというのも信じられない。 評価委員達は本当に本書を読んだのか? まともな翻訳が出ることを期待したい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これは邦訳が出る前に英訳で読んだが、何だか面白くなかった(よく分からなかった)。 映画も観たが何だかよく覚えていない。 いまつらつら考えるとバカミスである。 スコラ哲学というのはバカバカしいもので、そういうものと手を切ったから近代があるのである。 ロマン主義は中世好きだが、要するにノスタルジーである。 私は特に興味はない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 河島 英昭という翻訳者はマキャベリの君主論でもそうだったが 訳が非常に下手である それも言語的な訳のまずさと、内容理解の不足によるまずさが相まって 非常に退屈な出来に仕上がっている かろうじてストーリーだけ追える程度である 今後も、この翻訳者は避けたほうが無難だろう | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 映画は、10年以上前にビデオを借りて見たことがあるのですが、やっと原作に手を出しました。 今までも読みたいと思いつつ、図書館で手にとってはやめ、本屋さんでも、やっぱり分厚い・・・とめげていました。 知り合いのフランス人によると、「ダヴィンチコードと似てるけれど、もっと宗教的で、もっと深くて、もっと知的だ」と。 ただ、あまりに宗教色が濃いので、日本人にはちょっとなじみがなくて読みづらいかもしれない、とのことでした。 そう思って読み始めたら、意外と読みやすかったですが、宗教色が強いことと、ちょっと読むのに時間をかけすぎて 内容を忘れたところもあり、話がわからなくなってしまったりしました。 結局、誰が死んで、なぜそうならなければならなかったのか? など、ピンとこない、というか、わかったのですが、もう一度読み直した方がいいかも、という感じです。 面白いけれども、日本の作家の本しか読まない人にはちょっと勧め難いかなと思いました。 ただの娯楽では済まされないようで。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書の時代背景はルネサンス後のイタリアです。 キリスト教には全くと言っていいほど興味のなかった私ですが、 発売当時世界各国の賞を総なめにしていたという評判に裏切らない、 重厚な内容に圧倒されました。 入院中に読んでいた本ですが、おかげで単調な生活が楽しかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書は、イタリアの時代小説のような一面もあり、ある程度歴史的文脈を押さえておかないと分かりにくいと思いますので、この場をおかりして、簡単にその文脈の説明をさせていただきたいと思います。ネタバレはありません。おそらくイタリアの方にとってさえ、一部の歴史の愛好家、専門家をのぞくと、このような説明は必要なのでは、と失礼ながら思ってしまいます。ウベルティーノ・ダ・カザーレやベルナール・ギーという名前を聞いて、あああの人か!というくらいの知識を持っている方が主要な読者として想定されていると思います。ウィリアム・オッカムって誰?というような方には、すいませんが、かなりしんどいと思います。ですから、この本が、訳注も全くありませんし、日本でベストセラーになったのはちょっと不思議な感じがします。 舞台は1320年くらいですが、まず、その前の1200年代まで遡る必要があります。その頃、神聖ローマ皇帝、シュタウフェン朝のフリードリヒ2世と、ローマ教皇の対立が激化していました。フリードリヒ2世は、ドイツと南イタリアを領地として持っていました。要するに、北イタリアとローマを中心とするバチカンの領土を挟み込んだ広大な領土をもっていたわけです。それ以前から長い時代、神聖ローマ皇帝とバチカンは激しい覇権争いをしていましたから、フリードリヒ2世はこの機会に北イタリアとバチカンの領土をも併合し、今のドイツとイタリアを合わせたような大帝国を作ろうとします。長年の教皇とローマ皇帝の対立に永遠の終結をもたらそうとしたわけです。自前の軍隊を持たないバチカンにとってはとてつもない危機的状況です。 しかしこの争いになんとバチカンは勝利します。どうやって?ドイツ系のシュタウフェン朝と対立していたフランス王権を味方につけたのです。そこでご褒美として、南イタリア、シチリアは、フランスのアンジュー家の領地になり、シュタウフェン家は断絶し、神聖ローマ皇帝位は空位時代に入ります。 ところが、だからといって、バチカンに我が世の春が訪れたわけではありません。その結果フランス王権が、バチカンを脅かすほど、強くなってしまったのです。今度はフランス王権が、バチカンを配下にしてしまおうとします。バチカンの持つ世俗権力を奪い、教皇をフランス王家直属の司教のようなものにしようとします。とうとうその圧力の結果、バチカンは、長年の本拠地ローマを離れ、フランスのアヴィニョンに移らざるえなくなってしまいます(14 世紀初頭)。 そして、バチカンにとって泣きっ面にハチの状況ですが、空位だった神聖ローマ皇帝位に新たな後継者が決まり、新たにバチカンとの対立関係にはいります。皇帝は今回は、神学の側面からもバチカンに攻撃を与えます。それ以前からそれなりの影響力を持っていた、異端か異端でないか微妙な立ち位置の、宗教運動(清貧派)の応援をしたのです。それは、フランシスコ会という修道会の一派なのですが、この一派は、簡単にいうと、バチカンでさえ何も所有してはいけない、という主張をするのです。キリストや使徒が何も所有していなかった、ということがその根拠です。これは多くの財産を抱えて膨れ上がっていた当時のバチカンの在り方への間接的な批判を含んでいます。この主張が正当となれば、莫大な富を有しているバチカンは間違っていることになり、ひいてはバチカンは世俗権力を失うことになり、挙句の果てに、ローマ教皇は、フランス王家の望みどおり、フランス王家直属の司教のような地位に落ちぶれざるえなくなってしまいます。このような宗派は複数存在していて、本文中で、フラティチェッリとかドルチーノ派と呼ばれているのも、それに含まれます。ドルチーノというのは一個人の名で、そのような主張を掲げて、いわば壮大な一揆のようなものを起こして有名になりました。このようなグループは、膨大な富をもつバチカンの腐敗を苦々しく思う人々の支持を暗にえていて、それなりの支持を広げていたのです。 ここまで読んでいくとバチカン側は袋叩きにあってるような感じですが、当時の教皇ヨハネス22世はかなりのやり手で、この危機的な状況にもかかわらず、バチカンの勢力を拡大していました。先述の清貧派には、異端宣告を下し、その勢いに歯止めをかけようとします。ただ、この清貧派は、それなりに民衆的な支持を得ており、これに異端宣告を下すことは、バチカンの指導的な地位を、不安定化するという側面もあるわけです。この辺りの論争は「清貧派論争」などと呼ばれています。 この状況の中、清貧派が属していたフランシスコ会と、バチカンの間にも、緊張が走ります。同派が異端宣告を受ける少し前に、フランシスコ会は総会でその異端とされた思想を肯定するような決議を採択していたのです。ということで、バチカンは、そのフランシスコ会の総長に、アヴィニョンの教皇庁へ来るよう呼び出しをかけます。「お前はあの異端たちをどう思っているのか?」と問い正すためでしょう。「異端です」と答えると、巨大なフランシスコ会そのものが、分裂し崩壊してしまう恐れがあります。この異端とされた清貧派の主張は、あの有名なアッシジの聖フランチェスコの教えに最も忠実であることは、誰も否定できないからです。この異端を完全否定しては、フランシスコ会はそのアイデンティティーそのものを否定することになってしまうのです。しかしだからといって、総長が「異端ではない」と答えて、バチカンと正面から対立すると、フランシスコ会そのものが異端扱いされかねません。その他、そもそも、そのような試問さえ行われず、招待された総長が、どさくさにまぎれて、アヴィニョンで殺されてしまうのでは、という危惧さえあったのです。 さてここからはフィクションとしての『薔薇の名前』の中の話に入ります。ということで、それに先立って、バチカンの代表と、フランシスコ会の代表たちが、中立的な修道院で事前協議のようなものを行うことになりました。その修道院が、『薔薇の名前』の舞台となっている修道院です。その修道院の宗派(ベネディクト会系のクリュニー派)が、各勢力から適度な距離を保っていたからでしょう。また、その修道院には、先の世俗の富を否定する思想の最大の理論家ウベルティーノ・ダ・カザーレ(歴史上、実在した人物)がおり、このウベルティーノは、その高い人徳から、バチカンも一目置かざるえない大人物でしたが、そのような状況も、この修道院が調停の場を選ばれた理由でしょう。 しかし、そのような修道院で、その事前協議の直前になって、謎の自殺?殺人?が起こります。どこかの勢力が圧力を事前にかけたのでしょうか?バチカン?フランス王?皇帝?それ以外のどこか? しかし事件の真相はまったく分かりません。これは困ったということで、歴史上の哲学者ウィリアム・オッカムの学友でもある高い知性の持ち主の修道士ウィリアムが、事件の解決のために、その修道院に招かれます。そしてその修道士の付き人である、修道士見習いアドソが、この『薔薇の名前』の主人公で、彼の手記が『薔薇の名前』本文ということになっています。これくらいのことを抑えておけば十分です。後はみなさんでお楽しみください。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

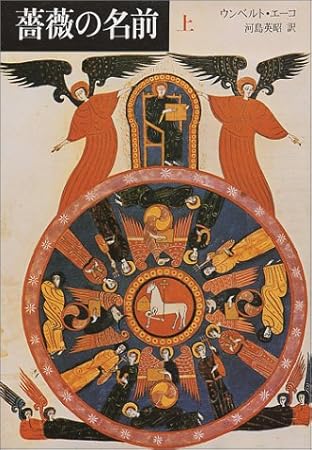



![薔薇の名前[完全版] 上 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51u3X3o71BL._SL500_._SL450_.jpg)
![薔薇の名前[完全版] 下 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51rmxbj67JL._SL500_._SL450_.jpg)
