■スポンサードリンク
薔薇の名前
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
薔薇の名前の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.19pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全19件 1~19 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「完全版」にかこつけて、単行本より800円も高い文庫本ってどうなんでしょう? 非常に高価なので、書店でビニール包装して陳列するようになるのかな? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 新刊なのに天の角部分の一部が潰れていた。読書に支障はないが、気分が悪い | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 定価より230円安かったので おかしいとは思ったのですが購入しました。 届いた本は 帯には皺がより一部裂け 内側の折り返しは折れている状態。 本体も数ページが折れていました。 がっかりして返品しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| やろうとしてることはすごいと思う! でもまるでウィキペディアを読んでいるような味気なさでした。残念。 やっぱメルヴィルってすごい! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 理解できない部分をすっ飛ばして読んだ。キリストの教義、中世ヨーロッパ、権力争い…。こうしたことを取り除いても愉しめる。本は読みたいように読むべし 知らなくても恥ずかしくないことはいっぱいにあるんだから | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 推理小説としては三流、物語としては四流。学者が知識をひけらかしてるだけ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 梱包の袋が裂けて、中身が半分露出していました。商品に傷がなかったので受け取りましたが、以前もアマゾン便で届いた荷物の箱が破損していて、全開の状態だったことがあります。ほかの通販で梱包が破損していたことはありません。中身が見える状態で配達されるのが正常だとは思えません。傷がなければよいというのでもありません。今後アマゾンで注文をするかどうか、ためらいます。評価はゼロかマイナスでもよいぐらいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ダンブラウンが好きで、新作が出るまでの繋ぎにと読み始めたものの…難し過ぎる説明が延々と続く為、頭の良くない私的にはその時点で眠くなってしまう。誰かもっと簡単に説明して!そもそもこの長ったらしい説明とか必要?と思ってしまう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| イタリア語のような、どちらかというとマイナーな言語の世界(業界)では、 この程度の、できの悪い学生の訳としか考えられないものでも、出版されてしまうのか! とにかく、日本語が酷い! 著者のウンベルト エーコに失礼な翻訳である。 これが日本翻訳文化賞を獲ったというのも信じられない。 評価委員達は本当に本書を読んだのか? まともな翻訳が出ることを期待したい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これは邦訳が出る前に英訳で読んだが、何だか面白くなかった(よく分からなかった)。 映画も観たが何だかよく覚えていない。 いまつらつら考えるとバカミスである。 スコラ哲学というのはバカバカしいもので、そういうものと手を切ったから近代があるのである。 ロマン主義は中世好きだが、要するにノスタルジーである。 私は特に興味はない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 河島 英昭という翻訳者はマキャベリの君主論でもそうだったが 訳が非常に下手である それも言語的な訳のまずさと、内容理解の不足によるまずさが相まって 非常に退屈な出来に仕上がっている かろうじてストーリーだけ追える程度である 今後も、この翻訳者は避けたほうが無難だろう | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 友人の面白いとの薦めで読みました。 中世14世紀の僧院での怪事件をホームズ役フランシスコ会修道士とワトソン役のベネディクト会見習い修道士(物語の語り手)が解決する話。 そこに宗教的な事柄が多数絡められています。カトリックの派閥対立とか、異端とは・清貧とは何ぞや?とか。 難しい(かつ失礼ながら興味を持てない)話が多く出てくるし、登場人物が外人名だから誰が誰だかわかりにくい(だから登場人物表しおりが付いてる)ので、正直読んでてツラかった。 最初のはしがきとプロローグでいきなり挫折しそうになり、オイオイっこれ本当にオモロイのか? と心配になってアマゾン書評をみたら、評価高かったので安心したぐらい。 下巻のアマゾン書評数が上巻に比べて少ないのは、上巻で挫折した人が多いからか? 友人が最初はあえて上巻しか持って来なかったのも、挫折を予測してたから? などと邪推してしまった。(その推理は正しいのかもですが...) 宗教的な問答では、キリストが笑ったか? の論争とか。 (それなりに笑ってたに決まってるやろっとツッコミながら読んでた) それに対する言で 「きっと笑わなかっただろう。なぜなら、神の子の名にふさわしく、全て知っていれば、私たちキリスト教徒が後年にどのような事をするのかぐらいはお見通しであっただろうから...」 なんてのは深いなぁと感じた。 上巻2/3頃からやっと面白くなってきた...と思ったら、下巻でカトリックの派閥対立話等でまたやや辛くなり、 なんかよくわからん動機(中世キリスト教の世界では十分に動機たりえるそうです)の主犯との攻防でやや盛り上がって終了。 「最も残酷なのは、自分の事を正しいと信じて疑わない人である」なんて言葉を強く思い出す内容でした。 薦めてくれた友人に対してもね... 推理小説はあまり好きでないし、キリスト教にも興味ないから、通常であれば120%読むことはない本なので、 そういうの読んで視野を広げれたという点は良かったです。 それにしても色々な事柄に対する表現がくどいなぁ〜と感じました。 まぁ正直なところ、 オモロイ箇所 <<<・・・<<< ツライ箇所 ということで、★★☆☆☆ とさせて頂きます。 理系・日本史専攻・仏教徒の評価とお考え下さい。 それから、この作品はショーン・コネリー主演で映画化されてるそうです。 ショーン・コネリーは好きなんでちょっと見てみたくなりました。 あと、解らない言葉や読み不明の漢字が多数だったんで調べながら読みました。 解らないことをWikiで調べたらドンドン派生して、そっちが止まらなくなったりしてました...。 まぁ勉強にはなったけど。 以下が調べた語の一部です。 ---ティンパヌム--- 建物入口上にあり、横木とアーチによって区画された装飾的な壁面のことで、半円形か三角形をしている。 ギリシャ・キリスト教建築においては、ティンパヌムに宗教的情景が描かれているのが通例。 (上巻最初のティンパヌム描写がやたらくどくて辟易した...) ---修道会--- キリスト教の西方教会における組織。カトリック教会においては教皇庁の認可を受けて、キリスト教精神を共同生活の中で生きる、誓願によって結ばれた信徒の組織。修道会の会員は修道者といわれる。 ---フランシスコ会--- 13世紀イタリアで、アッシジのフランチェスコによってはじめられたカトリック教会の修道会の総称。無所有と清貧を主張したフランチェスコの精神にもとづき、染色を施さない修道服をまとって活動。 居住する家屋も食物ももたず、人びとの施しにたよったところから「托鉢修道会」ないし「乞食僧団」とよばれ、どの教会管区にも属さず、ただローマ教皇にのみ属した。 ---ベネディクト会--- 現代も活動するカトリック教会最古の修道会。戒律は「服従」「清貧」「童貞(純潔)」。ベネディクト会士は黒い修道服を着たことから「黒い修道士」とも呼ばれた。 ---癩病人(らいびょうにん)--- ハンセン病患者のこと。この名称は差別的と感じる人が多いために、歴史的文脈以外では、一般的に避けられている。 この本では病気により社会から隔絶された人々を示して使われています。 聖書にでてくる皮膚病がどの病気を指しているのかは諸説あるそうで、聖書での最近の訳はこの語を使わずに「重い皮膚病」としているそうです。 ちなみに、ハンセン病の伝染力は非常に低く、治療法が確立しており、重篤な後遺症を残すことも自らが感染源になることもないとの事。 ---枢機卿--- カトリック教会において、教皇の助言者たる高位聖職者。教皇選挙権を持つ。 ---アナーニ事件--- 1303年、フランス国王フィリップ4世がローマ教皇ボニファティウス8世をイタリアの山間都市アナーニで捕らえた事件。 アヴィニョン捕囚を引き起こして教皇権に対する王権の優位を確立した。 この事件・結果は教皇権力の衰退と王権の伸張を印象づけ、近世絶対王政にいたる重大な一里塚となった。 ---アビニョン捕囚--- キリスト教のカトリック・ローマ教皇の座が、ローマからアヴィニョン(フランスの南東部に位置する都市)に移されていた時期(1309〜1377年)を指す。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 下巻はさすがに読ませどころが多い。いや、読む人が読めば読ませどころは全編に横溢しているわけだが、ひたすらエンターテインメントを求める向きには、その仕掛けがもどかしい。そんな僕のようなけしからん(?)読者にとっても、下巻は読ませどころが多いのだ。 実在した異端審問官ベルナール・ギーとの対決、徐々に全貌を現す玉虫色の真相、そしてカタストロフィー。最後のそれに、俗人である僕は横溝正史の『八つ墓村』を思い出さずにはいられない。うん、ストーリーだけ見るとこれは『八つ墓村』だな。記述者アドソのビルドゥングスロマンであり、師となるウィリアムはホームズというより金田一耕助だ。 つまり、ミステリとしての仕立ては実に“記号的”である。分かりやすい。その砂糖菓子のような骨組みに、目が眩むような知のデコレーションが重層的に施されている。作者のたくらみには文字通り「舌を巻く」が、それを味わい尽くすほどの肥えた舌を僕は残念ながら持っていなかった。だからせめて、「こういうものを面白がる人たちもいるんだ」という理解は示しながら、読み飛ばしていった。例えるならそれは「現代音楽を鑑賞する姿勢」に近かったろう。 読了後、ジャン=ジャック・アノーの映画をあらためて観ると、難解な現代音楽を実に要領よく咀嚼しているなあと感心した。もちろんそこに物足りなさを覚える原作ファンはあるだろうが、これだけの作品世界をいちいち具体的な「画」に置き換えていった丁寧な仕事には、頭が下がる。なんてことは映画のレビューに書くべきですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 好みでいえば、好きなタイプの小説ではない。現代アメリカ文学の大家ジョン・アーヴィングを枕頭の書とする僕は、圧倒的な物語が展開するディケンズ的な小説が好みだ。だから、モダニズム文学の首魁ジェイムズ・ジョイスみたいな「知の叙事詩」ともいうべき小説は、好みではないのである。本書をジョイス的と呼ぶのはいささか乱暴という気もするが、エーコはジョイスに大きな影響を受けているらしいので。 それでも本書を読もうと思ったのは、ミステリファンとして踏破しないわけにはいかないひとつの高峰であることは確かだから。そしてシャーロキアンとしては、ホームズもののパスティーシュにやはり関心を持たないわけにはいかなかったから。もちろんパスティーシュとか、あるいはメタミステリとか、そういう分かりのいいレッテルを貼って片付けるにはあまりに手ごわい小説であることは、充分承知している。 今、上巻を読み終えてこのレビューを書いている。キリスト教史や中世の西洋史、哲学、思想などの知識があるほうが楽しめる、というのは多くの方がここで書いておられる通り。もちろん知らなくてもミステリとして楽しめる、というのもまあその通りだろう。しかし予備知識はいらないにしても、それらに対する興味、関心、好奇心はあったほうがいい。僕には正直それらが欠如していた。「分からないことは分からないでいいや」というスタンスで読んで、結局少々退屈なまま上巻終了。 でもひとつ思ったのは、宗教上の相克において何が異端で何が正統か、また何が善で何が悪かというようなことは、何が残って何が残らなかったかという問題に過ぎないのではないか、ということ。圧倒的な情報量に触れながら、たったそれだけのことに感心しているのは情けない気もするけれど、下巻のミステリとしての面白さに期待しつつこのへんで―― | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 名訳との世評をずっと疑ってきた。驚くほど大量の初歩的な訳語・表記の選択ミスがあるからだ。大家といえども教養に限界はあるのだから責められないとも言えるが、最小限に抑える手はあったはず。現に、最新作『バウドリーノ』は歴史学者がチェックしたと仄聞する。それくらいのことをしないとエーコの学識には拮抗しえない。 重版のあいだに訂正はされているのだろうか。版元は早急に徹底的に手入れをした文庫版を出す義務がある。訳者が偉すぎる、あるいは偏屈にすぎるとこういう仕儀になり、読者がワリを食うという悪弊の典型である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 記号学の泰斗が書いたミステリとして著名な作品だが、読む前から単なる衒学的作品ではないかと言う懸念があった。初っ端からその不安が的中する。14世紀のイタリアを中心とする中世ヨーロッパ史、特に宗教史について造詣を持たない読者は門前払いと言う態度なのだ。また、探偵役の修道士ウィリアムの観察眼や推理法はホームズもののパロディで、この点でもガッカリさせられた。作者が本当にミステリを書こうとしたのか否か疑念が湧く内容で、作者自身の宗教史観・記号学の自省的考察を披瀝するために戯れに物語を捻り出した感が強い。 岩壁沿いの修道院で起きる事件の模様は殆ど語られず、代りに読者は当時のキリスト教諸派の対立や神学上の解釈の相違や院内の衆道関係等を延々と聞かされるハメになる。そして、修道院内の建物には秘密の通路が複数あったり、"魔法の薬草"や鏡で幻覚を起こす等、子供騙しの手法が堂々と使われる。表面的にはペダンティックな装いだが、内実は子供向けの冒険小説の趣きである。作者の専門を活かした筈の暗号も断片的過ぎる上にコケ脅しで、現代暗号理論からすれば幼稚極まりない。作中で強調される"迷宮"に陥っているのは読者や探偵役で無く、作者ではないかとの思いを強く覚えた。キリスト教における異端論争・教義対立などミステリ・ファンにとっては興味の埒外である事は自明だろう。 結末に到ってもミステリ的趣向が皆無で、徒労感・脱力感しか覚えない。ミステリを知らない碩学の書いた壮麗なる駄作と言えよう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 世間的にこれが「名作」とされていることは承知しています。エーコがどれほど淒い人かというのも、一応判っているつもりです。それが、うんちく折り込みまくりのベタな推理小説を書いたわけですから、ミステリファンとしては喜ぶべきなのかもしれませんが、これは本当に面白い作品なのでしょうか?読み方が間違っているのかもしれませんが、ページをめくりたくなるドライブ感も、目の前に場面が浮かんでくるような臨場感も、美しい文章に感嘆する気持ちも、何も感じられませんでした。それでも所々に見え隠れする、蠱惑的な雰囲気だけはありますが、やっぱり訳の問題なのか…、私にはついていけませんでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| エーコの記号論などまったく理解せぬ訳者のおかげで、せっかくの名作が台無しに。読むなら原書か、英訳がお勧め。あるいは気長に改訳を待った方が良い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読止。難解です。最近のライトな小説を読みすぎたせいか、はたまた脳みそが不足しているせいか、わたしには読みきることができませんでした。ストーリーの間と間に、ほんとうに長々と説明が入るので、物語世界にうまく入ることができませんでした。ああ。いったいどんな話だったんだろう。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

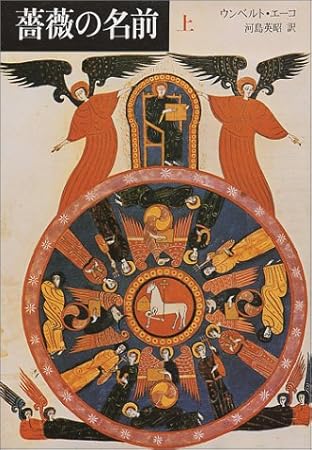



![薔薇の名前[完全版] 上 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51u3X3o71BL._SL500_._SL450_.jpg)
![薔薇の名前[完全版] 下 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51rmxbj67JL._SL500_._SL450_.jpg)
