■スポンサードリンク
薔薇の名前
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
薔薇の名前の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.19pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全6件 1~6 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 3点です。 言い表しづらいのですが、面白いには面白いし、ドラマチックだし、読み進めてしまうんだけど、何となく最後まで読んだ時にはそこまで釈然としない・・・みたいな作品でした。 中世ヨーロッパやらキリスト教史に詳しくはないながらも興味がありますし、僧院で起こる謎に満ちた連続殺人事件…と、ページをどんどんめくりたくなるのですが、この小説のジャンルは何なのかなと考えると「謎解き」ではないのだなと。 謎めいた伏線風のものがたびたび張り巡らされてるわけですが、結局その伏線をたどって自分で答えを見通せるのかというと「それは無理だろう」ということになる。 こういうジャンルを何と呼ぶのか知りませんが何というか・・・派手な血みどろとカオスつきの感傷小説みたいな感じもあるなという気もします。 充分面白かったし、余韻もあるのですが、冷静になると「かいつまむとこの話なんだ?」という気がしなくもないという。 そのように感じてしまう理由を考えるとまずは一つには「そもそも別に推理小説ではない」ということだと思います。ウイリアムという師と見習い修道士である書き手という構図と冒頭の推理シーンのせいで「推理小説なのかなワクワク」と思ってしまうのですが読み終わってみると別にそうではないです。 謎解きの要素はありますが若干ご都合主義。 犯行の背景の動機も早い段階でほのめかされてるわけですけど・・・いやいや、結局そういうオチになるなら何十年も前にそうしておけば良かったのでは?的な・・・。それじゃあ犯人頭悪いことになってしまう気がする。 殺人トリック?的なのも割と早い段階で「そうじゃないかな」って想像したのが「やっぱそうなんだね」的な。 「いや、でもそれでは説明できないこういう要素は・・・」と思ってたところはまさかの偶然という。 このご都合主義というか偶然を「神の意図なのか」とか小難しく読むものなのかもしれない。 そんなわけで「推理小説」として読むのであればあまりにもあまりにもなのです。 多分薔薇の名前上下巻の20-30%くらいのページ数で書けちゃうかなと思われます。 そうではなくて時代背景とか当時の考え方とかを読み込んでこの若き修道僧の世界を体験するというのがむしろ主眼なのかなと思います。 だから他の方も言っているように、背景説明がやーたら長くて「ほんとに必要ですか?」とは思うかもしれない。キリスト教徒なら面白いのかもしれませんがさすがにページを割きすぎな感じはありました。 それからこの若い見習い修道士が晩年に筆をとっているという体裁なのですが「フォトグラフィックメモリーかよ」くらいの重たい描写なので(延々入り口を説明された時はさすがに途中からページをめくる手が速くなりました。夢の話が延々続いた時も途中から「あいわかった、みなまでいうな」的な気持ち)こう世界を延々味わいたい人の方が楽しめるかもしれない。ただ、そこまで覚えてるって作品のリアリティ的にどうなんだという感じがしました。 最初の方に「その人がどんな見た目なのかとか言うことは退屈だから書きたくない」という主旨の断り書きがあるのですが、いやいや、ドアの説明するならそこ説明してくれよ、登場人物が横文字ばっかりで、さらに見た目の描写もないから頭の中で描きにくくて大変だよ!だいぶ読んでから「ああ、Aさんの方がBさんより年齢上で、Bさんはどうやらだいぶ若いのね」ってわかるという。 この書き手が見て明白な設定の事は書いてくれよ。みたいな。 そんなわけで、面白いのですけど、その面白いのは若干の物珍しさ、ジャンル的な独自性みたいなのが勝ってるのかなぁと思いました。 若い時代の感傷みたいなものは共感するところがあったし、終わり方は素敵なんですけどね。 そんな作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 随分以前に、読み応えのある推理小説として本書の存在を知ったが、文庫本になるまでは読むまいと顔を背けていた。ところが一向に文庫化される気配がなく、わたしも忘れていたが、地元の図書館に『江戸川乱歩と横溝正史』を返却した際にふと検索してみたら、しっかり蔵書されていたので借りてきた。 普通ハードカバーで出版されてから、文庫落ちするまでは凡そ三年、長くても五年といったところだと思うが、本書は一向に文庫化されない。なんでだ?と思っていたが、読んでみるとよく解った。 本書の語り手アドソとその師ウィリアムは、明らかにワトスンとホームズをなぞらえているし【注1】、前半に連続殺人事件が発生して、後半で犯人を特定するのだから、完全に探偵小説の体裁に乗っ取ってはいるが、まずカテゴライズされるべきは時代小説だから……。【注2】 重厚で読み応えのあるこの小説の主体は、14世紀前半の北イタリアの政治/宗教的時代背景であり、探偵小説的な構成はこの小説に起承転結をつけるための手段に過ぎない。 14世紀前半と言えば、すでにダンテの『神曲』は世に出て広く読まれていて、イタリア・ルネサンスが始まりつつあった。ウィリアムとアドソがそれについて語り合うシーンもあった。彼らをウェルギリウスとダンテになぞらえることも可能だろう。 そして当時は、後のペスト蔓延からのプロテスタントの登場を控えた、中世カトリックの衰退期の始まりとも重なっている。 とは言え、本書の中ではいまだキリスト教(カトリック)はアグレッシブで、活発な神学の議論にあけくれてる。 アリストテレスの喜劇に関する論争なども、キリスト教徒にとっては常識に近いことなのだろうか。【注3】 キリスト教徒(カトリック)であればもっと興味を持って読めるのかもしれないが、異教徒のわたしにしてみれば、なにをまたぐだぐだとどーでもいい議論ばっかして、そんなでは社会の発展などとても期待できんわと思ってしまったのが正直なところ。 わたしは歴史が好きなので、上段前半への流れに想いを馳せることでおもしろく読めたが、そうでなければ、本書を最後まで読むことも難しいのではないか。 推理小説への興味からこの小説の存在を知って手に取った読者の中には、途中で爆沈した人も多かった筈。 【注1】現在映画の『薔薇の名前』を視聴中だが、ショーン・コネリー(ウィリアム)がクリスチャン・スレーター(アドソ)に「Elemmentary(初歩だよ)」と言ってたww 【注2】わたし基準では、ホームズ物語は推理小説ではなく探偵小説、本書は歴史小説ではなく時代小説。 【注3】『神曲』もダンテ自身は『Comedia(喜劇)』とのみ題していたそうな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 上巻にも言える事ですが、この作品の各所には、『聖書』『神曲』『デカメロン』『バスカヴィル家の犬』などを暗示した表現が取り入れられています。 それらに詳しい方は、読んでいて興味をそそられる発見があるかもしれません。 私も関連する文献を一読してはいますが、本書に仄めかされた意味は部分的にしか理解できませんでした。 また時期を置いて読み直してみたいと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 物語としては、中世北イタリアで起きた不可解な連続殺人に関する推理小説です。 確かに面白いですが、事件とは直接関係のない話がやたらと多くなっていて 1300年代西欧の政治背景 宗教論争 教皇や皇帝の名前 権力の推移 地中海周辺の旧地名 などの史実が当たり前に出てくるので、取っ付きにくい作品ではあります。 「それがあってこその『薔薇の名前』なんだよ!」と仰っていた方がいましたが、良くも悪くもその通りなのかもしれません。 ただ興味はあるけど手に取りにくいと思っている方、本編とは直接関係のない部分は多少飛ばして読んでも大丈夫です。 聞きなれないイタリア人の名前(アッボーネ、セヴェリーノなど)と、それと役職を把握していれば理解できます。 まだ神と悪魔の思想が信じられていた時代、封建的社会の色が濃い暗黒時代が舞台となっていて、登場人物がどれも個性的と言うか、非常に強烈な人物ばかりなんです。 私は宗教色が強いということで本書を嫌厭していましたが、試しに読んでみると話自体は面白く、非常に読みごたえのある本でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『薔薇の名前』というのは20世紀を代表する小説らしい。らしい、というのはそれほどの作品なのならば私はとうの昔に知っていたはずなのだが、文学を読み始めて10年近く経ったにも関わらず、知ったのはつい最近だからである。確かに読み手は海外文学であるにも関わらずかなりいる。にも関わらず知らなかったのは、作品は20世紀の中でも後半に位置づけされるからか、とも考えた。あと、英独仏ではなく比較的マイナーなイタリア文学に分類されるから、というのもあるのかもしれない。 まあ、そう色々考えながら私はこの作品を手に取り、最後まで読んだ。 読み終わってみると、私は何とも言えない気持ちになった。この作品をどう評していいのかわからないのである。作品の基底にあるのは、推理小説的なものである。ある僧院において誰かが殺された。そしてその犯人は誰なのか、ということを推理していくものである。しかし、この作品は推理小説に単純に分類していいものではないこと位、読めば誰でもわかるだろう。歴史的な話が加わり、なにやら神学的な話、植物学的な話、といった学術的な話が色々と加わっていく。 この作品は歴史的背景を知っておかなければ楽しめないだろう作品なのだが、私は歴史的背景をつぶさに知っておかなければならない作品をそんなに評価したくない。確かにそういった背景を知らない非は私にもあるだろうがそういう歴史的な説明が必要なものを高評価下すことはどうしてもできない。いや、正確には作中においても説明されている(かもしれない)。だがあまりにも長々としておりとても頭に入ってこない。他の学術的な話も多々入るが、私は物語上の必要性はあるのか、と疑問に思った。 確かにこの作品は全く持って凡庸ではない。才能を持った人間でなければ決してこの作品を書くことができず、それ故天才の作品であるといっていいだろう。だが、私は正直楽しめなかった。脱線としか思えない学術的な話が多いし、結局なんで殺人が起きたのか私には把握できなかった。前衛的な作品でその意味で現代的な作品、といえよう。 だがネットのレビューをみるとかなり評価は高い。それ故私の感性がずれているのかと自分に疑問を呈する。まあ別にずれているのならばずれているので構わない。私のレビューもまた一人の読み手のレビューということで。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 宗教を題材にした名作といえばダビンチ・コードがあるが 本書はそれ以前に書かれたミステリー。 ウンベルト・エーコの小説は難解さで理解しがたい書もあるが、 とにかく、一気に読まないと登場人物と宗派の関係が分かりにくくなる。 宗教においてのもう一つのタブーって、 こういうこともあったのかということが描かれている。 いろんな解釈はあるが、最後のどんでん返しは面白いとは思う。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

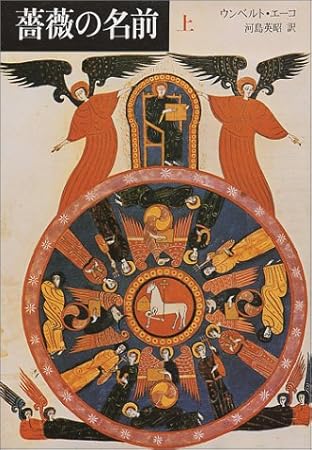



![薔薇の名前[完全版] 上 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51u3X3o71BL._SL500_._SL450_.jpg)
![薔薇の名前[完全版] 下 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51rmxbj67JL._SL500_._SL450_.jpg)
