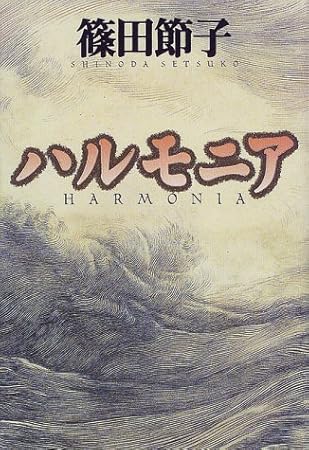■スポンサードリンク
ハルモニア
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ハルモニアの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.94pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全21件 1~20 1/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠田節子さんの直木賞受賞後第1作だけあって、読み応え十分です。音楽物強い。TVドラマにもなりましたね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中身に関する予備知識なしに読み始め、その日のうちに読了してしまいました。天才的な部分を有する障碍者、という私が嫌いな分野の本で、なおかつよくわからない超常現象が出てくる私が嫌いなタイプのホラー要素もあったのですが、とにかく途中でやめられないストーリー展開で、この作家の牽引力に、つくづく感心しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とにかく読ませる力のある篠田さんですが、本作も例外ではありません。 通奏低音のように全編に漂うヒリヒリ感。 先の気になる展開やサクサクと進むストーリーテリングなどなど小説としての魅力は十分ですが、ひとつ指摘しておきたいのは、SFとしても読める側面。 チェロを弾く女性の能力が、読み進むにつれて徐々にわかってくるのですが、この種の能力をこんなにリアルに生々しく描いた例は、SFを看板に掲げる作家の小説でもなかなかありません。 たいていは当たり前に「こういう能力があります」的に描いていますから。 でも本作は違います。 能力を生じる前提あるいは背景、そういったものからじわじわと生々しく描き出していくのです。 その、ある種すごみと言ってもいい描き方は、いわゆるSF作家の同ジャンルの作品にはない、とても新鮮なものでした。 鮮烈、と言いかえてもいいでしょう。 ホラーというくくりもされていて、痛々しい話でもありますが、なぜか爽やかで色鮮やかな読後感でした。 傑作です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 凡人が勘違いして、それなりに平凡に暮らせるようになるはずの人間を完全にぶっ壊すという胸糞悪い話。 ただ、篠田節子の冷徹なまでの人物の書き分けがやはり凄い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 浅羽由希 脳の損傷を受ける。それに関わったのが、深谷。 泉の里で、障害を克服する由希。それに関わる東野。 チェロを教える。 ルー・メイ・ネルソン 12階から転落死をする。 天才的とは、いかなる才能なのか? 中谷という女優が、テレビでやったことを思い出した。 そのイメージが、だぶって、小説がよみづらかった。 つまり、そのキャラクターがそっくりあっているということです。 東野は、堂本が、やったのだが、ちょっとイメージが違いすぎる。 欠損した脳が、修復していく過程で、 エキソシストのような、超能力を確保していく。 チェロの名器 アマティ。 コピーではなく、自分の個性をだしていく。 そのことが、大切になっている。 しかし、その自分の音を出すことによって、 自分自身のバランスが崩れていく。 ハッピイエンドにならないことが、 篠田節子らしいもって行き方である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 精神障害を持つ女性を取り巻く人たちが、各々の考えでその女性を導こうとするが、本当はその女性に導かれているのではないかという思いにとらわれました。 自身の音楽を表現することが本当に当人にとって幸せなのか、読後でもよくわかりませんが、それぞれの信念に従い行動する人たちは鬼気迫るものがあります。本当に彼女はこれで幸せだったのか?そもそも彼女の幸せを他人が理解することができるのか、様々な問いかけが自分に中に残る作品です。 最後に見せた微笑みは本当であって欲しいと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「静かなる黄昏」からの読者です。彼女の小説には多彩なテーマがあります。この「ハルモニア」が代表する音楽小説もその一つ。 入念な調査をして完成するリズミカルなストーリー展開です、どんどん読み手をストーリーに引き込んで行くのは、どのテーマの小説にも共通のおもしろさじゃないかしら。音楽の知識もさることながら、障害者目線や障害者施設に踏み込んだストーリー内容も読み応えあり。 とにかく、一刻も早く彼女の小説が日本語圏以外で紹介されることを願ってやみません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| チェロひきが、脳に傷を持つ女性に施設で教える。 どんどん上達し、演奏会を開催する。 集中すると周囲を傷つけることがあるのを理解していなさそう。 音楽会の裏表がわかる。 最後は、文学だから仕方がないのだが、幸せをつかむことができたのだろうか。人生と住んでいるところからの逃亡が幸せでは悲しい。 脳と音楽の関係が、もう少し深掘りしてあるといいかもしれない。 脳波と体温の関係とか、血中の諸物質の濃度との関係とか、肺での酸素の出入りとか。 解説を石堂藍が書いている。ファンタジー評論家とのこと。 解説ももう一歩、もう二歩、突っ込みが欲しいかも。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 期待感など殆ど持たないままに読み始めた作品です。篠田節子なる作家の存在を全く知りませんでした。 安定した実力を持つ作家によって書かれた作品だとわかりました。読み終えた後も妙に心に残ります。 登場人物の心理描写が秀逸です。読み手の心に食い込んで、その微妙な変化をしっかりと伝えにきてくれます。また、人物一人一人が大切に描かれ、視覚から入るように鮮やかな印象が残ります。 強いインパクトで迫ってくるような、何とも言えない魅力ある作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ドラマと内容がかなり違っている様です。まず登場人物が違います。 ドラマでは恩師の娘(矢田亜希子さん)が主人公(堂本光一さん)の 彼女でしたが、原作では大学時代の片思いの女性でした。 しかし由希(中谷美紀さん)の発するおぞましさを体験する事で、 ドラマでも原作でも彼女は酷い目に遭っていました。 ちなみに、ドラマ主題歌の『愛と沈黙』は素晴らしい曲です。 少年隊の皆さんが歌っています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 脳の病気のため手術となるも、医療ミスから重度の障害を負うが、特定の分野では天才的な能力を発揮する、サヴァン症候群(ここではチェロの演奏)になった薄幸の女性由希と、それを音楽療法で治そうとするチェロ奏者である東野との格闘の物語。 自分の努力に比べ、技術的にはあっという間に高みに上り詰める、由希に対する東野の困惑。それでもその素晴らしい才能を伸ばしてやりたい、との葛藤が延々続く。カノン の2年後出された音楽小説だが、ここでも一般受けのする演奏とは違う、それを超えたより偉大なものを求める考えが主題となる。考えてみれば音楽に限らず、文学でも絵画でもそれは同じ事ではないだろうか。 バッハの音楽が通俗的な演奏家と、由希をその影響から抜け出させようと、東野は努力するその果ては・・・。音楽関係の難しい用語、理論はよく分からぬがそれはあまり気にならない。ただある評論家が超能力が過剰と言っていたが、私もそう思う。無くても、いや無いほうが感動できる作品だ。真の音ハルモニアが五感の退化で、聴けなくなった我々、それが聴ける由希。悲しい物語ではあるがその差を想った。篠田は趣味でチェロを演奏するそうだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ハルモニア。 それはまるで世界をすべる黄金率にも似た調べ。 神聖で崇高な侵しがたい神の旋律。 凡庸なチェリスト東野は音楽療法のスタッフとして通った高原の精神医療施設で、凄まじい才能を数奇な運命を秘めた一人の浅羽由希と出会う。 東野は彼女の秘めたる才能を引き出そうと悪戦苦闘の個人レッスンを開始するが…… 超感覚ホラー。 サスペンス。 人間ドラマ。 この小説を飾る言葉はあまたあれど、一番しっくりくるのはやっぱり音楽小説だろう。 そう言うととかく高尚なものを思い浮かべがちだが、登場人物の苦悩や懊悩、葛藤が非常に生々しくリアルに迫ってくるせいで、どっぷりのめりこんでしまう。 血肉が通った饒舌でありながら流麗な描写は、とくに演奏シーンでその本領を発揮し、光の渦を巻いて読者をめくるめく翻弄する。 二十年間音楽に人生と情熱を注ぎ続けたチェリストでありながら、凡庸な秀才の域をでぬ東野は、重い障害を持ちながらけっして自分が叶いえぬ「天才」由希に激しい羨望と劣等感を抱く。 が。由希は紛れもなく音楽の天才でありながら、同時にコミュニケーション不全で、東野とも殆ど交流が成り立たない。 困惑する東野だが、一対一のレッスンを辛抱強く続けるうち、言葉よりも多弁な音楽を通して二人は次第に互いへの信頼を深めていく。 凄い、とにかく凄い。 音楽という神にして悪魔に魅入られ破滅した男女の物語にもとれるのですが、由希を背負って砂浜を歩く東野の姿には、「ハルモニア」を聞いた者だけが得る至福を感じられ、二人にとってどうするのが一番よかったのか、これでよかったのか、なにが幸せでなにがふしあわせだったのかわからなくなります……。 天才と凡才。 聖と俗。 虚構と真実。 さまざまに反発し対立する要素が絡み合って重層的な構造を生み出す物語の結末は、ぜひあなたの目で確かめて下さい。 願わくば砂浜を行く二人の耳に、今もハルモニアが聞こえんことを。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私も音楽家なので、読んでいて正直辛いなという箇所がありました。いろんな意味で。 ただ文中で東野自身の心理描写としてかかれていますが、 「一応は音楽で身をたてているが、演奏だけを生業にするまでではない。それでも演奏家でありたいと思う」 このような演奏家が果たして、天才的な素質を持つ人間を前にしたら・・・ この小節のようにはいかないと思います。 その才能は、「天才」と2文字におさめれるものではなく、東野を圧倒し己の限界をさまざまと見せ付けるもの。 果たして「なんとか育てたい」と思うのか否か、ですね。これを否定してしまうとお話がはじまりませんが。 実際に音楽の世界で生きてみると、天才と呼ばれさらに活躍しているのは1%にも満たないと思います。しかし多くの人間が神様から半端な才能を贈られ、それゆえ苦しみ、それゆえ時に喜び演奏しています。しかし多くの天才は音楽をすることに幸せを見出せているのかと問われたらどうでしょうか。本人にしかわからないでしょうが、自覚できるほどの才能ではない才能を持って演奏している人たちは、音楽に選ばれているのです。そこに本人に意思があるか否かは神ぞ知るです。 才能で測れるほどの才能は才能ではない と言います。が自覚できる才能の持ち主には選択権が与えられ、苦しみますが喜びもあるのです。その喜びは何者にもかえがたくしかし苦しみは恐怖です。 この作品はとても綺麗です。生々しい描写さえ卑猥で美しい。だけれど「生」が感じられない。東野が「一流になれない二流の苦しみ」を超えて、チェロを教えるということに何かを見出したならそれは「愛」以外何物でもありません。 本作品はラブストーリーだと思います。 音楽に関しては、篠田さんは実際とてもお好きなのでしょうし、ちゃんと取材されたのだなとうかがいしれます。プロの仕事だと感心いたしました。 でも曲の解説や技巧的な問題があまりに精密に描写されていてかえって「蛇足」の感も。 読者層を絞って書かれた作品というわけでもないでしょうし、もしご本人の感性なのだとしたら、演奏されないのが惜しいですね。 今後も音楽家についてかかれることがあったら、もっと醜く書いていただきたいものです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽にひかれるようになった中学生のころ、ドラマで見ました。しかし断片的にしか覚えておらず、また障害に関しての知識も今より断然少なかったため、改めて大人になった今読んでみても新鮮でした。おぼろげな記憶では、やはりドラマと原作では設定が少し違うような。(どちらも悪い印象はありません。)同じく音楽をモチーフにした作品「カノン」もお勧めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説の主人公由希は音楽に関してとてつもない能力を持ち、しかもその能力は超常現象まで引き起こし、音楽によってのみ世界とつながれている。盲目の人が聴覚、触覚、嗅覚がすぐれるように、結局人間の能力は足りないところを他の能力で補っているのかもしらない。数多くの音楽家なら「今音楽の神が乗り移って素晴らしい演奏が出来るなら、どんな犠牲を払ってもいい」と殆どの人が思ったことがあるであろう。私も幼いころ日々鍵盤を叩いていた。絶対音感をもち、多くのレッスン生の中でも抜群の音感を持っていた私に教師達は驚嘆し、音楽の道を勧めた。思い上がった私は、将来劇場の大観衆の拍手の中、美しい音楽を奏でるのが夢だった。しかし、小学3年生の時、私には才能はないと言うのを思い知らされた。旧ソ連の神童と呼ばれた多くの天才たちはわずか5歳で難曲を弾きこなしていた。私より幼い彼らの完成された演奏に衝撃を受け、それから私は、音楽の道を歩む事を断念した。大人になり、サヴァン症候群というものが存在するという事を知ったとき、何故私にそれが備わっていなかったのだろうと正直思った。しかし今はそんな能力を身に付けた人たちが社会に適合できず、どれだけ苦しむのかと思うと、そんな能力は無いほうが幸せなのかもしれない。実際同時の神童たちで今でも活躍しているのはほんの一握りである。精神を病んだものも数人いる、と聞いた。この小説をよみながらずっと頭の中にチェロが鳴っていた。以前聞いた有名なチェリストの音楽が記憶の奥底から蘇ってきたのである。この作品は勿論フィクションであるが、由希の力が私にまで及んでいるような感じをおぼえた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本を読むまで「芸術は多くの人に評価されなければ、所詮作者、演奏者の自己満足に過ぎない」と思っていた。そうでなければ作品、演奏に対して芸術家、演奏家が言いたい放題いえるてしまうから。本当に良いものは、理屈を超え、皆を納得させてしまうものだ。そう考えていた。もしかしたらそれは誤りだったのかもしれない...... 人々が待ち望んでいるもの、求めているものを与えるのが芸術ではない。文化的にはるかに高みにあるものを目指すのが芸術なのだろう。そのようにして作られたものならば誰にも理解されずともよいのではないだろうか。 「その時代に認められずとも、いつの日にか新しい時代が認めてくれる」 有形な物ならば、そういうこともあるだろう。では無形のものは?例えば録音などもされず、誰も覚えていないような演奏...... この物語には救いはない、が真理は描かれている。己の理解できないものをすべて批判するのは大衆のエゴでしかない | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| っと思いこの本をてにしました。設定など、多少は違いますが、ドラマ(98年放送NTV系“ハルモニア~この愛の涯て~”主演・堂本光一)の妖艶な世界感が充分に文字から伝わってきます。当時中学2年だった私は、このドラマのおかげで篠田節子さんの作品を読むようになりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠田節子作品はすべて勉強になることが多い。この作品もしかり。私自身音楽には全く素人で今まで何気なく聴いていたものの、この本を読んでから、もっと音にこだわり、そして弾き手の感情表現に注意がいくようになった。音楽というものに対し、何十冊の音楽の専門書を読んでも得られなかったであろう理解を得たような気がした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 異常とも言えるほどの音楽的才能を持ったサヴァン症候群の女性・浅羽由希。しかし、彼女は言語や感情と言うものを全く持たない。その由希にチェロを教えることになった東野秀行。彼は、自分では実現不可能な天上の音楽・ハルモニアの夢を由希に託し、レッスンを続ける。最後に由希が奏でた調べ。それは東野の求めていたものだったのか? そして聴衆の反応は? そんな二人はどこに行き着くのか?ラストシーンを破滅的だと感じた人がいるかもしれませんが、私はハッピーエンドだったのだと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| サヴァン症候群の由希を演奏者として独り立ちさせたいという女医と由希に自分自身の音を出させようとする東野がそれぞれの思惑で対立していく。2人とも由希の幸せは願っているが、自分の見地でしか物を見ることができない。本当の幸せとは何かを探している作品。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!