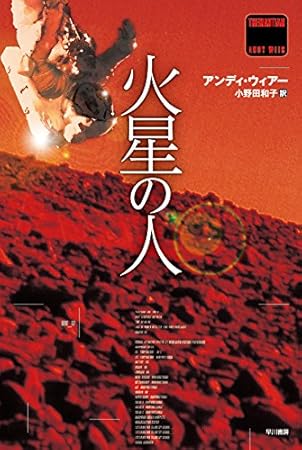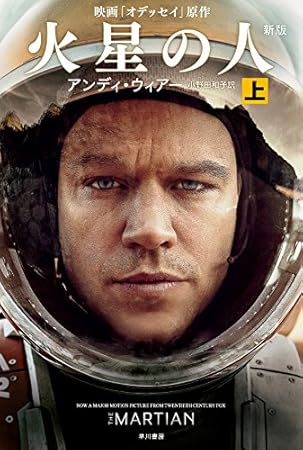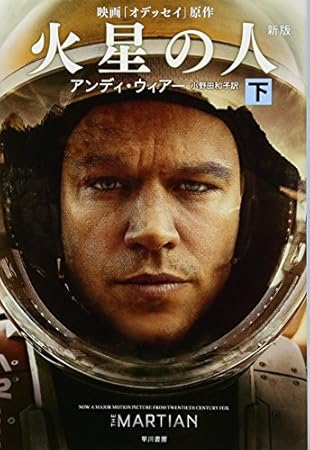■スポンサードリンク
火星の人
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
火星の人の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.46pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全247件 141~160 8/13ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まず、原作が内容的二面白かった。 キンドルははじめての利用だったが、使いやすかった!コストパフォーマンス藻良かった! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大半の人はこの本を読んでから映画館に向かったと思いますが、 私は逆に映画から入った組です。 時間内に収めるためにカットされたシーン、アレンジされたシーンなど、 映画版と比較しながら読むのもなかなか楽しめます。 何よりも既に映像で一度見た内容をそのままイメージしながら スムーズに読めるので、膨大な文章量でもサクサク行けます。 あと、映画でカットされた下品な発言もバッチリ収録。 もっとお下劣かと思ってたんですが、ワトニーはおちゃめさんでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本語で500p超の長編である。評者は日ごろ短編しか読まず、長編は「読まず嫌い」であった。 だがそこは伝統のハヤカワSF。間違い無く、アマゾンにおいて文庫1位に相応しい作品であると読み終わって感じた。 作者の自然科学についての知識は、おそらく並みの(凡人の)思考では追いつかないものだろう。「架空のロケット発射計画を頭の中で考え、それを最初から最後まで緻密にシュミレートするのが好き」という様な作者の言葉がそれを表している。 主人公マーク・ワトニーのウィットに富んだ一人語りに、思わずほくそ笑んでしまう。その理知的な振る舞いはまた、読み手をある意味安心させもするし様々な伏線を想起させる。中学校程度の理科の知識があれば前半は読めるが、後半はやや難しい描写もあった。(それは評者の知識レベルの低さによるもので、作品の質とは何ら関係がない) 映画を観ようかどうか、目下熟慮中である。 が、火星人は読者それぞれの心にあるマーク・ワトニーただひとり。 最高の物語に感謝したい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| そんなに難解な話も出てきませんし、内容的にも面白かったです。 ただし、基本的に火星の希薄な大気で帰還船が傾いたり、パラボラアンテナが飛ばされたりする事はあり得ないと思うのが唯一の難点でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 映画オデッセイを見て気に入ったため、本も買ってみました。あらすじは皆さん書いているので省略 火星に取り残されたマークが4年後のミッションまで生き残る決意をして、そのために何が必要か、 あるいは今あるものでどうやって4年間生き延びるのか考え、実践していくのか丁寧に書かれており、 読者も「これなら生き延びれるのでは」と考えることが出来るのが素晴らしかった。 当然それだけではお話にならないため、中盤~終盤と問題が発生するのですが、 それらに対して科学的、理性的にアプローチ、実践していく描写も良かったのですが、 流石に後半はご都合主義なのではと思う点もしばしば・・・ これが、星5ではなく、星4の理由です。 とは言え、近未来ハードSFの一方で、問題が明確な分、ハードSFにありがちな背景描写で 横道にそれることも無いため、万人に勧められると思います。 それにしても、絶望的な状況の中、ワトニーのユーモアのセンスには脱帽です。 楽観的、悲観的な性格よりもユーモアの有無が生存確率を上げたのは間違いないでしょうね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公のユーモアのセンスが抜群に優れている点と、火星サバイバルの過程が非常に科学的でリアリティを感じられた点で最高に楽しむことができた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あまりにも絶望的なピンチのただ中を、明るく前向きに、 かなり聡明な思考回路を持ったオタクな彼が大奮闘! 読み出してすぐに、マーク・ワトニーが大好きになります。 もう、彼の行く末を見届けるしかありません。久しぶりの一気読み!面白かったですー。 ハリウッドで映画化されたみたいですが、 邦名は「オデッセイ」…そのタイトルから受ける壮大かつ高尚なイメージは、個人的にはチョット違う感じ… まったくの勝手な好みを言わせてもらえば、 監督ならリドリー・スコットというより、ギレルモ・デル・トロで、 ワトニーならマット・デイモンというより…日本でゆうなら浜田岳さんのような俳優さんで、 見たかったなと思います。 もちろん、この後公開された「オデッセイ」鑑賞後、 私の思い込みはまったくの見当違いでしたー!!!となる可能性もあります(^^) 原作をメインとして楽しんだ後のデザート感覚で、 今度は「オデッセイ」を味わってみたいと思っています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 非常に面白かった。映画も是非みたいです。皆様にも是非お薦めします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 面白かった。映画も是非見たいです。楽しみです。皆様にもお薦めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 宇宙ものは数あれど、これは非常に技術面や専門分野のところも踏襲されている印象をうけます。 だからかリアルに感じられる。 火星においていかれて一人きりで生き抜く主人公が、どこか飄々としていてジョークまじりで、生き抜く事そのものを楽しんでいるように感じるのが面白い。 そしてこの主人公と、他のステーションにいる人物やNASAの人物など、場所が違う登場人物からの視点でも描かれており そのいったりきたり具合と物語の進行がスムーズで読みやすかったです。 しかし読んで思うのはやはり、生き抜くには知識と機転力がいるんだという事。 主人公は植物分野でスペシャリストだったわけですが(だからこそ火星で生き抜く事ができたのかもしれない)宇宙に行く人はいろんな分野から一流を取り揃えているんだなあと感心しました。 そして、それぞれが独立し信念をもっていなければならない。 働く人にもいろんな考え方があって、予算と対外面と人情がせめぎあう。 なんとなくチャレンジャー号の事故の事を思い出しました。あれも、結局は乗組員の事を案じ最初からずっと「このままでは危ない」と言い続けた人がNASAをやめる事になり 予算と対外面を重要視した人はそのまま残留した。 この物語でもそういう理不尽さを感じる部分はありましたが、逆にリアルにも感じられました。 わりとスピーディーに進むわりに専門的な色も強く、エンタメ性もあって面白かったです。 やはり宇宙とか、特殊なものに関してはそれなりに理屈も入っていた方が楽しく感じます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ちょうど上巻を読み終わったところ 次々と襲ってくる生命の危機に対して知恵を振り絞って対処する主人公。 けっしてあきらめない心のエネルギーはどこからやってくるのか? 2月の映画公開までにはしっかり読み終え、心に準備を整えたいと思っています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 米国SF、しかも映画作品原作である。 個人的にはこのカテゴリは敬遠してきたのだが、ついつい買ってしまった。 火星有人探査のクルーの一人が、緊急撤収時の事故で吹き飛ばされ、死んだと思われていたのだが実は生存していたという設定である。火星地表上に残された機材と物資と自らの化学・生物・工学知識、そして火星環境自体を使ってなんとか生き延びようとする戦いを描く。 本書のほとんどの分量は、取り残された植物学者かつエンジニアであるマーク・ワトニー飛行士のログ(日誌)の形をとる。ほぼ独白であり、誰かが読むことを期待していないログであるという設定もあって、ユーモアというか無茶な物言いがちょいちょい出てくる。きわめて口語調であるのと、直訳っぽいようでちゃんと雰囲気を伝える訳になっているところも良い感じ。特に理工学系にある程度通じている読者なら、読んでいてニヤッとすることがしばしばあるだろう。 ちゃくちゃくと生き延びるための計画を定量的に立て、突発的な事故(しかしそれは起こるべくして起きるたぐいのもので、空から隕石が落ちてくる的なものではない。作中でもそのあたりはちゃんと説明あり)や、検討見落としによるトラブルを乗り越え、多少の(かなりの?)僥倖にも恵まれながら、えぇ~というような方法で地球との連絡を確立し、、、といった流れでストーリーが進んでいく。 自分も含め擦れたSF読者だと、さてこのあたりで地球側で政治的駆け引きが始まるかも、とか、経済性がとか選挙民がみたいな話がでてくるころだよな、とか考えてしまうのだが、著者はそういう脇道にそれるのが嫌いなようだ。リアルさを求める読み手によっては物足りないと思うかもしれないが、個人的にはもうそういう話は現実世界でいやというほど付き合っているのでSFくらい気持ちよく技術の話を読ませてくれという気分だったりする。その意味ではたいへんすっきりした読後感で、ひさびさに良い時間をすごしたと思えたくらい。 ちなみに類似のテーマを扱った古典SFとして、ジョン・W・キャンベル・Jr, 「月は地獄だ!」 (1950) と対比するのも面白い。こちらは一人、あちらは15名。ヴェルヌとスウィフトみたいですネ。(笑) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 前半の生き延びる工夫に、先ず脱帽した。 よくもあんな無茶を考えつくものだ。 ローバーでの探検からの展開は、特に良かった。 次々と現れる火星からの嫌がらせ?にめげない闘志は立派! ストーリーが読み進むにつれてテンポを上げて行くのが心地よく、後半は一気に読んでしまった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 結論から先に書いてしまえば、ハッピーエンドだ。 しかし、それを迎えるまでに、次々とこれでもかという困難が襲いかかる。 そして、それをあらゆる工夫と観察と知識と判断で乗り越えていく。 また、火星というとなりの惑星の距離とそれ故の困難さを感じる事が出来るだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 友人火星探査が実現した近未来、ある事故により、たったひとり火星に取り残された宇宙飛行士が、いかに持てるリソースでサバイバルするのか。 深刻になりがちなテーマですが、この作品が、何より良いのが主人公が、とにかくポジティブなところ。脳天気とも思えるサバイバル日記が笑えます。 マット・デーモン主演で映画化に合わせて上下巻で再刊されました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今までに無い感動。 都合の良い、モンスター、エイリアンや未知のバクテリアなど出てきません。一人になっちゃいけないときに、待っていたかのように出てくる悪霊などもいません。都合よく、酸素のタンクがあったりしない火星での話です。 SFでも守らなければならない物理法則はすべて守られています。ですので、地球との交信は、片道12分かかります。交信のための無線機が壊れても部品がなければ直りません。コンピュータの部品と無線機の部品は根本的に違うのです。 当たり前のことでもストーリーの都合で曲げられるSFでも、『火星の人』では、ものの見事に必然と偶然が織り込まれています。私は好きです^^。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 善と悪の戦いとか、戦争とか、過去とか未来とか、おおよそSFにありがちな設定ではなく、ただひたすら宇宙飛行士が火星でサバイバルし、NASAと同僚の宇宙飛行士たちができるだけ現実的にリスクを抑えながら彼を助けようとする、そんな小説だ。 そんな話をただひたすらリアルに、専門的に描こうとせず、おたくのアメリカ青年が一人称で語っているところに、この小説の魅力がある。難しいところはドンドン飛ばして、スピード感たっぷりに読み進めることをおすすめする。火星に行っても、人間は人間であり、これから人間が宇宙へ進出して地球人ではなくなっても、やっぱり人間は人間なのである。ということは、火星にいてもおたくが七十年代のアメリカのテレビドラマを観て腹を抱えて笑ったりするのだ。 あたりまえといえばあたりまえだが、この小説にどっぷり浸かれるのは、同じ人間としての共感があるからで、主人公が危機に陥るたびにいっしょになってはらはらし、いっしょになって成功を喜べるのは、この小説が火星でのサバイバル自体よりも、火星でのサバイバルをする人間に焦点を当てることに成功しているからだと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本では2016年2月に公開される、リドリー・スコット監督、マット・デイモン主演の映画『オデッセイ』(原題は小説、映画ともに “The Martian” )の原作と聞いて読了。 ハードSFに分類される本書では、近い未来を舞台にして、有人探査の遂行中に遭遇した事故により火星に取り残されてしまった主人公、アメリカ人宇宙飛行士マーク・ワトニーのサバイバル劇が描かれています。通信手段が絶たれ、食料、空気、水に限りあるなか、科学者であるワトニーが自らの知識を駆使して生き残りを図る様は、緻密な科学考証にもとづいて描かれていて読み応え抜群でした。 語りの形式は主人公の一人称とそれ以外の人物の三人称の組み合わせです。主人公視点では、彼自身がログとして残す “日記” という体裁で語られています。そのため、“語り手” である主人公の抱く心情や経験する出来事が、直接的に描写されるわけではなく、彼により取捨選択されているという間接性をもって描かれています。ある事態に直面したとき彼が “本当に” どう思ったのか。それにはつねに留保がつきます。この語り口がとても効果的でした。 主人公は “日記” のなかでは悲観的に陥ることなく、いつも軽口をたたき、ジョークを飛ばす。もちろんそれは彼の前向きなキャラクターを示すものでしょう。けれど彼が置かれた環境を考えれば、絶えざる不安につきまとわれてもいるはず。もしかすると軽口やジョークは、絶望的な状況下に置かれた自分を鼓舞するためかもしれない。“日記” という間接的な語り方をとることで、悲観的な心情を明記せずに湿っぽさを排しつつも、そのように行間を想像させる余地を残しているのです。 くわえて、主人公以外の三人称のパートでは、主人公が置かれた事態の深刻さが客観的な視点から語られることで、主人公視点との強い対比を生み、物語をよりダイナミックかつドラマティックにしていました。 また、実際にアメリカが2030年までに火星での有人探査を計画しているという現状が、本作に影響を与えているのでしょう。だからこそ作中の世界に強いリアリティを感じることができるのだと思います。現在の世界情勢を反映してか、アメリカ一国の独力が描かれるわけでなく、中国が重要な役どころで登場するのもおもしろい。ですが、それでもやはり宇宙の片隅で孤軍奮闘する主人公の姿からは、剛健、忍耐、創意という、困難に打ち勝たんとするフロンティア・スピリットが伝わってきます。アメリカの建国精神はまだまだ健在なのだと確認させられました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 現代では、SF的手法というのはかくも普遍的なものになったのかという点にまず感心しました。 火星に人が取り残されて、生きるために奮闘する話を、肩肘張らずに書いた小説です。 どんなときにもユーモアを忘れず、ごく自然に不屈な主人公が魅力的です。 主人公の現状を残りのクルーに伝えるか否かで揉めるそれぞれの立場や、救出ミッションに関するあれこれも、読者として大変受け入れやすく、どんでん返しも含めて素直なストーリーとともに万人向けだと感じました。 映画化されるようですが、それには全く驚きがない物語の方向性と完成度です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ワープやタイムトラベルは出てきません(^o^;) でも、現実的な科学技術の基に(SFなので細かな数値は無視してね)物語が進んでいきます。 どじっ子だけど常に前向きで明るい所に共感させられました。 NASA好きな方から、SF初心者まで楽しめると思います。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!