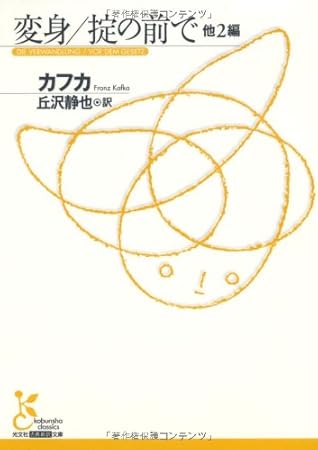■スポンサードリンク
変身
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
変身の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.08pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全293件 161~180 9/15ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品の主人公グレーゴルが見舞われた悲劇はまさに不条理そのものである。 家族の為を思い、「我」を抑え身を粉にして一心に働いていたのに、ある日突然虫になってしまったことによって かつて自分へ向けられていた家族の尊敬の感情は徐々に消え失せてゆき、どんどん邪険に扱われるようになる。 そして最後には、まるで最初から存在しなかったものかのように、家族たちの心から消失する。 グレーゴルは一体どんないわれがあってこんな仕打ちを受けたのか。 結局、家族にとってグレーゴルとは、自分たちの生活を支えてくれている存在でしかなく、 グレーゴルに価値を持たせていたのは唯一「働く」ということだけだったということか。 ここに、近代社会に生きる男の孤独感、疎外感を痛感する。これは現代にも通じるものである。 しかし、グレーゴルが最後に「感動と愛情とをもって家の人たちのことを思いかえす。」と語ったのが印象的である。 考えてみれば、虫になる以前人間として働いていた頃の彼の願いは、家族が自立することであった。 そしてグレーゴルが虫になってしまってから、差し当たって明日の暮らしをどうにかする必要のある家族は めいめい仕事を見つけ、父はかつての威厳のある姿に戻り、母も仕事を始め、妹は一人前の娘となった。 結果的にグレーゴルの願いは奇妙な形で実現することとなったのである。 だからこそ、グレーゴルは死の間際に「感動と愛情とをもって」家族を思い返し、静かに息を引き取ったのではないだろうか。 とすると、「我」を抑え遮二無二働いていた頃のグレーゴルと、虫になってからのグレーゴルとは 大して差がないのではないだろうか。むしろ、苦労のない分虫のほうがマシかもしれない……。 とまあ、色々と考えさせられるが、解釈は本当に人それぞれ、無数に存在すると思う。 時代を超え、読者の想像力を無限に掻き立てるこの作品は、まさしく海外文学最高傑作の一つと言っても過言ではないだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 恥ずかしながら初めて読了した。『城』と『審判』は読んだことはあったが高校の読書感想文の肥やしでしかすぎないとバカにしていたからだが。で実際に読了したら100ページにも満たない分量の短編ながらやはりカフカであった。期待を裏切らない作品だった。 カフカの作品の特徴として物語の初めと終わりがとにかく鋭利な刃物で切り落としたように切断されているのだと思う。『城』の主人公は理由もわからず仕事に呼ばれたはずの城から拒絶。『審判』の主人公もやはり理由もわからず裁判沙汰になる。そしてこの『変身』の主人公はやはり理由もわからず身体が毒虫になっているという。設定がどれも荒唐無稽であるが,人の生涯なんて多かれ少なかれそうではないのか? ある時気がついたら生を受け周囲が作り出した環境の中に放り込まれている。そういう意味においてこのような始まり方の小説というのは、実は荒唐無稽ではなくこの上もなくリアルな事象なのである。そして小説の中のやり取りもこれまた非常にリアルで行動も心理描写も並大抵の作家もどきでは真似することもできないだろう。 当然のことながら毒虫は隠喩である。初め自分は毒虫であるグレゴール・ザムザを登校拒否・出社拒否した引きこもりと思った。しかし途中からは介護老人を思い起こさせた。そして次の瞬間には手に余ったペットにも思えてきた。多分どれにも当てはまるのだろう。自分はまだ子供を持ったことがないから分からないが,ある日突然引きこもりになった子供を抱えた親は,息子と毒虫という親愛に思う感情と忌み嫌う感情に挟まれて逃れられない感情の迷宮をさ迷うだろうと思う。しかし毒虫を介護老人に見た時自分は自分の幼い頃の祖母を思った。確かに自分はこういう感情を持っていたのだ。そして手に余ったペット(熱帯魚)なのだが,引越しを考えていた時に熱帯魚が全滅したことにホッとしたのだった。そして自分はこの作品を読み始めた時に毒虫と化したグレゴール・ザムザを笑ったのだ。そして読後は虚しい読了感。きっと熱帯魚も祖母もベッドの上や砂利の上でグレゴール・ザムザような気持ちで周りを見て薄れ行く記憶の中で寂しく逝ったに違いないのだと考えるとなんともやりきれない思いがした。もちろん毒虫をユダヤ人の立場に置き換えてもあてはまるだろう。ナチスの強制収容所職員の感情は,なんとか口減らしをしたくてたまらずわざと過酷な状況にユダヤ人を置いて自然死させようとしていたのだから。 星を5つにしたいところだが4にするのは5以上と思ってもらいたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 古い本だが綺麗に扱ってあってとてもよかった。気にいっている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 商会でセールスマンとして勤め、両親と妹を養っているグレゴール・ザムザ。 ある朝目覚めると、突然大きな毒虫になってしまっていた。 両親は泣き、妹は果敢に毒虫の彼の世話をしはじめる。 グレゴールは意識だけはそのままで「家族思いで、みなに労りの気持ちを持ち続け」ている。 しかし、意思を伝える手段が全くなく、家族は彼をどうあつかったらいいかわからない。 毒虫になったグレゴールが自分の体の機能一つ一つに苦労したり、慣れていく様子が事細かに書かれ、あわせて家族に対する優しい気持ちも独白の形で述べられます。 にもかかわらず、毒虫のグレゴールに慣れようと努力していた家族が、だんだんい疲れていく様子が悲しくやるせない物語です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 現代の疎外される者、人は個性が過ぎる人を疎む傾向があり、それを誇張することで極限の疎外される者を読書にわかり易い様に書いている。 彼を私たちは実際に見たとき、家族にも耐えられなかった個性を他人が受け入れられるはずも無い。 私も疎外してしまうに違いない。 それが人であり、毒は私たちが攻撃的になり防衛手段として持たせるのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 学生時代に読んだ書籍を読み返そうと購入しました。 ユダヤ的な不条理を物語として、昇華している良書だと思います。 図書館の本があまりに古い場合には、是非文庫ですし、購入してください。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| はじめて読むカフカ。孤独な人だったそうである。文体は非常に淡々としており、どこか第三者的な視点である。シュールレアリズム、実存主義の先駆者であるとのこと。たしかに、この時代にこんなシュールな作品を書くとはある意味、自由な人でもあったのかもしれない。作品は、ある朝起きるとでっかい芋虫みたいなものになっちゃった青年の物語。笑ってしまってもいいのかもしれない、しかし笑いは皆無。ひたすら、地味に徐々に家族、その他から迫害されていく、それと気づかないようにひっそりと。最後のほうを淡々と読んでいたとき、ちょうど最寄りの駅につくかつかないかくらいの時に、報われない世界に対する、猛烈な孤独と絶望の悲哀がふわっとわかった気がした。どの文章だったかは忘れてしまったが… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 安倍の工房が好きな人は、この作品も好きになるはずである。 とりあえず、妹オイ! ってかんじだ。 時間が許せば、城を読みたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『変身』の視覚化は大変だったろうと思う。カフカ自身がグレーゴルの姿を視覚化することに反対だったからだ。そして「変身」だが、もともとのタイトル(Die Verwandlung)は「変貌」「変化」の意味合いで、そして「虫」に変身したといっても、その虫は「昆虫」の意味ではなくネズミなど害獣を含む広い意味をもった「Ungeziefer」であった。 訳文どおり、虫に変身したとしよう。虫であるならそういう描写はありえない矛盾したいくつもの描写がここにはある。さらにグレーゴルの思う「虫」と、まわりの大人が見た「虫」が、同一であるかどうかはわからない。「虫」に変身したグレーゴルをグレーゴルだと認識した根拠も不可解だ。まったくの「ゴキブリ」だったらグレーゴルとは思えないだろう。どこかにグレーゴルの痕跡がなくてはならない。なら、どのような姿をしていたのか。 そういう矛盾したというか、統一した世界を描いたとはとうていいえない作品がカフカの『変身』だった。しかしこのおかげでというべきか、作品世界の迫力は並のものではない。その後の野蛮な20世紀を予告した、予見の文学といっていいものになった。 『変身』を絵本にすることには、このように錯綜した作品世界を縮小していくことになり、その縮小には何重もの困難さがあっただろうと思う。牧野良幸の銅版画は、この世界に静かな諦念ともいうべき情緒を導いて、好感がもてた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ある日突然男が巨大な虫に変身してしまうという奇怪な設定だが、人間の裏をうまく描き出している。20世紀最高傑作と呼んでも過言ではない。 細かい心理描写で予想以上に読みやすくなっているのは、文豪のみが成せる技。有名な作品であるものの敬遠しがちだが、一日で簡単に読むことができ、かつ読み応えが抜群にある。 人間の不条理さと孤独について深く考えせられる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| オーストリア=ハンガリー帝国領プラハ出身の、20世紀文学を代表するユダヤ系作家フランツ・カフカ(1883-1924)の作品、1912年執筆。当時彼は、ボヘミア王国労働者傷害保険協会の勤勉な小役人で、近代官僚機構の最末端に身を置いていた。 近代ブルジョア社会は、個人を何者でもない何者かという suspending な存在でいることを許さない。個人は、「社会」の内に於いて当該「社会」の言語によって名指し可能な何者かとして在ることを強要される。断片化という原初的暴力だ。何者かである何かが、俺を同じ名前で呼ぼうとする。匿名多数の他者は、俺でない何かを持ち出して、それが俺だということにする。そもそも俺に名前など無いのに。実存――あらゆる即物的規定を超越する不定態として、人間存在は如何なる規定を拒否する機制。実存の死屍累々としての社会。 自我は、自己否定による自己破滅をも辞さないほどに否定性・超越性という自己関係的機制を純粋に徹底せんとする実存は、断片化の暴力に抗しようと、必然的に敗北を喫する以外にない闘争――日常性との血みどろの闘争――にその悲劇的な結末を承知しながらその上でなおも赴き、成就すべからざる成就としての全体性の回復を待つ。 「待つ」と云う美的態度。いつからか、待つことでしか、生きていくことができなくなっている。日常と云う時間は、そうした生の在りようの、戯画化された反復だ。その中で、俺は何処に腰を据えるのだろう。どの椅子も、それぞれに、居心地が悪い。家に、部屋に、タオルケットに、俺は退き下がり閉じ籠りたいのだけれど、そこはそこで、窒息の苦しみだ。 「社会」の内に在って、全体性の回復を希求する者は、毒虫の如き異形を晒すしかない。「社会」にとっては、不穏な存在――内在化された超越――なのだ。 現代は、communication ばかりが肥大化し、独在という構えに存在余地は無い。我々は communication へと疎外され、強迫的に関係を求める。予め設えられた商品としての communication へ参画することそれ自体が自己目的化している。そこでは「(当該「社会」で位置を与えられている限りでの)充実した私生活」を演出し見せ合わなければならないという無言の抑圧に支配されている。日々の止むに止まれぬ鬱屈は、選別され粉飾された多幸感に溢れる communication vacancy の中には、居場所が与えられない。皮膚にまとわる「日常」にもがき苦しむ者の赴く場所ではない。「communication tool の発達」と騒いでいるが、要は愛想笑いの場所が増えただけだ。効用と定型句に埋め尽くされた「社会」に、即物という暴力的な存在様態が遍在する「社会」に、人間の居場所は無い。そこは、縁の無い無限遠の穴のようだ。喧噪だけの空虚。 communication から人間を捉えるのは、倒錯している。communication tool を通して他者と一つに繋がった気でいられる者は、自己欺瞞に陥っている、独りであることを知らないのだ。そこで空疎な愛想笑いの交換をして何の摩擦抵抗を感じないでいられる者のほうが、却ってよほど毒虫じみて見えないか。自分が毒虫じみているなどと想像してみることさえ無い傍観者の非意識自体が、ザムザの毒虫以上に醜悪な姿を晒していないか。 独り言でしか口にできないことを誰かに伝達しようとする矛盾。そこにこそきっと、人間どうしの関係と云うものの存在理由があるのではないか。 communication tool に瀰漫する太平楽と冷笑と演劇的な深刻を、孤独な絶望へ転化せよ。 死に到る絶望が、致命的に足りない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 納期も早く商品も満足いくものでした。 また機会があったらよろしくお願いします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 朝おきたら虫になっていた そして母親が扉の向こうから「アンタ仕事の時間やで!何寝てんの!」 ってな感じで話が始まる、100p足らずの短編物語 ホラーではないと思った なんだか笑ってしまって私はコメディーだと解釈した 終盤は感動する所もある 虫になった自分の体のリアルな描写が、面白くて興味をそそられた カフカがシリアスなメッセージとして、これを書いたなら、どうだろう、と思うけど 笑いとして、センスのいいジョークとしてコレを書いたなら、やはり凄い人だと思う ベッドで腹を打って、ココが一番痛い部分か!、と言った所とか面白かった | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 難解と言われるカフカですが、この「変身」だけは、誰にわかりやすく、数十年ぶりに読んだのに、改めて感動しました。 こんな昔に、福祉社会の現代に通じるテーマを見事に描いてみせたカフカはやはり天才です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 子供の頃、僕は変身したかった。ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊ものの赤、セーラームーン、ゼブラーマン…自分ではないちょっとヒーロー的(ヒロイン的)な何者かになりたいという憧れが強かった。変身してヤンキー(ごめんなさい)を懲らしめ注目を浴び、あわよくば意中のあの娘を…などと妄想すること毎晩だった。それが無理ならせめて親類縁者にいないものかと、友達に自慢できるのに…などと依頼心を募らせてもいた。 けれども成人すると、さすがに人は変身できないのだと知った。いや、整形だとか性転換手術を受ければ、それはそれで劇的な変身が可能だとは知ったのだが、自分の求めるヒーロー的な変身とはどうやら方向性を異にしていた。自然と僕の変身願望はセピア色の思い出に変わり、むしろ今では恥ずかしい過去として封印したい。親類縁者に…という件もそうだ。「おれのいとこオーレンジャーなんだぜ、すげえだろ?」などと吹聴してしまったことをとても恥ずかしくまた申し訳なく思う。これらの感慨は、朝井リョウ氏の「何者」を読んでからさらに深まった。みんな自分が何者にもなれないとわかっているから必死に就活するんだ。それなのに僕ときたら… カフカの「変身」を読みながら、僕は身につまされる思いがした。朝起きて、たとえば自分が仮面ライダーに変身していたら、それはもうとても困る。家族はもっと困るだろう。「変身」というものは「出落ち」感が強いのだ。最初のインパクトこそ強烈だけれど、すぐに飽きられる。変身した人間と朝食を取る家族や、一緒に仕事をする同僚は、きっと気まずくて耐えられないだろう。ウルトラマンはそれをよくわかっていた。だから地球にいられる時間を3分に制限したのだろう。カップラーメンの標準的な待ち時間が3分に設定されているのも偶然ではなさそうだ。ましてや何もかもが高速化する現代では、出落ちの賞味期限はもっと短いだろう。 カフカはすべてをわかっていた。ウルトラマンや仮面ライダーが生まれるよりもずっと早く。そこが、スゴい。そして、僕は自分の馬鹿さ加減を思い知らされた。星5つ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 訳によってかなり印象がことなる作品らしいのですが… 個人的には、最初から最後まで自問自答の連続の作品だと思います。 もしこうなったら自分は… もしこうなったら家族は… それをひたすらさらりと…息絶える時もさらりと…その後もさらりと… 感動、不条理、後味の悪さそんなのは一切、個人的には感じません。 ただ、ふわふわしたなんだろな〜っていう感じは残ります。 インパクトで☆4です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 結末を含め、本当に重いです。 その意味では、精神的に安定したときに読むべき作品ですし、万人受けはしないと思います。 主人公が毒虫になるという異常な事件が、極めて冷静な報告調の文章で描かれます。 異常で不自然なことが、ごく自然な語り口で語られることで、異常な事柄がリアリティをもって読者に伝わってくるのは、カフカの類まれな才能によるものだと思います。 毒虫になってしまい、父の投げたリンゴのせいで最期をむかえる主人公を、「社会から疎外された存在」ととらえ、「私もいつそうなってもおかしくない」とか「今の自分がそうだ」と読むことが可能だと思います。 名作といわれる小説の特徴は、「まるで自分のことだ。自分にしかこの小説の真の意味は分からないはずだ」と読者に思わせるところにあるといいますが、まさにこの作品はその特徴を持っていると思います。 カフカのメッセージは、人間の存在は脆弱である、ということではないでしょうか。 人間の存在は脆弱である、ということはおそらく普遍的真理であると思います。 そうであるかぎり、この作品は古典として半永久的に読まれ続けるのだと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 正直よくわからなかった。 しかし、家族というコミュニティの中で一番必要とされていた状況から、毒虫にかわったことで一番の邪魔者へと変わり、不必要な、疎い存在にかわる。 そこに何か、ヒトの存在性の希薄さというか、本来的にヒトが無であるというようなことが感じられる。 所詮、ヒトがいる意味、私がいる意味というものは大きな意味での社会の中で与えられる、絶対的なものではなく、相対的なものにすぎない陳腐なものなのかなと思わされた。 解説のところでもあるように実存主義的な部分がすごい感じられる。 また、そこにこの本の価値を感じた気がする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| さまざまな解釈があるが、僕はこの結末は或る意味グレーゴル本人が望んだことだと思います。 セールスマンとして働き家族を養うグレーゴルと、グレーゴルが稼いだお金で生活する両親と妹の中で今の生活を一番嫌っていたのはグレーゴル本人だったからです。 養っていくべき家族がいなければ、とっくのむかしに辞表を出しているところだとグレーゴルは言うが、実際は歳をとって働く自信を失った父と、 家事もろくにできない母と、まだ17歳の妹に家族を養っていくという責任をおしつけることはできません。 すべてを清算して自由になりたいという気持ち(人生を変えたいという気持ち)と、 家の者を見すてることのできないという気持ちのあいだで、苦悩するグレーゴルに特別な力を持ったものが与えた助け舟が毒虫になるということだったのだと思います。 虫になったグレーゴルの姿を見た家族と会社の上司の反応はグレーゴルが期待したものだったような気がします。 自分はもう働けない(働かない)という行為を正当化し、相手を納得させるものだったからです。 もうこれは起こったことなのだから、あなたたちも受け入れるしかないのだという自分勝手な行為にも見えました。 グレーゴルは毒虫になった生活を楽しんでいるし、幸福にも感じていた部分も見受けられます。 しかし、毒虫に変わってしまったグレーゴルを家族は受け入れてはくれませんでした。 なぜなら、家族も変わってしまったのだから。 グレーゴルが最後の瞬間に家の人たちを感動と愛情とをもって思いかえしたのが印象的で、 グレーゴルがいなくなった朝に残された家族三人の目の腫れた原因はグレーゴルへの愛情からくるものであってほしいと思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 【変身・あらすじ】 グレゴール・ザムザがある日ふと目覚めてみると、自分の姿が巨大な毒虫になって いることに気がついた。 グレゴールの家族はと言えば、恐ろしい姿に変わってしまった彼を部屋に閉じ込め ながらも、食事の世話をしたり部屋の掃除をしたり、何とか一緒に生活をしようと する。しかし、そんな生活も長くは続かず、段々と異形の姿に変じたグレゴールを 疎むようになり―― 【変身・感想】 家族の為に尽くしてきた男が、異形の姿に変じたことで居場所を失っていく様が シュールに描かれています。グレゴールが良かれと思ってしたことが却って裏目に 出てしまっていたり、本当に何の理由もなく≪毒虫≫になってしまうなど、世の中 の不条理をそのまま切り取ったような作品です。 ただ残念なのは、個人的に訳が余り良くないと感じてしまう点です。原文をそのまま 日本語にしたような訳の為、一文がとても長く、また不自然で回りくどい表現が目に つきました。 『ある戦いの描写』はこの本にしか入っていないようですので買って損はありません が、『変身』は他の訳で読んだ方が良いかもしれません……。 【ある戦いの描写・あらすじ】 夜会でとある男と知り合った私は、共にラウレンチベルク山を目指すことになる。 そして道中繰り広げられる奇妙な会話の応酬……やがて物語は夢と現実の境界を 無くし、カフカの想像世界へと読み手を誘い、翻弄する―― 【ある戦いの描写・感想】 とにかく難解です(笑) 夜会で出会った男『知人』と山へ向かう合間に繰り広げられる会話は本当に奇妙でした。 『私』は唐突に『知人』は『私』が背が高いことが気に食わないのだと思います。 何故そう思ったのかは分かりません。とにかくそう思ったから、『私』は急に体を前に 屈めて歩きます。 『あなたは何をやってるんですか』 『いやはや図星ですな』『――あなたはなかなか鋭い目をもっていらっしゃる!』(P.131) このような奇妙なやりとりが幾度となく繰り返されます。そして章が変わると場面も急 に変わり、4人の裸体の男に神輿で担がれている≪肥大漢≫なる人物が登場します。 そしてその後の章では、肥大漢の友人なる祈祷者視点の語りへと移行します。 一体、『私』と『知人』の話は何処へ行ってしまったのでしょうか……? カフカが21歳の時に書かれたものらしいですが、このような奇怪で難解な話をその年 で書くとは……やはり只者ではないですね!(笑) この話は解説でも解説放棄されているくらいなので、自分の目で確かめた方が早いです。 『私』の自問自答のようでもありますし、自分自身を他の視点で見つめて語っているの でしょうか……? 本当に説明が出来ない作品です。 ただ、上でも記載しましたが、訳が余り良くないが為に、より理解が難しい……という面 もあるかと思います。本当に訳が残念でなりません。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!