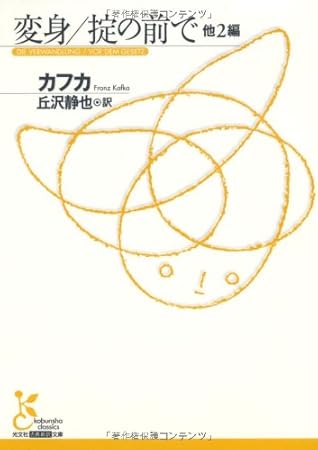■スポンサードリンク
変身
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
変身の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.08pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全293件 241~260 13/15ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「朝目覚めたら主人公グレゴール・ザムザが、巨大な虫になっていた・・・」というプロットだけはあまりに有名なこの作品。小説という形式において、その想像力の可能性を遺憾なく発揮しています。ただし、内容の解釈が極めて困難です。 平野啓一郎氏はこの『変身』をモチ−フとして、『最後の変身』なる短編を書いていますが、その主題は「引きこもり」です。さらに村上春樹氏も『海辺のカフカ』という長編を書いていますが、私なりの解釈ですと、そのメタファーに富んだ作品の主題もまた、「引きこもりの救済」であるように思います。虫に変わってしまったザムザに対する家族の対応の変貌、すなわち引きこもりという社会的に害虫のような存在が周囲に与える影響、というようなものを表現していると感じました。 つまりこのカフカの『変身』は、恐らく最も早く「引きこもり問題」を提起した、先駆け的作品なのではないでしょうか。少なくとも平野氏や村上氏は、そう解釈して、この『変身』をモチーフに自作を書かれているように見えます(といっても、やはり読み方によって多元的解釈を成すことが可能な作品であると思うので、私の考える解釈の仕方も、その内のホンの一部に過ぎないことは重々承知ですが・・・)。 また、もう一つの見方で、世の中何が起こっても不思議じゃない、というテーマも、映画『マグノリア』や、村上春樹氏の『海辺のカフカ』の、空からカエル、ヒルが降ってくる、という作品の先駆けでもあるように思います。 そもそも、タイトルの『変身』という言葉、これは意外とグロテスクです。我々は日々社会に適応すべく、仮面を付けつつ何らかの姿に「変身」して生活を送っています。その場合、普通、自分をより良く見せようと、善い人に見せようと、「変身」するのです。しかし、この物語の場合は、悪い方へ悪い方へと「変身」してしまいます。しかも自分の意志によってではなく。これはやはり凄く意味深長であるように思えます。とにかく、明確な掴み所がない作家であり作品で、『審判』『城』などを私はまだ未読ですが、それらを読むことでこの『変身』のポジションも理解し得るのではないかという気がします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 息子の部屋にいる毒虫を、気持ち悪いと思いながらも息子だと思っている(らしい)。しかしその理由といえば、息子の部屋にいたから、ってことでしょう? 私たちは、この虫が主人公だと知っているから、小説として違和感なく読んでしまう。読まされてしまう。これって、作者にうまく乗せられているのでは? 例えば実際に、朝になって息子のベッドにでかい毒虫がいたとしたら、普通「この虫が息子を食ってしまった」とか思うんじゃないの?虫が人の言葉で説明してくれるわけでもないんだし。 家族全員が、その辺の確認を曖昧にしたまま話が進んでいくから、家族の接し方は最後まで曖昧。 最後にやっと、みんな何となく思っていたことをお互い知ることができて、晴れ晴れとした明日が見えてきた。 などとつっこんでみても、やっぱり面白い小説でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ある朝、突然虫に変身してしまった、主人公。 あまりにも有名な作品ではあるが、あらためて読んでみると、変身したのは妹を中心とした、家族だったのでは・・・と思ってしまう。 ラストはある意味で象徴的だと私はおもうのですが・・・ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカはゴーゴリと同じで、とっても奇想天外。そしてサラリーマン、下級官吏の悲哀に満ちています。カフカの方がちょっと寂しそうで青白い青年風。ゴーゴリはもうちょっと破天荒で、やぶれかぶれの大立ち回り。お魚になった私?ならぬ虫さんになったカフカ。可愛い思いつきですね。なんだか小難しい哲学的?高邁な読書もいいんですが、自分なりの読み方をしてみるのも楽しい。虫になったおかげで会社もやすめたし。最近流行の引きこもり?在宅症候群の走りか?通勤拒否のサラリーマン、登校拒否の大学生、高校生、中学生の気持ちを代弁しているのかもしれません。 しかし実存主義って今はどうなっちゃったんでしょうか?高校生の頃、すごく難しそうで面白そう。って思った記憶が甦りました。若い頃って一見難しそうだと何でも良さそうに見えたものです。でも、結局こうして人生長く生きて、その度に読み返せる小説はなんとか主義を超えた小説としての、ブンガクとしての良さ、美しさ、胸にせまる詩、そして心地よい音楽に満ち満ちて輝いています。 実にすっきりと端正に無駄なく絵になったユーモアのセンスに溢れた作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品を読む上で注意すべきなのは、先入観を持たないことである。特に「不条理」などという固定観念ほど作品に接する上で邪魔になるものはない(「不条理」とはカミュが言い出したことであり、カフカが言い出したことではない)。先入観を排しさえすれば、この小説がいかに驚くべきものかがわかってくるのではないかと思う。作品そのものに向かい合って読むほどに、その深みと凄みが迫ってくる。まさに文学史上でも類のない、稀有なる傑作である。 余談になるが、カフカの晩年の作品に『歌姫ヨゼフィーネ、あるいは二十日鼠族』というものがある。この作品のタイトルを、カフカは天秤の両皿にたとえていた。つまり「あるいは」が天秤であり、「歌姫ヨゼフィーネ」と「二十日鼠族」とが同じ重さで釣り合っている、というわけであろう。このことを『変身』に当てはめてみると、次のようにタイトルを変えてみることもできるかもしれない。つまり『毒虫グレーゴル、あるいはザムザ家の人びと』と。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 何十年も前の小説とは思えないくらい、新しくも不思議な感覚だ。「情報は変わらないが、人間は変わる」と何かの本で読んだが、その言葉を思い出した。人は変わる。。。自分が意識しようが、しまいが。そのことを、突然虫に変わってしまった主人公を通して、切なく悲しく時には、おかしみをまじえて、語られる。意図しないで変わってしまった主人公と働き手を失った家族が自立していく姿。家族が主人公をだんだん重荷に感じるようになる過程がとても悲しい。それぞれの変身が人間社会を映している。名作といわれることはある。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あまりにも非現実的な話を淡々と、そして真剣に語られる文章から様々な解釈を引き起こしたと言うが、私は私なりの一つの解釈を挙げたい。 主人公ザムザは一家の長男で、必死に働きほとんど一人で家計を支えていたが、ある日突然目が覚めたら虫になっていた。それを見た家族、仕事先の支配人は驚き、家族は彼を嫌悪し、部屋に閉じこめる。一家の大黒柱が働けなくなった今、隠居生活に入っていた両親も働かざるを得なくなる。兄のザムザが大好きだった妹も、“餌”を与えるときしか兄の部屋に入らなくなる。 さて、“変身”したのはどっちだろうか。ザムザは本質的には何も変わってはいないのに、周りが急速に変わっていく恐怖。例えばあなたがいきなり何かの弾みですごい有名人になったとして、または事故にあって不自由になったとして、変わるのはあなたか、周りの人間か。 KAFUKAのKをZに、FをMに置き換えるとZAMUZAになるのも興味深い話である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 朝起きたら毒虫に変身。 絶対にありえないと分かっているのだけれど、それを上回るリアルさで表現された作品。 姿かたちは醜くなった主人公だが、それを取り巻く家族の醜さのほうが際立つ感がある。 この作品が何を訴えたいのかは読者次第だが、読んで、今の自分を見つめる機会にするのにはよいアイテム。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| おそらく世界文学の中でも1、2位を争う傑作。様々な解釈ができるストーリー、漂う不気味で恐ろしい雰囲気。現代社会を映してるようなストーリーで、これを先取りしたカフカはやはり天才だ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「城」と大違い。傑作だ(「城」も有害性の点では一流の文学作品だと思うが)。プロットや登場する事物に象徴主義的解釈を施せば切りがないが、それ以前に理屈抜きで読んでいて楽しい作品だと思う。 特に、ザムザが誰もいない部屋で足から粘液を出して壁の上をぺたぺた歩いている様(ピエール瀧が「ネバピョーンネバピョピョピョーン」と言い出しそう)や、長椅子の下でいじけたようにじっとしている様子を想像すると、憐れみと同時におかしみを感じくすっと笑ってしまう。不条理を突き抜けて笑いを獲得しているところが優れている。 プロットには「何かを再生させるためには犠牲が必要だ」というメッセージがあると感じた。 私のように笑いを得る人がどれくらいいるのか知らないが、読者のさまざまな感受性に異なる姿を映すだろうこの小説は見かけによらずそんなに重厚ではない気がする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 一次大戦後の社会(主にドイツ)情勢うんぬんは平和な現代じゃ理解し辛いものがあります。なので、もっと早く生まれて大戦後の混沌としていた時期に読んでみたかった。 そんなわけなので、物語の真の意味みたいなものはいまいち判りかねますが、時代性が失われても、その奇抜な設定と、対照的にひどく現実的な文体によって、現下においても多くの人に読まれているのでしょう。 物語の感想てして私見を述べさせて頂くと、まず、作者が毒虫としたからにはやはり毒虫でなければいけなかったのではないかと思います。 とは言えしかし、見方によれば、身勝手な人間に対して、真の意味でのアニマルライトを叫んだ作品とも見てとれますし、家族とは所詮他人なのだと説いた作品にも思えますし、アイデンティティークライシスへの不安を吐露した作品とさえ言えます。つまりそういったいい意味での抽象性が本作品にはあり、読者の数だけ、この本の良さもまさに、「変身」するのでしょう。 これらの様な鑑賞者の自由性を含んでいる事こそが優れた芸術作品の条件なのでしょうね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 同社からハードカバーで刊行されていた池内紀訳カフカ小説全集を、新書版の白水社uブックスで改訂再刊した1冊である。ハードカバーで読もうと思っていたが、スペースなどの問題もあり、二の足を踏んでいたのだが、新書なら有難い。 池内訳はこなれており、するりと読むことができるので、翻訳嫌いの読者にも受け入れやすいだろう。 いまこの小説を読むとすると、不条理なんて安易な言葉で片づけられない。やはりこれは身体と病気の問題なのだろう。うつ病のケアや脳梗塞発作、認知症患者などの介護問題にあまりにも近すぎる。 カフカのプロフィールに触れた解説も興味深い。原書初版の表紙の書影が掲載されているが、そこには主人公の姿を描かないようにカフカ自身が指定したという。結果として、エドワード・ゴーリーのような不気味な雰囲気になっていたのは面白い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 妹のためにお金を貯めておいて、クリスマスに音楽学校への入学をプレゼントをしようとしていたクレーゴルは毒虫になってしまった。なってしまったのならどうしようもない。毒虫として生き、毒虫が食べるものを食べなくちゃいけない。 その妹がバイオリンを披露したときクレーゴルは嬉しくて嬉しくて部屋を飛び出し、妹の足元まで来てしまう。しかし、当然気味悪がられてリンゴか何かを投げつけられてしまう。 グレーゴルは妹想いで親想いで良い人間だったと思う。仕事も不満はあったみたいだけど熱心にやっていた。だけど毒虫なので、皆に嫌がられてしまう。 一所懸命やっているのに認められない人がいる。とても残念だが、それは見た目が良くないのが理由であることもある。よく、「心が綺麗である事が大切だ」とか「見た目だけきれいにしても駄目だ」とか言われる。 しかし、他人は外から来る。すなわち外面がまあまあ良くて、取っ掛かりがあるからそこから内面の交流が始まる。だから朝起きたときに毒虫になってなければ感謝して目覚めよう。そしてきちんと髪を整えて、ちょっとおしゃれしたり、いい香りを付けたりして人生を楽しめるようにしよう。そうしないとせっかく心をきれいにしていても無駄になってしまう。 グレーゴルが息を引き取る場面には彼の心理描写は少ないが、彼は決して恨まなかったと思う。彼の周りの人のことも、彼自身の運命のことも。しかしそこまで彼の心が綺麗だったとしても、毒虫になれば毒虫として一所懸命に生きなくてはならない。それが心が綺麗だということなのだろうな、きっと。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 自意識を残したまま「毒虫」になってしまう男ザムザ。その姿を嫌悪しながらも虫になったことにはなにも疑問をもたない家族達。最初は彼の世話をしつつもだんだん冷たくなる妹。死んでしまったザムザに涙を流しながらも、家族は重い荷物を降ろしたのかのように休暇を取って出掛けてしまう。淡々とした、事務的とも言える文章で書かれたこの物語、何か覚えはないだろうか。私は、長い間認知症を患い最後は寝たきりになって死んだ同居の祖父に対する不謹慎な気持ちを思い出してしまった。 この作品が書かれたのは90年余り前のことである。実存主義文学の先駆をなしたといわれるこの作品が、当時どう読まれていたかはよくわからないのだが、私にとっては“ある朝、目が覚めたら虫になっていた”という不条理な設定で始まる、人間の奥底にある暗い心理を描き出したリアルで重い作品である。今読んでも決して古くない。 ただ、高校生になったばかりの頃初めてこの作品を読んだ私がそうだったのだが、流して読むと単なる気持ちの悪い話にすぎないかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私目が覚めたら私じゃなくなってて、 「でも私、私なんです。」 そんな私の変身を、 ただの変身として受け入れてくれる人がなかなかいない。 よく考えたらそもそも私なんてたいして変わっていない。 普通に死ぬし。 私にとって私はかけがえのない私だったけれど、 家族とか社会とか世界とか地球とか宇宙にとっては、 穴埋めのきく私なんだよなぁ。 困ったな。 でもとりあえず生きとこう。 そんなことが言いたいのかなぁと思いました。 でも、カフカのいいところは、 小説書いてるうちに自分にもよくわかってないことが出てきてしまうことに対する困惑も書けてしまうことかな。 私はそんな気がします。 読みたくない人は一生読まなくていいけど、 私は星を五つつけてしまいます。 (そもそも本なんて読みたい人だけ読めばいい。) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品を呼んで、ある日突然主人公が奇怪な毒虫となり、父親、さらには妹のグレーテにまで邪魔者扱いされ、最後は父親の投げた数発の林檎が原因で死んでしまう場面が描かれており、一種の疎外感のようなものが描かれていたが、家族がグレーゴルが死んでしまった後に、移り住む事を決意し、以前はグレーゴルが探してきた家に住んできたが、今回は自分達自身でよりよい住家を見つけようとした場面から、自分達自身で明るい未来を切り開いていこうとする姿が描かれていた。さらにここでは、切り捨てようとしていた過去は、自分達の過去の生活だけではなく、グレーゴル、及び彼と暮らしていた生活でもあったことが伺えると思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒虫がなにかって言うことを考えるだけで、この本が身近に感じると思う。たとえば、毒虫を、交通事故にあって半身不随になったということに置き換えてみたら?脳溢血で倒れて半身不随になって寝たきりになったとしたら?見た目は変わらないけれども、突然リストラされて無職になってしまったとしたら?等々。自意識は昨日までの自分と地続きで同じだし、自分の周りの人との関係も見た目の変化ほどにはあまり変わらないのだが、しかし、不幸な出来事は必ず、自分と関係のあるごく身近な人に影響をあたえ、長引くと、時には、酷薄ともいえるような感情さえ引き起こす・・・(死んでほっとしたりとか)。なんというか、だれの心にもある「痛い」ところを突いてきて、「かなしく、苦しい」話である。だから毒虫を毒虫としてしか読めないと、へたなSFみたいで、何を言っているんだかわからないとおもうが・・・。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 朝起きたら虫になっていたザムザ。そのことにザムザを含む登場人物たちは、誰一人として疑問を持たない。彼の家族は働き手がいなくなってしまったことに悩み、それを解決しようとは思うが誰もザムザを人間に戻そうとは考えない。結局、物語の中でその理由に関する説明はない。 不思議な話だった・・・ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカにとって、主人公グレーゴルが、巨大な虫になったことはどうでもよかったと思われる。 むしろ、その周り、(家族)の変化(変身)していくことのほうが、重要だったのかもしれない。 虫になったグレーゴルを、家族は、なぜ見捨てたのか?ということよりも、グレーゴルに依存していた家族が、心身ともに自立していく物語と、とえた方がよさそうである。 彼(グレーゴル)が、犠牲になることで、悲しいが家族は自由になっていく。そんな考えが浮かんできた。 家族の変身こそ、『変身』の隠されたテーマである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 或る日突然自分が「毒虫」に変身していたら、どうしますか? それでも会社に行こうとしますか? 逆に、大切な家族や愛する人が「毒虫」になっても、それまで通り愛せることができますか? 凄く深く考えさせられた1冊です。 正直始めは「面白いストーリーだな」と思って見ていました。 だって、「毒虫」になるなんて普通は考えられない。ましてや「文学作品」において、何の前ぶれもなくいくなんて。 そして、主人公グレーゴルは毒虫に変身してしまっても会社へいこうとする 普通「先ず、どうやって人間に戻れるようになるのだろう?」と考えないのか?と思ってしまうだろう。 そんな部分が「面白いな」と感じた。 しかし、段々とシビアな世界へと入っていく。 家族が愛してくれないのだ。 人間だった頃のグレーゴルは大黒柱であり、愛されつづけてきたのだと思う。しかし、「毒虫」に変った時から一転した。 彼を産んだ母親さえも彼を避けてしまう。 随分なお話である。 働かせるだけ働かせておいて虫になったら用なしというわけか? しかし、家族の気持ちもわかる気がする。 いくら中身は変らなくても、見た目が変りすぎている。 でも「人は見た目より中身」というのは「嘘」である。ということも伺える。 シビアな性格であったといわれているカフカならではである。 しかし、どんなに御託を並べても「人間は中身より見た目」なのだ。 それは学んだこと。 自分の不可抗力によって生じてしまってもこれは避けられないことである。 でも「グレーゴルは最期はやっぱり愛されていたこと」を忘れないで欲しいと願った。 グレーゴルが生きていて彼が見た最期の家族の姿は「彼を完全に避けている」ということ。それを抱いたまま死んでしまった。 しかし翌朝家族は亡骸を見て泣いたことをグレーゴルは知っていて欲しい。 「やっぱり愛されていた事を忘れないで欲しい」と・・・ | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!