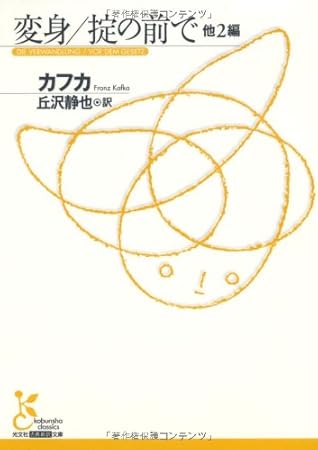■スポンサードリンク
変身
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
変身の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.08pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全293件 221~240 12/15ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| クラシック音楽におけるピリオド楽器によるオケの演奏は、ほとんどの場合好まない。特にベートヴェンやバッハの多くについては。 訳者は翻訳(これはある意味演奏と同様の行為だ)における「ピリオド奏法」を謳い、実践している。高橋義孝訳、池内紀訳を併読したが、この丘沢訳が一番しっくり来た。といってもドイツ語を解するわけではなし、先行訳にも美点は大いにある。 『変身』は、怖ろしい物語だ。筋だけを辿っていても、この力強さは旧約聖書に匹敵する。こういう真の世界文学の新訳は大歓迎だ。『星の王子様』程度のお子様物語の新訳に躍起になるのはどうかと思うが、『カラマーゾフ』といい、本書といい、意義がある。 そういえば『カラマーゾフ』の訳者・亀山郁夫は『罪と罰』にも取り掛かっているらしい。 光文社古典新訳文庫には大いに期待したい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 簡単な言葉で訳すことで、カフカの天才が出てきた。 養老猛司の言うように、自分は自分のままと思い続けた主人公ザムザは不気味だ。 だが、それ以上に頭に引っかかったことがある。家族はなぜ馬鹿でかい虫をザムザだと思ったのだろう。 馬鹿でかい虫に目がいって、家族の視点で読んでしまいそうになるにこらえて、 ザムザの視点で読み進めていきました。人生は切ない喜劇でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み終えて、胸の中がすこし重くなったような気がしました。 解釈としては色々あるのでしょうが(どういった解釈があるのか調べてないので知りませんが)、私は、後半場面での妹の発言がこの作品の中で一番印象に残りました。 やるだけのことはやったのだから、もういいでしょう。というような言葉です。 なぜかこの言葉を聞いて、各地の貧困であえいでいる人たちの姿が思い浮かびました。 妹は、虫になにをしたのか。 虫だけでなく、妹の行動、発言に注目してみるのも面白いと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 判決、変身、アカデミーで報告する、掟の前で、の4編を収録。 カフカの作品といえば、面白くないという印象がある。 作品の内容は、わけの分からない状況に置かれた主人公が右往左往するのを淡々と描くだけなので、読んでいるこちらも訳が分からす、それが延々と続くので、ただ退屈なだけ。 評論家はとそれを不条理とかなんとか難しいことを言って高く評価しているけれど、やっぱりだた退屈なだけ。 あまり読みたくない作家だ。 しかし、そういうカフカ像を産むに至ったのは、どうやら原典の編集段階に問題があったらしく、また、日本訳にもいろいろ問題があったらしい。 史的批判版」に基づく本書は、カフカのそんなイメージを覆す。 なによりも読んでいて面白い。退屈で無味乾燥なカフカではなく、筒井康隆のある種の作品に近い感じ。いやもっと近いのは、やはり吾妻ひでおのマンガだな。 考えてみれば、不条理というのは、主人公がヘンな目に遭わされて困っているということだから、「笑い」とかなり近いところにいるはずだ。不条理作品を読んで笑いが出てくるのは、だから、そんなにおかしなことではない。というよりもむしろその方が自然なのではないか。 最後の「掟の前で」は、いかにもいろいろな解釈をしたくなるような結末だが、「なんだこれ?」、という感想だけでも十分ではないか。 カフカを楽しめる一冊である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 規則正しい労働に嫌気が差したザムザはむしになった 巨大な醜い虫になった 家族はその汚らわしい虫に元のザムザの人間性を見出さずに部屋に閉じ込めた しかしザムザは部屋の中のちょっとしたことや妹のヴァイオリンにまで感動するのである。 労働にとらわれた家族 感動するザムザ。 真の人間らしさとは何なのだろう、カフカは家族とザムザのどちらに人間らしさを見出したのだろうか・・・ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 突然巨大な虫になってしまう主人公。家族は驚き、彼を部屋に封印して苦悩する。 主人公は分かってほしいものだと思いながらも自分がどうしようもない迷惑をかけていることを考え、どうすることもできず不条理と排除を受容してしまう。あるいはそれが主人公の最後の優しさだったのか。この不思議な優しさと、主人公の死によって苦悩から厳かに開放される家族の対比がなんともいえない読後感を醸し出している。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いやな夢の後、体が虫じゃん! その点で人間かなりっつうかありえないんで、現実逃避したりなんだりで、もう死にたくなりますわな。 でもなんか主人公、出勤しようとするし(現実逃避後、つうかこれ自体現実逃避か?逆に現実的すぎ?)、 家族と上司に自分の体みてもらおーとするし、鍵あけてね。部屋の。(出勤の過程かな?) まあ話は暗い方向に向かうかんじなんですがね。(つうか結局死ぬんだけどね) わたしにはこのはなし、コントにしか思えなくって。もう。 なんていうかとかげのおっさんみたいな(?) とにかく面白くって、読んだ後、また読んでしまい、それからまた読んでしまいました。 人それぞれ感想ありますけど、私の感想はシリアスなコントを延々観てるってかんじでした。 棺桶に入る前にぜひ読んでください! 興ざめするので、興味のある方は以下を読んでください。 ・もし無脊椎動物、甲殻類、陸上で生きる「虫」そのものを数倍(ドラえもんの道具みたいなので)にしたら、 虫は生きていけません。大気圧+自重(殻の重さ)に、内圧(肉)が耐えられず、存在してまもなく死にますねぇ。 ぐしゃり!べこっ! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 収録作品は『判決』『変身』『アカデミーで報告する』『掟の前で』です。 クラシック音楽でピリオド奏法が受け入れられていることを受け、 翻訳するに当たって丘沢氏は「相手の流儀をまず尊重」(168頁)するとしています。 そのため本書は史的批判版カフカ全集を底本としています。 この版は、現在のところ、カフカの書いたものが 最もそのまま提示されているとされます(164頁)。 全体として一文一文は短く区切って訳されていて、リズムカルです。 しかし、本書の魅力はこれまでの翻訳でカットされていた箇所 がしっかり掲載されている点です。 例えば、「訳者あとがき」(178頁)によると『判決』(23頁)の 今までカットされていた「答えが質問に衝突したのだ」 という一文が掲載されています。 このように、これまで削り取られていた箇所を掲載したことで 読者の側に時間的な余裕が生まれ、他方で登場人物の心情の変化が 今まで以上に分かるようになったと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 池内版の後に訳すというのはかなりの根性ですが、 訳者は原文の「犬」として訳すという後書きにある態度を徹底することで、 カフカの異様さをすくい上げてます。 ある意味、翻訳ソフトの訳のような異様さ(けなし言葉ではありません)。 「判決」のあまりにも有名な最後の一文の新訳を見るだけでも価値があります。 カフカは意図的に時制を混乱させている、ことがはっきりします。 名訳。池内版に敬意を払いつつこれも是非。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| と、作者のフランツ・カフカ自身語っている『変身』。 物語のあらすじはあまりに有名で、また既に多数の方が書かれているので割愛させて頂く。 ある日突然、自分がまったく知らぬ何かになってしまう恐怖。 そして、そのことを他の人間すべてに看破されてしまう戦慄。 作中グレーゴルの感情がどんどん最初の性格からかけ離れてしまっていっているように、私には感じられた。 自分でもコントロールできない方向に自身がある日突然変わる事への恐怖、とも言えるかもしれない。これは変身願望の一方で誰しもが抱える不安ではないか。(心理的・身体的ともに) 不条理の中にこそ、リアルな深層心理が表現できるのではないかとさえ感じてしまえる作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ある日、目を覚ますと主人公は虫になっているという奇怪なお話。 この作品には実に様々な解釈の仕方があると思うのでそこらへんを読み進めながら色々と考えると面白いと思います。 解説にもありましたが本作には不可解なことがあります。 一、人間が虫に変身してしまうこと。(現実には起こりえない) 二、それを誰も不審に思わないこと。 三、なぜ変身してしまったのか語られぬこと。 これらを踏まえながら「ここはこうなのではないか」などと考えていくと楽しめると思います。 家族の変化の仕方が少し残酷ではありますが、現実的な感じもします。 考えるのが楽しくなる一冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とても奇妙で哀しい、またどこかユニークでもある物語なのでですが、この虫に変わってしまった主人公とその家族の関わり(その変化)を通して伝わってくるものは、見えない本質に繋がるとも言える本当にリアルなものでした。これは主人公はもちろんですが、家族の「変身」の物語でもあります。「人間」と「その社会」の現実を、とても真摯的に、また冷静且つ丁寧に描き出していると思います。 個人とは?他者とは?家族とは?人間関係とは?本来の自分と社会の中の自分。容姿(社会的要素)において築かれているもの。 様々な解釈や想像を自分の中に呼び寄せて広げてくれる、考えさせてくれる、またそうする事の価値を強く感じさせてくれる、本当に深い含蓄を持ったメタファーです。虫を例えば病気、身体的障害の象徴と思うだけでも自分の世界にグッと近づきますし、そうして主人公や家族に自分を重ねる事で見えてくるものは様々に広がります。 またこの短い一種の寓話?童話?の中にこれだけのパワーと信用性を感じられる事に驚きもありました。今更自分が言うのもおこがましいですが、本当にぜひ読んで欲しい素晴らしい作品です。 あと、作者は本の扉絵の理想が「両親と妹が明るい部屋にいて、暗い隣室へのドアが開いているところ」だったそうです。作中にあるそういったシーンの描写もなんとも言えない印象深いものでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み終わったあとも、最後まで違和感が残ったままだった。なぜ「青虫に急に変身してしまった事」それ自体をなぜ誰も不思議に思わないのだろうか、と。 主人公自身はいきなりこんなことになってさぞかしびっくりしただろう。最後に自ら餓死を選んだのも家族に迷惑をかけたくなかったからに違いない。 結局この小説で筆者が訴えたかったことっていったい何なのだろうか?今の私にはまだはっきりと理解できていない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| グレゴール・ザムザはある朝、一匹のばかでかい毒虫に変わっていた。家族の稼ぎ頭であった彼の変貌ぶりに、家族は当惑し嘆くばかりだった。母親は気絶してしまうほどだった。妹は始め兄に食事を差し入れるのだが、グレゴールは姿形ばかりか味覚までも変わってしまったようである。彼の大好きだったミルクが、今では嫌悪感を催す代物になってしまった。視力も虫の必要とする程度まで低下してくる。 グレゴールが次第に「虫化」するにつれて、家族の態度もまた虫に対するものに変わってくる。毒虫が人目に触れるのを恐れる家族は、グレゴールを軟禁状態にする。だが、寂しさに耐えかねた彼はしばしば部屋の外に現れ、その姿を人目にさらす。父親からリンゴを投げつけられ背中についたままになって動く姿や、部屋に無理矢理押し込まれ背中から血を流したりする描写は痛々しい。しまいには、妹から「これを処分するしかないわ」という言葉がはき出されることになる。 妹の論理はこうだ。「兄が人間ほどの思慮分別をまだ持っているのならば、家族に迷惑をかけまいと自分から家を出て行くはずだ」まもなくしてグレゴールは息を引きとる。グレゴール亡き後の家族は、家族の一員が亡くなったことを思わせないほど希望に満ちあふれている。家族の前途は明るい。まるでそんな余韻を残して終わっている。 グレゴールを部屋の中に閉じこめたのは、そもそも家族である。にもかかわらず、妹は「これ」を「処分」することしか、家族が幸せになるために残された道はないと嘆く。これが、人間のエゴかもしれない。エゴは家族愛のあり方すらも変えてしまう。家族の一員、しかも稼ぎ頭を虫けらに変えてしまう。グレゴールを変身させたのはザムザ一家のエゴだったのか。 それにしても、本書の与えるインパクトは強烈だった。朝、鏡で自分の姿がまだ人間であるのに安堵し、いつ飛んでくるかもしれないリンゴに怯えるようになるかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| グレーゴルはなんで「変身」したのか?また何に「変身」したのか?そこは読者の想像に任されている。僕は大きくて変な色の芋虫を思った。 それにしても、両親や妹はその虫がグレーゴルだと信じられたのはなぜなのだろう?不思議な家族愛。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカは、この作品が出版される際に、「表紙に毒虫の絵は描かないでくれ」と注文したという。 「毒虫」は、あくまで「疎外される者」の象徴である。 いつの時代、どの場所にも「毒虫」はいる。 社会的に疎外される者と、彼らを身内に抱える家族。 「家族だから」と庇護する気持ちと「邪魔だ」と疎んじる気持ちは、矛盾しているように見えるけど、きっとどちらも本心なのだろうと思う。 最後、グレーゴルがいなくなった後、リセットされたかのように晴れ晴れとした気持ちで、娘の将来に期待をよせるザムザ一家。 その未来には、「毒虫」の存在は欠片も残っていない。 この話は説明はなく、オチもない。 しかしだからこそ、その丸投げっぷりと残酷さは、ひどく現実的に思えてならない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読後に虚しさを感じた。 裏表紙に海外文学最高傑作とある。 主人公は成績の上がらないサラリーマンだし、最後には妹にまでけだもの呼ばわりされるし。。ほんと悲しくなる。 こういう文学もあるんだと分からせてくれたので☆四つだけど、腑には落ちないな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 外見が変わるだけで、こうも周囲の人間の対応や心は変わるものかと思いながら読みました。もちろんあれへの変身はさすがに物語で空想ですが、私たちは「気持ち悪い」「嫌だ」などの主観でどれだけ他人への態度を決定しているでしょうか。私は「差別」を連想しましたがどう「解釈」するかは人それぞれです。そのへんの現代流行作家の本よりはよほど示唆に富み、上質だと思います。 まずは読むことです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あまりにも有名な「ある朝・・・」という冒頭は、読者に軽い虚無感を与えると同時に、 唐突なイリュージョンの世界へと誘う。そして更に読み進むと、冒頭の変身はすべての 始まりであって、文字通り「変身」が随所に現れる予兆であることに気付かされる。 それは作品の背後で静かにうねりながらゆっくりと、まるで水滴が水面にこぼれ落ち、 その波紋が水面に一輪ずつ広がっていくように、マクロからミクロへゆっくりと病理が 伝染していくように物語は展開してゆく。 社会的、パブリックな関係者からプライベートの関係者へと他者の目を的確に表現し、 そして最も近親者としての家族、特に誰よりも深い愛情を示していたは妹グレーテから の冷たい仕打ちへと変容する現実に、外見が変身した主人公と、内面が変身した家族や 周囲の人々の対比構造は、まさしく現代社会の希薄な人間関係の病理が見事に描かれ ているように思える。文学を一歩進歩させた業績はまさに未来を予見したこの内容にある ように思え、現代人は読むべき作品ではないでしょうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| カフカの中では最も有名な作品で、長編三部作より短いので本作からカフカに入ったという方が多いであろう。私もそうである。主人公が朝目覚めてみたら毒虫に「変身」していた。次第に家族からも冷たくされるようになり、最後には無残な死に方をする。有名過ぎるストーリーである。カフカの持ち味の寓話性が遺憾なく発揮されている。上述の通り短めなので読み易いのだが、カフカの場合、短ければ短い程難解になるのだ。 文章は平易なので単純に読み進める事は簡単なのだが、解釈は様々であろう。毒虫が象徴するものは何か ? 毒虫に変身する人物は主人公である必然性はあったのか ? 寓話的物語からその意味を探るのがカフカを読む楽しみであろう。私が35年くらい前(高校生時)に読んだ時は、毒虫は戦争に突入したドイツ、家族はヨーロッパの他の諸国かなぁ〜くらいに思っていたが、勿論正鵠を得ているとは思わない。その後も色々考えたが、結論らしきものは見出せない。現代的感覚からすれば、仕事・現実の重圧から逃避した"引き込もり"や鬱病等の精神的疾病とも解釈出来る。その割には家族は冷淡だが。 尚、作中の「毒虫」の原語の意味は「他から排除されるべきもの」だそうである。ただし、言葉の表面的な意味が分かっても上記の謎は解決しない。最近、小林秀雄の「無常といふ事」を思い出して、こう考えてもいる。世の中が急速に変って行くと良く言うが、実は変って行くのは自分自身なのである。ザムザの"変身"はそれを直截的に表現したものかもしれないと。 後世の人々に深い謎を残してくれたカフカの代表的傑作。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!