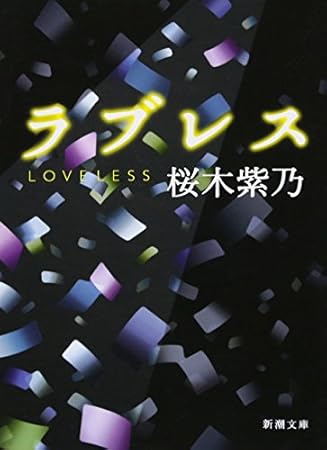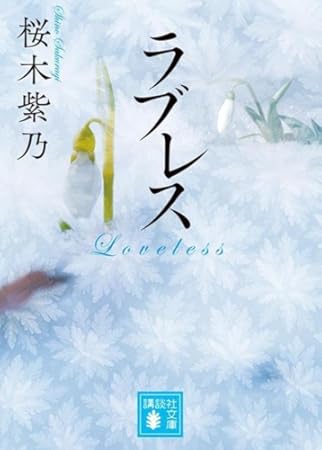■スポンサードリンク
ラブレス
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ラブレスの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.49pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全84件 61~80 4/5ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 良かったと聞いて、購入。一気に読んでしまいました。寒い夜に、凍てつく北海道を想像しながら、読みました。作り上げたにしても、すごい人生です。感動しました。買って悔い無し。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 感動した。 あまりにおもしろくて、一晩で読み切った。 小説の中身、あらすじもかなり良かった。 主人公のユッコも、妹の里実も、その母ハギも、みんな魅力的だ。 一条鈴子の生き方にも、どこか、凛としたものを感じた。 なにより、作者の冷静な描き方がよかった。 作者の筆力を感じる。 ホテルローヤルもよかったが、この長編は、ぜひたくさんの人に読んでほしいと思った。 私、はこの作家が好きだなあ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ひっそりと死んでいった百合江の人生は果たして幸せだったのだろうか、それとも不幸だったのだろうか… 北海道の開拓村に産まれた百合江の壮絶な人生を辿るうちに知らず、知らずに涙が滲んだ。この作品の主人公は百合江を中心とした女性たち全てであり、登場する男性は皆、その女性たちの人生を台無しにする存在のように思った。桜木紫乃の描く女性には強さがあり、その強さ故に女性たちが男性たちのエゴを一身に受けているようにも思う。山田宗樹の『嫌われ松子の一生』にも似た作品であるが、桜木紫乃の独特の雰囲気がある。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| はっきり言って暗い話ですが、秋から冬に読むにはぴったり。 最後は涙なくしては読めません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 紫乃さんの作品のなかで、一番気にいってます。道東の厳しい環境が よみがえります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み始めたらやめられない。ときには涙ぐんでしまう文句なしの傑作! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 昭和を生きた一人の女性の壮大な物語。ぐいぐい引き込まれて読み進めていった。 ただ終章が淡泊だったかな。それまでがとても濃いストーリーだっただけに、もう一盛り上がり欲しかった。 また、読んですぐに表紙から想像していた内容とは大きく違うので「えっ?中身が違うのでは?」と思うくらいのギャップがあった。読み終わって改めて表紙を見ても、やはりタイトルと装丁が作品の全体像を壊してしまっていてもったいない気がした。 ☆4.5 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 北海道に縁がなくても、育ちが平成でも関係なく、 圧倒的な文章能力と表現力に引っ張られてどんどん読める作品です。 ホテルローヤルもそうでしたが、何故か桜木さんの作品は 男の人のほとんどがどうしようもなく(男気あふれる方もいるにはいますが)、 女性はただひたすらにたくましく、ドライに、魅力的に描かれているなと思います。 本作の中に出てくる、 「最後には私は笑いたい」 「女も手に職つけなきゃだめ」 「3年後、5年後を考えなきゃ」という里美の言葉と、 「今日の夜食べれるかどうか」 「考えられても3日後くらい」という百合江の言葉と、 どちらともわかるから人間は面白いなと感じました。 自分が情にもろくなっているときに限って異性に惚れられ、 つぎつぎ懐妊してしまう百合江や、 酒飲みの夫の子を五人も生んだハギなど、 今の世代から1世代、2世代さかのぼるだけで 相当濃い血縁や地域の関係が存在していたことを連想させられます。 桜木さんの小説には、「大切なことは話さず黙っておく」美学がある登場人物が多く、 それが時に悔しく、時に美しく映ります。 最後に、どんな形であれ愛した人に「だいすき」と言ってもらえる旅立ちは 感動的でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 北海道のなんともいえない秋色や灰色の風景描写がすばらしいです。 二人の姉妹の壮絶な人生に感動しました。 そして開拓農民の苦労がよくわかりました。 直木賞のホテルローヤルと比べると非常に濃密な、ある意味「重厚」な作品です。 ラブレス→丁寧に読むべき作品(緻密な作品構成) ホテルローヤル(直木賞受賞作)→比較的リラックスして読める作品 作者の桜木 紫乃さんはNHKなどで紹介されご存じのかたも多いと思いますが 彼女の謙虚な、そして庶民的姿勢は賞賛に値します。 作家は桜木 紫乃さんのようにいろいろと人生経験を積んでこられた方のほうが 人の悩みとか苦しみとかに共感できるかなーと思いました。 ラブレスを一度ゆっくり読んで人の悲しみ苦悩を理解できる人になって下さい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 何行か読んで、「こういう本を読みたかった」本に出会えたという嬉しい感触。そこからは面白くて、面白くて、早く先が読みたい気持ちと、読み終わるのが惜しいという気持ちのせめぎ合い、まさに、特別な本との出会いでした。この著者の本は前にも読んだことがあるのですが、舞台となる北海道の特殊さが上手く書けていると思ったものの、あとは……って感じだったんですが、これはその北海道プラス時代背景、その時代の人々の生き様、芸能などなど、魅力たっぷりでした。 ただ、「終章」になってから、私的には一気にテンションが落ちてしまいました。現在を生きる二人の女性がなんというか、とっつきづらくて、会話がつまらなく感じてしまったからかな。百合江の物語の流れも止まって、あとは謎解きか?なんて期待したのもよくなかったかな。謎解きはあったけれど、ああ、やっぱりという内容で、ちょっとガッカリしてしまいました。惜しい。でも、それまでが良かったので、読んで良かったという気持ちには変わりありません。もっと長くても良かった! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 滅茶苦茶壮大です。 なんか序盤の貧乏なくだり、旅芸人の話、お針子時代など、NHKの朝ドラではなく、フジのミヤコ蝶々物語をすごい思い出してしまった。 ドラマ化してほしい。 表紙とタイトルで損してますね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 久しぶりに良い小説を読んだ。読了後の満足感が大きい作品。読者へのインパクトの大きさは、内容の濃いレビューがこれだけ並んでいることからも明白。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とても面白かったです。 読みやすさもあり、ぐんぐん読んでしまい、家事が滞りました。 主人公の生き方は、一見流されているようであり、実はとても芯が強いんだと思った。 過去を振り返り後悔をしない。 それが人間にとって一番難しいことではないかと思う。 百合江は決して後悔をしなかった。 誰も責めなかった。 すごいな!と思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 時の流れに身をまかせた浮き草の人生、あまりに哀しい昭和女の一生………とお膳立ては古めかしいのだが。「しあわせ」の尺度をひくりがえしてみえてくる生きることの値打ちには、漂流する現代の精神に対する力強いメッセージが込めれれている。 「馬鹿にしたければ笑えばいい。あたしは、とっても「しあわせ」だった。風呂は週に一度だけ。電気も、ない。酒に溺れる父の暴力による支配。北海道、極貧の、愛のない家。昭和26年。百合江は、奉公先から逃げ出して旅の一座に飛び込む「『歌」が自分の人生を変えてくれると信じて。それが儚い夢であることを知りながら―。他人の価値観では決して計れない、ひとりの女の「幸福な生」。「愛」に裏切られ続けた百合江を支えたものは、何だったのか?」 裏切られ続けた女の一生、この飾り帯にある解説コピーは本著の全体像を端的に説明できています。 家出した少女が旅芸人一座の仲間となり、場末の演芸場、温泉旅館で酔客相手の歌手となる。請われれば旅館の一室でストリップだってやってのける。昭和という時代の風俗がたどられ、演歌を地で行く根なし宿なしの主人公が哀しくて、私は昭和の流行歌をいくつか口ずさんでいました。 もしも あなたと逢えずにいたらわたしは何を してたでしょうか 平凡だけど 誰かを愛し普通の暮らし してたでしょうか 時の流れに 身をまかせあなたの色に 染められ 一度の人生それさえ 捨てることもかまわない 時の過ぎゆくままに この身をまかせ 男と女が ただよいながら 堕ちてゆくのも しあわせだよと 二人つめたい からだ合わせる だから お願い そばに置いてね いまは あなたしか 愛せない 水にただよう 浮草におなじさだめと 指をさす 言葉少なに 目をうるませて 俺をみつめて うなづくおまえ きめた きめた おまえとみちづれに 冒頭、釧路市役所で働く清水小夜子が札幌の従姉妹・杉山理恵から電話で「母・百合江の様子が変だからみてきてくれと」と依頼される。小夜子は母親である清水里美(百合江の妹)を連れて、生活保護を受けている杉山百合江の町営住宅を訪ねる。清水里美は数年ぶりに姉・百合江と会うのだが、部屋には白髪の老人に見守られて、小さな位牌を片手にした百合江が老衰のために意識不明に陥っていた。 ここで百合江・理恵の母娘、とくに百合江・里美の姉妹の仲がギスギスしたものであることが窺えます。また、それきり姿を見せない白髪の老人とは?小さな位牌とは?ラストを読み終えここに戻れば、登場人物たちそれぞれの抑制された情感がギュッと詰まった秀逸の「序章」だったことに気づかされます。あらためて涙が抑えきれなくなりました。 場面は昭和25年ごろの標茶の開拓小屋へさかのぼり、昭和10年に生まれた百合江の70歳過ぎまでの人生、昭和という時代を貧しく生きた「女の一生」が語られる。 疲弊した農村から職を求めて都市へ、大量の労働力が流れてきて、ようやく定職に就く、なんとか定住の地を得る。サラリーマン層が形成される。都市に流れ込んだ新世代は「定住、定職、親子の絆で結ばれた家庭」という家族像の原型を再構築していった。昭和という時代は流浪と定住が入り混じった時代だったととらえることができる。 たとえば私の両親にしてもそうだったなと実感できるのです。 ところで「人生において幸福とはなにか」と大衆小説やドラマが取り上げる時には、大概この家族像の原型を幸福の前提にしている。だから家族が崩壊すると不幸になると。私も含めて一般的にそういう見方が定着しているのではないでしょうか。ところが『ラブレス』はこの常識を覆してみせる斬新な試みがある。百合江の場合は家族の原型こそが不幸を招く元なのです。 物語は百合江中心だが、百合江を含め相互が劇的に干渉しあいつつ里美、理恵、小夜子らの生活姿勢がたくみに織り込まれ、起伏にとんだ絶妙のストーリー構成だ。4人の生活姿勢の違いは家族像の原型に対する距離感にある。「定住、定職で親子の絆で結ばれた家庭」に幸福を求めるのが常識人の里美であり、そんな価値尺度はもたずに漂泊を選択するのが百合江なのだ。 さらに百合江を巡る三人の男たちのこの距離感の相違を鮮明に描くことで、百合江とのかかわりにおいて三様の印象的ドラマを演出している。とにかく著者のストーリーテラーとしての構成力は驚くほど冴え渡っているのです。 牛馬のように働かされ、父親の暴力を無言のままで受け入れていた文盲の母親。豚小屋のような悪臭にまみれ、ごろ寝する粗野な弟たち。そこへ養女に出されていた妹の里美が引き取られ戻ってくる。嫌悪感をあらわにする理知的な美貌の妹の登場。 酒代の借金のかたに奉公に出され、そこの主人から陵辱された百合江、16歳。だが百合江はこの事実をゆすりの種にし、借金をチャラにして旅芸人一座の歌い手に身を投じるのであった。 百合江25歳で一座は解散。その後一座の女形だったギター引きの滝本宗太郎と二人、地方の演芸場、温泉宿、都会の裏通りとその日暮らしの流れ旅が続く。 宗太郎という人物、生活力のない、だらしないまったく魅力の感じられない男である。どうしてこんな奴とベタベタしているのかと腹が立ってくるのは、わたくし男目線でしょう。籍を入れないまま「綾子」が生まれる。 妹・里美のおせっかいで、役場勤めの高城春一と結婚するのが28〜29歳。二人の間(?)に理恵が生まれ、百合江は始めて「家庭生活の原型」を体験するのだが、決定的な絶望だけが残る結果となる。ここで彼と彼の母親から凄まじい暴力と苛めを加えられるのだ。男性の作家ではとうてい描けないような母性そのものをズタズタにする二重三重の破壊行為に、男の私は読んでいて戦慄を覚えました。 三人目の男は旅行会社に勤務する石黒。春一と結婚、温泉旅館に仲居として働く百合江を支え、お互いに惹かれ関係を持つ仲だが、結婚はしないで別れる。石黒は百合江の理解者であるがために、彼女は漂泊の人であり結婚という形に幸福を求める女性ではないことを知っているからだ。 余談だが、私はあの「フーテンの寅さん」を思い浮かべたのです。おいちゃん・おばちゃんの団子屋とさくらの家庭、幸せな暮らしを見て寅さんは立ち尽くしています。そして寅さんはあれだけ女性たちに惚れられながらなぜ結婚しなかったのだろうか。特にドサ回りの三流歌手・リリーとは結婚してもよかったと思った時期がありました。本著はその理由をはっきりさせてくれました。結婚したら壊れる愛だった。流浪のままでいるからこそ、お互いがなくてはならない存在であって、愛を確信し続けられる二人だったのです。 平易な文体に情感があふれる。登場人物のそれぞれの個性が際立つ。何よりも構成が絶妙である。愛とはなにか、結婚とはなにか、幸福とはなにか。家族とはなにか。これまでの価値尺度を完璧にひっくり返して問い直したところの新鮮さは衝撃的でした。 さすらう日々の過酷さは古くからある上出来の人情話風で涙に目がくもったが、よくよく焦点をあわせれば、その背後から見えてくるこの女性像にまた別な涙が零れ落ちました。私の涙腺はいくつあるのだろうか。 絶妙な語り口に乗せられて 百合江の生き様に寄せた思いを長々と述べてきましたが、百合江の歳に手が届きそうな私だからでしょうか、実はまったく異質な感動を受けているのです。私の心を激しく揺さぶったのは百合江の人生の有り様ではない。その死に際にあったことです。なんだかんだと理屈をつけてもこれは不幸な人生だったのだ。にもかかわらず死に際の彼女の内心には俗人にはおよびもつかない気高さがありました。 いくつものかくされた謎がラストで読者の前に氷解する。文脈では必ずしも百合江がこれら「事実」を知っていたかは明らかではない。でも私には彼女はそこにあった「真実」のすべてを感じ取っていたのだと思われるのです。そのうえで、この世に未練も悔恨も残さず、沈黙のままに、ただ自分の人生が充実したものだったことを確信して去っていく。彼女を知る人たちの胸に忘れがたい存在感をとどめながら。そこには単なる気高さというよりも、宗教的雰囲気をおびた清浄さが立ち昇っている。 そして、漂泊の人生ではない普通の人生であっても、この死に様には惹かれるところがあるものなのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身の子ども時代の極貧生活と出奔、出産した子ども の父親は失踪そして肝心の子どもが行方不明と、厳しい 人生の場面に幾度も直面しながらたおやかに生き抜いた 主人公の女性を中心に、親子と孫三代の来し方と現在と が、闊達に綴られていて飽きさせません。広い意味での 大河小説なのでしょうが、主人公の周りで起こる有為転 変は、滔々たる流れというより激流を感じさせるものでし た。 ただ、読み終えても「(最後に)深い愛が描かれていた」 (『読売新聞』2011.10.19)とまでは感じることはできず、 むしろ自分の罪を語る年老いた父親を「あの年くらいにな ると色々と帳尻を合わせたくなる」と蔑む娘のリアルさの 方に慄きました。 この後の『ワン・モア』でも人生の崖っぷちに立つ5人の 男女の姿が描かれていてドキドキさせられたのですが、 終章で一団でハッピーエンドとなってしまったのには唖然 とさせられました。この作家は、人の浮沈のバランスのと り方が少し不得手のように思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初に畳み掛けられるように複雑な人間関係が描写される。え?誰と誰が姉妹で、誰が不倫していてどの親子に何の確執があるの? そして突然時代も舞台も瞬間移動する。…とまどいながら、小説世界に引っ張り込まれました。力技です。 極貧で救いのない最下層の北海道開拓暮らし。ドサ周りの旅芸人一座。それぞれ、そんな中でも自分を信じて生き抜く人間たちが描かれていました。 人が人を思う。その思いのそれぞれの形が、多彩な角度で描かれていました。 ぐんぐん進むストーリーが、最後まで私を引っ張りまわしてくれました。 読み終わって、映画館を出た時のような、現実の方が色あせているような感覚に陥りました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人的な勝手な妄想ですので、あしからず 子供の名前、希望と願いをこめて付ける名前。 綾子・理恵、小夜子・絹子 ともに、名付け親は母親(百合江、里実)ではない。 宗太郎は母親の名前を付けた。 理恵のペンネームは祖母と叔母の名前から取った。 小夜子は生まれてくる子供にどんな希望を願い名前をつけるのだろう。 女の子なら、小夜子が付けるだろう、、 そんなことを考えつつ本を閉じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 小説冒頭の舞台となった北海道・標茶は、おそらくぼくの脳裏にある貧困なイメージからは想像もできないような風景だったろうと思う。しかし、だからこそ、主人公と他の登場人物の、情け容赦ない「生き抜く力」が、立体的に浮かび上がり、迫ってくる。 終始一貫、ぶれない主人公の振る舞いを見るにつけ、中上健次『軽蔑』の女主人公を思い出してしまった。 エンディングに泣いてしまったのは、自分が身勝手な男だからだろう。だが、いろいろあるのだ、人生は。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この装丁もったいないなぁと思う 内容とまるで合っていない なんだか軽い恋愛(昼メロ風)を想像しますよね とても素晴らしい内容なので残念です 多くの人に手にとってもらいたいんですが 5つ星は中身の評価 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 何度も心身を傷つけられても、どんなに辛くとも、北海道の大地のような壮大な力ですべての自分の中に包み込んでしまう百合江という女。おまりにも酷と思えるような境遇をもめげず、避けられない定めでも背負っているかのように生きる人生を百合江は見事に演じきっている。これほどまでに人を憎めずいられるものなのか。そこには確かに私には決して真似のできない人がいた。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!