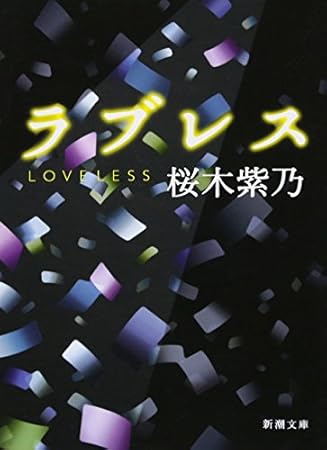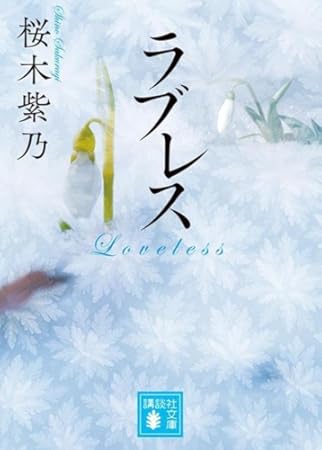■スポンサードリンク
ラブレス
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ラブレスの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.49pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全84件 1~20 1/5ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 桜木さんの中に名無し草的な要素があるのかは分かりませんが、揺れるように生きる百合絵の心理描写がとても良かったです。 桜木さんの作品の中で一番好きです。何回も読んでいます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| こんな過酷な時代に生き抜いた姉妹に圧倒されました。最初女性の名前がたくさん出てきて、誰が誰なのか把握できず読むのをやめようと思いましたが読み続けてよかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 桜木紫乃さんの多作品を読み面白かったので、こちらを購入。 自分的には、ここ半年間で読んだ中でトップ、くらい面白かったです。 話の進み、スピード感、人物の書き分け、などなどなど、随所に光るものがありました。 エンディングも含め、素晴らしい作品だと思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 冒頭のシーンで年老いた宗太郎はいつから百合江の部屋にいたのか、読後のミステリーとなりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者を初めて知ったのは友人から借りた「家族じまい」でした。登場人物の各人の深層心理の描写に圧倒され、いっぺんにファンになりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 百合江は幸せな人生だったか? 年齢の割に老衰し、波乱万丈で運命に翻弄された人生だったのに、位牌を握るその姿からは自分の人生に満足しているように感じるのはなぜだろう。 「どこへ向かうも風のなすまま。からりと明るく次の場所へ向かい、あっさりと昨日を捨てる。捨てた昨日を惜しんだりしない。」 それに死に際の枕元には愛した人が、そして2人の愛の結晶はいま自分の才を存分に花開かせている。。 もう何も思い残すことはない。 里実はどうだったか? たとえ経済的に成功したとしても「必ず見返してやる」と人に囚われてばかりで進んだ人生は? 「見開かれた瞳にふたりを映して、里実の体が壁をつたい床に崩れた。」 自分が手に入れられなかった尊いものを目の当たりにした里実。「逃げた男と逃げられた女」と軽んじていた二人の関係が、実は深く永遠の愛であったことを知った里実。 里実には悪いがスカッとした。。笑 百合江 = 折れない、なんとしても生き抜く、芯の強さ 里実 = 人を叩く、張りあう、わかりやすい強さ それにしても里実の「実」という字は名は体を表すなあ。。 現代の「小夜子と理恵」、その母親の「里実と百合江」の回想が サンドイッチのように交互に展開する形態で面白い。 ①現代 : 小夜子、理恵 (45歳) ②昭和25年~:百合江、里実 (中学~) ③現在 :小夜子、理恵 ④昭和35年~:百合江、里実(百合江25歳~ 出産) 百合江、里実(里実、百合江の結婚) ⑤現代 : 小夜子、理恵(高樹に会いに) ⑥昭和50年~:百合江、里実(卯一の死、ハギと同居、銀の目) ⑦現代 :小夜子、理恵(高樹老人の告白) ⑧現代 : 小夜子、理恵(百合江の病室にて) 女の強さ、凄み、逞しさがいつまでも残った。 北海道の田舎の「貧しさ」「閉塞感」「怖くなるほどの茫漠たる空と大地の拡がり」を感じる描写が印象的。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者の桜木先生を誇りに思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 安定した面白さ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| それぞれの、女性の人生が北海道ならではの、時代の流れのなかで複雑な悲しみが、なんとも、言えない感覚でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 地元が出てくるのでくるので、いつか映画化になるのを楽しみにしております。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 良かった | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 桜木さんの中で一番好きな作品。 これは、モデルの方がいないと 描けない世界だと思うけれど どうなんでしょう | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 久々に純文学純文学した一冊を手にしむした 丁寧に書かれていて、しかも面白い 自分の来し方と重ね、時の流れに呆然とし、読後の余韻にしばし浸っておりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主な登場人物はみんな女性。妊娠中に読んだので、母として感じるものがあった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 圧倒的な読後感。気持ちのありようが普通の本を読んだときとはまるで違う。まるで何か薬を一服盛られたかのように、何時間もその感覚からさめることはなかった。 読み始めからしてそう。独特な世界に引き寄せられ、抜けられなくなる。楽しい話はほとんど無い。もっぱら悲惨な荒々しい出来事がどこまでも綴られていく。こう言うと語弊があるが、こんなものをよく書き続けられるものだなあと感心した。この作家はどこまで強いのか。 登場人物の多くが人間的に歪んでいる。そして、誰もが真剣に生きているというわけでもない。単純に「いい人」と言えるような人は一人もいない。現実の人間世界にあまりにも近いのだ。貧しく、無教養で、暴力的。飛び交う暴言。諦観。放蕩。身勝手。 こう聞くとうんざりするような話に聞こえるかも知れないが、この作品が島清恋愛文学賞を受賞している。心温まる愛の話なのだ。 戦後しばらくの北海道の開拓家族から生まれた物語である。もちろん電気も水道もない。親父はアル中で働かず、すぐに母親を殴る、蹴る。向学心のある娘の進学を許さず、街の薬屋に奉公に出させる。それも親父の借金のカタ。受験勉強をしている娘に「貧乏人の娘が何を考えているんだ」。薬屋で働き出すと、そこで主人に強姦される。「借金無しにしてあげるよ」と言われながら。娘はその後すぐ、旅芸人の一座に付いて出奔する。養えないので親戚に預けられていた妹が、弟たちの面倒を見させるために、10歳になってから突然、無理矢理連れてこられる。妹は、風呂に入らない家族の体の臭さに驚き、電気がないことに驚き、母親だと言われた女が文盲であることに驚く。妹も当然高校へはやってもらえなかった。 実を言えば、これに通じる人間模様というものは、私自身も小さいときから見ている。実際、私によく飴をくれた近所のオバさんは文字が読めなかった。女中に入った家で強姦されて気が狂い、それ以降死ぬまで数十年、実家の押し入れの中で暮らしていた人もいた。 家族の間で優しい言葉を掛け合うような余裕もない。人がどう生きるべきかなど考えることもない。そんなものは、天上の世界のものだ。互いを傷つける言葉を吐き、気持ちを高ぶらせ飯を食う。 この世界を基準にすると、現在の生活はまるで漂白された綺麗ごとの世界のように感じられる。 ほんの数十年前まで、北海道とは言わず、埼玉の田舎でも同じようなものだった、のだと思う。 理髪店の職人として一人前になった妹が結婚式を挙げるシーンがある。さすがに、開拓村の家族も呼ばれている。控え室に行った姉に、一番上の弟が粗野な言葉遣いで憎しみのこもった皮肉を言う。「女郎」と。弟たちにすると、見捨てられたという思いがあるはずだ。なぜ、ネエチャンは俺たちを地獄に置き去りにしたんだという気持ちが。一番下の弟は中学にも行かせてもらえなかった。 家族が披露宴で恥をかかせないか、困ったことをしでかさないかと姉妹は気が気でない。披露宴が終わったらもう二度と顔を見せるな、と妹は家族に言ってあった。姉も披露宴の後、お祝いの席に水を差す前に早く帰れと言う。家族は貸衣装を脱ぐ。下は野良着同然の服。再び毒づいた弟も、アル中の父親も、太った母親も後は無言。 このやるせなさ、身を切られるように分かる。言いたくない暴言を吐かずにはいられない。暴言の矢は自分自身にも突き刺さる。自分が姉妹から恥ずかしがられる存在であることを自覚しながら、自分ではどうすることも出来ない。胸が熱くなる。希望は、無い。 そういう殺伐とした風景の中に愛の物語を紡ぎ出す。 北海道の開拓農民・漁民を取り上げた作品として有島武郎の「生まれいずる悩み」、「カインの末裔」などがあるが、この作品(に限らずこの作家の作品)は、それらの作品とは深さが違う。肉薄度が違う。切実さが違う。登場人物の悲鳴が行間から聞こえてくるかのようだ。 なお、筆者は直木賞作家。「ホテルローヤル」を書いた桜木紫乃である。「オール読み物9月号」に載った受賞作の短編3作を読んで興味をそそられ、この作品のkindle版を読むことにした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み終えたとき、一本の感動的な映画を見たという感覚になりました。 まさに、女の一生という感じです。 「ラブレス」ではなく、愛は、溢れている小説です。文章表現も上手です。 この小説の手法は、現在(平成)の主人公百合江の命が消えようとするところから始まり 戦前の時代に遡ります。しかも主人公のその手に位牌を持っているというミステリー 的なところが最後にわかるのです。 戦前の過去(開拓農民のこれ以上ないくらいの貧困と、酒乱の父の暴力など最低の 生活)から現在へと進んでいきます。主人公は、高校進学を断念、薬局の定員を経て 旅芸人一座に、その後弟子屈町で嫁ぎ老舗旅館の中居になり、自慢の歌で「歌う 中居」として活躍し、次は釧路へと流転します。 いつも不幸な方、不幸な方へと人生が進みますがめげないのです。 力強く生きていきます。 最後の章では、涙なくしては読めないです。疑問点の解明を最後に持っていきます。 実に感動的でありました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 桜木紫乃さんの本は殆ど読破しましたが、一番良かったと思います。 最後はなみだがとまりませんでした。 昭和を生き抜いた1人の女性の生き様。 悲しみ、哀愁、強さ、どの行間からも伝わってきました。主人公は昭和を強く生き抜いた女性ですが、よくある昭和女性の明るさと言ったものは感じません。 そのせいもあって、ラストをあのように(ネタバレになるのでいいませんが)してくれた作家に感謝の念がわいてきます。報われた想いになります。それだけ感情移入する事ができる作品です。今だ、感動の余韻がのこっています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 素晴らしい作品。 この作品は映画化して欲しい。そして主人公のゆりえの晩年は舞台となった標茶町出身の高橋恵子さんに演じて欲しいと思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| アイヌの人々や自然にあこがれての最近の移住を除き,北海道に住み続けている者たち(家族)は一定以上の覚悟をもってその地に赴いた開拓民の血を受け継いでいる.その血がいかに人生に影響を与えるのか,これは文学が向き合うべきテーマで,そして,これまで「北海道文学」にこの観点にあまり留意されてこなかったのではあるまいか.「内地」のものさしで北海道の文学を見過ぎていたのではあるまいか.反対に「北海道文学」は「内地」寄りの作品を志向していたのではあるまいか.本作には,そんな思いを抱かせる新鮮な気づきがあった.そして,本作はこのテーマに向き合っているように読める.ただ,単行本1冊に収めるには無理があり,せめて3巻くらいで読みたかった.最近の出版事情もあるのだろうが,気安く消費されてしまった感が残念.作品への愛をこめて,消化不良の秀作と感じた. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 一番好きな映画はワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカです。 そしてラブレスの構成が驚くほどこの映画に似ていました。 それゆえ桜木さん作品の中でも心に印象深く刻まれるのでした。 百合江がヌードルス、里実がマックス的な存在でしょうか。 時系列が不規則な進行 必然性のある性や暴力描写 ほんの少しのミステリー要素 二つの作品、ストーリーは全く違うものの共通項が多く、思わずレビュータイトルを付けてしまいました。 ラブレスのネタバレになるので詳しくは書きませんが、映画のラストシーンでのヌードルスの満面の笑顔を思いだしました。 映画をご覧になっていない方には全く無意味なレビューで申し訳ございません。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!