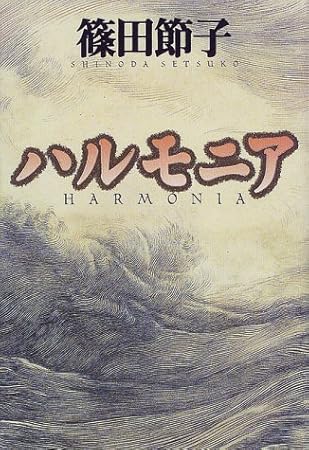■スポンサードリンク
ハルモニア
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ハルモニアの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.94pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全31件 21~31 2/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 由希のみっともない姿が丁寧に書かれすぎていて残酷な 卑劣な視線を感じました 「薬を投与すれば何でも言うことをきくようになる」なんて医師に対する患者に対する侮辱です 由希が可哀相だと並べていましたが、あるまじき優越感に裏打ちされたニュアンスでした 作者の意地悪さと不信感を感じました 取材の丸写しが多いのは作者に分析力 想像力がないのでしょう 真似しかできない演奏家 弟子の限界を喜ぶ教師 罪なくして見捨てられた主人公 人間性も才能も二流 三流の人物しか出てこない小説にどうして学んだり感動したりできるのでしょう? 独創性の何たるかを示せず 芸術と人生の新たな相互作用も見出せぬまま終わるこの作品は何のために書かれたのでしょう?弱者を晒し者にして何が残されたのでしょう?障害者団体に抗議されないのですか? 大江健三郎氏が本書を読んだらどんな気がするのでしょう? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ホラーって感じは全くなく、なんていうか、演奏者の心理が印象的でした。 上手い作家さんなので、最後まで勢いに乗って読ませます。 音楽をやってた人なんかには、特に面白いのかも? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽にひかれるようになった中学生のころ、ドラマで見ました。しかし断片的にしか覚えておらず、また障害に関しての知識も今より断然少なかったため、改めて大人になった今読んでみても新鮮でした。おぼろげな記憶では、やはりドラマと原作では設定が少し違うような。(どちらも悪い印象はありません。)同じく音楽をモチーフにした作品「カノン」もお勧めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人とは違う感覚で物をとらえ、自分の世界の中だけで生きている由希。音楽的な才能を伸ばすことで、彼女の世界を広げようとする人たち。その間には越えられない壁がある。人間の脳はひとつの宇宙だと言った人がいる。現代の医学や科学では解明しきれない謎がたくさんある。東野は知らず知らずの間に、由希の宇宙に飲み込まれていった。それは音楽家としてなのか、一人の男性としてなのか?東野が選んだ結末を、由希も望んでいたのだろうか?彼女の微笑がその答えなのだ・・・。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説の主人公由希は音楽に関してとてつもない能力を持ち、しかもその能力は超常現象まで引き起こし、音楽によってのみ世界とつながれている。盲目の人が聴覚、触覚、嗅覚がすぐれるように、結局人間の能力は足りないところを他の能力で補っているのかもしらない。数多くの音楽家なら「今音楽の神が乗り移って素晴らしい演奏が出来るなら、どんな犠牲を払ってもいい」と殆どの人が思ったことがあるであろう。私も幼いころ日々鍵盤を叩いていた。絶対音感をもち、多くのレッスン生の中でも抜群の音感を持っていた私に教師達は驚嘆し、音楽の道を勧めた。思い上がった私は、将来劇場の大観衆の拍手の中、美しい音楽を奏でるのが夢だった。しかし、小学3年生の時、私には才能はないと言うのを思い知らされた。旧ソ連の神童と呼ばれた多くの天才たちはわずか5歳で難曲を弾きこなしていた。私より幼い彼らの完成された演奏に衝撃を受け、それから私は、音楽の道を歩む事を断念した。大人になり、サヴァン症候群というものが存在するという事を知ったとき、何故私にそれが備わっていなかったのだろうと正直思った。しかし今はそんな能力を身に付けた人たちが社会に適合できず、どれだけ苦しむのかと思うと、そんな能力は無いほうが幸せなのかもしれない。実際同時の神童たちで今でも活躍しているのはほんの一握りである。精神を病んだものも数人いる、と聞いた。この小説をよみながらずっと頭の中にチェロが鳴っていた。以前聞いた有名なチェリストの音楽が記憶の奥底から蘇ってきたのである。この作品は勿論フィクションであるが、由希の力が私にまで及んでいるような感じをおぼえた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本を読むまで「芸術は多くの人に評価されなければ、所詮作者、演奏者の自己満足に過ぎない」と思っていた。そうでなければ作品、演奏に対して芸術家、演奏家が言いたい放題いえるてしまうから。本当に良いものは、理屈を超え、皆を納得させてしまうものだ。そう考えていた。もしかしたらそれは誤りだったのかもしれない...... 人々が待ち望んでいるもの、求めているものを与えるのが芸術ではない。文化的にはるかに高みにあるものを目指すのが芸術なのだろう。そのようにして作られたものならば誰にも理解されずともよいのではないだろうか。 「その時代に認められずとも、いつの日にか新しい時代が認めてくれる」 有形な物ならば、そういうこともあるだろう。では無形のものは?例えば録音などもされず、誰も覚えていないような演奏...... この物語には救いはない、が真理は描かれている。己の理解できないものをすべて批判するのは大衆のエゴでしかない | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| っと思いこの本をてにしました。設定など、多少は違いますが、ドラマ(98年放送NTV系“ハルモニア~この愛の涯て~”主演・堂本光一)の妖艶な世界感が充分に文字から伝わってきます。当時中学2年だった私は、このドラマのおかげで篠田節子さんの作品を読むようになりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠田節子作品はすべて勉強になることが多い。この作品もしかり。私自身音楽には全く素人で今まで何気なく聴いていたものの、この本を読んでから、もっと音にこだわり、そして弾き手の感情表現に注意がいくようになった。音楽というものに対し、何十冊の音楽の専門書を読んでも得られなかったであろう理解を得たような気がした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 異常とも言えるほどの音楽的才能を持ったサヴァン症候群の女性・浅羽由希。しかし、彼女は言語や感情と言うものを全く持たない。その由希にチェロを教えることになった東野秀行。彼は、自分では実現不可能な天上の音楽・ハルモニアの夢を由希に託し、レッスンを続ける。最後に由希が奏でた調べ。それは東野の求めていたものだったのか? そして聴衆の反応は? そんな二人はどこに行き着くのか?ラストシーンを破滅的だと感じた人がいるかもしれませんが、私はハッピーエンドだったのだと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| サヴァン症候群の由希を演奏者として独り立ちさせたいという女医と由希に自分自身の音を出させようとする東野がそれぞれの思惑で対立していく。2人とも由希の幸せは願っているが、自分の見地でしか物を見ることができない。本当の幸せとは何かを探している作品。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠田先生の本についてレビューを書くにあたり、昨日読んだにもかかわらず、その核となる部分は何だったのかと考えると「はっきりわからなかった」というのが私の正直な感想である。というのも、先生の本にはいろいろな要因が含まれていて、それを一言で言いくるめるのは難しい。そのことが、先生の本の奥深さをだしているのであろうと思う。私なりに解釈した「ハルモニア」は、音楽に携わる人々の心情、現代医学に対する恐れ、障害者に対する人々のあり方など、とても同ジャンルでまとめられないものを含んだ小説であるということである。さらに特筆すべきは、そんな複雑そうな内容にもかかわらず、この本を一日で読んでしまえることである。そこが、この本に限らない篠田先生の魅力だと思う。オススメの一!品!! | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!