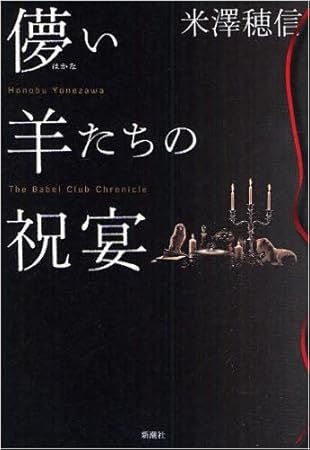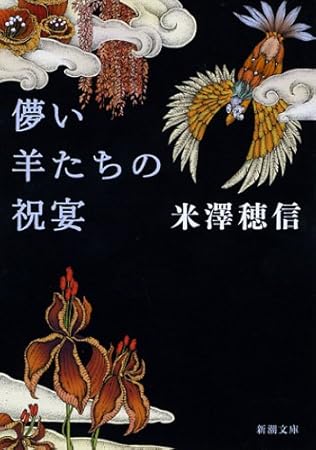■スポンサードリンク
(短編集)
儚い羊たちの祝宴
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
儚い羊たちの祝宴の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.99pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全111件 81~100 5/6ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この短編集は ただの殺人や猟奇的殺人でなく、 究極まで歪みきった思想による 殺人が描かれています。 読み切って、最後の文章で 鳥肌が立つような そういった芸術性を感じます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ホラー風味のミステリ。と聞いて読んでみました。 短編ながらそれぞれの物語が「バベルの会」でつながっており(内容は繋がってはいませんが) 全部良作!読み応えたっぷりで、あの話なんだっけ?ってなるようなものは無く全て濃い。 でもその分怖いです。気分が明るい時に読まないと、とことん沈みそうなので要注意☆ 何が怖いかって、無関心。ということでしょうかね。 好きの反対は無関心というのはよくありますが、まさにそんな感じ。 憎しみや恨みの殺人ではなく、無関心な殺人についての描写が異常にうまいですね作者は。 最後の一文で落とす!というより、伏線はいたる処に貼られておりますし、 あっとビックリどんでん返し!というようなトリックは無いです。 (そういう小説って、どんでん返しにコダワリすぎちゃうのが往々にして欠点ですよね。本著はそれが無いので良作ですね) それでも最後まで読むと斬新さと、不気味さが纏わりついて離れない。 おそらく、読みながら予想してた結末に「なってほしくない」と思いながら読んでいるのかもしれないです。 それでも作者は残酷にも結末を書いてくれますからね。 いちばんのお気に入り?は「玉野五十鈴の誉れ」ですねー。 これこそ最後の一文に「んぉぉ!」ってなりましたが、なぜかホッとするような不思議な感覚に陥りました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 。「バベルの会」つながりの5篇の連作短編集ですね。ラスト一行の衝撃というように、ラストのどんでん返しを売りにしているみたいだが、客観的にうまいなあという感じがするだけですね。見事なんだけど、面白いなあという感じはしなかった。ブラックミステリーみたいなものなんでしょうね。 身内に不幸がありまして 北の館の罪人 山荘秘聞 玉野五十鈴の誉れ 儚い羊たちの晩餐 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初に頁を開いた時は最後まで読めるかな?と不安に思いましたが おもしろくて一気に読んでしまいました。 文章がとても知的で上品でした。読みづらいかなぁと思ったけれど スラスラ読んでしまいました。 上品な文章なのに酷な内容のギャップが良かったです。 短編集ですがそれぞれがちょっとずつ絡んでいます。 私は特に「身内に不幸がありまして」が好きです。 「世にも奇妙な物語」のような、そんなお話です。 うまく全部はわからないんだけど怖い・・・こんな感じの本です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 米澤穂信氏は軽いタッチの学園ミステリーですらマニアも納得させられる本格推理作家(本格には様々な定義がありますが)ですが、この作品はそんな彼の真価を堪能出来る作品です。 どの短編も伏線、動機、意外性が十分であり、最後のオチについては謎解きのようで、読者が色々な所で解釈を広げる話題性まであります。ただ短編のため、ページ制限の中で少しひねり過ぎてる感があるように思いましたが、読後まで達すると統一感の方が勝ります。 内容は他の方が書いて下さっているので割愛しますが、昭和初期の独特な世界観とどんでん返しミステリーが好きな方にはお薦めします。とにかく購入して読むに値する本です | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者の語彙とそれを支える知識が4つの点で面白いです。 まず過去の出来事。次に今流行の言葉づかいやものの考え方。第3にミステリーの基礎知識。最後に作者自身の言葉づかいの韻律。 読んで面白く、聞いて面白い響きをもった表現がいたるところに見られます。 本作は、ミステリーとホラーの中間でしょうね。 さて、そのほかに付け加えるべきことがあって、最初の「身内に不幸がありまして」を私は短編とは知らずに読み始めました。 そして、文庫本の残りのページの分量から、きっと芥川龍之介の『藪の中』のような展開になるだろうと予想したのです。 語り手と語られる内容の相関がほどよく緊張感のあるものとなっていて、これはこのまま中長編に化けてもよかったかも知れません。 素晴らしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「バベルの会」という読書サークルが各話を繋いでいる短篇集。 各話は独立しているストーリの短篇集だが、 最終話の5話目で衝撃のラストを迎えるように布石がうたれている。 その登場する名前や話の設定は、ミステリーファンも心をくすぐる。 内容的には、恐怖を感じるような悲惨なストーリーであるが、 各話の最後まで、その恐怖を感じさせずに、 衝撃のラストで、存分に感じるようなストーリー展開となっている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008年に出た単行本の文庫化。 「身内に不幸がありまして」「北の館の罪人」「山荘秘聞」「玉野五十鈴の誉れ」「儚い羊たちの晩餐」の5本を収める短編集。 5本とも、とてつもない上流階級の家庭を舞台としている。大金持ちで、メイドやコックや管理人などの召使いを抱えており、そうしたサーヴァントたちが物語の主役となっていく。 「身内に不幸がありまして」は殺人の動機が秀逸。 「玉野五十鈴の誉れ」はラスト一行があまりにも怖い。 しかし、どの話も伏線の張り方や回収がイマイチで、読後にモヤモヤ感が残る。 ミステリ・マニア向け。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とある読書サークルのメンバーに起こる事件をテーマにした短編集. 時代も社会背景も明かされないのが, 時代掛かった語り口,全体に漂う閉塞感で,独特の世界観を作り出している. この雰囲気はかなり完成度が高く, 最終章でのサークルの成り立ちに説得力を与えている. 青春小説にあしらえたミステリーの多い米澤氏に,こんな小説も書けたのか?!と,正直,感嘆した. 単におどろおどろしいだけでなく,どこか歪んだ精神世界を巧みに描いた佳作. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 米澤穂信さんの作品は、『氷菓』をはじめとする古典部シリーズから始まり、いわゆる「ラノベ系ミステリー」(?)の作品に はまりました。それだけに、『インシテミル』あたりからの、方向性の変化を知りつつも今回の作品を読みました。 5篇の作品がどれも浮世離れした上流階級の中の主人公が語り手になっています。 古典的なミステリに絡めた象徴的な表現が「バベルの会」という読書会を接点にちりばめられます。 上流階級という設定に乾いた空気感が漂い、残酷、冷徹、寂しさという言葉を想起させる手助けをします。 なかでも『玉野五十鈴の誉れ』は、結末へ至るまでの伏線の巧みさやどんでん返しに、後味の悪ささえ覚えますが、結末の一行に 「見事だな」と思わずにはいられないあざやかさすら感じます。日本人の因習やこだわりを巧みに引用しているところに、少しだけ、一連の横溝正史の作品にも似た、人間のはかなさや悲しさを感じ、強烈な印象を受けました。 他4篇も息もつかせぬおもしろさで一気読みできました。 表題の『儚い羊たちの祝宴』も上流階級の転落する姿と語り手の怨念にも似た復讐の念が二本の糸をより合わせるように 絡み合い「アミルスタンの羊」のもつ意味が浮かび上がるのです。 古典的なミステリと独特の空気感の融合に、これからの作品が待ち遠しいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 米澤穂信さんの作品を初めて読んだのですが、面白かった!特に表題作は途中からドキドキが止まらず。他の米澤作品も読んでみたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| デビュー作の「古典部」や「小市民」シリーズや「インシテミル」「犬はどこだ」などのいわゆる本格ミステリとはまた異なったクラシカルで耽美的で狂気に満ちた乱歩や横溝正史的な作品集。ミステリというよりホラーに近い。過去の名作のオマージュ的な部分もあり、作者の引き出しの広さに感心した. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 帯にある「絶対零度」が何を表しているのかはよくわかりませんが、 十分楽しめることは確かです。 独特の世界が繰り広げられ、読み進むといつの間にか物語の世界に引き込まれています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 米澤博信こんなの書けたんだ!とまず驚いた。 傑作、というよりは実験作や意欲作、または野心作と銘打ちたくなる甘美な企みに満ちた一冊。 各話の語り手はいずれも名家に関係する若い女性だが、下働き・妾腹の娘・別荘の管理人とその立場は様々。 彼女達が目撃した、ないし首謀者となった事件について私小説的一人称で綴っていく形式なのだが、全員が何らかの形で「バベルの会」という読書好きな令嬢たちの集まりに関わっている(中にはただ小耳に挟んだだけのものもいるが) だがこのバベルの会なるサークルは登場人物の口の端に上るだけで、その片鱗を窺うことこそできるが、まるでそれ自体が空想上の存在なのではと疑いたくなるほどにその実態は謎のベールに包まれている。 物語は入れ子細工になっている。 桜庭一樹に「青年の為の読書クラブ」という著作があるが、あれが同好会の活動を中心に騒動を扱うのに対し、この本における「バベルの会」は、それぞれ独立した短編としても読める各話を緩やかに繋ぐ共通項として背景に退いている。 優美にして耽美、こだわり抜かれた文体は時代がかった雰囲気を生み出し読者を陶酔に誘う。 名家の因習やしきたり、一族ぐるみの犯罪の隠蔽という全編を貫くキーワードは、登場する家屋敷の独特な存在感とともに綾辻行人の館シリーズを彷彿とさせる。 泉鏡花「外科室」など、それぞれモチーフとなった本が設定されてるのも興味深い。 トリックの解明やロジックの哲理を追究する狭義のミステリーではなく、語られざる騙りの不条理性が幻想に昇華する広義のミステリーとして読むのが正しいかもしれない。 最終話の会長の言を引けばバベルの会は現実に抑圧された夢見がちな少女らの駆け込み寺。 この本で語られる事件が真実だという保証はなく、極論してしまえば全て信用ならざる語り手たちの「妄想」という線もありえ、何通りもの解釈ができるのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ただただ無心に読み、現実に帰る一瞬に身体を心を震わせることになる。 そういう作品です。 気をつけるべきは展開を読むべきミステリではないということ。 フーダニット、ハウダニット、ホワイダニットは大抵の場合容易に分かります。 ラスト数ページとまでいかなくとも、作中に登場する言葉や設定、また作品をみれば自然と想像できるでしょう。 昭和まで遡らなくても、この程度のミステリなどたくさんあります。世界観やキャラクタなども使い古されているものです。 ではなにがすごいのかと考えると、やはり最後の一文なのではないかと。 最後の一行、現実に戻される間際に我々は、はじめて人物の心に真に近づくことができるのです。 人物、世界観、展開、この作品そのものがこの一瞬のために用意された伏線でしかないのでしょう。 犯された殺人もその真相も、この作品の語るところではないのです。 そういった意味で、漫画のように展開を見たいだけのミステリ好きは読むべきではないでしょう。 使い古された動機、使い古された手法でがっかりすることになるはずです。 と、ここまで書いたが、もしかして僕は間違っていたのかもしれない。 このような作品を最後まで読ませる、その文章に注目するべきなのではないか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 短編集になっており、ちょっとした隙間時間で読み進めることができます。1作品ごとに事件の内容が全然違く、最後まで飽きの来ない作品でした。どの短編も、話はこのまま進んでいくのかなと思いきや、ラストでどんでん返し!!微妙な違和感の真相はこういうことだったのかぁと、後からしっくりきます。また、最後の章は作品全体の世界を包み込んでいるような感じです。 不思議な話、怖い話、ミステリー、これら全てが詰まった作品だと思います。お勧めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 短編集になっており、ちょっとした隙間時間で読み進めることができます。1作品ごとに事件の内容が全然違く、最後まで飽きの来ない作品でした。どの短編も、話はこのまま進んでいくのかなと思いきや、ラストでどんでん返し!!微妙な違和感の真相はこういうことだったのかぁと、後からしっくりきます。また、最後の章は作品全体の世界を包み込んでいるような感じです。不思議な話、怖い話、ミステリー、これら全てが詰まった作品だと思います。お勧めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 【北の館の罪人】の、北の館にもしも「住む」ことになったら・・・ 働くこともなく、誰に起こされ指示されることもなく、 食に困ることもなく・・・ 【山荘秘聞】のように人知れず匿われることになったのなら・・・ そのどちらも誰にも気付かれることのない「楽」な生活。 同時に「比べられることのない怠惰な時間」。 いろいろな記憶が、余計な思惑に踊らされ、 ほんの少し、憧れる。 イヤな自分を垣間見る。 儚い一瞬の十六夜が、心地よく嘆かわしく私の日常に降りてくる。 「ここ」に住む、つもりはない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 【北の館の罪人】の、北の館にもしも「住む」ことになったら・・・ 働くこともなく、誰に起こされ指示されることもなく、 食に困ることもなく・・・ 【山荘秘聞】のように人知れず匿われることになったのなら・・・ そのどちらも誰にも気付かれることのない「楽」な生活。 同時に「比べられることのない怠惰な時間」。 いろいろな記憶が、余計な思惑に踊らされ、 ほんの少し、憧れる。 イヤな自分を垣間見る。 儚い一瞬の十六夜が、心地よく嘆かわしく私の日常に降りてくる。 「ここ」に住む、つもりはない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 腰巻きには「あらゆる予想は、最後の最後で覆される。ラスト1行の衝撃にこだわり抜いた、暗黒連作ミステリ」とあり、ランキング本などでもそのように解説されていますが、率直に言ってそうではありません。こうした惹句どおりの衝撃を求めるなら、佐野洋の短編集の方が遙かに驚きに満ちています。「あらゆる予想は、最後の最後で覆される」という惹句は、この短編集の持つ凄みをきちんと表していません。収録された5編には、確かに「ラスト1行の衝撃」がありますが、それは読者の予想を覆す、とかではなく、見る気もなかったグロテスクな美術品を、気がついたら凝視していたような、そんな衝撃です。 5編の短編は、いずれも基本的に若い女性の一人称で語られます。女性は、裕福な家庭に暮らす令嬢、あるいはそうした家庭に使える使用人です。そして、明にあるいは暗に、殺人が関わってきます。これらの殺人にも共通点があります。殺人とは、いうまでもなく人が人を殺す行為ですが「儚い羊たちの祝宴」の5編で描かれる人を殺すという行為には、悪意や恨み、後悔といった感情が一切伴っていません。その歪みっぷりの怖さが、最後の1行で最大化される巧さが、5編に共通しています。高所恐怖は、上空1万メートルよりも地上数十メートルの方が大きかったりしますが、人間性の歪みとそこに起因する怖さというものも、まったく理解不能な行動よりも、常識的な感情からわずかに、しかし画然とずれてしまっている心理をつきつけられる方が衝撃的だということでしょう。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!