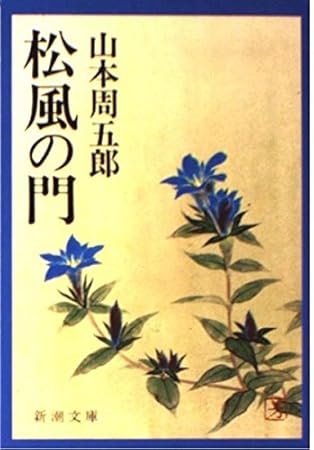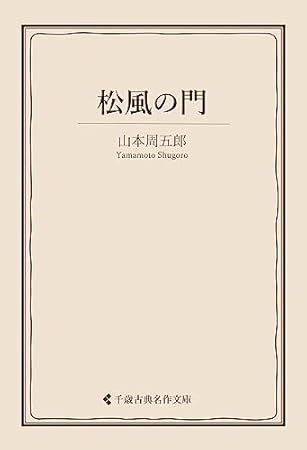■スポンサードリンク
松風の門
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
松風の門の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.57pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全14件 1~14 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 正直、時代小説には興味が無く、山本周五郎さんのお名前も「知ってはいる」というレベルでした。 そんなわけで読まずに長い間本棚に置きっぱなしだったのですが、先日読む本が無く、仕方なく読み始めたらメチャクチャ面白くて「今まで済みませんでした!」ってなりました。 短編集なのですが、どれも読んだ後の余韻が凄い。凄く複雑な顔をしながら「あ〜…」ってなります。 例えば、他のよくある作品では「実はあの噂話に出てきた人がこの人なんです!」っていう「実は!」で読者をビックリさせるのに最大限の力を注いでいる物が多いので、 途中で正体が分かってしまえば、とたんにつまらなくなってしまう事も多いのですが 、この作品はそこではなく、あくまでも人の心の動きの方を鮮やかに描き出すので、「実は!」とか、どうでもいいという感じです。 是非、読んで「あ〜…」ってなって欲しい。久しぶりに手放しで人に勧められる一冊に出会いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ・表題作を含む当初2作は、筋の典型さが味わいを薄くしているが、続く11作は、戦前の作にも著者の成長が窺え、また戦後一層伸びやかになった筋に、描かれる人物にも血の通いが濃く感じられ、文字通り味わい深い作目白押し、の本である。お馴染みの「おたふく物語」三部作の掉尾「湯治」を始め、性別・武家・町人を問わず、生身の人として懸命に生きる姿が、綿密多彩な筆致で描かれており、単なる筋の面白味を越えた、「本源的な人間のあり方」をテーマとした、周五郎ならではの豊かな「物語性」が詰まった、本である。場や人物設定の幅広さ、ストーリーの深い奥行きに、後世の時代物作家の及ぶべくもない高み、が感じられる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本周五郎の作品は、珠玉だらけである。ひっきりなしに新刊ものが発売されるが、彼らの作品を復刻して国民がもっとも読めば良い、と思う。今回の短編集の中では、特に、『釣忍』が良かった。「おはん」のような女房との出会いがあれば、店の一軒や二軒どうでもよい。 床の間に屏風を立てておくと、上下関係がなくなるという和室の使用法を初めて知った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 昔、国語の教科書に載っていた『鼓くらべ』のためだけに買いました。 主人公の言動は今で言うツンデレ美少女そのものです。ごく短いストーリーで見事に著された彼女の変化と美しさ。 真に師匠と呼べる人へ向けた言葉とそこに込められた決意。 私は鼓のことなどテレビで扱われる程度のことしか知らない無知な男ですが、粗末な部屋に凛と響き渡る「男舞」はたしかに聴こえてきました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初めて著者の短編を読みましたが、ガッカリです。他の長編と異なり底浅く薄っぺらで、感動はおろか興味も涌いて来ないものが殆んどでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業課題で鼓くらべを読む機会があったため購入しました。周五郎はこれまで読んだことがなく、司馬遼太郎に比較して虫の視点と言われる周五郎のきめ細やかな人々の心の描写に感動させられました。人を描かせたら右に出るものはないのではないかというほどの作品があり、初めて触れる周五郎作品ながらすっかりと魅了されました。これを機に周五郎作品を読み込んでみようと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 朗読CDを買ったのと、高校の現代文教科書に「紅梅月毛」が載っていて、ひさかたぶりに読み返しました。『松風の門』は幾度でも読み返したい作品がたくさんあります。「鼓くらべ」は30数年前ですが、中学校の国語の教科書に全文掲載で授業で読みました(ガルシンの「信号」も載っていた教科書でした)。最後にエゴが折れて初めて素直に涙を流すお留伊に、物語が与えてくれる感動をしみじみと味わえます。「醜聞」も読み返した一編です。人間というものは何かの機に気付きがあれば、変わりうるものだということを考えました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ヒーローは出てきません。 ですが日常を生きる普通の人々の人情味あふれる素敵な話が詰まっております。 じーんときました | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書には13の短編が収録されているが、タイトルになっている「松風の門」だけでなく、すべての短編が実によくできている。読み応えがあり、考えさせられ、感動させらる、素晴らしい作品集だ。著者の他の作品も読みたくなった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 13の短編集。背景描写の緻密さの上に、物語の展開は奇抜で夫々に楽しめます。「鼓くらべ」は勿論、「評釈堪忍記」の台詞の巧みさ、話のスピード感がイイです。また「失恋第五番」はこの本の中では唯一現代ものですが、戦後の葛藤がユーモラスにダイレクトに描かれています。「ぼろと釵」も悲しくもあり、せつないお話です。求めるまでもなく、何かが胸に語りかけてくるお話ばかりです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中学生から高校生にかけて、山本周五郎の短編が好きでした。 「おたふく」のおしずの明るさはえらいと思ったし、「水の下の石」のあごの不器用な生き様には涙しました。 彼らの不器用だがまっとうな生き方は今でも私の理想です。 けれども今大人になって読み返すと、男女の機微を描いた作品が一番面白い。 「その木戸を通って」「柘榴」「菊千代抄」「葦は見ていた」などもいいけれど、 ダントツだと思ったのがこの本の中の「薊」。 構成のうまさ、官能的なのに上品なストーリー、読んでいて震えました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本周五郎は既に古典というか...そこいらの書店ではちょいとこむずかしいようなセレクションは手に入らない。その点、偉大なる司馬氏や根強い池波氏のようには行かないのである。この松風の門もなかなか売っていない口だが...驚くほどスゴイ作品で占められているのでまたまたハタ、と膝を打つ次第。おたふく三部作の中盤「湯治」やちいさこべを彷彿させる下町男の気っ風に掘れました系「釣り忍」は当然としても「砦山の十七日」のような極限一場ものあれば、東南アジアな酒場同時進行群像劇的青べかの「おらあ抵抗しなかった」の江戸版「月夜の眺め」「醜聞」の悪妻悪女っぷりも際だっているし功兵衛の人間性回復も爽やかだ、なんといっても「薊」これがすごい。時制が複雑に交錯し、てつ太郎のゆきをを失った非現実的な喪失感をえぐり出す手腕には恐れ入谷の鬼子母神。スゴイ作家がいたものである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「鼓くらべ」は中学生のころ国語の授業で読み、人生観を変えたといっていいほどの素晴らしい作品です。「芸術はこの世で最も美しいものの一つ、人と優劣を争うものではない」との物語の大綱にさわやかな感動を覚え、価値観が一変したものです。それまで将来ピアニストになれるだろうかと、手の届くはずのない淡い夢を持っていた私ですが、この作品のおかげで新たな進路を見出すことができました。特にお留伊が、隣で鼓をたたく競争者の顔に自分の醜い修羅の心を見た衝撃は強く心に残ります。現在においても確かに、音楽家を目指す人々の顔に何とか人に勝ろうとする修羅の形相を見て取ることができます。今、ピアノは趣味として、また一アマオーケストラ団員として仕事は別に持ちつつ生活できる自分が幸せです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本周五郎は、短編小説が特にいい。 無駄な言葉が無く研ぎ澄まされているのだが、それが却って風景や感情をクリアに頭に描かせてくれる感じがします。 この本は短編集ですが、中でも好きなのは「鼓くらべ」です。 江戸時代加賀の国の鼓の演奏会に出場する女性(お留伊)の話です。 人より秀でるための努力や競争する意気込みはとても必要なことですが、それだけでは本当の意味では足りないものがある。 鼓は人を打ち負かす為のものではなくて、人の心を打たせるものなんだよという姿勢がとても共感できました。 現在の生活にも当てはまる気がします。是非読んでみてください。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!