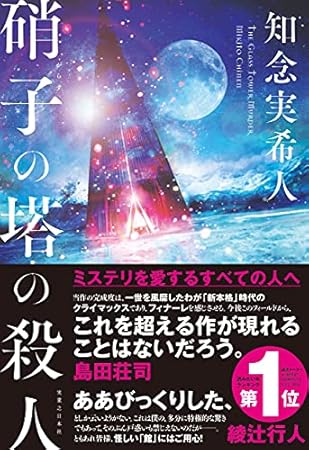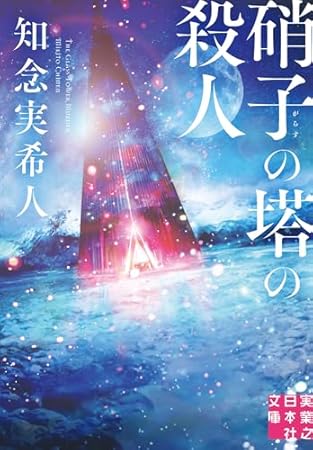■スポンサードリンク
硝子の塔の殺人
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
硝子の塔の殺人の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.57pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全204件 141~160 8/11ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 久しぶりに本格推理小説を読みました。18歳?くらいの時に十角館の殺人を読んで衝撃を受けてから、かなりの数のクローズドサークルものを読みましたが、最近は歴史小説ばかりでした。怪しい建物、怪しい登場人物、密室殺人、名探偵による真相究明…そしてその更に奥にある真実。クローズドサークルファンにとってはとても楽しめました。また名探偵と助手とのちょっと変わった形の関係も良く、切なさの残るラストもとても良かったと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み終わりました。 世界観のリアリティの無さに、あまり熱心に読み進めることが出来ませんでした。 ただ、盛り上がるところはあるので、もう乗っかって読んだ者勝ちかも。 旬のうちに読んでおきたい一冊。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初、なんだこの薄っぺらい感じ。と思いながら読んでいきました。プロローグに繋がった瞬間も、あー、はいはい、だったし、なんかトリックもダサいし見え見えな伏線だし何がそんなに高評価なん。と思いながら読みました。ら。ラストまじで気持ちよく楽しめました!どんでん返しを謳うミステリーが多すぎて、慣れっこになってましたがこちらは本当に久しぶりに楽しいミステリーでした! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初は長過ぎる導入のように思いましたが、終わりは早く展開しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| わざわざ買って読むほどでもなかった。 ミステリーやサスペンスが大好きで貴志祐介さんなどをよく読むから これも読んでみたけどイマイチすぎた | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いわゆる本格ミステリー、クローズドサークルものだ。いろいろな書評では高評価だが、好き嫌いがわかれる作品ではないだろうか。ストーリーの中に散りばめられるミステリーにまつわる蘊蓄と名著に対するリスペクトはマニアにはたまらない魅力なのかもしれないが、自分のようなミステリー好きレベルには脇道に外れ過ぎだろ、とツッコミを入れたくなる。せっかく結末には意外性があるのに、もったいつけ過ぎて何となくオチがわかってしまうところは、策士、策に溺れるといったところか。本格ものという枠に囚われ過ぎたのかなあ。もうちょっとダイナミックに話を進めてもよかったのかも。でも本格の枠組みをしっかり守って、意外性のある結末に持ち込んだことでプロの方々からは好評を得ているのかも知れない。通好みってことか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とにもかくにも、帯で褒められすぎ。 特に綾辻さんのがミスリードを誘う。 作品の”出来”に関してかと思ったら、そりゃあんなに作中で名前呼ばれてたらねぇ……。 綾辻行人に成りたかったのは、知念実希人本人だろうよ、というお話になってました。 硝子の塔と聞いて想像したのは、ラストに砕け散りながら崩落する塔の姿でした。 それ見せてくれりゃ、途中なんかどうでも良かった。 そうではなかったので-1 です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とにかく面白かった。そして、終盤は謎解きからの大どんでん返し!! ミステリーファン必読の一冊かと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本筋とは別のミステリの蘊蓄の数々に思わずニヤッとさせられました。これまで本格ミステリを読んできていない人には逆に邪魔だったかもしれませんが、当方にとってはストーリーをたどる楽しみとは別の喜びに満ちていたのも事実です。昔懐かしい探偵小説のスタイルを取り入れているのも成功のポイントでしょう。勿論、密室殺人のトリックも同様です。 半世紀以上前に出会った懐かしい暗号とも再会しました。世界的な名作へのオマージュです。随所に作者のその遊び心が見え隠れしていました。それらの原作をすでに読んでいる人が本書を手に取ると懐かしさすら覚えるはずでしょうから。 肝心のストーリーには全く触れません。読んでみてのお楽しみです。これまで数えきれないくらいのミステリを読んできた者ですから、既視感があったのも事実です。それでも満足させられました。本作への賛否は分かりますが、オールド・ミステリ・ファンを喜ばせたのも事実ですから。 作者の医療ミステリを読んできましたが、この路線もいいですね。次作もまた期待しています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 今年の話題作と聞いて気になっていたので。 想像以上に新本格への愛にみちた作品だった。中盤まであまり盛りあがれずに読んでいたものの終盤の展開に驚愕したので、読後の満足度は高かった。作中のミステリ談義も見どころの一つなのだろうが、ここは人によっては過剰だと感じてしまいそう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本のレビュー初めてで、拙いですが。 一通り、シャーロック・ホームズ、アガサ・クリスティ、綾辻先生、いろんなミステリーは読んできているつもりですが、 世間一般に聞く評判より全然面白く無かった… なんか、作者の登場人物を通して、ミステリマニアを読者にひけらかしているようで、尚、こんなことしたら読者楽しむでしょ?ほら、どんでん返しだよ〜って感じが、目に見えてしまって、興ざめしてしまいました。 いろんなミステリーのいい所を取って使ってるんだから楽しめる人には楽しめるとは思うんですが… ある程度、ミステリー読んでないと、なんの事?わからない。ってならないかなーって感じの本でした。 個人差がありますので、私の感想は1感想として、レビューを終わらせていただきます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| わけではないんですが 少しネタバレ 邸内見取り図を見ただけで、 どこかで見たようなと思い、 主催者の年齢を考慮したら、 EVないのはおかしいよなぁ、 やっぱアレですねと 全体的にいろいろ既視感ありまくりでした 同時期に他の作家さんのシリーズ最新作が 刊行したせいか、帯の煽り文が凄かったですが 逆に何もない方が良かったのではと思いました | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 密室、クローズドサークル、ミステリ談義、読者への挑戦等々懐かしいガジェットが多数登場し、ミステリ好きなら懐かしく読みやすくグイグイと引っ張る力のあるストーリー。 とても楽しんで一気に読了したけれど、逆に面白かっただけに粗も残念にうつる。 特に主人公。 何故医者にしてしまったのか。 これが秘書や使用人、とかなら全くストーリー上決定的な齟齬はきたしていなかったように思うが、医者であるせいであまりに大きな矛盾が目立つ。 その設定なら、まず最初に声をかけるのは医者のはずなのに、、 メイントリック自体は、新本格好きなら最初の数ページで想定できる気がする。 それでも、まぁそういう言いたいことはあるけれども、紛れもなく一気読みできて読後感も楽しい佳作ミステリです。帯がちょっと過剰。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 紹介文の過剰な賛美につられて手を出してみましたが大失敗でした。 ミステリは大好物ですが、このレベルのものを傑作だと業界が褒め称えている状況だから ミステリ業界は長らく停滞しているんだなと思いました。 以下、その理由です。 ①序盤の捨てトリックの程度が低すぎる。 ミステリマニアを自認する主人公が、刑事、名探偵、ミステリ作家らが揃っている状況で仕掛ける 渾身のトリックがコチラ↓ 被害者と二人きりのときに、毒入りカプセルを飲ませ、堂々と犯行を告げ、死亡も確認せずに部屋を出て施錠。 遺体発見時にこっそりと部屋の中に鍵を投げ捨てて、密室に仕立てる。 医師として診断して病死として処理。 ……いやいやいや。額に入れて博物館にでも飾っとけ、ってくらい古典的だな。。。 せめて医者なら、いや、医者じゃなくても、ターゲットの死亡確認はしようよ。 ってかカプセル溶けるの早いな! 案の定、ダイイングメッセージを残されて窮地に立たされるとか。。。 完全にギャグにしか思えず、期待は一気に萎み、 お願いだからユーモアミステリであってくれと祈りつつ、続きを読む羽目になりました。 最後のほうで、何故こんな無理のある展開にしたのか作者側の都合は分りましたが、ますますゲンナリ。 もうちょっと上手くやって。。。 ②キャラクターがラノベみたい。 探偵役がホームズのコスプレをしている自称名探偵の女。 ミステリを偏愛しており、ミステリのことになると、周囲の状況などお構いなしに我を忘れて喋べりつづけるが、それを咎められるとぷくーっとほっぺを膨らませる。 ……そんな大人の女性を想像してください。 彼女の言動は、普通の人が考えたって感じのエキセントリック言動なので、次にくるセリフが容易に予想できます。テンプレです。 こういうのはキャラが立っているとは思いません。 あと、自称どころか、周りの人にまで、名探偵呼びをさせるのは気になりました。 ③ミステリの知識をひけらかしすぎ。 登場人物にミステリ愛好家が多いので、全編を通して他のミステリ作家やその作品について言及されます。マニアというには、自分でも読んだことのある有名どころばっかりでしたが。 海外だと、カーとか、ポーとか、クリスティ、クイーンとか、 国内だと、帯に推薦も書いている島田、綾辻に、横溝、鮎川などなど(敬称略) 古い……新本格ってもう何十年前だよ。 一部のマニアは、ニンマリするのかもしれませんけれど、知らない人にとってはただの呪文だと思います。ヤサイニンニクアブラカラメマシマシみたいな。 この作品に限らず、ミステリって作中で登場人物にミステリ愛を語らせるパターンが多い気がします。特に新人の頃の作品なんかでは。 出版社や大御所に媚びているのか、ミステリを知ってますアピールなのか。 ④令和なのに昭和。 昔ながらのクローズドサークルもので、スマホなど一部のワードが出てこなければ、80年代を舞台とした作品と言われても、特に違和感を感じなかったと思います。 名探偵が思い入れたっぷりに糸やカンヌキを使った密室トリックについて、言及したりしますが 令和の時代に糸を使ったトリックはないでしょ。IT技術から取り残されすぎ。 無理に現代日本の設定にしなくてもいいのに。 ⑤結末もひどい。 ネタバレになるので語りませんが、真犯人やメイントリックは平凡、メイントリックに自信がないのか、ネタの数で勝負って感じです。 更に動機はひどく、こんな理由で殺されるのなら、ハンガーを投げつけたせいで、殺されたほうがまだ納得できる。 あと後日談で、ええ話風に締めたことになっているようですが、どんな神経してたら、そういう気持ちになるのか。理解に苦しむ。 とまあ、かなり酷評しましたが、自分はミステリが大好きです。 ミステリ愛ゆえに完走しましたが、ハッキリ言って苦行でした。 愛ゆえに! 人は苦しまねばならぬ!! 愛ゆえに! 人は悲しまねばならぬ!! ……こんなにも苦しいのなら、もう、愛などいらぬ! (訳:しばらくミステリは読みたくない) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これが新本格ミステリなんですか? 今までいわゆる犯人探しの本は割と読んで来ました でもこれより面白い物の方が多かったです トリックの絵が浮かんでこないし後付け感が満載 いや、普通に面白いのですがあまりに評価が高いと厳しい所に目がいくんです 読んで損はないけど期待し過ぎない方がいいと思います | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 酷評の嵐にとてもドキドキして買いましたが そこそこ面白かったです 作者がミステリ大好きなのは尋常じゃなく伝わってきます しかしネタバレ気味のレビューする人はどうにかならないですかね・・・ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 各部屋の地図があったり、本格的を思わせたが、 内容が貧困。最後はもっとつまらん。ちーとすぎる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 島田荘司をはじめとする新本格の面々が帯で絶賛しているのを見て買いましたが、個人的にはイマイチでした。 トリックは及第点だと思いますが、読者がある程度ミステリマニアでないと冗長でつまらなく感じるでしょう。 巻末で島田荘司が本作を「傑作」ではなく「秀作」と書いていることに納得しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 後半は一気読みしてしまいました。 映画化してほしいな。 ネタバレに触れたくないので、ここまで。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間も忘れてあっという間に読んでしまいました | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!